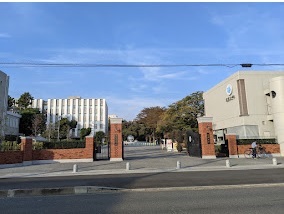私の父が高校生の頃(戦前ですが)、高校では上級生が下級生を殴るようなことは.よく行われていたと聞いています。
私が高校の頃(約60年前、戦後)には、そのような伝統は消えていました。
軍隊ではもっと酷いパワハラが行われていたと聞きますから、上下関係のパワハラは軍隊と関係あるかもしれません。
このところ、宝塚のパワハラが騒がれています。宝塚OGが、上級生からパワハラを受けたこと、自分も下級生に対してパワハラをしたことを懺悔し、改革を訴えていました。
確かに行き過ぎが有って、改革しなくてはいけないなと思います。何となく宝塚は、真っ黒なブラック組織に見えて、印象がダウンします。
でも、少し斜めから見てみると真っ黒ではなくて、伝統的な紫色にも見えます。
(1)明治時代の(厳しい上下関係の)伝統が今だに生きている組織なんて、他には無いように思います。(いい意味ですが)生きた歴史博物館みたいです。
(2)女性は意外と規律正しいことが好きなような印象があるので、「これが宝塚よ」って感じで、(行き過ぎた)規律を楽しんでいた部分もあるんじゃないかな、っても思います。
行き過ぎは改善して、紫色を薄紫のスミレ色に直せばいいんじゃないかと思います。