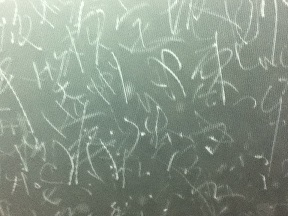実家に泊まり(夏はリビングに寝る)、夜トイレに起きると(リビングに付いている)流しのそばに大きなゴキブリがいました。
私はここ30年位5階や6階に住んでいたのでゴキブリに面会することはありませんでした。久しぶりの遭遇で動揺し、(無線のアンテナ固定用に物置から持ってきてあった)木刀を持ってしまいました(木刀は小学生の頃、筑波山で買った物、下の写真左)。次に、中性洗剤をかけると死ぬはずだと思い出し、かけましたが逃げられてしまいました。
少し落ち着き、そういえば私は昔ゴキブリをやっつけるのが得意で、逃げられるようなことは無かったなと、思い出しました。私は新聞紙を丸めてバシッと叩き気絶させるのが得意で、潰すことはありませんでした。
普段大きな顔をしている女房も何故かゴキブリにはやたら弱く、私の腕の見せ所でした。ゴキブリは亭主の権威に一役かっていたなと懐かしくなりました。
昔、「ゴキブリ亭主」という差別用語があったことも思い出しました。台所をウロチョロしたり、妻や娘にやたら嫌われている亭主をゴキブリ亭主と言った気がします。ゴキブリをやっつけるのがうまい亭主もゴキブリ亭主だなと思いました。
翌朝、父にゴキブリの話をしたら「ゴキブリはしょっちゅう出てくる」と言って、ゴキブリをやっつけるツールを持ってきました。柄の長い蠅叩き(写真右)でした。大昔、母が庭のシュロを使って作ったものだと思います。こんなのよく取ってあったなと思いました。
 手作りの「蠅叩き」なんて、若い人達は見たことないですよね。
手作りの「蠅叩き」なんて、若い人達は見たことないですよね。