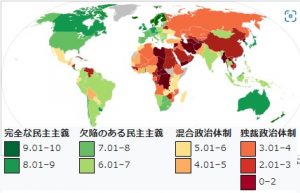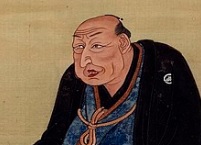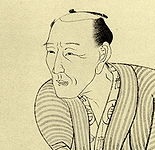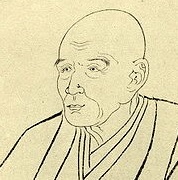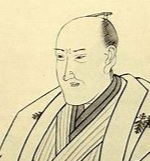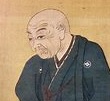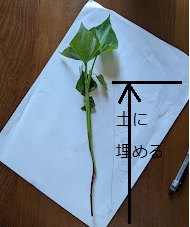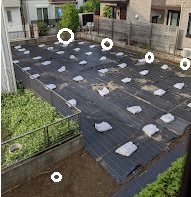今週月曜日、神式の葬儀に参列してきました。そこで神主さんが「”そうじょうさい”に続いて”とうかさい”を行います」と言われました。何のことか分からなかったので、少し調べました。
*神道では、故人の魂は極楽浄土などには行かずに、家の守護神となるというのが基本的な考え方です。
*神道では死を穢れと捉えているので、神社で葬儀を行うことはしません。
*遺族は忌明けの五十日祭が過ぎるまでは神社に参拝することも控えるべきだとされています。
*神社と同様に、神棚に宿っている神様にも死の影響を与えないようにするため、忌明けまでは神棚封じを行います。
葬儀に関連する主な祭事は次の通りです。
(1)通夜祭:
葬場祭の前夜には、通夜にあたる「通夜祭」を行います。
通夜祭の中では死者の御霊をご遺体から霊璽(れいじ、仏式の位牌にあたるもの)に移すための「遷霊祭(せんれいさい)」を行います。遷霊祭は別名、御霊移し(みたまうつし)とも呼ばれます。
(2)葬場祭 (そうじょうさい):
仏式でいう「葬儀・告別式」です。
(3)十日祭:
神式では、葬儀のが終わると十日ごとに霊祭を行い、これを「毎十日祭」と呼びます。
特に、十日祭と五十日祭は重要なようですが、(最近は略式で)葬場祭と一緒に十日祭を済ませることが多いようです。
五十日祭にて忌明けとなります。
本来は、一年祭が忌明けとされていましたが、最近では、五十日祭を忌明けとすることが一般的となっています。