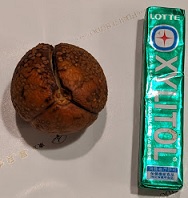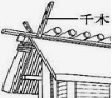紫の上の最期は、全く記憶になかったのですが、趣味どきっ「源氏物語の女君たち」で勉強しました。
(紫の上は小さなころ誘拐され)光源氏に育てられる。やがて光源氏と結婚するが子供がいなかったため、(光源氏が明石で明石の君と作った娘)明石の中宮(後に天皇の后となる)を育てる。
何だかんだあり、紫の上は体調を崩し、病の床に伏す(38歳位)。
紫の上、最後の夏、(宇治十帖に出てくる)匂宮(明石の君と光源氏の孫、まだ子供)に、「大人になったらここに住んで、庭にある梅と桜の花をお供えしてくださいね」と頼む。
その秋、(自分が育てた)明石の中宮(明石の君の娘)に手を取られて旅立つ。
せつない!
匂宮は、やがて梅と桜を仏前に供えて、紫の上の願いに答えたと思われる。
==全然別の話==
*G7がイランによるイスラエル攻撃をが非難したそうです。でも、その前にイスラエルを非難すべきではないかと思います。
*パレスチナを国連の正式な加盟国とするよう勧告する決議案が、アメリカが拒否権を行使して否決された。
これでは、G7のウクライナ支援の正当性に影を落とします。
*新首相は、(やるって言ってたんだから)日米地位協定の改正をやってくれるんでしょうね。
*アジア版NATOは、危ない話だと思います。