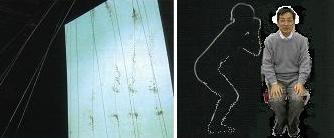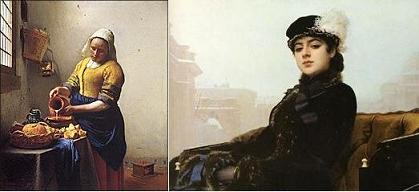2007年12月
2007年12月
12/01 Sat
12/02 Sun 大徳川展
12/03 Mon
12/04 Tue
12/05 Wed 芸術の秋
12/06 Thu
12/07 Fri
12/08 Sat 静電気の悩み解消
12/09 Sun
12/10 Mon
12/11 Tue
12/12 Wed ディジタルアートフェスティバル2007
12/13 Thu
12/14 Fri
12/15 Sat
12/16 Sun 今週の出来事
12/17 Mon
12/18 Tue
12/19 Wed ニューズウイーク
12/20 Thu
12/21 Fri
12/22 Sat
12/23 Sun ブレークスルーベスト10
12/24 Mon
12/25 Tue
12/26 Wed 耳順
12/27 Thu
12/28 Fri
12/29 Sat
12/30 Sun 今年最後
12/31 Mon
今年最後
2007 年 12 月 30 日
日曜日
昨日テレビで”男性のフラダンスが流行っている”というのを見てハッ!と思い出しました。今年も色々なことに挑戦しましたが、結果は様々です。
(1)始めるのも忘れていた:
私はハワイが大好きで、以前から男性のフラダンス(元々フラダンスは男性が神に捧げる踊りです。男性のフラダンスは女性のとは違って力強くてなかなかいいんです)をやりたいと思っていたのですが、当然この辺には男性フラ教室なんかありません。2,3ヶ月前、つくばイクスプレス大鷹の森の駅ビルのハワイショップで男性フラのDVDをみつけ購入しました。1,2度見たのですが練習もせず、そのまま放ってあります。来年は練習しなくっちゃ!
(2)頓挫:
テレビショッピングでサーフボーイ(乗馬健康器具のサーフボード版)が宣伝されていました。テレビショッピングでは値段が高いので買えませんでしたが、その後、ネットでテレビの半額ぐらいで売られていたので買ってしまいました。早速、始めたのですが、おなかの筋肉に来る前に膝に来て、膝が痛くなってしまいました。アッと言う間に邪魔ものに変身しました。
(3)とりあえず続いている:
以前、斉藤茂太氏の本で、食事の時(うまかろいが、まずかろうが)奥さんに聞こえるように”うまい”と言え、というのがあったので、実践しています。これ結構効果があって、言うの忘れていると”これはどう?”なんて催促されることもあります。先日、一寸塩分が多いな、と思ったのですがセオリー通り”うまい”と言っておきました。当然ハシは進みませんので、残りが翌日また登場してきました。食べないでいると、”何で食べないの?”と言うので、”しょっぱくて”と言いました。すると、”昨日おいしいと言ったじゃない”と言われました。
エ〜!昨日の話覚えてるのかよ!!”一応言ってるだけジャン”とは言えず、ン〜〜!と気まずい沈黙が流れてしまいました。女性は記憶力がよいのでいいかげんなことを言ってはいけない、と反省しました。
(4)今のところ続いている:
私は絵が下手で、5段階評価で言えば1か2です。でも絵を見るのは好きで、以前から何とか人並みに描けないものかと思っていました。2ヶ月くらい前、書店で”3分間スケッチ”という本を見つけたので購入しスケッチに挑戦しています。この本、色々”コツ”が書いてあるので、それに従って描いていくとそこそこうまくなるので楽しくなり続けています。今回まあまあ(自己評価3.5)の作品ができましたので年賀状に使いました。本サイト元旦に載せます(たいしたことはないので期待しないように)。同時に、絵を描くと、頭のリラックスに役立つことも発見しました。私は夜パソコンを使うと頭がさえて眠れなくなるんですが、そんな時でも15分位絵を描くと頭がリラックスして眠れます。パソコンで頭の中の血液が一箇所に集まっていたのが、絵を描くと全体の広がっていく感じです。
==
昨日は、仲良し卒業生の忘年会でした(集まるの今年3回目だと思います)。昨日金子研も卒業生の忘年会で6階まで魚を焼く匂いが充満していました。それでは、よいお年を!

耳順
2007 年 12 月 26 日
水曜日
耳順(”じじゅん”、”みみしたがう”あるいは”みみにしたがう”)ってどんな感じか?
気付いたら60歳になってしまいました。還暦ってどんな感じかお伝えしようと思います。
(A)素直な感じ
(1)歴史:60歳は暦の上での最初のゴールって感じで、60年生きたんだ、って感じです。短くもなかったな、って感じかしら。
最近100歳近い人もよくみかけます。この人の人生を10回繰り返せば平安時代か、って思うと平安もそう昔でもないな、って感じです。
(2)激老:この半年ほど急激に老いが進み(自他共に認める)、60ってのは一つの節目なんだと実感します。自分の顔を鏡で見るのも怖いのですが、同い年の家内の顔も(老いを見せ付けられる感じで)怖くて見られません。
(3)危険地帯:自分の健康、親の介護、自分の介護、と何が起こってもおかしくない危険ゾーンに入ったな、って感じです。
さらにこれから5年以内に新型インフルエンザが猛威を振るうだろうし、10年以内に日本は財政破綻で街には浮浪者があふれるだろうし、20年以内に地球温暖化で資源の奪い合いが起こるだろうし、すごい所に突入したな、って感じです。
(4)(あまり関係ないけど)今回、ケーキのないクリスマスを初めて経験しました(気がついたらクリスマスが終わってました)。
(B)孔子によれば「六十にして耳順」となります。
どういう意味かネットで調べてみると、
”品性の修養が進み、聞くことが直ちに理解でき、なんら差し障りも起こらない境地”
とか、
”事の善悪や相手の品性を見抜ける様になる”
とか、
”異なる考えも素直に聞き入れられるようになること”
とか出てきます。
品性の修養は進むか?:私が今までに多くの人を見てきた感じでは、歳を重ねることにより品性の修養が進むとは思えません。品性の高い人は若い時から高いし、低い人はいくついなっても品性が低い、という印象です。
欲?:ただ、歳を取ると欲がなくなるということはあります。体力の減退により体力に由来する欲は減退し、名誉欲もなくなってきます(人によっては歳をとっても名誉に執着する人がいて、私には全く理解できません)。お金も健康など他のものを犠牲にしても得ようとは思いません。
欲がなくなると、トラブルの当事者になることが少なくなり、他の人と衝突する機会は減ります。そのため、物事を一歩引いた所から冷静に見る機会は増えます。そんなことから、品性があるように”見える”可能性は高くなると思います(実際は品性が上がってないので、トラブルに巻き込まれれば即馬脚を現しますが)。
(ただし、欲がなくなると気力が落ちるという副作用が問題です)
(C)これからどういきるか
以前、定年退職する上司に、老後のプランを聞いたところ、親の介護や自分の健康など予期せぬことがいくらでも起きてくるのでプランなんか立てられないんだよ、と言われましたが、今はよく分かります。
とりあえず私としては、
(1)この所食い散らかしてきた感じの卒研を少し整理し、みんなが利用しやすい形でネットに公開しよう、
(2)小学生の理科離れが進んでいるというので、小学生向け理科サイトかテレビ番組を作ろう、
(3)何か、面白いものを作ってみよう、
なんて考えています。
また心がけとして:
(1)晩節を汚さぬように、品性が高いように”見えるよう”に、
(2)多くの方に色々お世話になってきたので、できるだけお返しをするように、
と思っています。
大学はあと5年です。ベストを尽くそうと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

ブレークスルーベスト10
2007 年 12 月 23 日 日曜日
SCIENCE誌2007年ブレークスルーベスト10(12/21日版)
日本語版が出るのは3ヵ月後らしいので、ホットなところで紹介します。
1位 ヒト遺伝子の多様性
数千人のDNAを調査し、疾患を持つ人と持たない人の差異から、心房細動、自己免疫疾患、躁鬱病、乳ガン、結腸直腸ガン、糖尿病、心疾患、高血圧症、関節リウマチなどに影響を与えている遺伝子を特定した。
2位 万能細胞
京大とウイスコンシン大のニュースで有名になった、体のどんな部分の細胞も作り出せる細胞の作成。
3位 宇宙線の追跡
宇宙線の中で一番エネルギーの大きい宇宙線はどこから来るのかは分かっていない。アルゼンチンのグループは、それが我々の銀河の外の活動銀河核(巨大なブラックホールを持つ)から来ている可能性が高いことを示した(まだ決着が付いてはいないが)。
(これに関しては北山先生に概要を教えていただきました、感謝いたします)
ここ(3位)までは間違いありませんが、4位以降は、よく分からずに書いている部分も多々あります(専門用語や研究の背景が分からないため、正式な用語と違っている場合もあると思います)。また、4位以降のいくつかの項目に関しては、専門分野が近そうな先生にお聞きしましたが、ご存知ないようでしたので、それほど有名な話ではないのかもしれません。
4位 受容体の可視化
視覚や嗅覚と関係があるGたんぱく質共役受容体の構造を解明しCGで表現した。これは、医薬品などの開発を加速する可能性が高い。
5位 シリコンを超える?
遷移金属酸化物は高温超伝導物質として注目を集め研究されてきた。これを用いて異なる酸化結晶の多層構造を作ると色々な特性を示すことが分かった。シリコントランジスタ以上の特性を示すかもしれない。
6位 水銀テルライド薄膜の積層を作ると量子スピンホール効果が得られる。これを利用するとスピン電子コンピューターが出来るかもしれない。
7位 免疫細胞が分化する仕組みが少し分かってきた。ワクチン改良に役立つかもしれない。
8位 医薬品化合物を効率よく合成する様々な方法が開発された。
9位 ”記憶がイマジネーション(将来イメージ)を作る”という、海馬が記憶や想像に果たす役割を裏付ける結果が報告された。。
10位「チェッカー」ゲームは、プレーヤがミスをしなければ引き分けになることを証明した。
===
卒業生がカンクウへ行ってきた、というので関西空港かと思ったらカンクーン(メキシコ)でした(写真)。

ニューズウイーク
2007 年 12 月 19 日
水曜日
ニューズウイーク(日本語版)は私の愛読誌で、お薦めです。海外の情報がバランスよく、分かりやすく、よく調べられて載っています(特に、日本のテレビや新聞の海外情報は少ない上に偏ったものが多い)。
最近面白かった特集を2つ紹介します(これから就職の面接を受ける学生さんに役立つかも)。
(A)格差社会(勝者総取り)はなぜ起こるか(12/5)
(1)インド中国などの参入で労働者が20億人増えた、その結果賃金が低下
(2)競争の激化と技術の進歩、投資の自由化で労働者の発言力が低下
(3)グローバル市場で事業規模が拡大(ごく少数の企業だけの一人勝ち)
(4)自由貿易や資金の流れの自由化により、富裕層にとって世界中への投資のチャンスが生まれた。資金が儲かる所に集中投下されるので、生産拠点の国外移転や技術革新を加速し労働者から仕事を奪う
(5)富裕層に有利な税制(政治が資金力のある団体に牛耳られている)
多くの国で”金持ちにやさしく、貧乏人に冷たい政策がとられている”
(6)富裕層はコネのネットワークを持ち、労働者には味方になる法律も組合もない
(7)CEOの報酬と自社株購入権を決める制度が上層部に有利になっている
CEOの報酬が急激に増加している
(8)教育に反映し、社会各層の固定化がおこる
(B)グーグルの危機?(11/21)
圧倒的シェアのグーグルに対する挑戦も色々行われている、という話(技術分野の記事でも内容はしっかりしている)。
現在、ヤフー、マイクロソフト、政府主導プロジェクト、などが検索技術に改良を加えてグーグルの後を追っているが、以下のようなさらに進んだ検索エンジンを作る動きも活発である。
(1)ユーザの望みを察知するサイト:検索語から意味を解釈し、意味で検索を行う(ハキア、レクシ)
(2)専門家(人間)が利用頻度の高そうな事柄についてあらかじめ検索を行い、役に立つページを選び出しておく(マハロ、チャチャ)
(3)住宅情報専門とか健康情報専門とか分野を限定して精度を上げる(トルーリア、ヘルスライン)
(4)ユーザを手助け:検索語を打ち込むと関連する複数の検索語やキーワードが表示される(米国ヤフー、クイントゥラ)
(5)ユーザの意見を参考にサイトの重要度を判断(ノージージョー、スクイドゥー)
(6)グーグルは他からのリンクで重要度を決めるが、リンクの代わりにブックマークを用いる(ミスターウォン)
もちろん、グーグルもジッとしているわけではなく、検索履歴を参考にした検索精度の向上などを試みている。
===
一寸寂しい冬景色

今週の出来事
2007 年 12 月 16 日
日曜日
(1)今年を代表する文字に”偽”が選ばれました。漢字を分解し、何で”人の為”が偽りなんだ?って話がありましたので調べてみたところ、”為”は”ため”ではなく”なす”という意味で、”人の為すこと”という意味だそうです。
清水寺の貫主が大きな紙にこの文字を書き”このような字が選ばれることは恥ずかしく、悲憤にたえない”と言われていました。(この貫主は関係ないと思いますが)以前、”祇園へ遊びにくる客の多くは坊さんだ”という話を聞きました。これは偽であって欲しいのですが。
(2)先日京成線の車内放送で”次は大久保です、ドアは確か左側が開きます”と言っていました。”確かかよ!!”って話です。ユーモアのある車掌さんだったのでしょう。
(3)最近の学生さんは、”♪柱の傷はおととしの、、”という背比べの歌を知らないということを知りました。そもそも、柱の傷の意味が分からないようです。そういえば最近の家には柱がないことにも気づきました。
(4)最近大学のテニスコートの裏を狸(外見は毛並みの悪い太った猫)が通ります。捕まえて狸汁にする案もありますが、申し訳なさそうな顔をして通るので許しています。でも狸は結構獰猛です。小学生のころ近くで捕まえてた狸を箱に入れて展示してあったのですが、手を入れた生徒が噛まれ大怪我をしました。くれぐれも化かされないように。
(5)木曜日に研究室で(誕生パーティーなのか忘年会なのか)今川焼きを大量買い込み他研究室の人達も集まって地獄の今川焼きパーティーをやっていました(写真)。10時過ぎから始まり、1時頃にはみんなぐったりしていました。私も部屋に入り匂いをかいだだけで胸焼けがして昼食をとれなくなりました。
(6)金曜、野里君がチーズケーキを沢山焼いて持ってきてくれました。学生さんは今川焼きの食べすぎで体調を崩し全員来ていません。幸い遊びに来ていた卒業生の岡本さんと山之内さんに振舞われました。そこで色々話しているうちに、山之内さんの義兄と野里君は時々サッカーをやってることが分かりました。あまりの奇遇に、人生に偶然はないのかな?と思ってしまいました。

ディジタルアートフェスティバル2007
2007 年 12 月 12 日
水曜日
新しく研究室に入った3年生とディジタルアートフェスティバルを見に行きました(12/11)。卒研のヒントや刺激になればと考え、ここ3年実施しています。
展示されている作品はインタラクティブアート系とCGアニメ系がありますが、見学はインタラクティブアート系を中心にしています。毎年斬新なアイデアの作品が展示されるので楽しみです。
(現物を見ないとイメージが涌かないと思いますが、目だった作品を紹介してみます)
(1)インタラクティブアート:写真左(今年の作品)はその典型で、ヒモが天井から何本も下がっていて、それが画面にも映っています。ヒモを揺らすと画面上でヒモから水玉が発生し上にあがっていきます(大変美しい作品でした)。インタラクティブアートとは、要するに人間の働きかけで映像が変化するアートです。
(2)昨年面白かったもの:戸外で2台の(本物の)ホバークラフトが爆音を立てて浮かんでいます。一方のホバークラフトを押して移動させると、他方のホバークラフトの動きに影響を与えます。相互に力を伝え合えるのでダイナミックな感覚が楽しめました。
(3)今年の一押し:暗い部屋に入ってヘッドフォンを付けて椅子に座ります。正面に大きな鏡があり、自分の姿が映りますので、鏡を見ています(写真右が鏡に映っている様子で、これを見ています)。スタートすると私の横(鏡の中)に人間(青い輪郭だけ)の映像が現れ、私にいたずら(刀らしきもので斬りかかったり、耳元でささやいたり)をします。鏡の中の出来事なのに実際に”人の形”とインタラクション(相互作用)している不思議な感覚に陥ります。
アートが人に働きかける点が斬新ですし、どのように”人の形”を鏡上の映像として出すのかもよくわかりませんが、何と、これを作ったのは同志社大の4年生(女性)というから、才能豊かな人がいるものだと感心しました。
(4)ヒューマンインタラクション:帰りに会場の隣にある、理数系の面白実験ルームに寄りました。そこには写真撮影コーナーがあり、写真は即ウエブにアップされます(撮影時にIDとパスワードを交付され、それで閲覧可)。記念にみんなで撮影しようということになり、狭い場所に7人が入りプリクラ状態で大騒ぎ、当日一番盛り上がりました。やっぱり人間同士のインタラクションが一番大切だと思いました。写真をご覧になりたい方は(いないと思いますが)、http://risupia.panasonic.co.jpのメンバーページへゆき、IDはGVCPZB、パスワードは9397で見られます(半年アクセスがないと消えるそうです)。
===
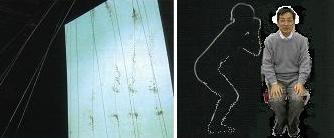
静電気の悩み解消
2007 年 12 月 8 日
土曜日
静電気の悩み解消(12月5日のNHKためしてガッテンより)
私を悩ませていた3つのケースの解消法が紹介されました。
(1)職場のドアノブ
ドアのそばの壁に手を触れてからドアノブに触れる。
(金属部に紙を張っておいてそこに触れてから金属に触ってもいいらしい)
(2)家のサッシ(干した布団の取り込み時など)
サッシのそばの木やコンクリに手を触れてからサッシに触れる。
(3)車のドアの開閉時
キーホルダーを木製にし、木で金属部に触れた後ドアを開閉する。
(車を降りる時の静電気は衣類と座席の摩擦で起こるので、降車時私はボディ(ドアの閉まる柱)のドアが引っかかる金属部をつまみながら降りて電荷をボディに戻しています)
===
写真は先日行った国立博物館の裏庭です。和風庭園の中に家(お茶室?)があるのも珍しい、かなと思います。昔の衣服を着た人を出入りさせると昔の雰囲気がでそうですね。マリーアントワネットが農村風の集落を作らせて農民の真似を楽しんだのに一寸似ているかもしれません。

芸術の秋
2007 年 12 月 5 日
水曜日
国立新美術館、フェルメール、日展、を見に六本木へ行ってきました。
(1)新国立美術館
(一見したところ)常設展示が無いようでルーブル美術館などとは位置づけが違うのかな?と思いました(とすると、日本でルーブル美術館に相当する美術館はどこなのかな?)。
外観は少し軽い感じですが、美術展示センターとしてであればモダンで高級感があり、よいのではないかしら。
(2)フェルメール
”牛乳を注ぐ女”をはじめ、オランダの風俗画が展示されています。”風俗画”と言っても十分芸術品ですが。さすがに”牛乳を注ぐ女”は一番よい出来ですが、これに近いものもいくつかありました。
何と言ってもすごいのは、この地味な題材を芸術まで高めている点でしょう。ただ、展示は上の方からの照明で光りが絵の具に変に反射して見にくい所もありました。
(3)日展
中学高校の頃は美術館がそばだったので、日展をよく見ました。その後ご無沙汰し、5年位前に久しぶりで見ましたが下手な絵が多いなと思いました。今回は、かなり良いレベルだと思います。ただ、どれも絵の雰囲気が似ている気がします。何となく明るい色調で軽快な感じのものが多いのですが(展示室の照明が以前より明るいのかもしれません)、もう少し迫力を感じるものが有ってもよい気がします。
彫刻は、例により裸体が多いのですが、(残念ながら)日本人モデルの体型の限界を感じます。ミロのビーナスは日本では生まれないでしょ。
(4)実物を見た名画
海外で見たものでは、やはり最高は”モナリザ”でしょう(ルーブルで再会した時は、”久しぶりで懐かしいですね”って感じでした)。(ルーブルだったと思いますが)モネの睡蓮とルノアールの作品が沢山並んでいました。睡蓮は20枚位有った気がしますし、ルノアールも沢山ありすぎて有り難みが減りました。(ニューヨークだったと思いますが)シャガールも沢山展示されていました。シャガールはどちらかと言うと苦手ですが、本物は写真より、はるかに魅力的でした。(ベルサイユの)ナポレオンの戴冠式の絵は(芸術的かどうかは分かりませんが)立派でした。
そうそう、ミケランジェロの(バチカン)システィーナ礼拝堂の天井画 には圧倒されましたね(美しいし、素晴らしかった!)。
日本でも色々見た気がするのですが、今思い出せるのは以下です。ベラスケスの”マルガリータ王女”とマネの”笛を吹く少年”は良かった。ロシアのモナリザと言われる”忘れえぬ人”も忘れられなくなりました。ロシアの物だったか、船だか筏だったかが難破している絵も印象に残っています。縁を黒く塗るルオーも好きです(小学生のとき物の縁を黒く塗ると叱られたので、なおさら気に入っています)。ピカソは残念ながら私の理解を超えています。最近ではダリも見ましたが、、、。
===
牛乳を注ぐ女と、忘れえぬ人(ネットから拾いましたが、昔の作品の著作権はどうなってるのかしらね?問題が有りそうでしたらお知らせ下さい、削除しますので)。
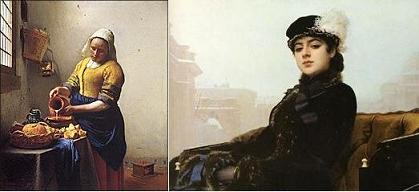
大徳川展
2007 年 12 月 2 日
日曜日
ご近所から招待券をいただいたので、”大徳川展”(上野の国立博物館)へ行ってきました。
衝撃的だったのは、関ケ原の翌年に家康が自ら作らせたという”等身大の座像(彫刻)”です(現在、芝東照宮の御神体らしい、木製?)。座像の顔の相は私が想像していたものと全く異なり、家康に対するイメージが完全に変わりました。
(1)一見穏やかな風貌かと思っていた:
家康像というと掛け軸に描かれた(たぬき親父と呼ばれたのが分かるような)老人の顔を思い浮かべます。また、”鳴くまで待とうホトトギス”と詠んだくらいですから、胸に一物はありそうですが、外見は穏やかそうに見える人かと思っていました。俳優でいうと津川雅彦のイメージを持っていました。
等身大座像のお顔(怖くて”お”をつけた)は、全てを見通すようなモノスゴク怖く、厳しい(子供の頃は人質になり、成長しては妻子を信長に殺させられるのに耐え、秀吉の悪意に満ちた無理難題にも耐えた)人相で、後に豊臣氏に因縁を付けて(注)冬の陣を起こしたり、何かにつけ領地没収御家断絶を命じたのがよく分かります。こういう人の前に出たら普通の人は怖くておもてを上げられないと思います。
(2)”関が原は家康の人望で勝った”とよく言われるが:
人相から判断する限り、人望というより、パワー(威圧を含む)に基づくリーダーシップで勝ったのだと思います。
ネットの産経ニュースでは、
”強烈な意思を秘めた眼光の鋭さは、400年の時を経ても衰えず、あたりを威圧するかのようだ”と表現しています。ニュースの写真では今一、スゴサが伝わってきませんが、その通りでした。
なかなか実物をご覧になれる機会はないと思いますので、あえて誤解を恐れず皆さんご存知の方でイメージの似た人を探すと、”もっともっと猜疑心を強くしたプーチン大統領”って感じかな?
生きるか死ぬかの戦国時代を勝ち抜くということはこういうことかと思い知らされました。非情に徹する強い精神力と桁違いの器が必要だったのだろうと思います。
===
注)大坂冬の陣:豊臣家が再建した方広寺の梵鐘銘文に記されている「国家安康」という言葉は家康の名を分断し、「君臣豊楽」は豊臣家の繁栄を願うもので、徳川家に対する呪が込められているとの理由で攻め込む。
===
早いものでもう師走、もう駆け抜けるしかないでしょう。11/28は研究室新メンバーの歓迎会でした:参加者は24名、内3年生6名、OB4名でした。