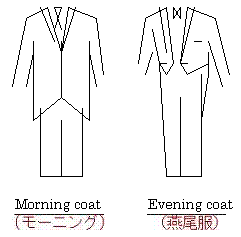2007年6月
2007年6月 
06/01 Fri
06/02 Sat
06/03 Sun
06/04 Mon
06/05 Tue
06/06 Wed
06/07 Thu
06/08 Fri
06/09 Sat
06/10 Sun 今更禁煙のすすめ、発見、誤(ゴ)キャブラリ
06/11 Mon
06/12 Tue
06/13 Wed 鏡
06/14 Thu
06/15 Fri
06/16 Sat 子は親の鏡
06/17 Sun
06/18 Mon
06/19 Tue
06/20 Wed 耳障り
06/21 Thu
06/22 Fri
06/23 Sat
06/24 Sun マーチとワルツ
06/25 Mon
06/26 Tue
06/27 Wed 残業
06/28 Thu
06/29 Fri
06/30 Sat アーティチョークとカールドン
アーティチョークとカールドン
2007 年 6 月 30 日
土曜日
カールドン(今回の写真)は背丈2m以上にもなる大薊(アザミ)で、アーティチョークの祖先だそうです。形はアーティチョークに似ていますが、花が小さく素朴というか、地味と言うか、アザミそのものといった感じです。
アーティチョークの和名は朝鮮アザミですが、カールドンの和名も朝鮮アザミのようです。また、カールドンはカルドンと記される場合も多いようです。
アメリカのスーパーでは、よくアーティチョークのつぼみ(前々回の写真)が山積みになって売られていました。どうやって食べるのか聞いてみると、茹でるか蒸して食べる、というので試してみましたが、どこを食べればよいのか、どこがおいしいのか分からずギブアップしました。アーティチョークはフランス料理やイタリア料理にも用いられるようです。
アーティチョークもカールドンも薬草園にあるくらいですから、薬草ですが、ハーブでもあるようです(と、思ったら、ハーブとは、薬効のある植物を言うようです。私は香りのある植物をハーブと言うのかと思っていました)。
私も2年ほど前、アーティチョークとカールドンの同じ位の大きさの株を実家の庭に植えてみました。2年後、カールドンは4倍に増え、棘があって痛いと両親に邪魔者扱いされています。一方、アーティチョークは1/4の大きさになって蕾も付けない状態になってしまいました。アーティチョークの蕾が日本でお目にかからないのは、栽培が難しいのかもしれません。
薬草園のアーティチョークは、写真の通り大きく成長している所を見ると、薬草園の管理には高度な栽培技術と、絶え間ない手間隙がかかっているのだろうと想像されます。
今度、アーティチョークの料理を出す店を発見したら教えて下さい。
===
当初、アーティチョークの写真を3回載せさせていただく予定でしたが、木曜に丁度カールドンの花が咲きましたので、それに差し替えさせていただきます。

残業
2007 年 6 月 27 日
水曜日
日本は残業大国と言われ、毎日、帰宅が11時、12時になる人も少なくないと聞く。さらにひどいことに、残業代が支払われないケースも多く、データに出ない残業も少なくない。過労死、うつ病、自殺などの原因にもなっている。
なんだか、江戸時代の水飲み百姓や明治時代の女工哀史の時代が復活してしまった感じである。
卒業生を社会へ送り出す者として大変気になる状況である。
世の中が”何か変だ”と思った時、その原因は必ず法律にある。
法律の問題点:
(1)残業に伴って会社が支払うべき賃金の割り増し率は日本が25%、アメリカが50%である。残業に対して会社が払うべき賃金が低いため、会社は残業を増やすことになる。せめてアメリカ並みに引き上げるべきである。
法律執行の問題点:
(3)サービス残業と言うと聞こえがいいが、要は無賃金労働である。残業代の踏み倒しと大差はない。これらは、経営者の犯罪であるというメッセージを国は発する(取り締まりを強化す)べきである。少なくとも、過労死などの労災を繰り返す会社の経営者は犯罪者として罰する必要がある。
現在の経営形態は、グローバル化と自由競争による競争激化を理由に、労働者に負担を強い、儲かった分は経営側が分け合うという形になっている(経営側のリスクが非常に低い)。
グローバル化による自由競争を推し進めるのであれば、同時に労働者を守る(経営者が遵守すべき)法律を即刻作る必要がある。
昨今、少子化が問題になっているが、”こんな人生は子供に体験させたくない”と思えば、子供を作ろうとしないはずである。少子化は政治の鏡である。
===
孔子ら一行は、墓地の前で泣く女に出会う。孔子は弟子にその理由を尋ねさせる。
女:さきに舅が虎に殺され、つぎに夫がやられ、今度は息子がやられました。
弟子:ではなぜこの土地を離れないのか。
女:ここには苛酷な政治がないからです。
孔子:覚えておくがよい。人民たちにとって、苛酷な政治は虎よりも恐ろしいのだ。

マーチとワルツ
2007 年 6 月 24 日
日曜日
夏時間(Day Saving Time)の導入が検討されるそうである。夏時間とは、夏の間、時計を1時間早めるもので、夕方5時はまだ昼ひなかといった感じである。私は、アメリカでうまく機能している夏時間が、日本ではうまくいかないだろうと思っている。理由は、日本と欧米の生活リズムの違いである。
日本人は1日をマーチ(働く、眠るの2拍子)で暮らし、
欧米人は1日をワルツ(働く、遊ぶ、眠るの3拍子)で暮らしている。
日本人の1日は、朝早く家を出て、9時過ぎに帰宅し、一寸テレビでも見てお休みとなる。
日本に居ると実感がないが、欧米人は5時になると大方の人は家路につく。職住接近の精もあり5時半には家に着く。6時から12時位までが自由時間で、一つの生活時間帯を確立している。この時間帯は主に次のような用途に使われている。
・家族と生活を楽しんだり、
・地域コミュニティーの活動に参加したり、
・趣味の世界を楽しんだり、
・新しい方面へ進出するための勉強をしたり(このような人のために、勉強する環境も整っている)、
この時間帯があることにより、会社での生活が人生に占める比重が減り、余裕が生まれ、やり直しのチャンスも増える。ただ、欧米スタイルを確立するには3つのことが不可欠である。
(1)残業がない、
(2)職住が接近していること、そして
(3)ワルツ生活への頭の切り替えである。
どれをとっても、今の日本では難しい。今、夏時間を導入すると、日本では残業時間がさらに増え、ますます過労社会になっていく気がする。
(次回は、残業大国日本の原因を明らかにする)
===
これから3回、本学薬草園のアーティチョークの写真を掲載します(写真提供は、薬草園の青山さんです)

耳障り
2007 年 6 月 20 日
水曜日
よろしか調:
(1)病院の受付で4,5人の事務員の方が、待っている患者に、
”カードを機械に入れていただいてよろしいでしょうか?”
”これに記入していただいてよろしいでしょうか?”
”持っていっていただいてよろしいでしょうか?”
など、
”〜〜していただいてよろしいでしょうか?”を連発していました。
何か変な感じです。”〜〜してよろしいでしょうか”の〜〜は自分のすることを聞く言い方(例えば、中に入ってもよろしいでしょうか?とか)だと思うんですが。
(2)また、受付に質問に来た患者に、
”今、お手続きをさせていただいております”と言っていました。この”お”も一寸変じゃないかな?手続きは事務の人がやっているので自分に敬語を使っていることにならないかな?なんて思い、語呂を確かめようと、”お手続き””お手続き”なんて2,3回言ってみている内に”おててづき”になってしまい、舌をかみそうになってしまいました。
蕎麦屋で:
(3)私は、自他共に認める蕎麦好きです。先週、蕎麦屋で隣に座った人がズルズルと大きな音を立てながら食べていました。そのズルズルを、なんか汚らしい音だなと思ってしまったら最後、蕎麦を食べる音が気になりだし、あちこちで聞こえる、ズルズルが不快に感じられるようになりました。蕎麦は音を立てて食べるのがマナーだ、なんて思っていましたが、一度”きたならしい音”だと思ってしまうと、本当に汚らしい音に感じられます。蕎麦屋へゆくのが憂鬱になってきました。
ただ、自分も音を立てて食べているので、音を立てない方法に挑戦してみたのですが、これがまた至難の業で今悩んでいます。
目障り、耳障り:
(4)新聞の人生相談で、相談者が”耳障りのよい言葉”という表現を使い、回答者に”耳障りのよい”という言い方はありません、と注意されていました。私も、相談部を読んだ時、問題点に気付きませんでした。漢字をよく見ると、確かに”目障り、耳障り”の”障り”は悪いことを言うので、聞き苦しいことを”耳障りだ”と表現すべきだということが分かります。私は多分、耳障りの”障り”を音(オン)で”触り”と勘違いしていたのだと思います。(叱られそうですが)”耳触りのよい言葉”なら結構ありますよね。

子は親の鏡
2007 年 6 月 16 日
土曜日
”子は親の鏡”という子育ての教科書のような詩(ドロシー・ロー・ノルト作)があります。
=====
”子は親の鏡”
けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもはみじめな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる
叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう
励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる
広い心で接すれば、キレる子にはならない
誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ
愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ
和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世はいいところだと思えるように
なる
=====
子としても親としても思い当たることが多く、胸が痛みます。でも、実際には、なかなかこんな風にはいきません。そんな時は、(バカの壁の)養老先生の次の言葉が慰めて(諦めさせて?)くれるでしょう。
「不完全な人間が行うは子育ては、うまくいかないのがあたりまえで、思い通りいかないことを学ぶのが子育てである」。

鏡
2007 年 6 月 13 日
水曜日
最近、自分の見ている世界は自分の鏡ではないかと感じることがよくあります。
(1)母と私:私は子供の頃から”母は、私を傷つけることをよく言う”と思っていたのですが。最近、母が”私が母を傷つけることをよく言う”と思っていたということを知りました。そんな気はなかったのですが、互いにそう思っていたのには驚きました。まさに鏡のようでした。
(2)授業と私:先日、若いけれど落ち着いた感じの先生の実験の時、実験室の端の方で計算機を使わせてもらいました。私は、同じ実験グループに対して実験指導をしたことがありますが、落ち着きのないザワザワしたグループだと思っていました。ところが、落ち着いた感じの先生の実験の雰囲気は、まさに先生の落ち着いた雰囲気が流れていました。私の実験で落ち着きがなくザワついていたのは、学生さんの精ではなく、私が落ち着きなくザワついているんだと気付かされました。学生さんは私の鏡でした。
===
写真募集:このサイトも写真があった方が楽しいので、齊藤さんに”よい写真が有ったら送って下さい”、とお願いしたら送ってくれました。これから3回、齊藤さんちの野菜さんが続きます。お楽しみに。また、皆さんも、よい写真があったら送って下さい。

誤(ゴ)キャブラリ
2007 年 6 月 10 日
日曜日
(1)テレハラ:公衆電話が減り、携帯電話を持っていない人にはつらい世の中になりました。先日通勤の途中、電話をする必要が発生し、やっとのことで公衆電話を見つけ電話をしようとしたら、テレホンカードでしか電話できない電話機でした。もうだめ!!これをテレフォンハラスメントと名付けました。
(2)パスハラ:パスモができてから、定期券購入機や精算機で選択画面が増え、読んで判断するのに時間がかかってしまいます。後ろに人が並んだりすると本当にあせります。これをパスハラと名づけました。もっとも、若い人はすんなり使っているようなので、もしかすると”老ハラ”かもしれません。
(3)過ぎたるは:
昼間の失敗を、夜、寝しなに”何であんな失敗したかな?”って悔やみましたが。その時、諺の新しい解釈を思い付き、おかしくなって眠ってしまいました。それは、”もう終わった事は考えてもしようがない”という意味で”過ぎたるは及ばざるがごとし”を使うアイデアです。小学生などに言うと本当に間違えて覚えそうで怖いのですが。
(4)モーニング違い:
カンヌ国際映画祭で”もがりの森”がグランプリを受賞し、授賞式でモーニングフォレストと紹介されていました。morningじゃなくて、mourningだろうなと思って見ていましたが。この時、長い間気になっていたモーニングコートに関する疑問が目を覚ましました。モーニングコートの綴りはmourningだと思っていたので、何でお祝いの式典にも着ていくのかな?、と思っていました。そこで、辞書を引いてみると、発音は同じですが、モーニングコートの綴りはmorning coat(昼間用礼服)でした。
さらに、私はモーニングが燕尾服だと思っていましたが、evening coat(夜用礼服)が燕尾服でした(燕尾服は指揮者がよく着るもので体の後ろにだけ尻尾があり、ズボンも黒です)。
===
NEWS:今週の月曜早朝、出勤時に(2年ぶり位で)齊藤さんと駅ですれ違いましたが、今度は金曜の帰宅時8時半ごろ、また齊藤さんと駅ですれ違いました。齊藤さんで始まり齊藤さんで終わった不思議な一週間でした。
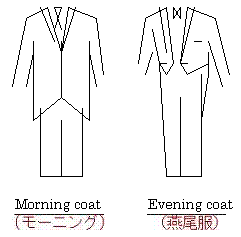
発見
2007 年 6 月 10 日
日曜日
(1)麻疹抗体検査:
先月21日血液採取分の検査結果が返ってきました(23日に採血した人の分は判定キットが品切れで、結果がいつでるか分からないそうです)。検査はEIA価という数値で判定しています。これがどんな数値なのかよく分からないんですが、ネットで調べた感じでは0〜1000位の範囲で、大体は0〜130位で平坦に分布しているようです(ネット上のデータから推測したもので、科学的根拠はない)。4以上が免疫ありだそうです。
健康管理室に今回の測定結果(EIA価の分布)を教えてくれないか聞いてみましたが駄目でした。、
あまり情報が無いのも寂しいので周辺の3名にEIA価を聞いてみたところ、
50代で、子供の頃、実際に麻疹をやった人2名のEIAは50台でした(含む私)。
ワクチン接種で抗体を付けた人は、40代の人がEIA価8、30代の人は125でした。
(まあ、バラバラという位の情報しかありませんね)
(2)齊藤さん:
月曜早朝出勤したら、7時20分位に新鎌ケ谷という駅で卒業生の齊藤さんとすれ違いました。随分早い出勤で大変だなと思いましたが、
”朝の誰もいない時、じっくり仕事に取り組むのが至福の時間”みたいで(いかにも齊藤さんって感じですが)、とても元気そうでした。
千葉県を出る機会は少ないようですが、皆さんも見かけたら声をかけて下さい、とのことでした。
(3)コーラ:
コーラはカロリーが高そうなので敬遠していましたが、昨日”ZeroSugar”というのを見つけました。(コーラは私が高校の頃日本に上陸したので青春の味って感じで)何となく懐かしく、2日間で4本も飲んでしまいました。人工甘味料も、随分自然な味になりました。オススメです。
(4)スポンジケーキの耳:
2,3ヶ月前、大久保通りにケーキ屋さんができました。夕方になると店先に、ケーキを作る時にできる(残る)スポンジケーキの耳(端の茶色い部分)がビニール袋に入って150円で並べられます。おいしそうだし、安いし、一度買って食べてみたいな、と思っていました。火曜日、店も混んでなさそうだったので、1つ取って店内のレジに並びました。並んでしまってから、ケーキを買わないで老人がケーキくずを持って並んでいるのは美しくないな、と思いましたが急にやめるのも変だし、学生さんに見られないといいな、と思いながら買ってしまいました。味はまあまあですが、耳の部分が薄いのでポロポロで食べにくい感じです。もう買うまいと思っていましたが、昨日また、チョコレートケーキの残りみたいなのを並べていて、これがまたおいしそう。誘惑と戦う日が続きます。
(2007/6/7)
今更禁煙のすすめ
2007 年 6 月 10 日
日曜日
(1)60歳近くで初めて分かったこと:
近頃、前の職場や学生時代のメールグループから頻繁に訃報が届く(昨年の感じでは3,4ヶ月に1回位の感じであった)。60歳近くなると、急にリスクが高まることを実感する。喫煙の習慣は寿命を約5年縮めるそうだ。特に、(女性より平均寿命が短い)男性に気付いて欲しいことは、30歳でほとんど人生の半分に来てしまっているということである。60はズッと先だ、なんて考えないほうがよい。年を取るほど時間が経つのが速くなり、気が付けば60って感じである。
(2)国民に尊敬される国にして欲しい:
日本のがん医療はアメリカに比べ20年遅れていると言われ、先進国で最も苦痛を強いられる国だそうだ。この度やっと「がん対策推進基本計画」の素案が出た。ただ、この計画案では、委員会が強く主張した喫煙率半減目標を、厚労省が削除したそうである。たばこ業界や、たばこの税収に配慮したものらしい(これって、薬害エイズやアスベストと全く同じ構図じゃない!何の反省もしてないんだ!)。目先の利益を重視し、多くの国民に苦痛と、将来に大きなつけを残すものである。オーストラリアでは喫煙率を減らすため、たばこのパッケージに喫煙がもたらす恐ろしい結果の写真を印刷させている(これこそが国民の命を守る政治ではないのか)。日本は、消えた国民年金を短命策で逃れようとしているのではないかと疑ってしまう。
(3)お医者さんのチェック項目を参考にしよう:
私は以前、胃の具合が悪くてお医者さんに行ったことがある。その時、お医者さんに先ず聞かれたことは”たばこを吸いますか?”であった。たばこは胃にも悪いんだ、と思った。
先週、夜よく咳が出るので呼吸器科の先生に診てもらった所、問診の最初に、現在の喫煙習慣だけでなく過去の喫煙経験まで細かく聞かれた。
(4)JT(日本たばこ産業株式会社)への提案:
(現在、JTホームページで)”弊社は、「喫煙者率の引き下げの数値目標」を設定することに強く反対します”、と(ダーティーな)宣言をしている。
JTは、技術部門もあるようなので喫煙習慣をやめさせる薬や食べ物の製品開発をした方がよい(早く発想の転換をした方がよい)と思う。テレビ新聞等で大々的に”私達の夢は、弊社たばこ事業部がなくなることです”位のことを言って撃って出た方が社会のためにも、会社自身の健康のためにもよいと思う。
(2007/6/3)