あなたは 3566 人目のお客様です。
雑記帳 by Furuya
The End ( 2008/03/29 06:07:50)
舞って桜
27日、上野と隅田川へお花見に行きました。上野は一応満開とのことでしたが、見た感じでは八分咲きでした。私は以前から、桜の花びらは散らなければ満点なのにと思っていました。27日の桜は、花びらが一片も飛ばず完璧でしたが、何か物足りない感じがしました。
そこで”桜は花びらがハラハラ舞ってこそ桜なんだ”と気付きました。”惜しむ気持ちも含めて美しいんだ”と。
メディア的に考えると、
桜以外の花は咲いている姿だけが花の”静止画像”であるのに対し、
桜は、舞う花びらも含めて花の”動画像”ということになります。
動画像の方が静止画像よりアピール度が高いので、桜が心に留まるはずです。
この動画と静止画のアイデア、デートやお花見に使えると思います(このサイトを読んでいる人は、ほとんどいませんから)。もし、恋人がこの話で感動しなかったら、風雅を理解できない人なので、早く別れましょう。
===
(突然ですが)おわりに
昨年の今頃、”夏休みまで続くかな?”なんて思いながら「雑記帳」を書き始めました。今回、皆様の関心に支えられ、年度末を迎えることができました。
同じパターンをいつまでも続けるのは”すさまじきもの(枕草子:興ざめするもの)”となる怖れがあるので、一旦、雑記帳を閉じることにしました。
長い間、ご協力どうも有難うございました。
==訂正==
終わりに当たり訂正があります。
m21のナイヤガラの写真で、(私の不案内で)\"カナダ側ナイヤガラ\"と書いてありますが、正式には”カナダ側から見たアメリカ滝”だそうです(ナイヤガラのプロからご連絡を頂きました、どうもありがとうございました)。
======
来年度は、ブログで再スタートすべく準備中です。最初は試運転って感じで始めますので、色々不手際がありそうですが辛抱強くお付き合い下さい。皆様の書き込みも期待しています。
URLは、
http://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/2008/blogn/index.php
の予定ですが。少なくとも、
http://www.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/
の2008年版HP、メンバーから辿れるはずです。
来年度も、よろしくお願いいたします。

n25 ( 2008/03/26 13:12:20)
花粉症
(1)今、図書館の3階で、人目を忍んで花粉の電子顕微鏡写真展が開かれています。いくつかの写真を撮影してきました。最もポピュラーなスギとヒノキは球形でそれほど悪いヤツに見えません。桜とピーマンは似ています。いかにも悪そうなカントータンポポとブタクサですが、私には影響ありません。
(2)2週間くらい前から本格的に花粉が飛び出し不快な日が続いています。
”マスクにガーゼをはさむとよい”というテレビ放送があったので、試してみましたが、なるほど、グー!です。ただ、息が苦しくて、昆明で高地トレーニングをしている感じです。
(3)母に、”花粉症なんだ”と言ったら、”生意気に!”という返事が返ってきました。昔の人から見ると花粉症は近代的でカッコよい症状のようです。昔は不潔なものを食べていたので、アレルギーにならなかった、と言った説もありました。
そう言えば、私10数年位前にピロリ菌の除去をやってから花粉症が発症するようになりました(因果関係はないと思いますが)。
(4)大学のバーチャルラボラトリというサイト
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/
には、花粉、アホウドリ、薬草など東邦っぽい色々な面白い解説があります。花粉に関しては日々の飛散状況なども掲載されています。お薦めです。
(5)花粉症対策:
(a)北海道物産展で売っている「ハッカ油」をマスクに点けるとよいそうなので買ってきました。
(b)クシャミが出たら、クシャミで喉が傷つき、喉から風邪をひくので、V3000ノンシュガーのど飴をなめます。
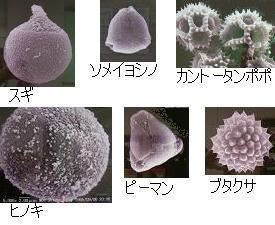
(
2008/03/23 06:10:24)
年度末
(1)チベット問題:
チベットの歴史を簡単にまとめると以下のようです。、
「チベットは1951年中国の支配下に入れられ、(一応自治区となっているが)チベット人は不利な扱いを受けたり、文化、生活、風俗が破壊され、これに反対し抵抗する動きは弾圧された。特に、1959年の独立運動では多くの犠牲者を出し、ダライ・ラマ等多数のチベット人がインドに亡命した。最近は鉄道開通で圧倒的資本力を持つ漢民族が多数流入し社会支配と差別が急激に進んで不満が爆発した。」
中国政府の頑固で容赦ない態度から察するに、また多数の犠牲者がでると思われ胸が痛みます。
パレスチナやバルカン半島周辺(セルビアなど)で延々と繰り返される民族問題、報復と不幸の連鎖は、このような形でスタートしたのだろうと思います。今ならまだ間に合います。新たに人類の不幸の種を撒き、育てることのないよう、中国政府に自制ある対応を望みます。
(2)桜開花(東京、静岡、など):
平年より6日早く、昨年より2日遅いそうです。1週間後が見ごろだそうで、楽しみです。。昨日(私は)は今年初めてモンシロチョウを見ました。
==
問題:写真は北習志野のホーム下のレールに出現した木の床です。何のために敷いたと思いますか?
夜間工事が行われ、自動車が入り込んだりするのだそうです。
また、以前書いた、新京成車内に週刊誌の中吊り広告がないのは私鉄グループの紳士協定によるものだそうです。

n23 ( 2008/03/19 11:11:39)
最後の春休み
卒業式を終えた春休みって少し空虚で、少しせつない思いなんかが残ってたりしますよね。
ユーミンの「最後の春休み」は、この感じをよく表現しています。ユーミンの曲の中ではあまりメジャーじゃないので知らない人もいるかと思い掲載します。
<一番の歌詞>
春休みのロッカー室に
忘れた物を取りに行った
ひっそりとした長い廊下を
歩いていたら 泣きたくなった
目立たなかった私となんて
交わした言葉 数えるほど
アルファベットの名前順さえ
あなたはひどく 離れてた
もしもできることなら この場所に
同じ時間に
ずっとずっと うずくまっていたい
もうすぐ別の道を歩き
思い出してもくれないの
たまに電車で 目と目が合っても
もう制服じゃない
==
メロディーもいいので是非聞いてみて下さい。
http://www.youtube.com/watch?v=rNVgH_jRuow
上のyoutubeのものは消されるかもしれないのでメロディーだけなら、
http://www.hi-ho.ne.jp/momose/mu_title/saigono_haruyasumi.htm
にも有ります。
===
レアルマドリッドの本拠地のサッカー場の写真を送ってもらいました。海外物が不足していますので送って下さい(特にしょっちゅう海外へ行ってる人)。ここにアップしておくと、すぐ見られるので好評ですよ。

n22 ( 2008/03/16 17:17:06)
卒業
14日は卒業式でした(卒業式にしてはめずらしく雨模様)。ご卒業、おめでとうございます。
今年の卒業生の特徴は、
(1)研究室を超えた大きな友達の輪ができていました。今月はじめ、夜行バスで関西へ(写真(上)の18人)団体卒業旅行に行ってきたそうです。
(2)先輩の大学院1年生とも交流があったようで、卒業式の後、プレゼントが贈られていました(写真下)。
(3)大学も気に入っていただいているようで、3月いっぱい大学へ出て来られる勢いです。既に、これから2回テニスコートが予約されています。
総括すると、よい仲間達と出会い、学生生活を楽しんだ、というところかと思います。大学も、よい場所を提供できてよかったと思います。
そうそう、
(4)村田君も博士を取られ卒業です。合計9年大学に席を置かれたことになります。
(5)卒業生の野里君(これから大学院へ進学)は、すぐ上のお兄さんが今年生物科の大学院出られ、一番上のお兄さんも本研究室で博士を取られているので、3兄弟優秀な成績で本学を出られたことになります。
東邦を愛していただき、大学としても嬉しいことです。
Bon voyage!(良き航海を!)

n21 ( 2008/03/12 06:43:38)
好文木(こうぶんぼく)= 梅
(1)中国の故事に
「文を好めば則ち梅開き,学を廃すれば則ち梅開かず」
(意味:学問を怠ると梅の花が咲かず、励むと花が開く)
というものがあり、梅は好文木とも呼ばれます。
水戸偕楽園の”好文亭”は、ここから命名されました。
写真左には好文亭がチラッと見えます。写真右は好文亭から見た偕楽園の庭です。
学問と言えば、
(2)菅原道真も梅が好きだったようで、九州へ左遷される時の、
”東風(こち)吹かば にほいおこせよ梅の花 あるじなしとて春を忘るな”
はよく知られていますが、これに応えてか、道真を慕って京都から飛んでいったという”飛び梅”も有名です。
また、
(3)泉鏡花の”婦系図(おんなけいず)湯島の白梅”では、先生(独和辞典編纂中の学者)が弟子(主税:ちから)に「学問を取るか婦(お蔦:おつた)を取るか」と迫ります。
主税がお蔦(元芸者で今は主税と同棲中)に別れを切り出した時の、お蔦のせりふ、
「別れる切れるは、芸者の時に言う言葉、今の私にはいっそ、、、」は涙をさそいます。
(昔はよくテレビで舞台中継ってのがあって、湯島の白梅などをよくやっていたのですが、今でもやってるんですかね?)
(4)私が行ったことのあるオススメ梅園
(a)つくば梅園(TXつくば駅下車バス約30分):梅が多い
(b)熱海梅園:よく手入れされている(もう今年は終わっているでしょう)
(c)水戸偕楽園(土日は特急臨時駅有り、上野から7、80分):園の下(千波湖の方)にも梅園を拡張しています

n20 ( 2008/03/09 06:27:04)
曽野綾子氏の”言い残された言葉”(光文社)
曽野綾子さんは、苛酷な家庭に育ち、空襲を生き延び、クリスチャンで、アフリカ、インドなど危険な地域でボランティアをしたり国際協力事業をしてきた人です。その人の話なので迫力があります。同意できない点もありますが、啓発されることも多く、お薦めです。かなり強引ですが、まとめてみました。
A. 人道主義は言葉でなく、態度で示せ。
口先だけで体裁のいいことは誰でも言える。危険覚悟の労働を提供したり、大金を寄付する覚悟のある人だけ人道主義を語れ。自分は何ら行動しない口先だけの人権主義者、理想主義者、平和主義者のきれい事が、日本の精神的骨組みを壊し、日本をガタガタ(犯罪の多発、経済破綻、など)にしている。
B. 現実離れした理想主義を振り回すな
(1)人間は平等だ、(2)平和を願えば平和が来る、(3)成せば成る、(4)誰にでも才能がある、(5)先生は完全だ、(6)初歩的ミスは起こらない、(7)人の命は地球より重い、
といったことを目標にするのはよいが、理想が現実であると誤解させてはいけない。
人生は不平等なものだし、才能は誰にでもあるものではないし、才能の無い人がいくら努力しても事は成らない。様々な事故は初歩的ミスによって発生するもので、これが無くなることはない。
不戦の決意で戦争はなくならない。不戦を叫ぶ人は、殺されても抵抗しない覚悟はあるのか。
C. 甘ったれた考えを許すな
(1) 人生とは理解され、誤解されることだ。誤解は常なので、その位の逆境に耐える力を付けることは必要だ。
(2) PTSD(精神的後遺症)は、自分で乗り越えるものだ(有って当たり前などど考えるな)。自分の心身の不調はすべて外に原因があるという軟弱な人になってはいけない。
(3) 公園を占拠するホームレスを合法とするのは、法を守ることは必要ない、と言っていることと同じだ。
(4) ”値上がりで老人が旅行もできなくて惨めだ”という様な発言はおかしい。外国にはお金がなくて修学旅行に行けない子供が5万といる。
(5) 自分の選んだ生き方、仕事、生活に責任を持て。
D. 日本人は精神の貧困に陥っている
(1)テレビが幼稚化して、(2)若者は本を読まず、(3)個性、勇気、気概などなく、(4)強烈な個性、輝くような知性を持った人がいない。
(5)自分の信ずるものに従って生きる姿勢がない。
(6)自分の行動が法律に抵触しないか、といった保身ばかり考えて、本質を考えようとしない。
(7)国際社会に対し無思想、危機感がなく、悪を学ぶことを怠っている。
(8)人は危険や冒険を冒さなければ何も得られない。
(9)自分で料理をし、みんなで会話をして食事をとれ。
E. その他
(1)事故の責任を他人や社会の責任にするのはよせ。
(2)プライバシー保護もいいかげんにせよ。プライバシーは公開されている方が安全なくらいだ。
(3)格差はあるのが当たり前で、昔の格差は今の比ではなかった。
(4)人は誰でも人に言えない怨念を持っている。
(5)スポーツ選手がもてはやされるが、スポーツより汚物処理の仕事のほうが大切だ。
(6)世の中に”全て正しい”などというものは無く、物事には必ず良いところがあれば悪いところもあることを常に考えなくてはいけない。
(7)善にも意味があるが、悪にも意味があることを理解する強い性格になれ。
==
道後温泉本館と旅の一行
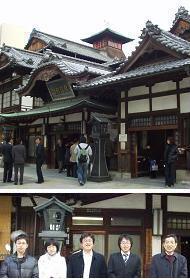
n19 ( 2008/03/06 12:37:06)
サーバーダウンで一日遅れました。このサーバー、私がいない時に限って落ちます、不思議。
===
松山
学会で石田さんと野里君が発表するので、松山(道後温泉)に行ってきました。
(1)約30年ぶりの松山です。道後温泉本館とお堀のアヒル小屋は昔のままでした。
(2)日露戦争で活躍した秋山兄弟の生誕地に行ってきました(写真左)。秋山好古氏は東邦大習志野キャンパスの場所に連隊を作り騎馬隊の訓練をした、という話は以前書きました。
(3)写真右は最近の有名人、友近さんの出身校(松山東雲:お城の様な入口がある)です。
(4)万葉集の有名な、
”熟田津(にぎたづ)に船乗りせむと月待てば潮もかないぬ今は漕ぎ出でな”
は、戦(いくさ)か遣唐使の旅立ちの歌かと思っていましたが、道後温泉に出発する時の歌だそうです(ガク!)。
(5)(サンプル数は少ないのですが)松山の人は老いも若きも教養と郷土への誇りと自信があるようで、話がしっかりしていました。主語述語、起承転結が、きちんと語られ、言葉を大切にしているように感じます。街には句碑が沢山有るので、その影響かとも思ったのですが、元々そのような風土があって”正岡子規”が誕生したのかもしれません。
(6)坊ちゃんに出てくる”〜なもし”という方言が聞けないので、お店の人に聞いてみたら、
”そんなのは今の鹿児島の人が 〜デゴワス と言わないようなもので、親の世代でも使いませんよ”とのことでした。方言の文化も大切にして欲しい、一寸残念です!
(7)約30年前、道後温泉に行ったのも学会発表で、その時は同僚の山口さん(現、筑波大教授)と一緒でした。今回、一緒に行った筑波大の学生さんの博士論文の副査が山口さんだそうで、ほんの少し不思議な縁を感じました。
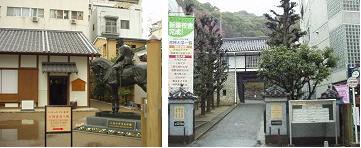
n18 ( 2008/03/02 06:19:24)
裁判員制度
ロス疑惑が再燃し、陪審員制度がよく話題になっている。日本でも、それを真似た裁判員制度が来年から始まるらしいが、やめて欲しい。
(1)人を裁けるか?:マグダラのマリアへの石打ちの刑の際、キリストの
”あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、 まず、この女に石を投げなさい”
という言葉が浮かんでしまう。
特に重罪を裁くらしいので、裁いたことが心の傷となり、裁判員を罪の意識が苦しめるケースが出てくると思う。
(2)裁判員は大丈夫か?:裁判員は無作為に選ぶらしいが、裁判員にふさわしくない人が選ばれて他のメンバーに悪い影響を与える場合が考えられる。私のアメリカ滞在わずか1年の間に、陪審員になれという手紙が来た。そこには理由なく出廷しないと、、、とか書いてあった。私は外国人で、、、とか辞退願いを書いた。こんなのでいいの?
(3)所詮素人:所詮素人には判断ができず、裁判官の導きで答えをだすしかない。また、素人は弁護士の誘導に惑わされることが少なくない。弁護士の能力で判決が大きく左右される裁判には疑問を感じる。お金のある人が優秀な弁護士を雇い、刑をまぬがれる話は有名である。
(4)西部劇世代の者としては、何だか昔に戻るようで違和感がある。劇中ではよく、犯人からの仕返しや脅迫の話も取り上げられていた。
==裁判に関する聞きかじり==
(1)昔、裁判官の友人から聞いた話
(A)裁判官はかっこよい職業と思うかもしれないが、毎日人間の最も醜い部分ばかり見ざるをえないのでいやになる。
(B)しばしば、時の権力寄りの判決が問題になるが、政府の方針を否定してしまうと世の中の秩序が保てなくなるので、やむを得ない。
(2)地方裁判所の裁判に立ち会ったことのある人の話
(A)本当に世間知らずな裁判官もいる。
(B)裁判官は大病院のお医者さんのように分刻みで次々と裁判を行っている。
===
我が家の雛人形は、ここ10年以上、内裏雛だけが飾られている(内裏雛とは、カップルのことで、”お内裏様とお雛様、2人並んで、、、”という歌は誤り)。

n17 ( 2008/02/27 15:16:39)
新京成線
前回、子牛が侵入した新京成線ですが、新京成の楽しみを紹介してみます。
(1)子牛が侵入した日の帰り、また急停車しました。”また牛か?”と思ったら今度は”自転車が踏み切りに入ったため停車しました”とのこと。特に最近よく踏切りへの人の侵入で急停車します、のどか!
でもスリルを味わうこともできます。
(2)初富駅は構内に踏み切りがあります(写真)。改札(左の建物内)を通った人はこの踏切を通ってホーム(右)にたどりつきます。津田沼行きの電車の先頭は、この手前に止まります。たまに止まりかけの電車の前を、閉まりかけの遮断機をくぐって滑り込もうとする人がいます。そのような人はあわてているので、線路の上あたりでよく転びます。電車がまだ停車していない2,3m先で線路に横たわるのは勇気がいります。
ソフト面でも充実しています:
(3)最近、上品な車掌さんがデビューしました。彼は、車内放送で次の駅を紹介する時”次は〜〜ドス”と言います。京の雅を感じます。
(4)他の路線より明らかに優れているのは、週刊誌の中づり広告がないことです。車内はさわやかです。広告を出す出版社がないのではなく、会社の見識だろうと想像しています。
線路にも特徴があります:
(5)くねくね曲がっています。これは戦時中爆撃を避けるためだ、とか、戦時中の運転練習路線だった、とかいうのを聞いたことがあります。線路に油をたらして摩擦を減らす車両もあるようです(本当?)。
(6)線路幅は広軌と言って新幹線と同じ広い幅です。京成線も広軌で、相互乗り入れをしています。広軌は世界標準で、元々はローマ時代の馬車の車輪の幅です。
==
メモ:24日(日)春一番というか砂嵐(昨年より9日遅い)。
==

n16 ( 2008/02/24 05:14:22)
星(太陽)の子
久しぶりでお薦めしたい本に出会いました。あのホーキング博士親子が書いた”宇宙への秘密の鍵(岩崎書店)”です。
小学校高学年向きのスペースアドベンチャーですが、大人が読んでも十分楽しい本です。冒険物語の中で宇宙を紹介していく仕組みになっています。本の中で面白いと思ったアイデアなどを紹介してみます。
(1)私達は「星(太陽)の子」:星(太陽も星の一つ)の中では小さな粒子がぎゅっと押されてものすごい量のエネルギーを放出しながら融けあったりつながったり(核融合)しています。これで原子ができあがり、星が最期に爆発して、宇宙に大放出されます。これが我々の体を作っている原子です。ですから我々は元々太陽の様な燃える星の中で生まれた部品でできあがっている星(太陽)の子ということになります。(どうりで熱いヤツがいたり、太陽を拝む人が出てくるはずです!)
(2)ブラックホール:星が最期に大爆発を起こす時、超高圧で中心部に押し込められたものがブラックホールになります。非常に強い重力を持っていて光も吸い込まれてしまいます。かつて、ブラックホールへ落ちたものは永久に戻ってこられないと考えられていました。しかし、最近ブラックホールは何百億年もすると消滅し、吸い込まれたものは素粒子に戻って放出される、と考えられるようになりました。
物語の中でチャーミングなコンピュータ(コスモス)が出てきます。
(3)コスモスの特徴:人を見て挨拶をする。空中に宇宙を見る窓を作る。そこから宇宙に入り込める。こちらに飛んできた物体はモニタ画面にぶつかって音をだす。感情を持つ。盗まれると”助けて”と言う。本を一気に読みこむ。
(私のコメント:本に、内容を全て記録したチップを埋め込んでおくと本の中身をコンピュータに読み込むことができていいな)。
(4)余談:物語にはブタもでてきます。この本を新京成の車内で読んでいて、物語が、現実と空想の世界が入り組んだハラハラする場面になった時、電車が急停車し、”子牛が線路に入ったため停車しました”という放送がありました。一瞬自分が本当に現実の世界にいるのか混乱してしまいました。
==
彗星に乗って(英語版の表紙から)
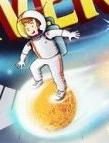
n15 ( 2008/02/20 10:42:18)
太陽のずっと先
俳句のテレビを見ていたら太陽に関する面白いアイデアが紹介されていました。
”(普通我々は、)太陽は遠い所にあり太陽のズッと後ろの方のことを考えることはないが、
半年後に我々は太陽の向こう(今の反対)側の、現在の場所と太陽の距離の2倍離れた所にいっている”
という考え方です。
地球が太陽の周りを回っているので当然ですが、”半年後には、あの向こう側にいるんだ”なんて太陽を見たことはありませんでした。
地球と太陽の距離は約1億5千万kmで、光でも8分半かかるの距離なので、半年で太陽の向こう側に行くには相当の速度で移動しなくてはならないな、と思い調べてみました。
すると、地球は時速約11万Km(秒速約30km:音の速さの約100倍)でブッ飛んでいることが分かりました。マラソンの距離なら1.4秒で通過します。
(光速が秒速約30万Kmですから、地球は光速の1万分の1という高速でブッ飛んでいます:見方を変えると光って意外と遅いんです)
これは、公転速度なので、ついでに自転による速度も調べてみると、日本では約1400km/h(秒速約388m:音より少し速い)でした。
ついでですが、地球が太陽から受けるエネルギーは、太陽の発するエネルギーの約22億分の1だそうです。
==
恒例(ほぼ毎日)の昼食クッキング風景(左に立っている男性はジャガイモとニンジンの皮をむき、手前の男性はカレーをかき混ぜ、右の女性達はうどんを食べています)。注目すべき点は、卒研発表が終わってからも続いていること、他研究室の人達が多いこと、です。

n14 ( 2008/02/17 07:06:05)
博士・卒研発表
14日大学院研究発表
15日卒研発表
大学院の方では、村田君が博士論文を発表しました。発表後の審査会も通り、博士内定です(あと、教授会での私の報告が残っていますが)。おめでとうございます。また3月にはマイコンクラブの先輩と華燭の典をあげられるそうで、重ね重ねおめでとうございます。
卒研の発表も無事終わりました。3セッションパラレルで1人9分(発表6分、質疑3分)でしたが、9時半から5時近くまでかかりました。気づいた点は、
(a)”楽をしてるな(させてるな?)”と思う研究が増えているように思います。中にはよくやっている研究もありますので、卒研も2極化しているのかもしれません。
(b)3年生の見学が例年より少し少ないように思いました。毎年就活時期が早まり、今ちょうどピークの時期なので、会社から呼ばれてしまっているのかもしれません。
今後の予定:2月は、
2月20日大学院修士1年生中間発表
2月25日大学院入試
2月27日教授会での博士審査結果報告
3月は、
3月1日信学会東京支部で野里君発表
3月5日情報処理学会(松山)で石田さん、野里君発表
3月14日卒業式
この間、基本的には毎日大学へ出るつもりですが、少し不確定要素がありますので、御用の方は予めご連絡下さい。
==
卒研発表風景

n13 ( 2008/02/13 17:29:44)
平成19年度NHK全国俳句・短歌大会
私は、父の句集作りを毎年手伝っている関係で、俳句と短歌に少し興味を持っています。
NHKでは毎年、全国俳句大会と全国短歌大会が開かれます。大会では特選作品が紹介され、その中から大賞が選ばれます。
(1)この日曜日に今年度の俳句大会の放送がありました。私が最も気に入ったのは次の作品です(大賞ではありませんが)。
待つことの長いこと 君待てば雪
この句は575というより、5552という構成で、これにより物語性が出ていて魅力的です。
次も大賞ではないが、芭蕉を彷彿とさせる秀作です。
なかんづく 二月の風の 二月堂
(2)平成19年度NHK全国短歌大会特選の中から私の選んだ2首。
源氏謡ふ晶子の声が流されてホールの百の心臓ふるふ
(与謝野晶子の声が聞けるDVDがあるらしい)
風呂場より走り出でたるゴムマリの女孫の髪を拭きやるたのし
(でたよ〜!なんて女の子が駆け出してくるのが目に見えるよう)
(3)父の句集の今年度の優秀作品はつぎのものでした。
落葉降る ひとりひとりに 径岐れ
(ねんりんピック茨城2007俳句交流大会賞)
春雷や 父の怒りに 似てをりし
(平成19年度NHK全国俳句大会入選)
(父が体調を崩し一部の方にご迷惑をおかけしています、すみません)
==
この冬最寒の日が続いています、少しは暖まるかとニュージーランドの羊です。

n12 ( 2008/02/10 06:30:02)
雑学
(A)最近知ったコンピュータの雑学
(1)データベースで有名な ORACLE には、神託とか預言者という意味がある。
(2)スパムメールの SPAM とは、豚の缶詰の名前である。イギリスにSPAM、SPAMと連呼するコメディーがあり、連呼が大量コピーそして迷惑メールに関連付けられた。
(3)最近の携帯電話のプログラムは500万行、自動車に内蔵されているマイクロプロセッサのプログラムは700万行にもなる(想像もしたくない量ですね)。
(4)昨年、首都圏の鉄道各社の自動改札機がいっせいにストップしたのは、約80万行のプログラム中の1行に ”+ offset”という変数の加算を書き忘れたため(プログラムをしていると、よくあることなので身につまされますね)。
(5)電車内の高校生の話によると、携帯にメール貯まると(重量が)重くなる(そうです)。
(B)学生さんのボキャブラリ増加に役立ちそうなIT用語
(1)iPodのPodは、元々えんどう豆などのサヤの意味で、小さな袋って意味。
(2)ブラウザは、家畜が若芽を貪る(browse)から来た言葉で、拾い読みする、の意味。
(3)JavaのEclipse(エクリプス:自動車の名前にもなっています)は、日食、月食の”食”って意味で、他を陰らすという意味。
(4)ディレクトリ(directory)は、住所氏名録や電話帳という意味。
(5)ビスタ(Vista)は、展望とか見晴らしという意味。
(C)ITと関係ないけど
(1)亀レス:亀のように遅いメールの返事。
(2)スリッポンとローファー:学生さんに高校生がよく履いている紐なし靴をスリッポンと言った(昔はそう言った)ら通じないので、絵を描いたら、”それはローファーです”と言われた。
調べてみたら、スリッポン(Slip-on)は靴紐のない靴の総称で、その中の一つがよく学生靴になっているローファー。ローファー(loafer)は、怠け者の意味で、元々は商品名だった。
(3)ケンタッキーフライドチキンは、関東で「ケンタ」、関西で「ドチキン」、九州で「ケンチキ」と言う(らしい)。
==
研究紹介: 普通、コンピュータ(PC)は、PC内に入り込んでしまったウイルスをソフトウエアで検出する。これに対し本研究は、インターネットとPCの間に特殊なウイルス検出装置を置き、ウィルスをコンピュータの中に入れないようにするものである。FPGAを用いて、ハードウエアによる高速ウイルス検出、新種ウイルスへの柔軟な対応、暗号化などを実現している。
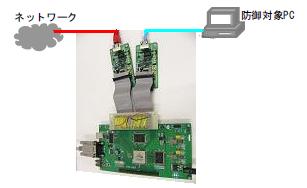
n11 ( 2008/02/06 15:16:21)
ゆき
今日は入試で、小雪が降り続いています。私も某大学を受験した時、雪だったことを覚えているので、今日の受験生にとっても一生の思い出かもしれません(良い思い出になってくれるとよいのですが)。
日曜日(3日の立春)にも雪が降ったし、先週も2度降った気がします(温暖化による多雪?)。
雪について:
(1)教訓:高校の合格発表日は雪でした。受験票を2つ折(V字型)にして、V字の上を下(∧)にして胸の内ポケットに入れて家を出ました。駅までいって受験票を落としたことに気付き、家までの道を戻って探しました。雪が積もってほとんど見えない状態の受験票を、幸い発見できました。紙を2つ折にした場合はVの字の尖った方を下にしてポケットに入れないと、歩いている間に少しづつ上にあがり、落ちてしまうことがあります。ポケットに折った紙を入れる時は方向に注意しましょう。
(2)私の胃は、精度の高い降雪センサで、雪の降る前日には必ず痛くなります。当然、昨日も痛みました。
(3)私が子供の頃は、よく大雪が降り、松林をぬけて古墳でスキー(板すべりに近い)をしました。松林では、松の枝から時々雪の塊がザザーと落ちてきて子供心にも感動しました。
(4)万葉集に、天武天皇と藤原夫人の心温まる遣り取りの歌があり、雪が降ると思い出します。
わが里に大雪降れり大原の 古りにし里に降らまくは後(のち)(天武天皇)
(こっちには大雪降ったけど、貴方のいる田舎じゃ降るのはもう少し先だね)
わが岡のおかみに言ひて降らしめし 雪のくだけし其処(そこ)に散りけむ(藤原夫人)
(私が神様に頼んで降らせてもらった雪の破片がそっちに飛んでったみたいね)
(注:大原は京都の大原ではなく、奈良の小原)
===
写真はチェコの世界遺産「チェスキークロムコフ」の雪景色です。13世紀から世界大戦の頃まで、銀や魚の養殖で繁栄した美しい城下町です。街にはゴシック、ルネッサンス、バロックのアートが積み重なっています。大戦のドイツ侵攻で廃墟になりましたが、現在復元が進んでいます(NHK世界遺産の受売り)。写真下の方はモルダウの蛇行らしい(モルダウも蛇行するんだ!)。

n10 ( 2008/02/03 05:48:02)
Java & Mac
1.卒研Java:
”卒研Java”という怪しげな冊子を作りました(写真)。実験Iの私の分(中級Java)が今年度で終了するので、今までの実験資料や卒研によく使うJavaプログラムを一冊にまとめました。
(a)中級Java(実験I資料:卒研プログラムの型紙に便利)
(b)Javaによるピクセルレベルの画像処理
(c)COMポートプログラム(RS232Cのシリアル通信)
(d)USBIOプロラム(USBに自作ハードなどの低速IOを接続できる)
(e)JMFプログラミングマニュアル(JMFマニュアルのカメラ映像処理部のみ)
関心のある方は、メールまたは直接来てもらえれば差し上げます(どちらかと言えば、もらって下さい、って感じ)。ただ、解説書ではないので説明が不十分な点は多々あります(質問は歓迎です)。
2.帰ってきたMac:
昨年Vistaマシンを購入しましたが、メールで字化けが起こり、その日のメールが全て読めなくなるというトラブルに見舞われたため、マシンを学生さんの部屋に放出しました。
現在使用中のXPマシンはそろそろ寿命なので更新したいのですが、今更 XP もないだろうしVistaもまだ心配だなと思っていたら、アップルがMacOS X(Leopard)を出したので、10年ぶりでiMacに飛びつきました。
使い始めてみると、色々問題もあります。
(a)文字が小さく、目が疲れる。(画面のピクセル数で字を大きくするとボケる)
(b)モニタ画面が反射するタイプなので背景が写り、見にくい。
(c)文字コードを意識しなくてならない。
でもよい点もあります。
(a)タイムマシンで過去の好きな時点の状況に戻れる。
(b)スペースという機能でデスクトップを4種類切り替えられる。
最初からMacに付いてくるアプリは使いにくい点が多く(文字が小さかったりWindowsとの情報交換が不便)、今、環境を整えていています(基本アプリの全とっかえ、って感じ)。昔Macを使っていたので愛着もあり何とかなりますが、Windows全盛の世の中で、初めて使おうとすると苦労が多いと思います(Mac愛用者は意外と年長者が多いのではないか?)。

n9 ( 2008/01/30 17:26:48)
卒論の謝辞
今日は卒論提出締め切り日、当研究室はおかげさまで全員無事提出できました(発表は2月15日です)。
卒論の”謝辞”は、形式的に数行書くのが普通で、書くほうも、読むほうも、軽く流してしまうパートです。
(1)過去には、ごく希に、友達への感謝をしっかり書いたものもありました。
-----
謝辞
この研究を進めるに当たりX教授をはじめ、同研究室のA先輩、B君、C君、D君、E君、F君には、感謝しても感謝しきれない程、大変お世話になりました。また、他研究室のG君、H君にも随分とご迷惑をおかけしました。みなさんお忙しいにもかかわらず、毎日質問を浴びせかける無知な私にBP法、C言語、UNIX、研究方法、TEX、その他様々な事を御親切、丁寧に教えて下さり、本当に有難うございました。すばらしい人々と充実した機器に囲まれたX研究室での1年間は、私にはもったいないような恵まれた環境でした。ここに、厚くお礼申し上げます。
-----
(2)今年は、ご両親にも感謝の言葉を添えている謝辞がありました。
-----
謝辞
・・・・・略・・・・・・・・。
・・・・・略・・・・・・・・。
最後に、研究生活、下宿生活を応援してくれた両親に感謝したい。
-----
勉学をサポートしてくれた両親に感謝するのは立派なことだと思います。
(恥ずかしながら)私の場合で言うと、自分の子供が大学を卒業するまで、私は自分の力だけで大学を卒業したような気になっていて、親に対して感謝の気持ちを持ったことはありませんでした。
(3)今年は謝辞に関してこんな会話もありました。
-----
学生A: 先生、私はY先生にもお世話になったので、謝辞に書こうと思うのですが、Y先生に断った方がいいですかね?
学生B: 感謝するのに断る必要はないじゃん。
学生A: もしかすると、”断りもなく、勝手に感謝すんじゃネーヨ!”って思うかもしれないじゃない。
(笑、笑、笑)
-----
===
写真は、今年の卒研「全景写真合成(素敵、くっつけ画像!)」(複数のデジカメ画像をつないで大きな画像を作る研究)で合成した画像です。右の画像はカメラが少し傾いて撮ってしまったものです(意図的ですが)。2枚をつなぐため、右の画像に回転アフィン変換をかけているので少し画像が劣化しています。

n8 ( 2008/01/27 07:14:54)
百人一首
10日の暗記期間を経て、名人に挑戦しました。名人は、さすがでした。私は、上の句から下の句を想起する練習をしたのですが、それでは駄目で、最初の数文字から下の句を想起する必要がありました。
ゲームは約5名で行ったのですが、驚いたのは、プチ名人が何人もいたことです。東邦の学生の教養レベルを再認識しました。
百人一首の勉強で、和歌に関する色々なことを知ったのは収穫でした。
1:かささぎ(伝説):沢山のかささぎが翼を広げて天の川に橋をかけ、織り姫を彦星の方に渡した。
2:雲の通い路(伝説):雲の上には鳥や月や天女が通る空中の道がある。
3:澪標(みおつくし):船に航路を示す杭(高校の文学誌名だったのでどんなものなのか気になっていました。下図左で、大阪市のマークにもなっています)。
4:小倉百人一首:藤原定家が宇都宮蓮生の小倉山山荘のふすまに貼る色紙として選んだもの。
この時、定家は70を超えていたはずだし、蓮生も高齢で僧侶であるとすると、何でこんなに恋の歌が多いのか疑問(あやしい?)。
5:しがらみ:川に杭を打ち、そこに木の枝などを結んで、流れをせき止めたもの。
6:歌枕:和歌に詠み込まれた地名。
7:花筏(はないかだ):小川などの水面に落ちた桜の花びらが、筏のように連なって流れる様(下図右)。
8:和泉式部:”とどめおきて...”が有名なので暗いイメージを持っていたのですが、情熱的な女性だったようです。
”もの思えば沢のほたるもわが身より あくがれいづる魂かとぞ見る”
(あの人のこと考えると、蛍さえ私の体を抜け出した魂って感じだワ。アツ!:これは百人一首の歌ではありませんが)
9:(一寸怖いけど)笑えるもの:
”忘らるる身おば思わずちかひして 人の命の惜しくもあるかな”
(私は捨てられてもいいんだけど〜、”神に誓って愛してる”なんて言ったバチが当たって命を落とさないといいけどネ。コワ!)
==
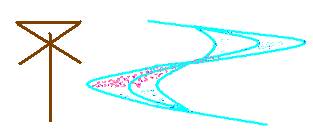
n7 ( 2008/01/23 11:47:02)
ペーパーレス生活
私の住んでいるあたりでは、新聞の契約競争が盛んで、石鹸を持って来たり、ビール券を持ってきたりで、1年先位まで契約を迫ります。大新聞社が、こんなことやっていいのか疑問に思います。しつこい勧誘に閉口することも少なくありません。
今月から我が家には新聞が来ていません。最初、新聞がないこと違和感がありましたが、最近は慣れ、ペーパーレスで熱帯雨林保護に貢献しています。以前、我が家は(贈り物攻勢の)新聞契約を甘受してきたため、朝日、読売、毎日を繰り返していました。2、3年前、(何だか思い出せないのですが)朝日の主張が納得できず、朝日をはずし、読売、毎日のローテーションになりました。ところが、最近、今度は読売がおかしくなり、やたら”政界の大連立”を主張します。こんなにしつこく主張をする新聞では記事まで偏ったものになる可能性があると思い読売をやめました。新聞は、事実だけを淡々と伝えてくれればいいのですが。
1:新聞を断る方法:”おたくの新聞の主張とは考え方が違うのでやめたい”と言うと、簡単に諦めてくれます。今度、しつこい勧誘があったら使ってみてください。
2:新しい新聞:日本の新聞は国内の事柄に関する記事が大半を占めています。もう少し世界の中の日本という立場で紙面づくりをする新聞が欲しいと思います。あまり、国内ばかりを見ていると、自分の位置づけが分からなくなります(最近経済は日本の一人負け状態のようですから)。
世界の新聞の紙面を分析し、記事バランスを作る研究もありそうです。
3:広告配布ビジネス:新聞が来ないと近所の安売り情報が入ってこない問題があります。新聞に折り込む宣伝ちらしだけを配るビジネスも有り得るんじゃないかと思います(現在、新聞にちらしを折り込んでもらうのが無料だとしたら成り立ちませんが)。
==
写真は科学博物館にあったシロナガスクジラの実物大オブジェです。また、捕鯨妨害のトラブルがあったようです。Yahooの意識調査では日本人の90%が捕鯨賛成だそうで、一寸驚きました。テレビや映画で動物ものに感動して涙を流している日本人って多いと思うのですが。テレビで捕鯨船からモリを発射するシーンを見ると胸が痛みます。

n6 ( 2008/01/20 05:52:32)
大相撲
春場所が始まりました。先場所は空席ばかり目立ちましたが、今場所は観客が戻ってきたようです。先日NHKニュースで、朝青龍の謝罪会見と今場所初日の取組みをトップニュースで流していました(そんな大きな話じゃないでしょう)。マスコミは朝青龍の一挙手一投足に食い付いていて一寸異常だと思います(日本人が怖くなります)。
==
相撲と私(くだらない昔話です_o_)
(1)松登(まつのぼり):
私は、3歳まで松戸に住んでいたのですが、当時、近所の炭屋さんで働いていた若者がやがて松登という力士になり大関まで出世しました。私は入門前の松登にダッコしてもらったことがあるそうです(自慢になるのか微妙ですが)。
(2)始めての相撲観戦(多分小学校2,3年):
当時はテレビもなく、相撲はラジオで聞いていました。初めて蔵前国技館に行く前日、私は父に相撲はマス席で見るんだ、と言われました。その晩、私はマス席で観戦している夢を見ました。それが下の写真左です、そしてこれが私の覚えている最古の夢です。
(3)若乃花物語(最近の若乃花のおじさん):
小学校の頃、スポーツ系有名人の伝記映画がはやり、若の花物語とか川上哲治物語とかを見に、祖父に連れて行ってもらいました。若乃花は、貧しい石炭の積み降ろし人夫から頑張って横綱になる話で、自分も頑張らなくては、って思ったものです。船と岸壁をつなぐ細い板の上を石炭を運ぶ姿は今も覚えています。若乃花物語なんていうマンガもはやりました。(今も、スーパースターの伝記映画とか伝記マンガってあるんですかね?)
(4)朝潮(先代)
当時の小学生はほとんど若の花ファンだったのですが、私は例によって(弱い方を応援するので)朝潮を応援していました。朝潮は奄美大島出身で顔がでかくて胸毛があって強い時は強いんですがもろい所がありました。それでも横綱まで出世し最盛期は若乃花といい勝負でした。
http://sumo.goo.ne.jp/kiroku_daicho/mei_yokozuna/asashio.html
(5)相撲カルタ
今もあるのかどうか知りませんが相撲カルタや野球カルタがあって完全に暗記していました。百人一首に比べると語呂もよく何と覚えやすかったことか。藤原定家は、わざと口がまわりにくい和歌を選んだんじゃないかと思うくらいです。でも頑張っています。
(6)小学生に相撲を
昔は小学校の休み時間、みんな裸足で校庭に駆け出し、丸(土俵)を描いて、その周りに並んで、勝ち抜きで相撲をとったものです。子供の頃に思い切って力と力をフェアにぶつけあう機会は必要だと思います。体全体によるコミュニケーションができ、痛みが直接分かり、転んだ時の体の反射(受身)も自然に身に付きます。小学校で是非相撲を復活して欲しいと思います。
(7)格闘技じゃない
最近相撲は格闘技のように見られているようですが、以前は格闘技じゃなかったんです。”力と技の遊び”というのが適当な気がします。フランスの詩人が”相撲の立会いはバランスの奇跡”と言ったそうですが、さすがです。格闘技化したのは、重量級の外国人力士の登場と相撲経験のないマスコミ関係者の誤解によるものだと思います。
(8)さいごに相撲改革案
(a)土俵を拡げる:日本人の体格が向上し、大型の外国人力士も増えているので、土俵の直径を1m位大きくした方がよいと思います。これにより力より技の占める比率が増えると思います。
(b)マス席を拡げる:マス席は狭すぎます、4人で行ったらエコノミー症候群になりそうです。縦横それぞれ1.5倍(面積約2倍)にすべきです。
(c)値段を下げる:マス席4人で(おみやげ無しで)4万円位するらしいので、半額位にして、会社の接待用に頼らず、若い人達が気軽に楽しめるようにする。
(d)おみやげに工夫を:私が子供の頃は相撲のお土産が楽しみでした。私の祖母はお土産を親戚に分けるのを生甲斐にしていました。最近行ったことがないのでお土産はどうなっているのか分かりませんが、まずいチョコレート、黒焦げの焼き鳥は健在でしょうか?
(e)立会いの前にポーンと音を鳴らす:飲み食いしている間に勝負が始まって、ワー!とかいう声で土俵を見るともう終わっていたりするので(単なるノンベの我侭ですが)。
==
写真右は食器棚の奥に残っていた昔の相撲みやげ(湯飲みの力士名は左から:北の湖は現理事長、朝汐はパイロットシャツの親方、貴乃花は皆の知っている横綱貴乃花のお父さんです)

n5 ( 2008/01/16 12:04:14)
成人の日
成人式のトラブルもあまり無かったようです。沖縄で少しあったようですが、沖縄の若者は”目立とう”というのがメインらしいので、いっそ、ヨサコイ祭のように”成人式祭”とし(派手な衣装、髪型、化粧を競う)イベントとして観光に役立てたらどうでしょうね。
3連休でしたので、上野へ”ロボット博”を見にいってきました。
科学博物館(ロボット博)
テレビで紹介されていた範囲内で、特別印象に残るものはありませんでした。
科学博物館は何十年ぶりで、中が完全に変わっていましたが、フーコーの大きな振り子は相変わらず動いていました。また、館外にはシロナガスクジラの実物大の模型が飾ってあり、あまりの大きさに(大きい命も小さい命も一つの命には変わりない、とは言え)捕鯨は残酷だと思いました。昨日オーストラリアで捕鯨を違法とする法律が通ったようです。頑張って捕鯨を続ける必要あるんでしょうか?
ついでにお隣、国立博物館の「宮廷のみやび―近衞家1000年の名宝」を見てきました。
感動的だったのは、藤原道長の日記です。
理由1:展示されていた部分は1007年と1008年の部分で、ちょうど1000年前のものです。
理由2:道長と言えば、
”この世をばわが世とぞ思ふ 望月の欠けたることもなしと思へば”
が有名で、傲慢で豪放磊落なイメージを持っていましたが、日記の文字を見ると(私の判断では)几帳面で繊細な人という感じを受けます。後世の絵画では下膨れの太った人、といった感じですが、実際にはどちらかというと痩せていて策を弄するタイプではないかと思いました。
写真は、その日記の一部です。”沐浴”とか”大歳位”とあります。平安貴族はたまにしか体を清め(洗わ)なかったと聞いたことがあります。また、”大歳位”とは、大安とか友引とかいうような暦の日和の一種のようです。占いは重要な要素だったことが窺えます。
展示には藤原定家の書もありました。偶然でしょうが、先週金曜研究室で、百人一首がらみの一寸した出来事がありました。卒研生の中に百人一首に精通した人がいて、百人一首のカルタを持ってきたのですが、誰も挑戦しなかったので失望されていました。
よい機会なので、昨日マンガ百人一首の本を買って暗記を始めました。車内片道10首を目標にしていますので、来週末には挑戦する予定です。
ロボット博より、ついでに入った宮廷のみやび展の方が収穫でした。お薦めです。
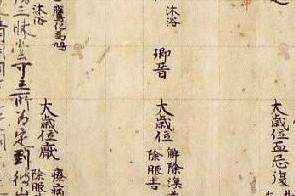
n4 ( 2008/01/13 06:44:53)
卒研もいよいよ終盤(締め切り1月30日)
これから時々、分かりやすくて興味を持ってもらえそうな卒研を紹介します。
第一弾:乗っている電車のスピードを測ってみよう
(1)動機
新京成で電車が鎌ヶ谷大仏駅に進入する際、運転手さんが下手だと乗客は”バン”と横に跳ばされます。一度女子高生が尻餅をついたこともありました。そこで、運転技術を計測できないかと思い研究をスタートしました。
(2)道具立て
パソコンに加速度計と方位計を接続して加速度と方位を測定します。
(3)実測
今まで建物内での実験を行っていましたが、今回、実際に電車に乗って(京成大久保―実籾間で)計測を行いました。写真左が計測風景で、キーボードの上に、方位計と加速度計が乗っています。
(4)結果
写真右が2駅間の加速度と速度の変化で、最初速度が急激に上がった後、徐々に減速するフェーズに入り、やがて急激に減速して停車しています。
(加速度を少し加工(積分)すると”速度が求まります)
(5)評価
私は毎朝電車の一番前で、運転操作を観察しているので、運転の手順を熟知しています。
運転手さんは発車するとすぐ電気を最大に入れて加速し、しばらく行くと電気を完全に切ってしまって惰性で走ります。その後駅が近くなるとブレーキをかけます。
計測結果を見ると、その様子がよく分かります。最初に加速(電力フル投入)し、後に単調減速(惰性走行)、最後に急速減速(ブレーキ)しています。ブレーキをかけている部分はガタガタした線になっていて、停車位置を予測しながら調整している様子(心の動き)もよく分かります。
(6)今後
運転技術は要約すると”加速後に電気を切るタイミング”と”ブレーキのかけ方”ということになります。今後新米運転手とベテランの違いを調べてみたいと思っています。
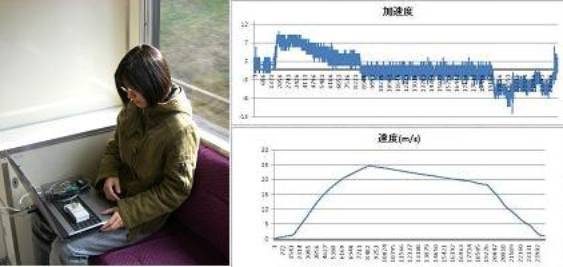
n3 ( 2008/01/09 17:39:37)
運、他:
解答:前回の世界不思議発見、正解は(写真提供者に確認したところ)”椅子が床に固定されていない”だそうです。
訂正:昨年末の写真の地名カンク―ンは、”カンクン”が正しいそうです。
冬休みの成果(Javaによるピクセルレベルでの画像処理):HomePage2007の授業のページの一番下に載せました。説明は少し雑ですが、よいサンプルプログラムが揃っていて、この辺をやる人には大変役に立つと思います。かなり広い範囲をカバーしていると思います。この分野、大分分かってきましたので、質問があったら遠慮なく聞いてきて下さい。
心配性の方へ:
昨年末から変に”運”という言葉が私のアンテナに引っかかります。
気になりだしたきっかけは、
(1)父母会で面談の際、あるお母さんが”うちの子は強運なので心配してないんです”と言われたことです。
私の気持ち:”この考え方楽天的でいいな”!
あまり時を経ずして、
(2)テレビで池坊某さんが”私、強運なんでうまくいくと思ってるんです”と言われていました。
私の気持ち:”うまくいくと言われると、うまくいくような気がしてくるな”
最近、
(3)赤子を見た古老がしみじみと”この子も、ある運を授かってこの世に生を受けたんだ”と言うシーンを見しました。
私の気持ち:”確かに運命は定まっていなくても、赤ん坊でも大人と同様に運は授かっているだろうな”
人間60年もやっていると、色々なことがあるし、”人間万事塞翁が馬”って事を何度も見たり経験したりしました。何がよくなるのか、わるくなるのか本当に分からないものです。所詮どう展開するのか分からないのなら(いつでも)自分の強運を信じてしまった方がポジティブに生きられて得だし、よい結果に結びつきそうな気がします。何か心配事が起こったら、ちゃんと運を授かって来たのだから大丈夫、大丈夫って考えちゃった方が余計な心配をしないで済みます。
心配性の私としては、これから、強運をとなえ、不安を吹き飛ばしていこうと思った次第です。大丈夫、大丈夫、みんなうまくいくから、って。
==
写真はカンクン第2弾、世界遺産のピラミッドです。階段の角度45度で、スキーのジャンプ台が35度、蔵王懺悔坂(37度)でもどうなっちゃうかと思いましたから、絶壁って感じだと思います。事故があり、現在登るのが禁止されているという噂もあります。

n2 ( 2008/01/06 06:40:27)
お正月
元旦両親と初詣、2日子供達と昼食、3日銀座ショッピング、4日登校新年会。
この間、
(1)Javaによる画像処理の全貌を整理:特に、ピクセルレベルで画像を操作する人の為の案内を作成したので、近いうちにネット公開。
(2)箱根駅伝(祝)中央学院大3位:以下の理由で中央学院大を応援。
(a)我孫子で実家が近い
(b)大学が小さい(12名のランナーがよく集まるなと思うくらい)
(c)応援する人が最も少ない大学ではないか、と思われる。
例年シード校に残れない位なので3位は奇跡的。
(3)三村君のお母さんがケーキ屋さんを始め、昨年購入したらおいしかったので、正月に購入し御年賀に使用。
(4)1日ウイーンフィルニューイヤーコンサートをNHKで見る。お笑い芸人の騒々しい番組ばかりの中、本物の世界標準を見る、って感じ。
(5)4日、いつも歩いて来る途中に二宮神社があり、少し人が出ていたので初めて境内に入り、いつも横を通していただいているのでお礼とお参り。大変立派なお御輿が飾ってあった。
==
クイズ:写真は上記ニューイヤーコンサートが行われる楽友協会大ホールをバルコニーから見たものです。さてバルコニー席2列目の人はどうやって座るのでしょうか(足が入らない)?

n1 ( 2008/01/01 07:30:13)
明けましておめでとうございます。
旧年中は色々お世話になりました。
本年もよろしくお願いいたします。
本年がよい年でありますようお祈
りいたします。
==
今朝7時の富士山と今年の年賀状です。
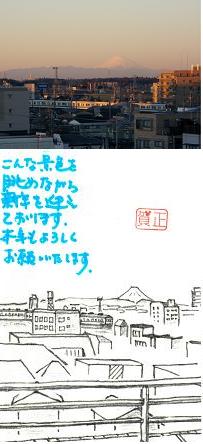
m42 ( 2007/12/30 23:28:49)
今年最後
昨日テレビで”男性のフラダンスが流行っている”というのを見てハッ!と思い出しました。今年も色々なことに挑戦しましたが、結果は様々です。
(1)始めるのも忘れていた:
私はハワイが大好きで、以前から男性のフラダンス(元々フラダンスは男性が神に捧げる踊りです。男性のフラダンスは女性のとは違って力強くてなかなかいいんです)をやりたいと思っていたのですが、当然この辺には男性フラ教室なんかありません。2,3ヶ月前、つくばイクスプレス大鷹の森の駅ビルのハワイショップで男性フラのDVDをみつけ購入しました。1,2度見たのですが練習もせず、そのまま放ってあります。来年は練習しなくっちゃ!
(2)頓挫:
テレビショッピングでサーフボーイ(乗馬健康器具のサーフボード版)が宣伝されていました。テレビショッピングでは値段が高いので買えませんでしたが、その後、ネットでテレビの半額ぐらいで売られていたので買ってしまいました。早速、始めたのですが、おなかの筋肉に来る前に膝に来て、膝が痛くなってしまいました。アッと言う間に邪魔ものに変身しました。
(3)とりあえず続いている:
以前、斉藤茂太氏の本で、食事の時(うまかろいが、まずかろうが)奥さんに聞こえるように”うまい”と言え、というのがあったので、実践しています。これ結構効果があって、言うの忘れていると”これはどう?”なんて催促されることもあります。先日、一寸塩分が多いな、と思ったのですがセオリー通り”うまい”と言っておきました。当然ハシは進みませんので、残りが翌日また登場してきました。食べないでいると、”何で食べないの?”と言うので、”しょっぱくて”と言いました。すると、”昨日おいしいと言ったじゃない”と言われました。
エ〜!昨日の話覚えてるのかよ!!”一応言ってるだけジャン”とは言えず、ン〜〜!と気まずい沈黙が流れてしまいました。女性は記憶力がよいのでいいかげんなことを言ってはいけない、と反省しました。
(4)今のところ続いている:
私は絵が下手で、5段階評価で言えば1か2です。でも絵を見るのは好きで、以前から何とか人並みに描けないものかと思っていました。2ヶ月くらい前、書店で”3分間スケッチ”という本を見つけたので購入しスケッチに挑戦しています。この本、色々”コツ”が書いてあるので、それに従って描いていくとそこそこうまくなるので楽しくなり続けています。今回まあまあ(自己評価3.5)の作品ができましたので年賀状に使いました。本サイト元旦に載せます(たいしたことはないので期待しないように)。同時に、絵を描くと、頭のリラックスに役立つことも発見しました。私は夜パソコンを使うと頭がさえて眠れなくなるんですが、そんな時でも15分位絵を描くと頭がリラックスして眠れます。パソコンで頭の中の血液が一箇所に集まっていたのが、絵を描くと全体の広がっていく感じです。
==
昨日は、仲良し卒業生の忘年会でした(集まるの今年3回目だと思います)。昨日金子研も卒業生の忘年会で6階まで魚を焼く匂いが充満していました。それでは、よいお年を!

m41 ( 2007/12/26 16:22:13)
耳順(”じじゅん”、”みみしたがう”あるいは”みみにしたがう”)ってどんな感じか?
気付いたら60歳になってしまいました。還暦ってどんな感じかお伝えしようと思います。
(A)素直な感じ
(1)歴史:60歳は暦の上での最初のゴールって感じで、60年生きたんだ、って感じです。短くもなかったな、って感じかしら。
最近100歳近い人もよくみかけます。この人の人生を10回繰り返せば平安時代か、って思うと平安もそう昔でもないな、って感じです。
(2)激老:この半年ほど急激に老いが進み(自他共に認める)、60ってのは一つの節目なんだと実感します。自分の顔を鏡で見るのも怖いのですが、同い年の家内の顔も(老いを見せ付けられる感じで)怖くて見られません。
(3)危険地帯:自分の健康、親の介護、自分の介護、と何が起こってもおかしくない危険ゾーンに入ったな、って感じです。
さらにこれから5年以内に新型インフルエンザが猛威を振るうだろうし、10年以内に日本は財政破綻で街には浮浪者があふれるだろうし、20年以内に地球温暖化で資源の奪い合いが起こるだろうし、すごい所に突入したな、って感じです。
(4)(あまり関係ないけど)今回、ケーキのないクリスマスを初めて経験しました(気がついたらクリスマスが終わってました)。
(B)孔子によれば「六十にして耳順」となります。
どういう意味かネットで調べてみると、
”品性の修養が進み、聞くことが直ちに理解でき、なんら差し障りも起こらない境地”
とか、
”事の善悪や相手の品性を見抜ける様になる”
とか、
”異なる考えも素直に聞き入れられるようになること”
とか出てきます。
品性の修養は進むか?:私が今までに多くの人を見てきた感じでは、歳を重ねることにより品性の修養が進むとは思えません。品性の高い人は若い時から高いし、低い人はいくついなっても品性が低い、という印象です。
欲?:ただ、歳を取ると欲がなくなるということはあります。体力の減退により体力に由来する欲は減退し、名誉欲もなくなってきます(人によっては歳をとっても名誉に執着する人がいて、私には全く理解できません)。お金も健康など他のものを犠牲にしても得ようとは思いません。
欲がなくなると、トラブルの当事者になることが少なくなり、他の人と衝突する機会は減ります。そのため、物事を一歩引いた所から冷静に見る機会は増えます。そんなことから、品性があるように”見える”可能性は高くなると思います(実際は品性が上がってないので、トラブルに巻き込まれれば即馬脚を現しますが)。
(ただし、欲がなくなると気力が落ちるという副作用が問題です)
(C)これからどういきるか
以前、定年退職する上司に、老後のプランを聞いたところ、親の介護や自分の健康など予期せぬことがいくらでも起きてくるのでプランなんか立てられないんだよ、と言われましたが、今はよく分かります。
とりあえず私としては、
(1)この所食い散らかしてきた感じの卒研を少し整理し、みんなが利用しやすい形でネットに公開しよう、
(2)小学生の理科離れが進んでいるというので、小学生向け理科サイトかテレビ番組を作ろう、
(3)何か、面白いものを作ってみよう、
なんて考えています。
また心がけとして:
(1)晩節を汚さぬように、品性が高いように”見えるよう”に、
(2)多くの方に色々お世話になってきたので、できるだけお返しをするように、
と思っています。
大学はあと5年です。ベストを尽くそうと思いますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

m40 ( 2007/12/23 07:03:20)
SCIENCE誌2007年ブレークスルーベスト10(12/21日版)
日本語版が出るのは3ヵ月後らしいので、ホットなところで紹介します。
1位 ヒト遺伝子の多様性
数千人のDNAを調査し、疾患を持つ人と持たない人の差異から、心房細動、自己免疫疾患、躁鬱病、乳ガン、結腸直腸ガン、糖尿病、心疾患、高血圧症、関節リウマチなどに影響を与えている遺伝子を特定した。
2位 万能細胞
京大とウイスコンシン大のニュースで有名になった、体のどんな部分の細胞も作り出せる細胞の作成。
3位 宇宙線の追跡
宇宙線の中で一番エネルギーの大きい宇宙線はどこから来るのかは分かっていない。アルゼンチンのグループは、それが我々の銀河の外の活動銀河核(巨大なブラックホールを持つ)から来ている可能性が高いことを示した(まだ決着が付いてはいないが)。
(これに関しては北山先生に概要を教えていただきました、感謝いたします)
ここ(3位)までは間違いありませんが、4位以降は、よく分からずに書いている部分も多々あります(専門用語や研究の背景が分からないため、正式な用語と違っている場合もあると思います)。また、4位以降のいくつかの項目に関しては、専門分野が近そうな先生にお聞きしましたが、ご存知ないようでしたので、それほど有名な話ではないのかもしれません。
4位 受容体の可視化
視覚や嗅覚と関係があるGたんぱく質共役受容体の構造を解明しCGで表現した。これは、医薬品などの開発を加速する可能性が高い。
5位 シリコンを超える?
遷移金属酸化物は高温超伝導物質として注目を集め研究されてきた。これを用いて異なる酸化結晶の多層構造を作ると色々な特性を示すことが分かった。シリコントランジスタ以上の特性を示すかもしれない。
6位 水銀テルライド薄膜の積層を作ると量子スピンホール効果が得られる。これを利用するとスピン電子コンピューターが出来るかもしれない。
7位 免疫細胞が分化する仕組みが少し分かってきた。ワクチン改良に役立つかもしれない。
8位 医薬品化合物を効率よく合成する様々な方法が開発された。
9位 ”記憶がイマジネーション(将来イメージ)を作る”という、海馬が記憶や想像に果たす役割を裏付ける結果が報告された。。
10位「チェッカー」ゲームは、プレーヤがミスをしなければ引き分けになることを証明した。
===
卒業生がカンクウへ行ってきた、というので関西空港かと思ったらカンクーン(メキシコ)でした(写真)。

m39 ( 2007/12/19 16:31:41)
ニューズウイーク
ニューズウイーク(日本語版)は私の愛読誌で、お薦めです。海外の情報がバランスよく、分かりやすく、よく調べられて載っています(特に、日本のテレビや新聞の海外情報は少ない上に偏ったものが多い)。
最近面白かった特集を2つ紹介します(これから就職の面接を受ける学生さんに役立つかも)。
(A)格差社会(勝者総取り)はなぜ起こるか(12/5)
(1)インド中国などの参入で労働者が20億人増えた、その結果賃金が低下
(2)競争の激化と技術の進歩、投資の自由化で労働者の発言力が低下
(3)グローバル市場で事業規模が拡大(ごく少数の企業だけの一人勝ち)
(4)自由貿易や資金の流れの自由化により、富裕層にとって世界中への投資のチャンスが生まれた。資金が儲かる所に集中投下されるので、生産拠点の国外移転や技術革新を加速し労働者から仕事を奪う
(5)富裕層に有利な税制(政治が資金力のある団体に牛耳られている)
多くの国で”金持ちにやさしく、貧乏人に冷たい政策がとられている”
(6)富裕層はコネのネットワークを持ち、労働者には味方になる法律も組合もない
(7)CEOの報酬と自社株購入権を決める制度が上層部に有利になっている
CEOの報酬が急激に増加している
(8)教育に反映し、社会各層の固定化がおこる
(B)グーグルの危機?(11/21)
圧倒的シェアのグーグルに対する挑戦も色々行われている、という話(技術分野の記事でも内容はしっかりしている)。
現在、ヤフー、マイクロソフト、政府主導プロジェクト、などが検索技術に改良を加えてグーグルの後を追っているが、以下のようなさらに進んだ検索エンジンを作る動きも活発である。
(1)ユーザの望みを察知するサイト:検索語から意味を解釈し、意味で検索を行う(ハキア、レクシ)
(2)専門家(人間)が利用頻度の高そうな事柄についてあらかじめ検索を行い、役に立つページを選び出しておく(マハロ、チャチャ)
(3)住宅情報専門とか健康情報専門とか分野を限定して精度を上げる(トルーリア、ヘルスライン)
(4)ユーザを手助け:検索語を打ち込むと関連する複数の検索語やキーワードが表示される(米国ヤフー、クイントゥラ)
(5)ユーザの意見を参考にサイトの重要度を判断(ノージージョー、スクイドゥー)
(6)グーグルは他からのリンクで重要度を決めるが、リンクの代わりにブックマークを用いる(ミスターウォン)
もちろん、グーグルもジッとしているわけではなく、検索履歴を参考にした検索精度の向上などを試みている。
===
一寸寂しい冬景色

m38 ( 2007/12/16 07:22:41)
今週の出来事
(1)今年を代表する文字に”偽”が選ばれました。漢字を分解し、何で”人の為”が偽りなんだ?って話がありましたので調べてみたところ、”為”は”ため”ではなく”なす”という意味で、”人の為すこと”という意味だそうです。
清水寺の貫主が大きな紙にこの文字を書き”このような字が選ばれることは恥ずかしく、悲憤にたえない”と言われていました。(この貫主は関係ないと思いますが)以前、”祇園へ遊びにくる客の多くは坊さんだ”という話を聞きました。これは偽であって欲しいのですが。
(2)先日京成線の車内放送で”次は大久保です、ドアは確か左側が開きます”と言っていました。”確かかよ!!”って話です。ユーモアのある車掌さんだったのでしょう。
(3)最近の学生さんは、”♪柱の傷はおととしの、、”という背比べの歌を知らないということを知りました。そもそも、柱の傷の意味が分からないようです。そういえば最近の家には柱がないことにも気づきました。
(4)最近大学のテニスコートの裏を狸(外見は毛並みの悪い太った猫)が通ります。捕まえて狸汁にする案もありますが、申し訳なさそうな顔をして通るので許しています。でも狸は結構獰猛です。小学生のころ近くで捕まえてた狸を箱に入れて展示してあったのですが、手を入れた生徒が噛まれ大怪我をしました。くれぐれも化かされないように。
(5)木曜日に研究室で(誕生パーティーなのか忘年会なのか)今川焼きを大量買い込み他研究室の人達も集まって地獄の今川焼きパーティーをやっていました(写真)。10時過ぎから始まり、1時頃にはみんなぐったりしていました。私も部屋に入り匂いをかいだだけで胸焼けがして昼食をとれなくなりました。
(6)金曜、野里君がチーズケーキを沢山焼いて持ってきてくれました。学生さんは今川焼きの食べすぎで体調を崩し全員来ていません。幸い遊びに来ていた卒業生の岡本さんと山之内さんに振舞われました。そこで色々話しているうちに、山之内さんの義兄と野里君は時々サッカーをやってることが分かりました。あまりの奇遇に、人生に偶然はないのかな?と思ってしまいました。

m37 ( 2007/12/12 19:15:18)
ディジタルアートフェスティバル2007
新しく研究室に入った3年生とディジタルアートフェスティバルを見に行きました(12/11)。卒研のヒントや刺激になればと考え、ここ3年実施しています。
展示されている作品はインタラクティブアート系とCGアニメ系がありますが、見学はインタラクティブアート系を中心にしています。毎年斬新なアイデアの作品が展示されるので楽しみです。
(現物を見ないとイメージが涌かないと思いますが、目だった作品を紹介してみます)
(1)インタラクティブアート:写真左(今年の作品)はその典型で、ヒモが天井から何本も下がっていて、それが画面にも映っています。ヒモを揺らすと画面上でヒモから水玉が発生し上にあがっていきます(大変美しい作品でした)。インタラクティブアートとは、要するに人間の働きかけで映像が変化するアートです。
(2)昨年面白かったもの:戸外で2台の(本物の)ホバークラフトが爆音を立てて浮かんでいます。一方のホバークラフトを押して移動させると、他方のホバークラフトの動きに影響を与えます。相互に力を伝え合えるのでダイナミックな感覚が楽しめました。
(3)今年の一押し:暗い部屋に入ってヘッドフォンを付けて椅子に座ります。正面に大きな鏡があり、自分の姿が映りますので、鏡を見ています(写真右が鏡に映っている様子で、これを見ています)。スタートすると私の横(鏡の中)に人間(青い輪郭だけ)の映像が現れ、私にいたずら(刀らしきもので斬りかかったり、耳元でささやいたり)をします。鏡の中の出来事なのに実際に”人の形”とインタラクション(相互作用)している不思議な感覚に陥ります。
アートが人に働きかける点が斬新ですし、どのように”人の形”を鏡上の映像として出すのかもよくわかりませんが、何と、これを作ったのは同志社大の4年生(女性)というから、才能豊かな人がいるものだと感心しました。
(4)ヒューマンインタラクション:帰りに会場の隣にある、理数系の面白実験ルームに寄りました。そこには写真撮影コーナーがあり、写真は即ウエブにアップされます(撮影時にIDとパスワードを交付され、それで閲覧可)。記念にみんなで撮影しようということになり、狭い場所に7人が入りプリクラ状態で大騒ぎ、当日一番盛り上がりました。やっぱり人間同士のインタラクションが一番大切だと思いました。写真をご覧になりたい方は(いないと思いますが)、http://risupia.panasonic.co.jpのメンバーページへゆき、IDはGVCPZB、パスワードは9397で見られます(半年アクセスがないと消えるそうです)。
===
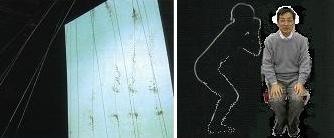
m36 ( 2007/12/08 17:57:14)
静電気の悩み解消(12月5日のNHKためしてガッテンより)
私を悩ませていた3つのケースの解消法が紹介されました。
(1)職場のドアノブ
ドアのそばの壁に手を触れてからドアノブに触れる。
(金属部に紙を張っておいてそこに触れてから金属に触ってもいいらしい)
(2)家のサッシ(干した布団の取り込み時など)
サッシのそばの木やコンクリに手を触れてからサッシに触れる。
(3)車のドアの開閉時
キーホルダーを木製にし、木で金属部に触れた後ドアを開閉する。
(車を降りる時の静電気は衣類と座席の摩擦で起こるので、降車時私はボディ(ドアの閉まる柱)のドアが引っかかる金属部をつまみながら降りて電荷をボディに戻しています)
===
写真は先日行った国立博物館の裏庭です。和風庭園の中に家(お茶室?)があるのも珍しい、かなと思います。昔の衣服を着た人を出入りさせると昔の雰囲気がでそうですね。マリーアントワネットが農村風の集落を作らせて農民の真似を楽しんだのに一寸似ているかもしれません。

m35 ( 2007/12/05 12:27:12)
芸術の秋
国立新美術館、フェルメール、日展、を見に六本木へ行ってきました。
(1)新国立美術館
(一見したところ)常設展示が無いようでルーブル美術館などとは位置づけが違うのかな?と思いました(とすると、日本でルーブル美術館に相当する美術館はどこなのかな?)。
外観は少し軽い感じですが、美術展示センターとしてであればモダンで高級感があり、よいのではないかしら。
(2)フェルメール
”牛乳を注ぐ女”をはじめ、オランダの風俗画が展示されています。”風俗画”と言っても十分芸術品ですが。さすがに”牛乳を注ぐ女”は一番よい出来ですが、これに近いものもいくつかありました。
何と言ってもすごいのは、この地味な題材を芸術まで高めている点でしょう。ただ、展示は上の方からの照明で光りが絵の具に変に反射して見にくい所もありました。
(3)日展
中学高校の頃は美術館がそばだったので、日展をよく見ました。その後ご無沙汰し、5年位前に久しぶりで見ましたが下手な絵が多いなと思いました。今回は、かなり良いレベルだと思います。ただ、どれも絵の雰囲気が似ている気がします。何となく明るい色調で軽快な感じのものが多いのですが(展示室の照明が以前より明るいのかもしれません)、もう少し迫力を感じるものが有ってもよい気がします。
彫刻は、例により裸体が多いのですが、(残念ながら)日本人モデルの体型の限界を感じます。ミロのビーナスは日本では生まれないでしょ。
(4)実物を見た名画
海外で見たものでは、やはり最高は”モナリザ”でしょう(ルーブルで再会した時は、”久しぶりで懐かしいですね”って感じでした)。(ルーブルだったと思いますが)モネの睡蓮とルノアールの作品が沢山並んでいました。睡蓮は20枚位有った気がしますし、ルノアールも沢山ありすぎて有り難みが減りました。(ニューヨークだったと思いますが)シャガールも沢山展示されていました。シャガールはどちらかと言うと苦手ですが、本物は写真より、はるかに魅力的でした。(ベルサイユの)ナポレオンの戴冠式の絵は(芸術的かどうかは分かりませんが)立派でした。
そうそう、ミケランジェロの(バチカン)システィーナ礼拝堂の天井画 には圧倒されましたね(美しいし、素晴らしかった!)。
日本でも色々見た気がするのですが、今思い出せるのは以下です。ベラスケスの”マルガリータ王女”とマネの”笛を吹く少年”は良かった。ロシアのモナリザと言われる”忘れえぬ人”も忘れられなくなりました。ロシアの物だったか、船だか筏だったかが難破している絵も印象に残っています。縁を黒く塗るルオーも好きです(小学生のとき物の縁を黒く塗ると叱られたので、なおさら気に入っています)。ピカソは残念ながら私の理解を超えています。最近ではダリも見ましたが、、、。
===
牛乳を注ぐ女と、忘れえぬ人(ネットから拾いましたが、昔の作品の著作権はどうなってるのかしらね?問題が有りそうでしたらお知らせ下さい、削除しますので)。
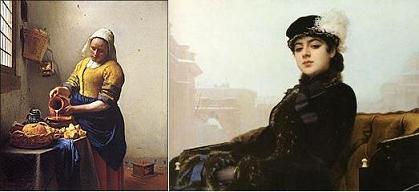
m34 ( 2007/12/02 11:44:54)
大徳川展
ご近所から招待券をいただいたので、”大徳川展”(上野の国立博物館)へ行ってきました。
衝撃的だったのは、関ケ原の翌年に家康が自ら作らせたという”等身大の座像(彫刻)”です(現在、芝東照宮の御神体らしい、木製?)。座像の顔の相は私が想像していたものと全く異なり、家康に対するイメージが完全に変わりました。
(1)一見穏やかな風貌かと思っていた:
家康像というと掛け軸に描かれた(たぬき親父と呼ばれたのが分かるような)老人の顔を思い浮かべます。また、”鳴くまで待とうホトトギス”と詠んだくらいですから、胸に一物はありそうですが、外見は穏やかそうに見える人かと思っていました。俳優でいうと津川雅彦のイメージを持っていました。
等身大座像のお顔(怖くて”お”をつけた)は、全てを見通すようなモノスゴク怖く、厳しい(子供の頃は人質になり、成長しては妻子を信長に殺させられるのに耐え、秀吉の悪意に満ちた無理難題にも耐えた)人相で、後に豊臣氏に因縁を付けて(注)冬の陣を起こしたり、何かにつけ領地没収御家断絶を命じたのがよく分かります。こういう人の前に出たら普通の人は怖くておもてを上げられないと思います。
(2)”関が原は家康の人望で勝った”とよく言われるが:
人相から判断する限り、人望というより、パワー(威圧を含む)に基づくリーダーシップで勝ったのだと思います。
ネットの産経ニュースでは、
”強烈な意思を秘めた眼光の鋭さは、400年の時を経ても衰えず、あたりを威圧するかのようだ”と表現しています。ニュースの写真では今一、スゴサが伝わってきませんが、その通りでした。
なかなか実物をご覧になれる機会はないと思いますので、あえて誤解を恐れず皆さんご存知の方でイメージの似た人を探すと、”もっともっと猜疑心を強くしたプーチン大統領”って感じかな?
生きるか死ぬかの戦国時代を勝ち抜くということはこういうことかと思い知らされました。非情に徹する強い精神力と桁違いの器が必要だったのだろうと思います。
===
注)大坂冬の陣:豊臣家が再建した方広寺の梵鐘銘文に記されている「国家安康」という言葉は家康の名を分断し、「君臣豊楽」は豊臣家の繁栄を願うもので、徳川家に対する呪が込められているとの理由で攻め込む。
===
早いものでもう師走、もう駆け抜けるしかないでしょう。11/28は研究室新メンバーの歓迎会でした:参加者は24名、内3年生6名、OB4名でした。

m33 ( 2007/11/28 12:22:48)
正義
先日(11/23or24)国際アスベスト会議に関する以下のNHKニュースがありました。大変重要な情報だと思うのですが、他ではこれらの情報が報道されていません。そこで、ここに採録、保存しました。
==NHKニュースより==
アスベストの使用が日本よりも早く禁止されたヨーロッパの救済制度や対策が報告されました。このうち、フランスでは、日本のように中皮腫や肺がんの患者に限って救済するのではなく、アスベストを吸い込んだことがX線検査などで確認されると発病するしないにかかわらず救済の対象になっているということです。また、職場でアスベストを吸い込んだ被害者が日本で補償を受けるためには、自分で当時の職場の実態などを明らかにせざるをえず、かつての勤務先の協力を得られずに申請をあきらめる人もいますが、イギリスでは迅速な手続きへの協力を企業に義務づけていることが報告されました。
==NHKニュースより、終わり==
いつものことながら、国民を大切にしない日本の政治に落胆を禁じ得ません。社会正義の観点からも問題があり、国家の品格が疑われます。
+++正義とは何か+++
大学時代の哲学の先生は市井三郎という哲学者で、毎年最後の授業で先生の”正義論”が述べられます。その時ばかりは教室がいっぱいになりました。私の記憶では、正義を判断する基準として以下のようなことが語られていたと思います。
”正義とは、自分の責任以外の苦痛や災いを受けないこと”
(これに従えば、アスベストの被害は本人の責任ではないので救わなくてはいけない、ということになります)
+++正義とは何か、終わり+++
会議運営グループも、上の様な重要な情報は積極的に新聞、テレビ、ネットに紹介していくべきだと思います。折角やった会議も外部に発信しないと仲間内だけの盛り上がりで終わってしまいます。”横浜宣言”というのを出したようですが、ネットをザッと見たところでは全文がみつかりませんでした。
===
11/20〜23日、北九州市で学会があり、4年の野里君と、修士1年の石田さんが発表しました。論文は2007年ホームページに掲載しました。関門海峡の写真です(撮影石田さん)。

m32 ( 2007/11/24 16:19:37)
今週も色々なことががありました。
万能細胞:
皮膚から万能細胞を作ったという日本発の嬉しいニュースがありました。大きな壁が破れ、バイオ関連の研究がさらに加速しそうです。やがて分化(受精卵から体の各器官が作られていく)の仕組みまで完全に分かって来るでしょうから大変興味深いのですが、何だか神の領域に足を踏み込む感じですね。
ミシュラン:
ミシュラン東京版が出て、星印が付いた店のリストを見ました。吉兆が出ていなくて、額賀大臣で有名になった濱田家が載っていたのはさすがでした。カリスマシェフや鉄人としてよくテレビに出ている人達のお店にも注目したのですが星をもらっていないようで”そういう話だったのか”と反省しました。
セクハラ(ニューズウイークに面白い記事が出ていたので紹介します):
アメリカでは最近セクハラで処分を受ける園児や小学生が増えているそうです。昨年テキサス州では4歳の男の子が女性スタッフの胸に顔を埋めたという理由で4日間の停園処分。オハイオ州ではクラスメイトや職員に抱きついたりしたという理由で昨年74人の小学1年生が停学処分を受けたそうです。気をつけましょう。
学部のイベント:
昨日(11/23)は公開講座(囲碁と心のミステリー):ミステリー作家夏樹静子先生と女流棋聖梅沢由香里先生の対談が行われました(参加者約350名)。
今日(11/24)は父母会:情報科は例年より多い約50名の御父母が来られました。多くは、1年生の御父母と、就職が気になっている3年生の御父母です。学科の全体説明(写真)、個人面談、懇親会が行われました。
お天気情報:今週は1週間に4日、家から富士山が見えました。また、東北地方で11月としては記録的な積雪がありました。

m31 ( 2007/11/21 11:07:16)
進むしかない
最近上海へ行った方から、時速431kmのリニアモーターカーに乗ってきたという話を聞きました。私は世界最速営業列車はフランスTGV(320km/h)で、次が新幹線(300km/h)だと思っていたので時速431kmには驚きました。ネットで調べてみると上海リニアは2003年末から営業されていて、431km/hの動画も多数アップされていました。
時速300km級の列車もTGVと新幹線だけかと思っていたのですが、ヨーロッパにはTGV系の路線が多数、ドイツにもICEという独自のものがあるようです(認識不足でした)。
今まで、”東京−大阪間を1時間で移動する必要は、ないよな”なんて思いJRのリニア開発に冷ややかだったのですが、(フツフツとライバル心あるいは技術屋魂が目覚め)やっぱりやらなきゃ駄目だ!って気になりました。
(コンピュータ、半導体、液晶など)最先端分野を見てみると、グローバル経済下で最後に生き残るのは世界で1社か2社です。やめたらそこで終わりです、多くの周辺技術も消えてしまいます。行けるうちは行けるところまで行かなくては!
世界最高や世界初を目指す意識は研究のモチュベーションを高め、関連分野を活性化し、ひいては社会を元気にします。早く500km/h営業を実現して欲しいと思います。
電通の社訓にも次のようなものがあります(以下、”鬼十則”の一部)。
3.大きな仕事と取り組め、小さな仕事はおのれを小さくする。
4.難しい仕事を狙え、そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。
5.取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……。
===
卒研のテーマ:車体を完全に浮上させなくても、浮力を使い(多数の羽根をコントロールし)レールにかかる荷重を0近くにしてレール上を滑走(または滑空)するリニアもありかと思います(素人考えですが)。来年模型でも作ってみようかと思い始めました。
===
上海リニアのイメージ図

m30 ( 2007/11/17 11:02:35)
その後
本日はAO入試で大学へ来ています。今回は、過去に書いた記事のその後を報告します。
(1)SE系卒業生
14日、企業ガイダンスという集まりがあり、多くの卒業生が参加してくれました。前回、激ヤセショックがあったので、積極的に各社のブースを回り会社の状況を聞いてきました。その結果、卒業生はおおむね会社に満足していて、健康で楽しくやっているようでした。
先日の、激ヤセの一人も来ていたので、一緒に来ていた人事の人に健康管理をしっかりするよう頼みました。本人によると、学生時代太りすぎていた精で激ヤセに見えるが、現在標準体重ですのでご心配なくとのことでした。また、その会社では残業代もきちんと出るので、来月は給料が30万位いくと思います、とのことで、一安心しました。
(2)新柏駅
以前、東武線新柏の線路がゴミだらけだと書きましたが、ここ半年位改善が進み大変綺麗になりました(駅長が変わったのかな?)。私の使っている東武線、新京成線通して1,2を争うレベルです。
(3)テニス
学生さんのテニス練習に参加させてもらった結果、腕前はかなり戻ってきました(昔の60%位)。テニスをやりたい人はいつでも声をかけて下さい。
試合は、やるとムキになるので、やらないように心がけています。前回学生さんに試合形式で練習しましょうかと言われ、”形式”ならいいかと思いやってしまいました。学生さんは手加減してくれているのに、こちらは本気になり全力でサーブなど打ってしまい、背中が痛くなって危険でした。これからは、”形式”にも注意します。
(4)低カロリーコーラ
低カロリーコーラはおいしいのですが、私は翌日必ず胃が痛くなります。炭酸の刺激か、コーラ成分の刺激かなと思っています。原因を特定する予定はありませんが。
(5)冬の空気
前回、富士山が見える季節になったと書きましたが、今週見えたのは12、13日の2日だけでした。
==
企業ガイダンスの後の懇親会の写真

m29 ( 2007/11/14 14:53:38)
最近気になった事
1.激ヤセ
この1週間に3人の卒業生に会いました(昨年大学院を修了した人1名、今年学部を卒業した人2名)。この3人ともが激やせでビックリしました。健康診断でイエローカードが出たり、飲み会で倒れたりしているようです。
会社の様子などを聞いたのですが、残業も多いようです。夜10時退社は普通で、それでも手取り20万円前後だそうで、会社は残業代をきちんと払っているのでしょうか?。10年位前も残業が多いという不満をよく聞きましたが、その時は基本給以上に残業代が出る(手取りは基本給の2倍)というような話だったと思います。
女工哀史ならぬSE哀史なんてことになりはしないか心配しています。今日も、これから卒業生が大勢来ますので情報収集をしてみます。
2.大相撲:
スポーツニュースで相撲を見ると、今場所客席がガラガラなのに驚きます(多分満員の1/4位ではないか?)。朝青竜や時津風問題の影響でしょう。かつて相撲人気が一時落ちたことがありますが、観客数がここまで減ったことはないと思います。相撲に関しては一言ありますので、近いうちに改めて書かせていただきます。
3.コミックガンボ(無料マンガ雑誌):
3か月位前から柏駅でガンボが配られるようになりました。私も今までに5冊位もらって読んでいます。最初の頃は、面白いと思う作品が全くありませんでしたが、最近ではいくつかの作品を面白いと思うようになりました。マンガの質が向上したのか、私のマンガセンスがよみがえったのか、どちらかな?と思っています。それにしても無料なのに広告が少ないのに驚かされます。あの程度の広告で無料の雑誌が成り立つのなら、他の雑誌はどうなっているのかな?と疑ってしまいます。
メモ:
私の家(6F)のベランダから冬になると富士山が正面に見えます。今週の月曜(11/12)から見えるようになりました(今日14日は、見えませんでしたが)。これから見える日が増えていきます。これと同時に研究室の廊下の突き当たりの窓から筑波山が見えるようになります。空気が冬の空気と入れ替わり始めたようです。
==
今年卒業した人達の集まり(11/11)

m28 ( 2007/11/11 13:54:09)
東邦祭
今年の学園祭の出店数は例年より2割減といった感じで少し寂しいのですが、講演は充実していました。
本日は日曜日ですが、ノーベル賞の小柴先生の講演があるので出てきました。お話は一応高校生向けということでしたが、参加された人の半分以上は、おじさんおばさんでした。
お話は約90分で、30分づつの3つのパートに分かれていました。
パート1、パート2、は”本気でやれば出来る”というお話で、
パート1:小児麻痺障害克服の話、
パート2:平成基礎科学財団(若者に科学に対する興味を持ってもらうための財団)の設立の話。
この中で、先生がいつも研究者に言っている言葉を紹介。
”いつかは成し遂げたいことの卵の3つや4つは抱えていなさい”
パート3は、カミオカンデでの素粒子検出の話。
パート3の概要:
(1)カミオカンデは地中1Kmのところに3000トンの水を溜め、周囲に光りセンサーをびっしり貼り付け、水中の水素原子から出る光を撮影する。
(2)素粒子が水中を光りより速く飛ぶと光の衝撃波が出るのでそれを観測(ジェット機が音速より速く飛ぶと音の衝撃波が出るのと同じ原理)。
(3)超新星爆発の際のニュートリノ衝撃波(上の衝撃波とは違う)を観測。
素粒子関連は素人なので、ここまでにします。

m27 ( 2007/11/07 10:57:17)
看護覚え書
先日、数年前に松島研を出た上村さんに会いました。上村さんは3年間SEをやった後”人とかかわる仕事がしたい”と、医学部看護学科に入られ勉強中とのことです。最近、社会へ出てから進路変更される方は時々見受けられるようになりましたが、より重い荷を負う方向の選択は、なかなかできるものではないと思います(頑張って下さい)。
私は10年位前、県立野田看護専門学校で情報科学を教えていたことがあり、多少看護の仕事に関心を持っています。
私が看護学校の経験から知った看護の一面を紹介します。
(1)看護覚え書(ナイチンゲール著:現代社):当時看護学校の図書館で借りて読んだので、内容はよく覚えていませんが2点頭に残っていることがあります。
(a)現在、”看護”という概念はあたりまえで誰でも知っていますが、1800年代それまで無かった”看護”という概念を確立したナイチンゲールの想像力(創造力)のすごさに驚きます(万有引力を発見したニュートンに勝るとも劣らないと思います)。
(b)看護は”思いやり”という(はかないと思っていた)考え方の上に成り立っています。今風に言えば”思いやり”ベースのビジネスモデルなんです。”思いやり”が基礎となる職業が存在することにビックリしました。
(看護学校では”思いやり”の考え方をしっかり教育されます)
(2)思いやり:普段、町のお医者さんで接する看護士さんは冷たい感じで”思いやり”を感じたことはありませんでした。そこで、看護学校の先生にその話をした所、”そうかもしれませんね、でも手術で入院したりすると”思いやり”が分かると思いますよ”と言われました。
程なくして父が大腸がんで手術を受けることになり入院病棟に出入りすることになりました。その時、看護の先生の言われたことが、その通りだと分かりました。看護士さんは本当に献身的に治療と回復を助けてくれ家族の者としてはお医者さん以上に感謝したのを覚えています。退院の時お礼を言って頭を下げましたが、肉体的頭以上に心の頭が下がった経験はこれが初めてでした。
(3)戴帽式:看護士さんの立志式で、先生からナースキャップを付けてもらい、ナイチンゲール像から蝋燭に火をもらい、誓詞を読み上げます。おごそかで、先生方の厳しさと暖かさ、学生さん達の覚悟が伝わってきて感動的です。世俗的な欲求を犠牲にし、奉仕と献身を誓う儀式といった感じです。
(4)天使:看護の学生さんと接していて気付くことは、みんな人一倍、元気がよく、明るく、まじめである、ということです。神様から特別なパワーを与えられてこの世に遣わされたのではないかと思うくらいです。
(5)本当の学び:学生さんの中には准看護士の資格を持って病院で働いていて、看護士の資格を取るために病院から勉学の機会を与えられている人もいました。その人の話で印象に残っているものを紹介します。
”私は、この学校に来られて本当に嬉しいんです。私は病院で働いていて、原理が分からないまま、指示される通りに看護せざるを得ないことがよくありました。この学校で、今まで分かっていなかったことが色々分かってきて、ここに送ってくれた病院にも感謝しているんです”とのことでした。
将来この学生さんはきっと良い看護士さんになるなと思いました。
===
連絡:家のノートPCを買い替え、メールが使えるようになりました。
===
戴帽式

m26 ( 2007/11/03 15:04:02)
坂の上の雲
11月3日、大久保商店街収穫祭フリーマーケットというのがあり、今年のテーマは”坂の上の雲”(”ゆーろーどお休み処”に写真等展示)だそうです。
(0)坂の上の雲って何だ?:司馬遼太郎の長編歴史小説。明治という日本近代化の時代、日露戦争を通して3人の青年(秋山好古(よしふる)、秋山真之、兄弟と、正岡子規)の生き方を描いている。私が若い頃は必読書って感じだった(7、8冊からなる長い小説だが読み出すと面白くて一気に読めてしまう)。
(1)なぜ坂の上の雲か?:2009年秋から3年間に渡りNHKスペシャルドラマ”坂の上の雲”が放送されることが決定。
(2)大久保通りとどんな関係があるのか?:主人公の一人、秋山好古はロシアのコサック騎兵を破るため日本騎兵隊(第一、第二旅団)を一から作り上げたが、その場所が現在、東邦大学と日大生産工になっている所。
実は、私にとっても日露戦争は生まれる40年前の話でほとんどリアリティーがないんです。リアリティーは、身近な者から、その人の経験をその人の言葉で聞いて始めて生まれます。
今の学生さんにとって太平洋戦争は生まれる40年前の話なので、何となく昔の話、って感じなのだろうと思います。まして100年前の日露戦争は遠い昔の話でしょうが。
私が子供の頃、親(明治の人ではない)などから聞いた日露戦争の断片を挙げてみます。
(一)二百三高地:乃木大将率いる日本軍は人海戦術で203高地を奪取。激戦で多数の犠牲者を出す(その中に乃木大将の息子もいた)。乃木大将夫妻は明治天皇に殉死。
(二)日本海海戦で大国ロシアのバルチック艦隊を破る:
(以下、有名な格調高い交信文)
「敵艦見ゆ」
「敵艦隊見ゆとの警報に接し連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。本日天気晴朗なれども波高し」
「皇国の興廃此の一戦に在り、各員一層奮励努力せよ」(秋山真之の作)
(戦いの前の緊張、高揚、そして抑制が100年の時を超えて伝わってきますね)
ちなみに、日本海海戦の旗艦は”三笠”(現在横須賀に保存)で、(私事ですが)私が作った最初のプラモデルです。
(三)大山 巌(おおやま いわお)の歌:
♪海棠(かいどう)天を突くところ
♪燃えて火を吐く桜島
♪薩摩が生んだ健男児
♪姓はおおやま 名はいわお
(この歌は父に教わりましたが、薩摩の人も聞いたことがないとのこと。ネットでも見つかりません)
(四)お手玉あるいは手まりの数え歌(団塊世代は子供の頃よく歌いました):
♪一列談判 破裂して
♪日露戦争 始まった
♪さっさと逃げるは ロシアの兵
♪死んでも尽くすは 日本の兵
(この後、勇ましい歌詞が続くようですがほとんど覚えはありません。お母さんやお婆さんに聞けば喜んで歌ってくれます)
===
連絡:家のPCが壊れ、現在メールが読めません。しばらくお待ち下さい。
===
大久保商店街収穫祭フリーマーケット(往時の賑わいは偲ぶべくもありませんが、やっぱり平和がいいですね)
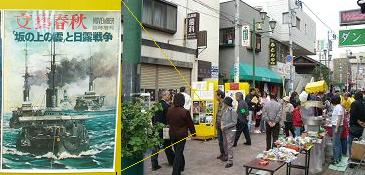
m25 ( 2007/10/31 15:54:08)
ハロウィン
速いもので10月も終わりで、そろそろ冬支度が始まります。
(1)秋の虫の声もほとんど聞かなくなりました。
(2)先週あたりからコートを羽織った人やマフラーをした人が登場しました。
(3)21、28日実家の植木の刈り込みをしました。柿とみかんも少し採れました。
(4)急に寒くなって体が固まり内臓が動かなくなったので、22、31日と新津田沼の整体に行ってきました。
今週の出来事
10月29日 研究室配属決定(今年はルール変更で少しバタバタしました)。昨日からそれぞれの研究室で実験IIを開始しました。
10月29日 柳さんと色部さんが遊びに来ました。
10月31日 ハロウイン(最近あちこちでハロウイングッズを目にするが、古い人間としては今一受け入れにくい。日本の風習じゃねーだろ!って感じで。一寸古いけど”欧米か!”)
11月は行事がいっぱいです。
11月3日 指定校推薦面接
11月4日 卒業生関連の集まり(台場)
11月11日 学園祭(11:00〜ノーベル賞小柴先生の講演)
11月11日 卒業生の集まり(津田沼)
11月14日 大学院修士2年生中間発表
11月14日 就職企業ガイダンス(大畑君が来ます:お父さんになったそうです)
11月16日 インフルエンザ予防接種(学生さんと接するので義務らしい)
11月17日 AO入試
11月23日 公開講座(囲碁とミステリー)梅澤由香里先生、夏樹静子先生
11月25日 父母会
11月28日 新人歓迎会
その他
(1)ついにVistaマシンをあきらめ、学生さんの部屋に放出します。今度は7,8年ぶりでMacに戻ろうかと思っています。
(2)PCが1台具合悪くなったので購入。昨年度からプリンタを速いのにしてくれとの要望があったので購入。
(3)前回の画像(カナダの国旗もどき)ですが、私は戴いた沢山の写真の中から何となく気になった1枚を国旗風にしました。その後、提供者から連絡を戴き”あの写真はカナダの国旗に似ている葉を選んで撮ったので、葉っぱも本望だと思います”とのことでした(ビックリ!)。
===
薬草園に咲いていた”イヌサフラン”。

m24 ( 2007/10/28 07:58:48)
キャナダ(カナダ)
大学の先生の話で記憶に残っているものはほとんどないのですが、私が一つだけ覚えているものがあります。
**私の先生の話**
君らが社会の中核で働く頃には日本はもっと発展し科学も進歩するので、君らは週末はキャナダへ行って保養し、月曜には戻って来て仕事をする、って生活を送るようになるよ。
**********
そうなのか!!さすが先生の考えはスケールが大きいな、と思い希望と勇気が湧いたものでした。当時海外旅行は夢のまた夢でしたし、キャナダなんて発音を聞くと”相当海外慣れしてるんだな”なんて神々しく見えたものです。
35年後の現在、状況はご覧の通りですが、先生は夢のある話をするのも大切だなと思います。
それでは、ってことで:
皆さんが私と同じ位の歳になる3,40年後の明るい未来を予想してみますと、間違いなく皆さんは労働から解放されているでしょう。
労働は全てロボットがやります。ロボットはアシモの様な形があるものばかりではなく、セカンドライフで働くキャラクターだったり、デイトレードソフトだったりします。皆さんは、時々ロボットからの結果の報告を受けたり、方針の相談を受けたり、時に一緒に働いたり、といった生活になります。
もちろんロボットとのコラボはネット上で行えますのでいつも決まったオフィスにいる必要はありません。週末飛行機で遠出する必要もなく、夏はヨーロッパ、冬はハワイででも過ごすことになります。ヨーロッパではズーリック(チューリッヒ)やビエナ(ウイーン)あたりに滞在し、バック(バッハ)の演奏会を楽しむって生活かしら(キャナダに対抗し、思い付く英語読みを並べてみました。アメリカでは”ウイーン”では通じませんので)。
===
(いただいた)キャナダの落ち葉の写真を使用(産地偽装はありません)。

m23 ( 2007/10/24 18:05:47)
中間発表
昨日、卒業研究の中間発表を情報科全体で行いました(今回初めて)。学科全体を2つに分割(13:00〜14:20発表グループと14:30〜15:50発表グループ)し、ポスター形式で発表しました。全員がA1サイズのポスターを作り、指定された時間帯にポスターの前で説明したり質問を受けたりします(写真)。
研究室配属
中間発表は研究室配属とリンクしています。3年生は中間発表を見学し、その後希望研究室を提出します。研究室の人数は昨年まで最大7名としていましたが、昨年研究室の人数に偏りが大きかったので今年は(紆余曲折を経て)6名に変更されました。
配属方式は、4,5年前から始めて不満の少ない2回投票方式を採っています(1回目は参考程度に希望を出し、その結果が公表され、それを見て最終希望を提出します)。配属は明日決定されます。
===

m22 ( 2007/10/21 06:33:35)
秋はコスモス
最も好きな草花かもしれません。コスモスで思い付くものを並べてみます。
(1) やさしいね 陽のむらさきに透けて咲く 去年の秋を知らぬコスモス(俵万智)
(2) 学生時代通学途中新宿で気が変わり富士五湖行きの高速バスに乗ってしまうことがありました。晩秋の頃だったと思いますが西湖の湖畔に2,3本コスモスが美しく咲いていました。
(2’)新宿付近を通過する方へ:会社や学校がいやになった時は気分転換に高速バスで富士五湖へ行くのもいいですよ。湖だけでなく、風穴・氷穴とか、樹海散策路といった見所も沢山有って1日のんびりするのに最適です。
(3) コスモスの花あそびをる虚空かな (虚子)
(4) 最近あちこちにコスモス畑が出来て大量のコスモスも見ものです。私の行ったことのある所では、
(a)船橋なら”佐久間牧場”(新京成、滝不動下車徒歩3分)(写真左):乳牛がいるので新鮮なアイスクリームが食べられます。
(b)柏なら”あけぼの山農業公園”(柏か我孫子からバスか車):写真右の薄黄色のコスモスが見られます。2年位前はブルーのコスモスもありましたが、今年はありません。
(c)つくばなら”下坂田のコスモス畑”(車)です。
(5) コスモスは日本の風景になじんでいるので、日本古来のものかと思っていましたが、メキシコ原産で明治時代に入ってきたそうです。
(6) サンフランシスコ(リンカーン公園)のコスモスの花はデカッ!!かった(花の直径2倍以上)。種を持ち帰って植えてみましたが普通のコスモスになってしましました。メキシコのコスモスの花はデカイのかな?
(7) コスモスと言えば、やはり、
♪淡紅の秋桜が秋の日の
♪何気ない陽溜りに揺れている
♪此頃涙脆くなった母が
♪庭先でひとつ咳をする
、、、ですよね。
===
訂正: m1 で、”涼宮ハルヒの憂鬱”が美文となっていましたが、”家守奇譚”が美文の誤りです。(1)と(2)の指定が間違っていたので直しました。
===
Vistaの問題1:早くVistaに移行しようと、メールをVistaで読むようにしたのですが、昨日受信したメールに字化けが起こり、スパムの方に捨てられていました。ネットで調べた所、Vistaの日本語の字化け問題があるようで、メールをまたXPで読むようにするしかありません。
Vistaの問題2:UltraCというC言語のインタプリターがあります。これをVistaで実行しようとするとファイルがうまくできません。これからソフトの買い替えが多発するのかと思うと憂鬱です。Linuxに移ればいいんですが、様々な特殊入出力機器のドライバーがLinuxに対応していないんです。せめてOfficeだけはOpenOfficeに移行しようかと思っています。
PCを購入するのに、XPにするかVistaにするか悩んでしまいます。
===

m21 ( 2007/10/17 10:01:04)
アレルギーは突然やってくる
10月1日の晩寒かったので毛布を出して掛けたら途端にクシャミ連続丸一日。その後、喉を痛め、声が変になり、気管が変になり、10月14日やっと回復。
これが、風邪かアレルギーか不明なんです。6月ごろ同じ症状になりアレルギー検査やCTの精密検査までして、ハウスダストやダニのアレルギーが有る事までは分かったんですが、お医者さんも、風邪かアレルギーか判定できないんです。
私は半年押し入れに入っていた毛布に付いたハウスダストやダニのアレルギーだと思っているんですが。
アレルギー分野では”押入れに入れてあった冬物の寝具は干したり洗ったりして使え”という話があるそうです。皆さんも注意して下さい。
6月の精密検査でCTにかけられた時の話:
CT室で機械に乗せられるとやがて機械が、
> ”はい、息を大きく吸って止めて下さい。”
と言ってしばらくしたら、
> ”はい、楽にして下さい。”
と言う。
CT室の中なので質問するわけにもいかず、
”楽にする”、ってどういうことだ?って悩み出す。
(a) 息を吐き出してよいのか、
(b) 息を止めたまま筋肉の力を抜くのか?
後で技師の人に聞いたら、息を吐けっ、てことだそうで、それなら、
”息をして結構です”とか言って欲しいと思いました。
アレルギーは清潔な環境で育った良家の子女がかかるもんだと思っていたら、自分もかかってしまいました。いつの間にチャマに変身?
聞くところによれば、アレルギー反応の強い人には即効で効く薬が供与されていて、クシャミ連発が起こった時はすぐ飲むそうです。よい話を聞いたと薬局で、そんな薬はないかと聞いたところ、それはステロイド系の強い薬でお医者さんしか出せないとのこと。それでもアレルギー性の症状に効くと言う”パブロン鼻炎カプセル”というのを買ってきました。今度同じ症状が出たら飲んでみます。これでアレルギーか風邪かの決着がつくと思います。
===
写真はカナダ側ナイヤガラの滝です(提供旧姓岡本さん)。左の写真の右下に観光船”Maid of the Mist”が見えます。Maid
of the Mistは”霧の召使”という意味かと思い素晴らしい命名だと思ったのですが間違いでした。
Maid of the Mistは”霧の乙女号”と呼ばれ、先住民の伝説に由来します。美しい乙女が酋長の命令で村の長老と結婚することになりましたが、結婚式を逃げ出し、滝つぼに住む精霊に呼び寄せられ一体となりました。今でも瀑布の霧の中に乙女の姿を見ることが出来ると信じられています。写真(右)は滝の近くの紅葉です。

m20 ( 2007/10/14 06:16:49)
研究テーマ (電子教科書)
最近興味が湧いてきた研究テーマがいくつかあります。社会的にも重要な気がするので提案し、検討していきたいと思います(近い内に、もう一つ)。
先日、高校の授業を見学して2つのことに気付きました。
(1)授業スタイルが昔のまま:これは大学も同じですが、典型的な工場型教育方式で、机をならべ先生が前で講義をするタイプです。このスタイル、最近弱くなっている忍耐力を養うのには最高ですが、もう少し各学生の興味や能力に合わせた教育法を導入した方がよいと思います。これには次の電子教科書が役に立つでしょう。
(2)”本”形式の教科書は古い:教科書も”本”で昔のままです(ちょっと怖ろしいのは厚さと内容が昔の半分位)。そこで思い付くのは、もっとITを駆使した教科書(電子教科書)です。最近、辞書も電子化されており、その延長で電子教科書が導入されてもよいのではないかと思います。
(a)最も有効だと思うのは、社会科系です。例えば地理:
グーグルアースやグーグルマップなどと連携し実際に上空からのアクセスを行ったり、各地の産業を実際の会社訪問動画などで見ることができるようにすれば、ほとんど自力で勉強できるのではないでしょうか。
(b)英語も、読み上げや、質問を英語で発音してくれたりするとリッスニングにも有効です(しゃべる教科書)。
(c)理科系でも従来の教科書には載せきれないものが沢山あります。例えば化学では、名前を丸暗記しているが実物を見たことがない化学薬品は少なくありません。また、授業ではやりきれない化学実験動画を用意したり、化学反応のシミュレーションが見られると理解が進むと思われます。
(d)数学でも、多くの時間が図形と数式との関連を理解するのに使われています。方程式と因数分解の関係など、ダイナミックな図を用いると説明しやすいのではないかと思います。
要約すると、電子教科書は、能動的学習が可能で工場型教育を変える可能性があるということです。特徴をまとめると、次のようなことかと思います。
(i)従来のビデオ授業と違う重要なところは、クリックで自分に必要な知識にたどりつける。
(ii)興味に応じて深く自習できる。
(iii)インターネットとリンクすることにより、最新の情報を得たり、広い立場で物を見ることが可能になる。
以上です、こんなのやってみたい学生さんいませんかね?
===
おまけ1:KYは以前書きましたが、MTってのもあって”まさかの展開”だそうです。
おまけ2:齊藤茂太さんの本で読んだのですが、齊藤さんは夕食の時必ず奥さんに聞こえるように、小声で”ああ、うまい!”と言うのだそうです(うまかろうがまずかろうが)。私も試してみたところ、簡単で意外と言い易いし、言った方も気持ちがよくなります。不思議なのでお試し下さい。独身の人は食事を作ってくれるお母さんなどに言ってみましょう。
===
写真は、白石君の学会発表風景です(於、北海道工業大学)

m19 ( 2007/10/10 11:32:03)
元体育の日
今日10月10日は元体育の日です。この日は”晴れ”の特異日で、東京オリンピックの開会式に選ばれました。東京オリンピックって言ったって遠い昔で、皆さんのお父さんやお母さんさえ知らないと思います。”河西、宮本、金メダルポイント”なんて聞いて涙が出るのは団塊の世代以上ってことでしょうね。
今日はその名に恥じず、昨日までのグズグズ天気を跳ね飛ばして晴れました。
女心と秋の空ってわけじゃないんですが少し並べてみました。
(1)女性の気持1
先日電車に体が私よりひと回り大きい女性が乗ってきました。彼女が私の立っている所に近づいて来ると、何となく圧力を感じ後ずさってしまいます。これを3度ほど繰り返しました。一般女性は普段体の大きな男性を相手に、いつもこんな感じで場所を空けざるを得ないんだな、と同情しました。
(2)女性の気持2
それにしても女性は体が小さいのに気の強い人が多く、たいしたもんだなと思っていたのですが、体が小さいので気が強くないとやってられないんだ、という話も聞きました。
(3)女性の気持3
固く閉まったビンの蓋は女性では開かず、男性が評価される唯一のケースと思っていたのですが、先日、テレビで松井直美さんが”本当は本気出せば開くんだよね”って言っていたので、そうだったのか、と納得しました。
(4)女性の気持4
電車の女性専用車は結構混雑しているので、悪い男が多いってことかな、と思って見ています。先日、女性専用車では皆頑張って立たないので急停車時には皆倒れる、という話を聞きました。その話を家で女性軍にしたら、その話は女性差別のセクハラだとお叱りを受け謝りました。女性専用車で女性が倒れているという話はしない方が安全です。
(5)女性の気持5
先日テレビで女性の方がウツになりやすいという話をしていました。理由は、女性は脳リョウが大きく左右の脳の情報交換がスムースなので、何か一つの事を聞くと、”それは、こう言う意味じゃないか?”とか”こういう裏があるんじゃないか?”とか考えすぎるためだそうです。そう言えば我が家でも、一つの話に”よくそんな話を関連付けて来るな”と思うような話を引っ張りだしてきてイライラさせられることがよくありました(そんなのカンケエネエ!って感じなんですが)。今度、そのようなケースに出会ったら”アッ脳リョウを情報が駆け巡っているな”と冷静に観察できることでしょう。女性は、考え過ぎないように。
(6)男性の気持
男性は脳リョウが小さいので脳の並列処理ができないそうです。ですから、新聞を読んでいたりテレビを見ている男性に話しかけると同時に2つのことができないので、”ウルサイ!”って話になるようです。女性は右から左に、左から右に聞き流せるらしいのです。
また女性の脳リョウの大きさは男性を悩ませる”女の勘”を生むそうです。
(7)男女差
車内で高校生等の話を聞いていて気付くことは、
女子高校生達の話はジェネラル(誰だ好きだとか)で内容が分かる、のに対し
男子高校生達の話はスペシャル(例えばゲームの話)で内容が分からない。
これは、社会人などの場合にも大体当てはまります。何でかしらね?
(8)男女差縮小
最近の男子学生の中には人前で泣く者が出てきて心配しています。泣くな!!って感じですが。
日本は良い気候帯に属していると思われていますが、本当に気持ちの良い日は年に14日ぐらいしかありません。こんな日は外に出てよい空気をいっぱい吸ってきましょう。
===
写真は中国武漢の立ったまま化石になった木だそうです。

m18 ( 2007/10/07 06:50:19)
中国
(1)武漢
先月村田君が中国武漢の国際会議で発表してきました。
武漢は上海から内陸に約900Km行った所にある長江に面した大都市です。武漢と言ってもピンと来ない人が多いと思いますが、次の漢詩なら知らない人はいないと思います。
写真(左)は李白の詩で有名な黄鶴楼です(唐時代とは形も場所も少し違うようですが)。
右は黄鶴楼から見た長江です。1250年前に思いを馳せ李白の詩を味わってみましょう。
”黄鶴樓送孟浩然之廣陵 ”
(黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之(ゆ)くを送る) 李白(701-762年)
故人西辭黄鶴樓
煙花三月下揚州
孤帆遠影碧空盡
惟見長江天際流
(読み)
故人西のかた黄鶴樓を辞し
煙花三月揚州に下る
孤帆の遠影 碧空に盡(つ)き
惟(た)だ見る長江の天際に流るるを
(訳)
古い知り合いの孟浩然が、西の方の黄鶴樓のある武昌を去って、
春霞がたって美しい三月(陰暦)に、下流の揚州に向かう。
帆掛け船の姿がひとつ 遙か彼方の青空に消え、
ただ、天の際(きわ)まで流れる長江が見えるだけだ。
===
黄鶴楼の謂れ:
昔、飲み屋に老人が酒を飲みに来た。老人は半年も通い続けた後、酒代の代わりに店の壁に黄色い鶴の絵を描いて立ち去った。この鶴は、客の歌に合わせて舞うため店は繁盛した。
十年ほどして、その老人がまた訪ねて来て笛を演奏すると、鶴は壁からおどり出て、老人は鶴と白雲に乗り飛び去った。主人はこれを記念して、長江を望む所に黄鶴楼を建てた。
===
(2)北京
私も20年くらい前中国(北京近郊の香山)での会議に参加しました。その時のメモを引っ張り出してみましたので、その中からいくつか中国の印象を紹介します。
(a)大きい
北京で紫禁城(故宮とも呼ばれ外壁に毛沢東の額がある)、頤和園、天壇公園、などを見学するがどれもスケールが大きくホッとする。
特に万里の長城の見渡す限り続く壁は圧巻である。
(b)レンガと壁
家は木で作るものと思っていたが中国ではレンガ造りの家が多い。また敷地を高い塀(レンガやコンクリ)で囲って家をよくみた(20年前の話なので今は分からないが)。万里の長城も英語だとGreat Wallなので、中国では壁を作る習慣が定着しているのかもしれない。
(c)足が長い
中国に行くとき、日本人の祖先は中国から渡ってきた人も多いだろうから、我々のルーツを見ることになるかな、と期待していた。北京で最初に気付いたのは皆足が長いことである。少なくとも私の祖先は北京付近から来たのではなさそうだと確信した。
(d)コミュニケーションが取りやすい
何人かの中国人とそれぞれ2、3時間行動を共にしたが、話題には事欠かなかった。我々も漢文や三国志などを通じ色々な知識を持っているし、中国人も日本についてよく知っていたので、すぐ話が合った。
よく欧米人同士は比較的簡単に友達になれるのに、日本人は欧米人となかなか親しくなれず、日本人は国際感覚がないと言われる。多分、欧米人同士は共通の文化があるので親しくなりやすいのだと思う。
(e)漢字
英語が分から時は筆談が頼りに成る。買い物や道が分からない時など大変役に立った。観光ツアーで隣り合ったスウェーデン人は馬という字は馬の形に似てますね、と言ってきたので象形文字の話をしてあげたら、あなたは日本人なのにどうして漢字に詳しいんですか?と聞いてきた(確かに、日本で漢字が使われていることを知らない方が自然ですよね)。
(f)謝るべきか
私の知人は初めて中国人と話す機会があった時、”祖先が貴方の国に迷惑をかけて申し訳ありませんでした”と謝ったそうです。すると、その中国人は”貴方が戦争について謝ってくれた最初の日本人です”と感激したそうです。最初に謝るって結構勇気がいりますよね。
まとめ:
最近、中国の話となると危険な食物、不法コピー、ウエブ検閲などとマイナスイメージが先行し今一元気がでない。テレビで見る中国要人や報道官はみな強面(こわもて)でお付き合いできるような気がしない。ところが、中国で普通の人に会うと大変親切だし暖かい感じがして、このギャップは何なのだと思う。早く余計な障害が取り除かれ自然なおつきあいができるようになるとよいと思う。

m17 ( 2007/10/03 09:12:35)
飛行機も好き
海上自衛隊下総航空基地(鎌ヶ谷&柏)は、対潜哨戒機P-3Cを使用した海上自衛隊の教育訓練や、太平洋海域の救難業務を担当しています。毎年一回基地公開が行われ、航空ショーなどが実施されます(今年は、9/29)。去年に続き今年も見に行ってきました。
基地内には今の日本にあまり見られない独特の雰囲気が流れています。うまく表現できないんですが、
・国を守る使命感
・規律
・ファイティングスピリッツ
・若さ
の混ざったような、さわやかな感じです。
航空及び地上展示される飛行機のフォルムも美しくて好きです。
エンジンの爆音を体で聞くと、気分が少し高揚するのを感じます。またヘリコプターのエンジン音を近くで聞くと変に懐かしい感情がよみがえりウルっと来ます(何でしょうね?)。
帰りのバスの中で、”アッ!若い時の気持ってこんな感じだったな”って思い出しました。これも説明しにくいんですが、
・自然にアドレナリンが今よりでていてほんの少し興奮気味
・そのため、全てのものが楽しい
・前向きで何かいいこと起こりそうな予感
って感じかな。
体の話だと分かり易いと思うんですが、マッサージに行くと体が軽くなります。この時マッサージ師の人はよく”若い時はこんな感じだったんですよ”と言います。その心版(心が軽い)って感じです。
ついでに、自衛隊に関する話を2つ。
(1)強い!
以前、自衛隊を中退して大学へ入った学生さんがいました。その人は津田沼で暴漢に襲われ棒で胸を殴られました。この時肋骨が折れたのですが、その棒を取り上げ逆に暴漢を打ちのめしたそうです。
(2)かわいい?
よく自衛隊の人が私服で電車に乗ってきます。彼らの中に女性自衛官がいると別れ際に自衛隊の人たちだと分かる時があります。女性自衛官は習慣で別れ際に敬礼をしそうになるのですが、途中で気付き恥ずかしくなり、挙げかけた手を途中で止め、頭を傾けて(頭を手の方に近づけ)敬礼と気づかれないようにごまかそうとします。このパターンを今まで2回見ました。
===
写真(左)はYS11の前で警備の隊員に撮ってもらいました。右は小学生の頃行った航空ショーでの写真です。50年たってもまだ同じことをやって喜んでるんで進歩ないですね(両方とも体が右に傾いてるし)。

m16 ( 2007/09/30 05:24:05)
学会シーズン
国際会議や国内学会の大会は夏休み(9月)と春休み(3月)に開かれることが多くなっています。今回は学会ってどんな世界かを紹介します。
(1)学会って何だ:
研究や開発に携わっている人が入会する組織。国内の学会の場合入会金は年間1万円程度。情報関連の学会には、”情報処理学会””電子情報通信学会””人工知能学会””電気学会””応用物理学会”などがあります。アメリカではIEEEという学会が有名です。
(2)サービス:
学会では会員の研究成果を発表する論文誌を発行しています。論文誌に掲載されるには、数人の査読者の審査にパスする必要があります。
(大学院博士過程の学生が博士号を取得するには普通2報程度の論文が学会誌に掲載される必要があります。今博士過程3年の村田君は数日前2報目の論文が審査をパスしました(3年間に2報の論文を出すのは結構大変です。おめでとうメールを送りましょう)。
また普通、学会では毎月学会誌を発行し、最新の科学技術情報などを紹介しています。
(3)国内の研究発表会
最新の研究成果をいち早く発表するために、査読のない2種類の口頭発表会を行っています。
(3-1)年2回程度の全国大会(準備する資料は1ページ程度)
(3-2)もう少しまとまった結果を発表する”研究会”(資料は8ページ程度、隔月位)
(4)国際会議:世界規模で行われる研究成果発表会は国際会議と呼ばれます。普通各国を巡回していることが多く、一般にバカンスを兼ね、観光地で開かれます。
論文は英語で査読があります。発表形態は演台での口頭発表と、衝立に論文概要を貼って説明するポスター形式があります。
研究室では今月、
修士1年の白石君が応用物理学会、同じく修士1年の中村君が情報処理学会で発表しています。11月には石田さんと野里君が電子情報通信学会(研究会)で発表する予定です。
また、国際会議では、
今月村田君がICES(進化システムの国際会議、於中国武漢)で、10月には博士2年の諏佐君がSASIMI(情報統合の国際会議、於北海道)で発表します。
===
写真は野里君が参加したSPIEという半導体関連の国際会議の様子(左)です。この会議は米国モントレー(西海岸、SFとLAの中間位の別荘地)で開かれました。写真右は太平洋、この先が日本です(この海岸風景は松が多く日本の海岸風景と似ていることでも知られています)。
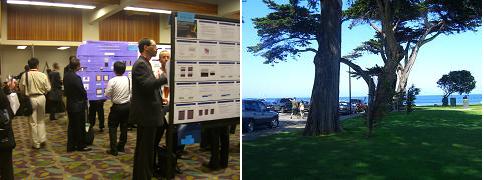
m15 ( 2007/09/26 12:21:29)
秋の虫 右脳左脳
(1)絶滅危惧昆虫(鳴く虫編)
秋の虫が鳴きだして1ヶ月がたちました。当初、ほとんどはアオマツムシでしたが、最近コオロギの声が半分くらいに増えてきました。
アオマツムシ(写真左)は、マツムシとは名ばかりでコオロギの仲間です。100年くらい前に中国から来たものらしく、東京では1970年ころから急に増えだしたそうです。私が気になりだしたのはここ10年くらいだと思います。これは木の上に生息するので、草むらが無くても問題ないそうです。
コオロギも健在で、これも縁の下や道路の隅など草むらがなくても済むためだろうと思います。
さて問題なのは草むらが必要な、スズムシ、マツムシ、ウマオイ、クツワムシです。スズムシ、マツムシは私が子供の時分いたのかどうか不明です(子供の頃なので他の虫と区別が付かない)。少なくとも見たことはありませんでした(草の下に隠れているため目に付かなかったのかもしれません)。
ウマオイ(写真中)とクツワムシ(写真右)の音は現在、少なくとも私の付近で聞くことができません。
(a)ウマオイはスイッチョンと鳴き、よく部屋の中に入ってきて蚊帳の上にとまったりしました。鳴き方が涼しげで可愛い感じでした。
(b)クツワムシはガシャガシャと言い、その名の通り大音量でガシャガシャと鳴きます。当時小学校では”鳴く虫コンクール”というのがあり、ガシャガシャはスターでした。私はガシャガシャの声を聞くと父と家の前の松林にとんでいきました。私が提灯で虫を探して照らし、父が両手で包むように捕らえました。
(考察1)結局都市部に生き残っているのは、コオロギ族のようです。都市部で成功している人達もコオロギっぽい人ってことかしら?
(考察2)草むらが無くなり、声の良い、癒し系の音色が減っているようです。最近癒し系音楽やグッズが売れるのはそれと関係があるかも?
(2)右脳と左脳
右脳と左脳という話がはやった時、日本人と欧米人では虫の音を聞く脳が左右逆で、日本人は虫の音を芸術と感じ、欧米人は雑音と感じる、という話がありました(ネットを見ると、今も広く信じられているようです)。
私は、この話に興味があったのでアメリカ滞在時に虫の音に注目していました。しかし、アメリカで虫の音を聞いてもどうも美しく感じませんでした(要するに虫の声が悪い)。
この時、虫の音に対する日本人の特異性に疑いを持つようになりました。
その後、アオマツムシが増えて騒々しくなってくるに従い益々日本人の虫の音に対する特異性の話は信じられなくなってきています。
日本人が虫の音に風流を感じたのは、昔の日本の虫の声が優れていたためだと思います!!

m14 ( 2007/09/23 05:46:17)
教育実習
教職を取っている学生さんが教育実習に行くと、最後の頃に研究授業という公開授業があります。大学教員はお礼を兼ねその授業を見学させてもらいます。研究授業でいつも感心するのは、担当の先生が実習の学生をよく指導してくれていることです。
今年は、20日に東邦高校へ行ってきました。授業の準備もよくなされているし、学生さん(高校1年)も集中が切れず、よく授業に参加していました。
今までにお邪魔した高校で印象的だった所を挙げてみます(印象的と言っても授業とは関係のない話がほとんどですが)。
(1)諏訪双葉高校:諏訪市は諏訪湖に面した市で、諏訪大社、ハイテク企業、御神渡(おみわたり)、御柱祭、等で有名です。精密機器でも有名なので寒冷地で冷たい感じのイメージを持っていましたが、行ってみると気候、人間共に大変暖かい感じのする市でした。
ハイテク産業で潤っている精か、ガツガツした感じがなく余裕を感じます。普通、有名な神社やお寺があると、その周りに商魂逞しい人たちが群がり、雰囲気を台無しにしてしまいますが、諏訪の場合はその様な雰囲気なく、大社が神社として立派に存在しています。
諏訪は私のお気に入りの都市ベスト5に入ります。特に、歴史を背負いながら歴史負けしていない都市としては”凛とした雰囲気を持ち背筋が伸びる感じのする金沢”と双璧だと思っています。
(2)佐野女子高校:つくばから車で行きました。途中大変美しい渡良瀬遊水地の周りを走ります。市内には立派な山城があり登ってみました。ラーメンも有名なので、佐野一番という店を紹介してもらい(町のはずれの方だった気がする)たずねました。幅の広い独特の麺で、大変おいしかったのを覚えています。そう言えば、帰りに佐野厄除大師をお参りしたり、地元の物産店で地酒だったか地ビールだったかを買ったりと、ほとんど観光気分でした(弁解:研究授業は大体昼前後のいい時間帯が多く、高校が大学から離れていると、もう大学に帰っても仕事にならないんです)。
教育実習の学生さんは掘口さんと言い、腹の据わった人で佐野女子高にボート部を作ったり、高校をアピールして指定校推薦枠を取るきっかけを作ったりしました。現在研究室によく出入りしている佐野女子卒の学生さんを見るたびに、堀口さんの貢献かなと懐かしく思い出しています。
(3)木更津高校:ここへ行くのは楽しみでした。理由は”お富さん”の故郷だからです。”お富さん”とは歌舞伎の演目の一つ(与話情浮名横櫛)ですが、私が小学校1、2年の頃春日八郎の大ヒット曲にもなりました。父がよくレコードを聞いていたので、私も覚えてしまい小学校で歌っていたところ、当時、歌謡曲を学校で歌うのは許されない時代だったので、母が呼び出されるはめになりました。
お富さんの物語は出だしだけ言うと、与三郎(江戸の大店の若旦那)が、木更津でお富さん(やくざの妾)に出会い一目ぼれ、それがバレて斬られ(傷痕だらけの)”切られ与三”になって、、、、、って話。
高校訪問の日、電車が木更津に着くと駅の観光案内板に”こうもり安(与三郎の相棒)の墓”と書いてあったので、気分はいやが上にも盛り上がってしまいました。研究授業の後さっそく先生と”お富さん談義”でもできるかと、話を持ち出したところ先生は”お富さん”をご存知なかったので拍子抜けしました(先生は私より少し若いのと木更津出身ではなかったためかもしれません)。
一般的に言って、最近は地元の歴史上の人物の話を子供達に伝えていないのではないかと気になっています(もっとも、お富さんが歴史上の人物かどうかは疑問ですが)。
(4)駒場東邦中学(ここだけは授業の中身です):授業は中学1年の数学の幾何でした。面と面が垂直に交わるとどうのこうの、といった部分です。私にとってこの辺りはあまり興味がなかったので、学生さんも退屈するんじゃないかな、と思って見ていました。ところが、先生が課題を出し”周りの人と議論してごらん”と言うと、一人残らず食いつき、熱心に議論を繰り広げています(普通40人もいれば5人位は眠ったり集中を切らしていたりするものだと思いますが)。これなら教えるの楽だな!!と感心しました。
===
あとがき:並べてみて気付いたのですが、上の内(3)以外は全て同じ年(2000年)でした。この学年は印象に残る人が多く、いまだによく訪ねてきてくれる卒業生が何人もいます。
===
回答:前々回の北海道の写真に関して”先生も行ったのか?”という質問を何度か受けました。あれは、行ったフリをしているだけです。
===
諏訪には美術館やガラス工房などがいくつかありました。写真はそのどこかで購入したビアカップで、底の辺に金箔を溶かしたようなものが入っているのがミソです(お値段何と5千円でした)。

m13 ( 2007/09/20 16:27:28)
夏休み終わる
(1)大学へ学生さんが戻ってきました
みんな元気で、少したくましくなった感じです。
(2)Vistaへの移行
Vistaに移行しようと思って、春にマシンを購入したのですが一向に移行が進みません。
一番大きな原因はモニタが1つしか付かなかった(XPは3モニタ)ことです。
最近USBでモニタを増やせるアダプタのVista対応が行われたので2モニタにしました。
これで使いやすくなりましたが、それでもやっぱりVista使いにくいですよね。
(3)夏休みの電子工作(電子工作は趣味)
(a)USB接続の 方位計、加速度計、各2種類を作成
(b)PCで制御できる照明照度制御回路
(4)中高年のディズニーランド
上野から軽井沢まで1時間と知ってしまうと、もう新宿、渋谷、舞浜あたりへ行くのと気分は変わりません。
連休の中日(16日)また日帰りで軽井沢に行ってきました。
家を10時発。軽井沢12時着。駅前で蕎麦。
駅から碓氷峠見晴台までタクシー(ジャスト2千円)。
熊野神社にお参りし、見晴台で展望
見晴台から遊歩道で旧軽井沢まで4、5Km下山(たっぷり森林浴)。
旧軽からウインドウショッピングしながら軽井沢駅まで歩く(1、2Km)
5時少し前の新幹線に乗り家に7時前に到着
電車賃は片道5、6千円で少し高いですが、リフレッシュには最適です。軽井沢近辺には見どころが山のようにあります。次に、楽しみにしているのは、
(a)離山登山、(b)旧中山道を横河まで下る、(c)白糸の滝、(d)美術館や文化施設、等々です。また、季節による自然の変化も楽しみです。
軽井沢は中高年のディズニーランドって感じです。若い人も楽しめると思いますよ。
===
写真は、見晴台から見た山々と、遊歩道の吊り橋です(熊が時々でるようなので注意が必要です)。

m12 ( 2007/09/16 05:26:28)
テレビの偏向
最近、社会(特に若者)に悪い影響を与えているテレビ番組(特に民放)が多すぎると思う。
(a)暴力、残忍な犯罪の再現、裸や性描写、
(b)態度の悪い芸能人やスポーツ選手をスター扱いし、弱いものをいじめ、
(c)”まじめ”をバカにし、不真面目を賞賛し、建前を極端な本音で笑いものにし、
(d)暴力、ドラッグ、レイプ犯を簡単にテレビ復帰させる。
(e)ワイドショーは一見ニュース番組に見えるが、実はショーであり、不幸な事件など起ころうものなら一番喜んではしゃいでいるのがテレビだったりする。
テレビ局は自分に都合の良い時だけ”公器”と言い、後は”面白ければ何でもあり”で知らんぷりしている。特に日本ではテレビが生活の中心にあり、テレビを通して様々な情報が無差別に家庭の中に入ってくる。
テレビには、社会の教育まで担っているという自覚を持って欲しい。最近の目を覆いたくなる犯罪の増加は、テレビやマスメディアの影響と無縁とは思えない。
以前”富の未来(トフラー夫妻著)”という本を紹介した。この本の中にテレビや映画が若者に与えている影響を記述している部分があるので、そのいくつかを紹介する。
===以下、富の未来の一部(少し簡略化した部分もある)===
(1)大衆文化のかなりの部分は、悪党やギャング、ドラッグ王、ドラッグの売人やうつろな目をした中毒者を美化している。
どこまでも続くカーチェイスや、派手な特殊撮影、性差別の毒をしたたらせた歌などで、極端なまでの暴力を称賛している。そしてこれらの商品を売り込むために、限界を超えた強引な広告が使われているので、悪影響が一層強まっている。
(2)ハリウッド映画が描くアメリカは、若者の快楽主義が絶対的力をもっており、警官や教師、政治家、経営者がいつも”こけ”にされる夢想の世界である。映画やテレビ番組がこれでもかと言わんばかりに、若者の多くが聞きたがる話を聞かせている。大人はみな間抜けだ、お馬鹿で何が悪い、勉強なんかしなくていい、悪いことをするのは良いことだ、やってやってやりまくれ。
(3)極端に走るのは良いことであり、自制するのは良くないと繰り返し聞かされている。
(4)スポーツはかつて、各人が自分で楽しむためであったが、やがてクラブやリーグに組織化され、マーケッティング業界が各種商品を売り込もうとし、テレビ産業のニーズにしたがうようになった。オリンピックに関する贈収賄、リトルリーグの腐敗、有名選手のドラッグ、レイプ、暴行、殺人が後を絶たない。
(5)特に若者は映画、テレビ、ゲーム、インターネットで暗黒の未来のイメージにたえず接している。
(6)メディアが作り上げ、若者の憧れの的とされているスターは、街角のチンピラや傍若無人な歌手、禁止薬物を使うスポーツ選手などだ。
===引用、終わり===
日本よりは少し過激だが本質的にはさほど変わらない、日本が後を追っている状況である。我々は恐ろしい環境にさらされているものである。
このようにテレビやマスメディアの偏向した環境でも、我々は自分自身を正常に保たなくてはならない(至難の業であるが)。偏向に流されれば待っているものは転落と犯罪である。
せめて学生さんに最低限、
(a)学を志す者は、芸能人を真似た薄茶色のボサボサ頭にするな。単位を落としそうな学生は、皆この髪型をしているぞ。
(b)ズボンを落としてはくな、パンツを出すなんてもっての他だ。バカな格好をしていると本当にバカになっちゃうぞ。
(c)思い通りいかない時、物に当たるなど、自制のない行動をとるな。うまくいかない時ベンチを蹴ったり運動具を投げつけたりするスポーツマンや芸能人がいるが、あれはサッカーの試合中にグランドで大便をしているようなものだ。
(d)残酷なゲームや醜い映像、不気味な本など避けよ。本当にそんな状況に陥ってしまうぞ。
以上。
===
追伸:昨日、うちのそばで嶋根さんをみかけました。友達と別れを惜しんでいたので、雰囲気を壊すといけないと思い通り過ぎました。少しやせたかな?
===
写真は、4年生の北海道旅行です(北海道旧庁舎と富良野)。

m11 ( 2007/09/12 18:21:40)
生物学の知識
生物と無生物のあいだ(福田伸一著:講談社現代新書)
(1)この本は、生物と無生物を区別する2つの特徴を紹介しています。
(生物の特徴1)全ての細胞は常に入れ替わっている(今の自分は過去の自分ではない):
半年か1年もすれば体の全ての細胞が新しいのものに入れ替わっているそうです。この話はどこかで聞いたような気がします。驚くのは、憎き皮下脂肪までが古いままで溜(た)まっているのではなく、常に新しいものと置き換わっているのだそうです。
(生物の特徴2)生物を構成するタンパク質の融通無碍(ユウヅウムゲ):
生物は色々な種類のタンパク質でできています。そして、
(a1)DNAに仕掛けをし、特定(どれでもよい一つ)のタンパク質を取り除いた生物を作っても生物は何の異常もなく生存できるそうです。しかし、
(a2)その特定のタンパク質を作るDNAを一部壊した場合、生物は生存できなくなるそうです。
これに対し、無生物では、
(b1)テレビなどの電子機器は部品を一つ取り除けばテレビが映りません。しかし、
(b2)その部品を取り除くのではなく、その部品の一部を壊した場合、映りは悪くても少しは映ったりすることもあります。
(2)この他、DNAの2重螺旋を発見したワトソンとクリックの話が書かれています。その中で彼らの発見に当たっては、フランクリンという女性のX線解析結果を密かに覗き見ていた(と思われる)、という話を紹介しています。ワトソンとクリックがノーベル賞で脚光を浴びている時、フランクリンはガンでこの世を去った、という話が紹介されており(著者の説が正しければ)ワトソンとクリックのノーベル賞がくすんで見えます。
(3)余談1(プチ自慢):著者福田氏は、ソーク研究所を訪問した際カフェテリアでクリックと遭遇し、感激した様子を書いています。それなら、私もUCSDの研究所を訪問し10人程度の研究室ゼミに参加した際、クリックも参加していました。あまり綺麗ではない真っ赤なジャケットを着ていて、院生の怪しげな研究提案に、”新しい提案は、時としてすぐには理解されないものだ”とか助け舟を出していました。
(4)余談2(文才):本の最後に著者の小学生時代の思い出話があり、”アオスジアゲハ”を次のように表現しています。
”アオスジアゲハは小型のアゲハチョウで、黒いビロード地の羽に、四角い斑点が、小さなガラスブロックを端正に並べたように縦向きに走っている。その斑点の色彩は、透きとおるように鮮やかなミントブルーをしている”
以前私が書いた、アオスジアゲハの記述に比べると細やかな観察に基づき繊細で情緒的な美しい表現がなされており、文筆の才とは、かくなるものかと感心させられます。
==
前回のパプリカにもアオスジアゲハが象徴的に出てきます。オジサン達、アオスジアゲハが好きなのかもしれませんね。写真はWikiPediaアオスジアゲハISAKA Yoji氏の作品の一部です。

m10 ( 2007/09/09 05:56:10)
パプリカ
(1)パプリカ(アニメDVD by SONY)
半年くらい前、ニューズウイークで高く評価されていたので、初めてアニメDVDを購入してみました。
他人の夢を共有したり支配したりするマシンが盗まれ、それを解決する話です。よくできていて何だか現在の自分が夢の中にいるのかもしれないという錯覚に陥ります。
欲を言えば、
(a)絵的には少し宮崎アニメの影響を受けている。
(b)ラストにもう一ひねり欲しい。
(c)もう少し工夫して子供も見られるようにするとよい。
と思いました。
興味のある方はメールを下さい、お貸しします。
(2)テツ
江戸東京博物館で”大鉄道博覧会”というのをやっていたので見てきました。”大”は大袈裟で、ミニ鉄道博覧会って感じでした。昔の”こだま(下図)”とHOゲージの模型には少し心が動きましたが、のめり込むことはなさそうです。
それより、普段、東武、新京成、京成線しか使っていないので、久しぶりで総武線に乗ったら速いこと、速いこと、特に船橋市川間なんか、ジェットコースターみたいで引きつってしまいました。
(3)船橋ららぽーと
”マジすごい”って話なので、初めて行ってみました。確かに大きくて柏ららぽーとの2、3倍って感じで、迷子になりました。
気になった点:
(a)さんるーむという健康食店で韃靼(だったん)そばを食べました。柏の高島屋にもさんるーむがあり、よく韃靼そばを食べるのですが、そばの色が柏のものと全然違います(船橋のは黄土色)。系列店でこんなに色が違うってことあるのかしら。
(b)東京パン屋ストリート:菓子パンやおかずパンの店がほとんど。パン好きの私としては、せめて半分位の店はパン生地だけで勝負する店にして欲しいと思います。
特に個人的に許せないのは”メロンパン”です。普通合成着色料で着色している(船橋のものは食べてないので分かりませんが)のでツーンとした匂いがして大切なパンの匂いが台無しになってしまいます。私の前でメロンパンが好きだと言わないように(味覚のない人というレッテルを貼られますので)。
(4)船橋港親水公園(ららぽーとの裏)
ららぽーとの裏という折角の立地条件なのに、工夫のない公園で、ホームレスの人が何人か寝ているだけでした。以前は横浜まで船が出ていた模様です。
船着場はあるので、
(a)東京湾までゆく納涼屋形船を用意するとか、
(b)ボート乗り場にするとか、
(c)海老川を使って船橋駅との連絡船にするとか、
船橋市も工夫すれば立派な観光資源になると思います。
(5)菱木さん
5日夜、新鎌ヶ谷駅で今年吉田研を出た菱木さんと電車のドアですれ違い(私は降車、菱木さんは乗車)ました。大学時代よりはるかに元気そうでした。
(6)歳時記1 野分
7日早朝、台風9号が小田原から熊谷にぬけていきました。村田君ちや梅澤君ち、大丈夫だったかしら?
芭蕉野分して盥に雨を聞く夜かな (芭蕉)
(ばしょうのわきして たらいにあめを きくよかな)
ってのが有名です。私が子供の頃も家が粗末だったので、洗面器で雨漏りをしのいだり、玄関の戸がしなって飛ばされそうになり、交代で戸を押さえたりしたものです。
(7)歳時記2 秋
8月最後の週、朝窓を開けると秋の虫が沢山鳴いていました。また今週、5時くらいに大学の庭にでると、セミの声と秋の虫の声が5分5分で聞こえてきました。
”秋きぬと 目にはさやかに 見えねども 虫の声にぞ 驚かれぬる”
といったところかしら。そう言えば、今週2回ツクツクボウシが鳴いているのを聞きました。
(8)訂正1:l35でBYと書いたものは、KY(空気読めない)の誤りでした。
(9)訂正2:同じくl35で、ドンダケ〜!は省略形ではない、と書きましたが、ドンダケノモン!!(多分、ナニサマってことか?)の省略形のようです。
==
これは昔の”こだま(1958年、私小学5年生)”のイメージ図です。当時、電車と言えば直方体で、色もこげ茶だったので、この”こだま”は新鮮でかっこよく思えました。その頃はプラモデルもなく、模型といえば木だったのですが、”こだま”の模型は高くて買えませんでした。

m9 ( 2007/09/05 17:02:28)
ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く(リサ・ランドール著:NHK出版)
新聞の書評と”5次元”というキーワードに魅かれて読み始めた。欧米で物理科の教科書に使われているだけのことはあり難解で、何回もギブアップしそうになる(読み終わるのに2ヶ月近くかかった。物理科の学生にはお薦めだが、その他の人には無理)。
内容は素粒子物理学で、正直ほとんど分からないが、素粒子物理学(あるいは素粒子物理学者)の熱さに感じて読み進んでしまった(この本のおかげで、3回電車の乗り越しをしてしまった)。
分からないなりに分かったこと:
(1)素粒子物理学とは:物質を作る最小構成要素を探す学問である。
昔は、物質は原子からできていると習った(原子が素粒子だった)。その後、研究が進み今や、クオークや電子がさらに何で出来ているかという話になっている。
==原子の構造==
原子
||
原子核+電子(原子は原子核と電子からできている)
||
中性子+陽子+電子(原子核は中性子と陽子からできている)
||
クオーク+レプトン+電子(中性子や陽子はクオークとレプトンでできている)
||
ひも+ブレーン+余次元 <==(本書のテーマ)
=========
本書は、現在、有望な素粒子と考えられている”ひも+ブレーン+余剰次元”の研究について数式を使わずに説明している。
(2)ひも理論とは、電子やクオークは粒子ではなく”ひもの振動”でできている、という説。
(3)高エネルギー加速器との関係
この様に小さな世界の話になると直接見ることができないので、様々な理論的素粒子が提案できる。そこで、どれが正しいか、電子や陽子を光速近くまで加速し(加速器は山手線がスッポリ入るほどの大きさ)、衝突させて出て来る粒子を調べ、理論の絞込みを行う。
(4)宇宙との関係
素粒子は極小世界の話で、宇宙は極大世界の話なので関係ないと思っていた。素粒子を提案する際、それが宇宙をどう構成するか(宇宙の創生と構造)まで説明できるものでなくてはならない。そのため両分野の研究は密接に関係している。
素粒子物理は気宇壮大なロマンチックな学問だった!
(5)5次元などの異次元が、ごく自然に出てきて、なんだかスピリチュアルな世界があってもおかしくないような気になる。
(6)重力のみが異次元全てに通じる力らしいので、重力通信で異次元と交流ができるかも(私のSF的発想)。
(7)高エネルギー加速器で小さなブラックホールが作れるらしい。
小さなブラックホールは、すぐ消えるらしいが、その理論に誤りがあり、ブラックホールが消えずに大きくなり、加速器を飲み込み、都市そして地球を飲み込む、なんてSFが作れそう。
(8)電磁場は、素粒子論的には”光子”の受け渡しで生じる。
電磁気の理論は50年以上も前に完成していると思っていたので、このアイデアにはビックリ。自分の信じているのもの本質が全く違うものだったりすることがあるものだ。
(9)素粒子物理学者の熱さに触れると、自分が若い頃抱いていた情熱(今までにないコンピュータを作りたい、人間のような柔軟な思考を実現する情報処理方式を確立したい)を思い出し、懐かしくなる。
(10)こんな難解で売れそうもない本を出版した”NHK出版”の見識に敬意を表する。
この本は、私が持っていても宝の持ち腐れになるので図書館に寄付しました。
==
写真は薬学部6年制移行のために建てた薬学部棟(8月23日竣工)

m8 ( 2007/09/01 13:49:13)
ディズニーシーひとりぼっち
以前から一度ディズニーシーを覗いてみたいと思っていましたが、8月29日、近くに用があったので(おじさん一人では恥ずかしいのですが)思いきって入ってみました。
どうやら2つの新記録を更新したようです:
(1)一人で入場する人の最年長記録
(2)最短滞在時間(10時入場、1時退場)
気付いた点を並べてみると:
(1)夏休み最終週で、割と涼しい日でしたが、入場者数が少ない。でも、人気アトラクションは1時間待ち。
(2)レストランや売店はほとんど人が入っていない。
(3)従業員同士の私語が多い。
(4)従業員に欧米人が少ない。アトラクションの案内放送はほとんど全部日本語だったが、英語にした方が非日常性がでて良いかも(英語放送の近くに放送英文の和訳や解説員を用意し、楽しみながら英語を学べるようにするとよい)。
(5)施設に貼られているスポンサーの会社名(赤)が目障り(せめて目立たない色で英語表記にならないか)。
利用した乗り物とアトラクション:
(1)蒸気船:ワニやカバは出てこない。
(2)シンドバッドの冒険:ディズニーランドではスモールワールドがお気に入りなので、シンドバッドも最高でした(”人生は地図のない冒険”とかいう歌詞の歌が流れていた)。
(3)ストームライダー:この程度なら目を回さない。
(4)電車:車内から本物の海が見える(写真)ので、いっそ、水門を壊して海に直結するとスゴイかも。
総括すると:
(1)一人で行くのは一寸さびしい:遊園地やテーマパークでは、”一緒に行った人が喜ぶ姿を見るのが喜び”、というハイレベルな喜びが実現されていることを知る(同伴者もアトラクションの一部であり、自分もまたアトラクションの一部となりうる)。
(2)今回は急な思いつきで入場したので勉強不足だった:後でパンフレットをゆっくり見ると、入ってみたかったな、という所もある。
(3)大人向けテーマパーク:ディズニーシー内のモスクなどの建物はどうも高級感がないので、本物と同じ作りのモスクや実物大のピラミッドを製作し、世界のショーや料理を楽しめるものを作るとよいかもしれない(老人はお金を使わないので成り立たない、という噂もあるが)。

m7 ( 2007/08/29 15:13:00)
8月最終週
早いもので、もう8月も終わりです。猛暑でフーフー言った夏でしたが、個人的には体調が良かった(良くなった)月でした。
”眠りの浅さ”に関する健康情報(シニア向けかも)
今月、私を長いこと悩ませてきた眠りの浅さと、それに伴うトイレから開放されました。これまで、眠りが浅く90分ごとに目を覚ましてしまい、ついでにトイレへいく状態でした。
自己分析で、脳が昼と夜を間違えてしまっているのだなと思っていました。
この夏(不眠解消に役立ったかもしれない)いつもと違った生活パターンを挙げてみます:
(1)運動: 今年の夏は運動する機会に恵まれました。
(a)テニス
5、6階の4年生の(あそび)練習に入れてもらって週一1時間くらい楽しませてもらっています。炎天下で球を追っていると、強い日差しが目に入り、脳の昼夜切り替えスイッチが正常化したのかもしれません。あるいは体がテニス狂時代を思い出したのかもしれません。
(b)水泳
家から歩いて10分位の所に”ひばりが丘市民プール”というプールがあることを発見して朝一に30分くらい泳ぎにいきます。ただ、水泳を始めたのは昼夜正常化後です。
このメインプールは50mの屋外プールですが、その他、円形子供プール、25mの浅いプールがあり、子供はそちらの方にいくため比較的すいています。
(2)体調が正常に戻ったのは軽井沢(2泊)から帰った日(8月7日)からです。軽井沢との関係は偶然だろうと思っていたのですが、数日前テレビで”自然の中にいると脳のリズムが正常になる”、というのをやっていて、もしかすると軽井沢で早朝別荘地帯を長時間散策したりしたので(森林浴効果?)、脳の昼夜切り替えスイッチが正常にもどったのかもしれません。
(3)寝方(2寝床方式):私の寝室はリビングの隣の和室です。私の部屋にはエアコンがないので、夜はリビングのエアコンを点け、リビングとの間のフスマを20cm位開けて寝ます。
この時寝室には2つの寝場所を用意します:
(1)竹シーツ(面積2x3cm厚さ7mm位の竹片を沢山並べたもの、中国製2千円弱、ヒンヤリして涼しい)を畳の上に直接敷き、隣に
(2)ベッドのソファー部を畳の上に置きます。
就寝時は、先ず竹シーツの上に寝ます。やがて、1時か2時位になると寒くなって目を覚ますので、エアコンを切り、隣のソファーに移り2度目の眠りに入ります。
畳に敷いた竹シーツは一寸痛いのですが”臥薪嘗胆”の臥薪よりはましだと耐えます。
(4)早寝:9〜10時に床に入ります。幸い、眠りに入るのはアッという間です。
お父さんやお母さんが”眠りが浅くて”と悩んでいたらヒントになるかもしれないので教えてあげて下さい。
(注)臥薪嘗胆とは:中国の春秋時代、越王勾践(こうせん)に父を討たれた呉王夫差(ふさ)は悔しさを忘れぬよう薪(たきぎ)の上に寝て、やがて仇を討つ。敗れた勾践は敗戦の恥辱を忘れぬよう室内に胆(きも)を吊るして嘗め、ついに夫差を滅ぼしたという。
===
写真:8月28日、中高生向け夏休み理科教室がありました。講師は(ヒカルの碁監修)梅沢由香里さんでした。私も中高生に混じり囲碁を初体験しました。ムズカシ!、でも、面白いかも。

m6 ( 2007/08/26 14:06:12)
閑中忙
8月23、24日 FD(Faculty Development)教育の見直しや改革を検討する研究会(1泊2日ユーカリが丘ウイシュトンホテル(佐倉)缶詰)
8月27日 大学院入試
9月1日 AO入試
(1)24日早朝、ホテルから10分位の所にある公園(上座公園)までウオーキング:
広くてなかなかよい公園です(一寸外国の公園みたい:言い過ぎかも)。公園内に”カノコガ”(写真右下隅)が何匹かいました。”カノコガ”は蛾には見えず、かわいいトンボか蝶って感じで、私が小学生時代、朝ラジオ体操に学校へ行く途中でよくみかけました。
また、”サトキマダラヒカゲ”も何匹もみかけました。佐倉はまだ少し自然が残っていました。
(2)本を2冊読みました:いずれも当初売り切れでしたが、最近は手に入ります(いずれもお勧めです)。
(a)川の光(中央公論新社):川のほとりに平穏に暮らしていた3匹のネズミ一家が、巣穴から追い立てられ、新天地を求めて川を上流に遡る冒険物語。人生を感じさせる、癒し系冒険物。
(b)「気づき」の幸せ(小学館):青森の神様、初の著書。スピリチュアル系とは言え、物事がうまくいかない時は、先ず、自分に問題がないかを確認しましょう(気づきましょう)、という心霊がかっていないお話。
(3)教育:
FDでは、最近の教育の流れに沿って、
・学生さんに対し、きめ細かく、丁寧に、個人の特性をよく見て対応していきましょう。
・学生さんに強いストレスを与えることなく、学問に対する興味を引き出すよう工夫しましょう。
・学生さんの授業評価を参考に授業を改善しましょう。
といった精神をベースにしていて、確かに、結構で当然の流れのように思える。
でも、何だか学生さんをお客様扱いしているように見えて、教育はこれでよいのかな?って気もする。
大方の学生さんは問題ないにしても、小さい頃からこのような教育を受けてくると、人によっては心配な点も出てくる気がする:
(a)長い間お客様扱いされていると傲慢になり、やがては勘違いして”オレ様”に、そして”給食費を払わない親”に変化していく怖れはないか?
(b)人間あまり大切にされ過ぎると弱くなり、社会に出てやっていけるかという不安も残る。監視員付きのお子様プールで遊んでいた人が、突然背も立たず、サメも泳いでいる荒海に放り出される感じになりはしないか? 最近増えているという20代、30代の人の”うつ”は、これと関係があるのではないか?
(c)至れり尽せりの環境で好奇心はうまれるのか? 最近面白実験などで科学への興味を引き出そうという番組をよく見る。(ああいうアプローチもあるかとは思うが)何か違うよな、と思う。与えられ過ぎているし、お膳立てされすぎているし、面白さで引いた興味なんてそう長続きはしないのではないか。
===
写真はベランダのケイトウとカノコガです。

m5 ( 2007/08/22 12:45:17)
船橋、柏、我孫子のブランディング
上の3市は、私が日常99%の時間を過ごしている生活域である。最近、これらの市がお笑いのネタになっていて残念である。
柳原可奈子は総武線船橋(たまに柏も出てくる)ネタで笑いを取り、
狩野英孝は”ぼく我孫子”で笑いを取っている。
はなわの歌には”♪牧瀬里穂も「佐賀」!でも公表してねえ〜!”というのがあるが、はなわ自身も我孫子で育ったことを公表していない。
一昔前には、”夕方、中央線に乗ると皆日経新聞を読んでいるが、常磐線に乗ると皆東京スポーツを読んでいる”というのもあった。
そんな先入観があるからか、
横浜駅に降りると、女性の着ているものが”おしゃれ”な感じがするし、
中央線に乗ると何か品がよく気取っている感じがして、気おくれしてしまう。
それではということで、我々の生活圏をブランド化する荒業を:
(1)ディズニーランド市:
船橋は、浦安、市川、と組んで政令指定都市になり、ディズニーランド市と改名する。
(2)環境改善モデル:
手賀沼を取り囲む我孫子、柏などの市が組んで(かつて日本で最も汚かった)手賀沼の水質を日本一にし、各種水上スポーツの拠点とする。
===
l35で紹介した卒業生が花火大会の写真を送ってくれました(葛西臨海公園2007_08_18)。

m4 ( 2007/08/19 05:39:26)
絶滅危惧昆虫(蝶編)
(1)モンシロ蝶、モン黄蝶、筋黒白蝶:
・モンシロ蝶は今でも早い時期によくみかける。
・モン黄はモン白の黄色版で、最近あまりみかけない。
・筋黒白蝶はモンシロ蝶の筋が黒いもので昔でもたまにしか見なかった(年に2,3度)。白と黒のコントラストが美しい。
(2)アゲハ、黄アゲハ、青筋アゲハ、黒アゲハ、烏アゲハ:
・アゲハ蝶は今も主役でよく見かける。
・黄アゲハは黄色っぽいアゲハでこれも見かける気がする。
・青筋アゲハは今の方が多いような気がする。美しいので採りたかったが、羽が細いためジェット戦闘機のように身軽に体勢を変えるのでなかなかつかまらない。
・黒アゲハと烏アゲハは比較的暗くて涼しい所に現れる印象がある。
(3)赤タテハ、瑠璃タテハ、コミスジ:
・赤タテハ(写真上左)は呼塚(ヨバツカ)付近のニラ畑に沢山いて、採りにいったがすばしっこくてめったなことでは採れない。前々回オニヤンマとの一騎打ちの話を書いたが、蝶では赤タテハが一騎打ちの対象であった。
・瑠璃タテハ(上中)は当時でも年5,6回しか出会わなかったが、これも身軽でなかなか採れなかった。本物はモルフォのような光沢があり、下の図より格段美しい。
・コミスジ(上右)はよく見かけた。空気の上を滑るように旋回する。速度はたいしたことがないので採りやすく思えるが、なかなかすばしっこくて採れない。
(4)ジャノメ蝶、サトキマダラヒカゲ:これらは地味な連中で採ろうとする人はまずいない。
・ジャノメ蝶(下左)は家の裏手の(当時は汲み取り式)トイレのあたりによくいた。
・サトキマダラヒカゲ(下中:この写真は羽の裏側)はゴミ捨て場や腐った柿の実から蜜を吸っている感じだった。
これらは、不浄な場所でも生きられるのでタフな種だと思っていたが真っ先に絶滅してしまった。環境が綺麗になったということか?。
(5)イチモンジセセリ(下右):
・これは、道(舗装されていなくて草が生え、リヤカーや荷車の車輪の跡がある)によくいた。これも掃いて捨てるほどいたので、永遠に生き延びそうな感じだったが絶滅した。
(6)アサギマダラ:友達が採ってきたので欲しくてしょうがなかったが我孫子にはいなかった。当時箱根に行った時大群と出会った。箱根にはアサギマダラが大量にいるのだと思ったが、以後箱根でもあまり見ない。最近テレビで知ったのはアサギマダラは”渡り蝶”で大群で長距離を移動するらしい。箱根での大群との出会いは移動中に偶然遭遇したものらしい。
===
一昨日NHKで”生物の大発生”をやっていました。地球温暖化により日本では、クマゼミ、アルゼンチン蟻、食べられないウニ、が大発生しているそうです。
印象深かった2点:
(1)温暖化で雪解けが遅れると、花が咲く時期と、蜂が目を覚ます時期のタイミングが合わず、実を付けられないケースが起こってくるそうです。花と昆虫なんて別の種だと思っていましたが、何だか花と昆虫がセットで一つの種に見えてきました。人間も含め、自然とセットで一つの生物と考えると現状は一寸怖いですね。
(2)日本蟻は蝶の幼虫を養ったりしているそうで、日本の生態系を構成する一員です。ここに最近、身体能力が高い上、作戦能力にも優れたアルゼンチン蟻が侵入し急速に領地を拡大しているそうです。日本とブラジルのサッカーとか日本とキューバの女子バレーを見る思いがしました。
グローバル化は人類にも同じような影響を与えるでしょう。今までは、それぞれの風土と文化に最適に適応した体型や考え方を持った多くの人種が存在しました。これからは、地球規模の社会に適応した人種だけ、あるいは適応するように進化した数少ない人種だけが生き残ることになるでしょう。日本人も、何らかの形に収束していくのでしょう?
===

m3 ( 2007/08/17 05:58:22)
40、9度(74年ぶり日本新記録)特別号
昨日、日本最高気温が出たようです。本当アツッ!!って感じで、身の危険を感じ通勤ウオーキングを中止しました。それでも大学に着いた時には汗ビッショリでシャワーを浴びました(念のため持っていった下着が役に立ちました)。
ハワイやシンガポールもこれほどの暑さは経験していません。唯一経験があるのは10数年前の京都です。会議場とホテルの間約100mを、走って移動しました。
地球温暖化どころか熱帯化と呼んだ方がよさそうです。昨夜のニュースによれば、石垣島付近の珊瑚は枯れ出し、北極の氷は予想よりも2、30年速い速度で融けだしているそうです(北極氷面積世界最小記録を更新したそうです)。
家のごみも臭くなるので今ゴミ置き小屋へ持っていきましたが、小屋の中がものすごい腐敗臭で倒れそうでした。昨日は学生さんの研究室にゴキブリが現れ、大騒ぎでした。
北海道への移住を検討する人が増えてきそうですが、北海道ではミートホープに続き”白い恋人”が炎上中です。
エアコンをかけないと危険だと言い、エアコンをかければ電気を使って熱帯化が進む、という悪循環に入ってしまったのかもしてません。戦争なんかやってる場合か!って感じです。
暑くて、段々話が支離滅裂になってきました。少しでも清涼感をと、下の写真は軽井沢の早朝”雲場の池”(8/7日撮影)です。

m2 ( 2007/08/15 05:49:38)
絶滅危惧昆虫(セミ、トンボ編)
私が子供の頃の夏休みの遊びと言えば虫捕りであった(昆虫にはご迷惑をおかけしたが)。今の子供たちがゲームのキャラクター名で話が通じるように、当時の男の子たちの間では蝶やトンボの種名で会話が成り立っていた。
最近、あまり見なくなってしまった昆虫が気になるので今回と次回、絶滅が心配される種を中心に我孫子付近の昆虫と虫達との思い出を書いてみる。
蝉:
現在、大学はアブラゼミとミンミンゼミの大合唱である。
(1)ニイニイゼミ(写真左):夏休みが始まるか始まらないかの一番早い時期に鳴き出す。これは鳴き声からチイチイゼミとも呼ばれた。採るのが最も簡単なセミであった。
(2)アブラゼミ:今同様、夏中鳴き続ける主役であった。当時、市川の梨園に行ったところ、梨園は今のように網を張っていないのでアブラゼミが沢山いて、顔にバシバシぶつかってきた。
(3)ミンミンゼミ:今ほど多くなく、年に数えるほどしか出合わなかった。ミンミンゼミが来ると羽が透明で美しいので何とか採りたいと外へ飛び出すが、大体非常に高い所に留まるし、体の割りにすばしっこくて捕まえた記憶は全くない。
(4)ヒグラシ(写真中):その鳴き声からカナカナとも呼ばれ、比較的夏の早い時期に鳴く。それでも夕方カナカナの声を聞くと何だか寂しくなった。もし、夏の終わり頃にでも鳴かれようものならとても耐えられなっかったかもしれない。ヒグラシは比較的採りやすい。
(5)ツクツクホウシ(写真右):ツクツクコインヨーと暑い盛りに鳴く。これはヒグラシより高い所に留まり、すばしこいので採りにくい。
蜻蛉:
(1)ムギワラトンボにシオカラトンボ(どちらかが雌):これらは今同様主役だったが数は今の10倍くらいいた。
(2)赤トンボ:これは、今のほうが多いように思う。
(3)オニヤンマ:トンボの王様って感じで今でも年に1,2度出くわす。昔、オニヤンマがよく、家の前の7、80mある直線道路を高速で行ったり来たりしていた。私は道路の中ごろに陣取り高速直球風に飛んでくるオニヤンマを狙う。真っ直ぐ飛んでくるので捕まえやすいように思うが敵もさる者そう簡単には捕まえることはできない。トンボとの一騎打という感じで気分が高揚した。オニヤンマの親戚のギンヤンマとかというのもいた。
(4)チョートンボ(写真左上):蝶の様な黒いトンボで家の前の松林には沢山いた。簡単に捕まる。
(5)糸トンボ(写真右上):池のそばなどに沢山いて、手で簡単に捕まえられた。綺麗な青や緑の種がいて、かわいい感じだった。
(6)コシアキトンボ(写真左下):腰が白く透き通っているのでこのように呼ばれる。当時、年に10回位みかけた。
(7)オハグロトンボ(写真右下):我孫子ではめったに出会わなかったが(もう少し田舎の)守谷ではよく見かけた。
===
現在、写真のセミ達の声はめったに聞かない。写真のトンボ達もほとんど見かけない。もし、これらの昆虫達に遭遇したら、4、50年前の環境がどの辺まで後退しているのか知りたいのでご一報下さい。
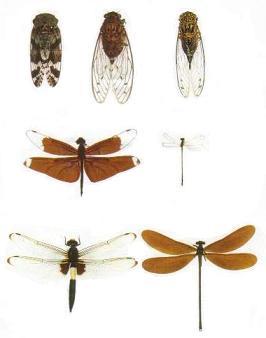
m1 ( 2007/08/11 06:16:13)
余剰(異)次元
期末テストのアンケート結果(最近読んだ本)を基に2冊の本を読んでみた。
(1)家守奇譚(梨木香歩、新潮文庫):学生さんが読みそうもない書名というか、古典的雰囲気の書名に惹かれ読んでみた。
内容は、何ともうまく説明できないが、異次元と自然な往き来が行われる昔(明治時代)の世界の話、って感じである。癒し系で、暑い電車の中で読んでいても、頬の筋肉が緩む感じ。車内で読んでいると、隣の人が、ひょっとして”かわうそ”かもしれないな、なんて気がしてくる本である。
本の厚さはせいぜい5mm位で薄いが、意外と読むのに時間がかかった、というよりゆっくり雰囲気を味わえる、って感じ。文章自体も品格があり、絶対お薦め!!
(2)涼宮ハルヒの憂鬱(谷川 流、角川スニーカー文庫):複数の学生さんが読んでいた唯一の本(他の本は全て1名のみ)なので読んでみた。表紙がロリっぽいので本屋さんで買うのがかなり恥ずかしい。内容は、異次元と不自然な往き来が行われる近未来学園話って感じである。文章で読む漫画といった感じ。
文章は今一だが、内容は大変面白く(1)にはない、ハラハラドキドキ感が少しある。特に感心したアイデアは”時間は連続でなく、アニメの1コマの様に離散的である”という話(そう言われると、何となくそんな気もする)。お薦め!!
本屋さんの”ライトノベルコーナー”が知らない間に拡大されている理由が分かる。
文章として2冊を比較すると、(2)は、汚い字で書きなぐった感じで、(1)は美しい(かつ分かり易い)草書で書いた芸術品といった感じである。学生さんが、この違いに気付いてくれればしめたものである。
私は社会人になってしばらくの間(1〜2年)、論文を書いて先輩に見てもらうと、真っ赤に朱が入った。最初は自分の文が”どう悪いのか”さえ分からなかった。やがて、3年もすると、段々朱がなくなってきて、同時に自分の文章を客観的に観ることができるようになってきた。
学生さんが始めて書く長文(卒業論文)も最初は文になっていないことが多い。
卒論を書く学生さんにはいつも:
”卒論は自分がやったことを書くのではなく、論文を読んだ人の脳に研究内容がどう組み立てられるかを考えて書くんだ”と言っている(これが簡単ではないのだが)。
話がそれちゃいましたが、
(3)ワープする宇宙(リサ・ランドール、NHK出版):新聞の書評で知った本、ハーバード大学物理学教授が書いた異次元(余剰次元)世界。厚い本で、ある程度難解。まだ半分も読んでないが、異次元が科学的に自然に導入されて不思議な感覚を経験できる。物理好きな人には、お薦め!!
==
写真は昨日(灼熱)の薬草園。大音量のミンミンゼミとアブラゼミの声を加えて見てください。

k42 ( 2007/08/08 10:40:53)
軽井沢
8月5〜7日、20年ぶりで軽井沢に行ってきました。軽井沢というと色々思い出があるので並べてみます。
(1)小学5年生の夏休み家族旅行(約50年前、最初の軽井沢):
(1-1)軽井沢は標高が高いため、列車はアブト式(歯車付き線路)とスイッチバック(行ったり来たり)を使って碓氷峠を超える(テッチャンにはたまらない)。
(1-2)鬼押出し:浅間山の溶岩が広がる斜面。
(1-3)小瀬温泉(軽井沢の奥の方)泊:小川を渡って旅館に入る、小川の音が夜部屋まで聞こえ心地良い。
(1-4)牧場:宿でおにぎりを作ってもらい、(南が丘?)牧場へ行き、草原の隅に座って昼食。牧場と言っても今のような観光牧場ではなく、本当の牧場のみ。
(1-5)草軽電鉄:軽井沢から草津に抜けるトロッコ列車で、山の斜面に沿って走り、空の青、山の緑、下は谷、ススキや蔦に手が触れそう。美しさが今でも印象に残っている。
(模型が有ったら買いたいと、トラウマになっている)
(2)子供が小さい時(2度目の軽井沢、約30年前、):
(2-1)鬼押出し:20年を経て、溶岩の山にも少し木や草が生え、記念館もきれいになっていた。
(2-2)揚水発電所(夜余った電力で水を上の池にくみ上げる)の見学:揚水池まで(エレベータだったか?)上る。池の周りにはニッコウキスゲが咲き乱れ美しかった。避暑に行って親子連れで揚水発電所を見学するあたり、技術屋っぽい。
(2-3)”かぎもとや”と言う手打ち蕎麦屋があり、おいしさに感激。
(3)塩沢湖のテニス合宿:
上と同じ頃テニスに凝っていて、あちらのテニススクール、こちらのテニスクラブの合宿、と妻子をほっぽり出して遠征を繰り返していた。
(4)学会(1986?):
国際会議が軽井沢であり、帰りに懐かしいので小瀬温泉まで足を伸ばす。宿は増改築が繰り返されたようで、昔の面影は2割程度。家に帰ってみると、父親が心臓発作で入院中。小瀬温泉は私の中で急に鬼門に位置づけられてしまった。
(5)時流れ、今回:
(5-1)ショッピングテーマパーク:駅の南側は大規模ショッピングモール(ららぽーとのでかいやつと言うか、アラモアナショッピングセンターみたい)。北側も駅から軽井沢銀座までほとんどショップが並ぶ。軽井沢は、ほとんどショッピングテーマパークだ(写真下:循環バス)
(5-2)かぎもとや:軽井沢店が店を閉め、中軽井沢本店だけになった模様。昔の味が忘れられず中軽井沢まで足を伸ばす。店は駅前食堂風だが、ファンがいるらしく大変混雑。味は、おいしいが昔ほどの感激はない(昔はワサビが本物だった気がする、蕎麦はワサビで決まる)。
テーマパークでよいのか?
観光地がどこもテーマパーク化している。軽井沢へ行くほとんどの人は浅間山に行かないだろうし、別荘エリア(写真上)を散策することさえなかろう。
北海道旅行の場合でさえ、若い人たちが挙げる観光地は、旭山動物園や富良野ラベンダー畑だったりする。北海道なら洞爺湖、阿寒湖、摩周湖、知床だろ、って言いたくなる。
テーマパークは苦労せずに楽しませてくれるが所詮人間の浅知恵の産物である。
夏休みは折角の機会なので、時間がかかったり、労力を要したりすると思うが大自然の素晴らしさを見てきて欲しいと思う。本当の感動って、山登りみたいなもので、苦労して自分の力で登った人だけ感じることができるものである。
一番心配なのは、人生の送り方がテーマパーク化してしまうことである。楽しみをお金で買って歩くような人生。”(安直な)楽しさ”にしか価値を見出せない人生。人生はそもそも”重い荷を負うて坂道を登るようなもので”、お金で楽しさを買って歩くようなのもではないし、そんな所に本当の喜びや価値は見出せないのだから。
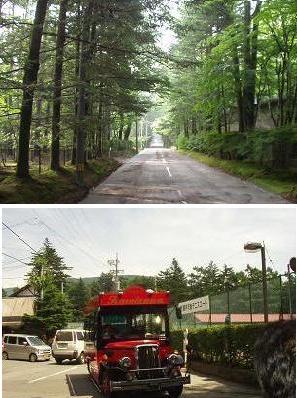
l41 ( 2007/08/03 16:55:38)
春学期終わる(あるいは夏休み始まる)
Open Campus:8/3日はオープンキャンパスで大勢の高校生が来られました。研究室の案内も4年生が上手にこなしてくれました(感謝!)。
結果報告:情報科学実験Iの追試の結果は全員パスで、おめでとうございます(ホッとしました)。
期末テストの印象2つ:
(1)今年の3年生が、例年と違うのは試験の結果を聞きに来る人がやたら多いことです。約70人受けて20人位が聞きに来ました。昨年までは聞きに来る人はほとんどありませんでした。
(2)今年は補助監督も含め2度試験に立ち会いました。特に気がついたことは、3人の学生さんが試験中トイレに行ったことです。今まで、十数年定期試験の監督をやってきましたが、昨年まではトイレに行った人は全くいませんでした。今年だけの偶然か、デリケートな人が増えたのか、準備の悪い人が増えたのか、今後注意して観察していこうと思います(部屋が寒いんだ、という意見もありましたが)。
形から入れ:追試の前には、危険水域近くの学生さんが5名位集団で質問に来ました。そこで気付いたのは、皆ほとんど同じ格好をしていて区別がつきにくいことです。どんな格好かと言うと、髪の毛を薄茶色に染め、髪は(私から見れば)ボーボーで大きな鳥の巣という感じで、服は大きめでだらしがない感じです。
いつまでも危険水域にいたくない人は、先ず見かけを変えてみる((大人から見て)さわやかにする)と結果が付いてくるような気がします。
==
下は、オープンキャンパスのイベント会場と個人相談会場です。
間もなくコンピュータの電源を落とすので、これをご覧になるのは来週だと思いますが、”とりあえず↑”。

l40 ( 2007/08/03 08:29:08)
連絡忘れてました!
今日はOpenCampusで、来週月火が大学の設備点検のため、今夜から7日までコンピュータの電源を落とします。
また、来週お会いできるのを楽しみにしています。
l39 ( 2007/08/01 13:27:09)
「(独立行政法人)産業技術総合研究所」(略称:産総研)
つくばには産総研(昔の国立研究所)という研究所がある。文科省が10年位前に、大学と外部との交流を盛んにする目的で”連携大学院”という制度を作った。本学情報科は産総研との間で連携大学院の契約を結び、共同研究を行ったり、大学院の研究指導をお願いしたりしている。現在5名の大学院生がこの制度を利用し、週2,3日研究所に通い研究を行っている。
この制度の利点は:
(1)最先端の研究を行っている人達と一緒に研究を行うことにより研究モチュベーションが高まること。
(2)同契約を産総研と結んでいる筑波大、千葉工大など様々な大学から学生が来ており、年長者が年少者を指導したり面倒を見たりといった大学の枠を超えた交流も行われている、と言った点である。
注意を要する点は:
(1)先方は、学生を一応学生(子供)扱いしてくれるが、大学に比べれば厳しい環境になる。自分から進んで研究する姿勢と実力そしてタフな精神力が求められる。
そんな訳で、この制度の利用を希望される学生がいた場合、強い意思と実力を確認して許可し、その後も精神状態を常に注意して見守るようにしている。
この制度も10年近く続いた結果、産総研内に、次の様なちょっとした東邦コネクションができあがっている。院生達、産総研で働いている卒業生、産総研関連のベンチャーで働いている卒業生達、数年前に退任された佐藤洋一先生も週1、2度産総研に来られていて本学科佐藤文明先生とも共同研究を行っている。
===
(私が産総研との窓口で)昨日は、研究連絡と学生さん達の様子を見に産総研に行ってきました。写真は、上記の東邦関係者との昼食の様子です。

l38 ( 2007/07/29 17:13:59)
人工知能の期末テスト:
ヒューマンインタフェースの出来がよかったので、調子に乗って難しい問題を出してしまい大ブーイングでした。部分点なしで点数を付けたらあまりに点数が出ないので、もう一度最初から”好意的に部分点を付ける方式”等で採点しなおし、何とか例年並の評点を付けることができました。
難問が成績に悪影響を与えていないことは点数を見ていただければ分かると思います。
アンケート:試験問題の最後にアンケートを用意し、この半年間に読んだ本の冊数と、書名を書き込んでもらいました。その結果、興味深いことが分かりました。
(1)集計結果(受験者数約70名)
回答なし(含む0冊):約30%、
1冊:約20%、
2〜4冊:約30%、
5〜10冊:約10%、
10冊以上:約10%(20冊以上の人も数人いました)。
この結果を見る限り、”最近の若者は本を読まない”、という話は当たっていません。
(2)書名(20人位が書名を書いてくれました)に関しても2つの興味深い点がありました。
(2-1)書名にほとんどダブリがない:私が学生の頃だと、若者の間(あるいは学科内)での流行があり、多くの人が共通の本を読んでいました。すぐ、思い出せるものでは、”竜馬が行く”、”ドクトルマンボー”、”沈黙”、”青春の蹉跌”とか。
(2-2)聞いたことのない書名が多かった:ネットで調べながら分類してみると、
*1:ネット小説、携帯小説、アニメ、ゲーム由来の小説(含む、未来型ファンタジー、ファンタジーミステリーホラー等):約20%
*2:ライトノベル系:約20%
*3:TVドラマや映画由来のもの:約20%
*4:古典的なもの(こころ、レ・ミゼラブルなど):約10%
*5:その他:約30%
(*1〜*3は、絡み合っていて完全に分類するのが難しい。この分野は不案内なので、多少誤りがあるかも)
私が普段良く読むのは*4、*5(せいぜい*3)あたりで、*1、*2はほとんど読んだことがありませんでした。本屋さんに行ってみると、なるほど、*1、*2系のコーナーが大きなスペースを占めていました。これらは表紙が漫画っぽいので、私は文庫本サイズの漫画だろうと思っていました。
読み物がこんなに違っているとコミュニケーションが難しくなってきます。幸い夏休みに入るので学生さんの読んでいるような本を読んでみようと思います。感想は、追って報告させていただきます。
l37 ( 2007/07/25 12:23:42)
今週末は参議院選挙投票日
(1)大臣が代わるたびに出てくる政治資金の不正使用疑惑。言を左右してして逃げようとするいつも見る姿。世間では通用しないこんなことさえ正せない国の中枢。
国の中枢は、コンピュータに例えるとOSであり、OSが正しい判断をできなくなるとシステムは暴走し、今まで地道に積み上げてきたルールやデータを全て壊してしまう。
政治家は立場によって、言い逃れ、言い訳、論点のすり替え、法律の捻じ曲げ、法律のご都合解釈、など、いくらでも平気でやる人達に見える。
(2)最近話題の憲法第9条問題も、憲法を捻じ曲げて作った現実が、憲法と乖離しているので、現実と矛盾のないように憲法を変えようという話だと理解している。現実に憲法を合わせたら、今度は又どこまで憲法の捻じ曲げが行われるかと思うと非常に心配である。アフガンなどに兵を送らされることにならなければよいが。
(3)政党政治の限界:社会は多様化し、経済、外交、教育、医療福祉、などの様々な分野に関する個人の考え方も多様化してきている今、2,3の政党の方針と一致する価値観を持った人などそうはいない。政党内でさえ考え方の違いで統一できない状況である。
結論を言えば、政党政治が限界に来ているということである。早い所、ネット社会が成熟し、ネットを介した国民全員参加の直接民主制に移行できればよいのだが。
(4)そこまで、まだ少し時間が必要だと言うのであれば、国会議員を専門分野別代議士制にしてはどうか(例えば、厚生代議士、教育代議士、外交代議士、など)。専門分野別代議士は専門分野に関して自分の方針を公表し、国民は自分の主義に合った人に投票する。もちろん、各分野がバラバラでは困るので、各分野を統括する統括代議士も用意する。
(5)それも無理なら、裁判員制度にならって、(常識が通じなくなってしまった政治に庶民感覚を取り入れるため)政治員制度を設け、無作為に選ばれた国民が立法に参加できるようにしてはどうだろうか。当然プロの国会議員の数は半減させて。
==
下の写真は、ここ1ヶ月位続いている4年生の水曜テニス会です(私も入れてもらっていて、テニス勘は少し戻ってきました)。いつもは20分位で引き上げるのに、今日は40分もお邪魔してしてしまいました。今、シャワーを浴びてきましたが、汗が止まりません。

l36 ( 2007/07/22 22:12:32)
日本語力
(1)小学校のカリキュラムに英語を入れる議論があると必ず、英語をやるなら日本語をしっかり学ぶ方が大切だという論陣を張る識者がいる。
私のように英語にコンプレックスがあるものにしてみると、日本語など自然に学べるので、小さいうちから英語をやらせてあげた方がよいのではないかと思っていた。
(2)ところが最近、この考えが少し揺らいでいる。”新しい概念”の理解が遅い学生さんに説明をしていると、以前は概念の理解力が弱いのではないかと思っていたのだが、最近たまに、概念の理解力ではなく”文章を読む能力”や”話を理解する”日本語の力が弱いのではないかと思う時がある。
最近の若い人はあまり本を読まなくなったと聞く。私は、日本語で生活をしていれば、本など読まなくても日本語力に問題はないだろうと思っていた。しかし、本を読まないと、文章の理解力が付かず、ひいては概念の理解力も育たないのではないかと考えるようになった。考えてみれば、文章の理解も概念の理解も基本的には同じはずである。
(3)”日本語力を付ける事は理解力をあげることだ”と気付いてから自分の中高時代を思い出してみると、国語を軽んじていたことを思い出す。これが自分の限界を作ってしまっていたかと思うと残念な気がする。
国語を国語と呼ばず、”概念理解力”を略し”概理”くらいにしたり、読書も”概念理解訓練”を略し”理訓”とでも呼ぶと、子供達も早いうちから、その重要性に気付くかもしれない。
l35 ( 2007/07/18 09:43:35)
DONDAKE〜!
先週の土曜、柏で3年前の研究室メンバーの飲み会がありました。この学年は不思議な学年で、”集まり”は夏冬夏冬夏ともう5回目ですが、無理なく集まっている感じがします。某さんに言わせれば”他生の縁”が少し深いのかもしれません。
若い人達と飲むと、色々勉強になります。私が最近頭を痛めていた問題も解決しました。
テレビで、よく”どんだけ〜”と言うのを聞きますが、どういう状況で使うのか分からず悩んでいました。多分、”どんだけ〜”の後ろに何かが省略されているのだろうと、色々当てはめてみましたが、”これ”と特定できる言葉がありません。
飲み会で、”ウソ〜!”の代わりに使えばいいのだと教わりました(微妙に、違う気もしますが、老人には分かり易い説明で納得しました)。なるほど、省略形というより、感嘆詞だったんだ!!
以前”なにげに”が流行った時、やはり学生さんに”意外に”の代わりに使えばいいんだと教わり納得したのを思い出しました、”とりあえず”。
この”とりあえず”も、適当な状況で会話に、はさめないと現代人とは言えず、BY(場を読めない奴)ということになるのだそうです。
最近、コミュニケーション能力のない人が増えているそうで、そういう人達の会話訓練には、話の中に”どんだけ〜”を頻繁に入れるよう練習させるとよいかもしれません。もっとも、”どんだけ〜”は元々オネー語らしいので、今まで気付いていなかった性格に目覚めてしまったりしても責任は負いかねますが、とりあえず。
===

l34 ( 2007/07/15 05:28:37)
ヒューマンインタフェース(HI)
2年前からHIという授業を行っていて、期末には試験がわりにflashを使った作品を提出してもらっています。
今年度は、計算機実習室の関係でflashが使えず、flashもどきのsuzukaというソフトを使いました。suzukaは、よく出来ているのですが参考資料が少ないのが悩みの種です。特にアクションスクリプトを使う資料はほとんどなく、私の(一見)いいかげんな資料を参考にせざるを得ません。
もちろん、suzukaはflashとほとんど同じなのでネットに沢山載っているflashの資料を参考にできるのですが、flashを知らない人には、読み替えが面倒だろうと推察されます。
今年度の作品提出の締め切りは一昨日でした。昨年までは、優れた作品のみをホームページに掲載していましたが、今年は、全ての作品を公開することにしました。
作品展示室は以下です。玉石混合ですが、なかなかよくできたものもあるので、楽しめます。是非覗いてみてください。
http://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/lecture/hi2007/ss3/index.html
suzukaに関して言うと、私の(一見)いいかげんな資料は、うまく組み合わせれば飛行物体から弾丸を発射するシューティングゲームを作ることができる部品を用意しています(これらの部品は様々に応用可能)。もちろん学生さんには、そのことを言ってありません。提出された作品を見ると、私の意図通りの作品を作った学生さんがいるので、びっくりしました。さらに、私の想像を超えた作品を作った学生さんが何人かいたので、若い人達のオリジナリティーに感動しました。
なお、過去の秀作は以下のページでご覧になれます。
http://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/lecture/hi2006/hi2006.html
http://www.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/lecture/human.html
l33 ( 2007/07/11 16:36:17)
鳥
(1)私は6階に住んでいます。早朝、外を眺めていたら前方から2匹のカップル鳥が並んでこちらに向かって飛んできて、屋上の方へ上昇していきました。上昇直前、向かって右の鳥が首を曲げて左の鳥を見ました。明らかに、話しかけた感じでした。並んで飛んでいる鳥なんか、片目で相手を見ているだけだと思っていましたが、愛情こまやかな感じで驚きました。
鳥達から見ると、相手の顔を覗いたのは左の鳥なので、覗いたのはメスかな、と勝手に思っています。
(2)子供が生まれたころ、家の戸袋に”ムクドリ”が巣を作ったことがあります。追い出すのも可愛そうかと放っておくと、やがて、ムクドリの巣から小さな虫(1mm以下)が行列を作って赤ん坊の布団に近づいてきていました。驚いて巣を取り払いました。
鳥には虫が付いていることがあるので、要注意です!!
(3)私の部屋のドア”行き先提示鳥”に新しいメンバーが加わりました。今まで”赤しょうびん”でしたが、夏なので、涼しげな青い鳥に代えました。
==

l32 ( 2007/07/09 08:36:42)
七夕ウイーク
今週は色々ありました。
(1)追試:プログラミング実験の最後に試験を行い38名の追試者を発表しました(昨年は26人)。学生さんにとって、勉強する機会が増えた方が本人のためになると思い、どんどん追試に回しました。5,6人が苦情を言ってきました(甘えは許さん!!^^)。
(2)さすが七夕:何人もの卒業生から色々な連絡が入りました。結婚話、転職話、進学話、選挙話、飲み会話、と。
(3)テニス:先週から、4年生のテニス会に参加させてもらっています。ウン年ぶりで始めたのでボロボロ状態です。ラケットの精にして、ガットを張り直しにいったら、状態の良いヨネックスの中古ラケットが5千円で売られていたので、衝動買いしてしまいました。
(4)故障:火曜、授業に持っていったDELLノートのOSが、おかしくなりました。金曜、PCがネットにつながらなくなり、ブロードバンドルータを交換しました。ブロードバンドルータに付いてきたウイルスバスターを走らせたら、ウイルスも一匹いました。簡単に書いていますが、検出と復帰には随分手間がかかりました。
(5)テレビ:千葉テレビの高校野球予選の中で、大学紹介コーナーがあり、古谷研の様子が紹介されることになりました。2週間位前に撮影があり、金曜に試作検討版が出来上がってきて検討会を行いました。学生さんの映像はなかなかなものでした(芸能界からスカウトされそうな人もいました)。先生の方はだいぶ見劣りしますが、学生生活の紹介がメインなので、引き立て役になっていました。
(6)てこ入れ:今年も研究室の学生さんは熱心で、(7月時点なのに)朝9時に来て夜7時過ぎまでいる学生さんがいるし、1週間毎日研究室に出てくる学生さんも大勢います。皆の熱が冷めないよう、授業も大体終わりなので、研究のてこ入れを始めました。とりあえず、方位計の値をJavaで読む(これがうまくいかず、今日も持ち帰って格闘中です)、ウエブクリエータ系のテーマを検討(雑誌PEN参照)、内蔵PCの応用の考案(頭絞り)、などなど。
授業は、いよいよ前期最終週に入ります。
==
この記事、昨日家から掲示しようとしたら、サーバーがダウンしていて、週明けになってしまいました。このPC系故障連鎖は異常な感じです。連鎖よ止まれ!!
l31 ( 2007/07/04 15:04:57)
miscellaneous
1.新技術
壁やフスマに留まっている蚊を退治するのに、タオルなどの布を手のひらより少し大きめに広げて、手のひらに乗せて叩くとよいことを発見しました。
利点1:手が痛くない
利点2:蚊が指の間に入って逃げたりしない。
利点3:うまく叩けば、血を吸った蚊をつぶさずに、失神状態にすることができ、壁が汚れない。
2.油断大敵
原油価格の高騰を理由に、石油や石油関連製品が値上がりしています。
昔、中東戦争によるオイルショックと言われる事態が起こり、石油関連商品が高騰しました。私はその時、あるパーティーで、大手石油会社の人と話す機会がありました。その人は(アルコールも手伝って)、”今、世間はオイルショックでパニック状態ですが、実は、石油関連会社は便乗値上げで笑いが止まらないんです。会社では、外では”困った”って顔してろよ、ってことになってるんです”、とのことでした。エ〜本当かよ!!って感じでした。
その時以来、私は石油の値上げ話は油断ならないと思っています。
石油大幅値上げなら、オイルショックを契機に作った国の石油備蓄を少し放出したら?
l30 ( 2007/06/30 05:19:17)
アーティチョークとカールドン
カールドン(今回の写真)は背丈2m以上にもなる大薊(アザミ)で、アーティチョークの祖先だそうです。形はアーティチョークに似ていますが、花が小さく素朴というか、地味と言うか、アザミそのものといった感じです。
アーティチョークの和名は朝鮮アザミですが、カールドンの和名も朝鮮アザミのようです。また、カールドンはカルドンと記される場合も多いようです。
アメリカのスーパーでは、よくアーティチョークのつぼみ(前々回の写真)が山積みになって売られていました。どうやって食べるのか聞いてみると、茹でるか蒸して食べる、というので試してみましたが、どこを食べればよいのか、どこがおいしいのか分からずギブアップしました。アーティチョークはフランス料理やイタリア料理にも用いられるようです。
アーティチョークもカールドンも薬草園にあるくらいですから、薬草ですが、ハーブでもあるようです(と、思ったら、ハーブとは、薬効のある植物を言うようです。私は香りのある植物をハーブと言うのかと思っていました)。
私も2年ほど前、アーティチョークとカールドンの同じ位の大きさの株を実家の庭に植えてみました。2年後、カールドンは4倍に増え、棘があって痛いと両親に邪魔者扱いされています。一方、アーティチョークは1/4の大きさになって蕾も付けない状態になってしまいました。アーティチョークの蕾が日本でお目にかからないのは、栽培が難しいのかもしれません。
薬草園のアーティチョークは、写真の通り大きく成長している所を見ると、薬草園の管理には高度な栽培技術と、絶え間ない手間隙がかかっているのだろうと想像されます。
今度、アーティチョークの料理を出す店を発見したら教えて下さい。
===
当初、アーティチョークの写真を3回載せさせていただく予定でしたが、木曜に丁度カールドンの花が咲きましたので、それに差し替えさせていただきます。

l29 ( 2007/06/27 12:11:46)
残業
日本は残業大国と言われ、毎日、帰宅が11時、12時になる人も少なくないと聞く。さらにひどいことに、残業代が支払われないケースも多く、データに出ない残業も少なくない。過労死、うつ病、自殺などの原因にもなっている。
なんだか、江戸時代の水飲み百姓や明治時代の女工哀史の時代が復活してしまった感じである。
卒業生を社会へ送り出す者として大変気になる状況である。
世の中が”何か変だ”と思った時、その原因は必ず法律にある。
法律の問題点:
(1)残業に伴って会社が支払うべき賃金の割り増し率は日本が25%、アメリカが50%である。残業に対して会社が払うべき賃金が低いため、会社は残業を増やすことになる。せめてアメリカ並みに引き上げるべきである。
法律執行の問題点:
(3)サービス残業と言うと聞こえがいいが、要は無賃金労働である。残業代の踏み倒しと大差はない。これらは、経営者の犯罪であるというメッセージを国は発する(取り締まりを強化す)べきである。少なくとも、過労死などの労災を繰り返す会社の経営者は犯罪者として罰する必要がある。
現在の経営形態は、グローバル化と自由競争による競争激化を理由に、労働者に負担を強い、儲かった分は経営側が分け合うという形になっている(経営側のリスクが非常に低い)。
グローバル化による自由競争を推し進めるのであれば、同時に労働者を守る(経営者が遵守すべき)法律を即刻作る必要がある。
昨今、少子化が問題になっているが、”こんな人生は子供に体験させたくない”と思えば、子供を作ろうとしないはずである。少子化は政治の鏡である。
===
孔子ら一行は、墓地の前で泣く女に出会う。孔子は弟子にその理由を尋ねさせる。
女:さきに舅が虎に殺され、つぎに夫がやられ、今度は息子がやられました。
弟子:ではなぜこの土地を離れないのか。
女:ここには苛酷な政治がないからです。
孔子:覚えておくがよい。人民たちにとって、苛酷な政治は虎よりも恐ろしいのだ。

l28 ( 2007/06/24 05:15:02)
マーチとワルツ
夏時間(Day Saving Time)の導入が検討されるそうである。夏時間とは、夏の間、時計を1時間早めるもので、夕方5時はまだ昼ひなかといった感じである。私は、アメリカでうまく機能している夏時間が、日本ではうまくいかないだろうと思っている。理由は、日本と欧米の生活リズムの違いである。
日本人は1日をマーチ(働く、眠るの2拍子)で暮らし、
欧米人は1日をワルツ(働く、遊ぶ、眠るの3拍子)で暮らしている。
日本人の1日は、朝早く家を出て、9時過ぎに帰宅し、一寸テレビでも見てお休みとなる。
日本に居ると実感がないが、欧米人は5時になると大方の人は家路につく。職住接近の精もあり5時半には家に着く。6時から12時位までが自由時間で、一つの生活時間帯を確立している。この時間帯は主に次のような用途に使われている。
・家族と生活を楽しんだり、
・地域コミュニティーの活動に参加したり、
・趣味の世界を楽しんだり、
・新しい方面へ進出するための勉強をしたり(このような人のために、勉強する環境も整っている)、
この時間帯があることにより、会社での生活が人生に占める比重が減り、余裕が生まれ、やり直しのチャンスも増える。ただ、欧米スタイルを確立するには3つのことが不可欠である。
(1)残業がない、
(2)職住が接近していること、そして
(3)ワルツ生活への頭の切り替えである。
どれをとっても、今の日本では難しい。今、夏時間を導入すると、日本では残業時間がさらに増え、ますます過労社会になっていく気がする。
(次回は、残業大国日本の原因を明らかにする)
===
これから3回、本学薬草園のアーティチョークの写真を掲載します(写真提供は、薬草園の青山さんです)

l27 ( 2007/06/20 13:06:05)
耳障り
よろしか調:
(1)病院の受付で4,5人の事務員の方が、待っている患者に、
”カードを機械に入れていただいてよろしいでしょうか?”
”これに記入していただいてよろしいでしょうか?”
”持っていっていただいてよろしいでしょうか?”
など、
”〜〜していただいてよろしいでしょうか?”を連発していました。
何か変な感じです。”〜〜してよろしいでしょうか”の〜〜は自分のすることを聞く言い方(例えば、中に入ってもよろしいでしょうか?とか)だと思うんですが。
(2)また、受付に質問に来た患者に、
”今、お手続きをさせていただいております”と言っていました。この”お”も一寸変じゃないかな?手続きは事務の人がやっているので自分に敬語を使っていることにならないかな?なんて思い、語呂を確かめようと、”お手続き””お手続き”なんて2,3回言ってみている内に”おててづき”になってしまい、舌をかみそうになってしまいました。
蕎麦屋で:
(3)私は、自他共に認める蕎麦好きです。先週、蕎麦屋で隣に座った人がズルズルと大きな音を立てながら食べていました。そのズルズルを、なんか汚らしい音だなと思ってしまったら最後、蕎麦を食べる音が気になりだし、あちこちで聞こえる、ズルズルが不快に感じられるようになりました。蕎麦は音を立てて食べるのがマナーだ、なんて思っていましたが、一度”きたならしい音”だと思ってしまうと、本当に汚らしい音に感じられます。蕎麦屋へゆくのが憂鬱になってきました。
ただ、自分も音を立てて食べているので、音を立てない方法に挑戦してみたのですが、これがまた至難の業で今悩んでいます。
目障り、耳障り:
(4)新聞の人生相談で、相談者が”耳障りのよい言葉”という表現を使い、回答者に”耳障りのよい”という言い方はありません、と注意されていました。私も、相談部を読んだ時、問題点に気付きませんでした。漢字をよく見ると、確かに”目障り、耳障り”の”障り”は悪いことを言うので、聞き苦しいことを”耳障りだ”と表現すべきだということが分かります。私は多分、耳障りの”障り”を音(オン)で”触り”と勘違いしていたのだと思います。(叱られそうですが)”耳触りのよい言葉”なら結構ありますよね。

l26 ( 2007/06/16 05:43:09)
子は親の鏡
”子は親の鏡”という子育ての教科書のような詩(ドロシー・ロー・ノルト作)があります。
=====
”子は親の鏡”
けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもはみじめな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる
叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう
励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる
広い心で接すれば、キレる子にはならない
誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ
愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ
和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世はいいところだと思えるように
なる
=====
子としても親としても思い当たることが多く、胸が痛みます。でも、実際には、なかなかこんな風にはいきません。そんな時は、(バカの壁の)養老先生の次の言葉が慰めて(諦めさせて?)くれるでしょう。
「不完全な人間が行うは子育ては、うまくいかないのがあたりまえで、思い通りいかないことを学ぶのが子育てである」。

l25 ( 2007/06/13 13:16:58)
鏡
最近、自分の見ている世界は自分の鏡ではないかと感じることがよくあります。
(1)母と私:私は子供の頃から”母は、私を傷つけることをよく言う”と思っていたのですが。最近、母が”私が母を傷つけることをよく言う”と思っていたということを知りました。そんな気はなかったのですが、互いにそう思っていたのには驚きました。まさに鏡のようでした。
(2)授業と私:先日、若いけれど落ち着いた感じの先生の実験の時、実験室の端の方で計算機を使わせてもらいました。私は、同じ実験グループに対して実験指導をしたことがありますが、落ち着きのないザワザワしたグループだと思っていました。ところが、落ち着いた感じの先生の実験の雰囲気は、まさに先生の落ち着いた雰囲気が流れていました。私の実験で落ち着きがなくザワついていたのは、学生さんの精ではなく、私が落ち着きなくザワついているんだと気付かされました。学生さんは私の鏡でした。
===
写真募集:このサイトも写真があった方が楽しいので、齊藤さんに”よい写真が有ったら送って下さい”、とお願いしたら送ってくれました。これから3回、齊藤さんちの野菜さんが続きます。お楽しみに。また、皆さんも、よい写真があったら送って下さい。

l24 ( 2007/06/10 05:30:12)
誤(ゴ)キャブラリ
(1)テレハラ:公衆電話が減り、携帯電話を持っていない人にはつらい世の中になりました。先日通勤の途中、電話をする必要が発生し、やっとのことで公衆電話を見つけ電話をしようとしたら、テレホンカードでしか電話できない電話機でした。もうだめ!!これをテレフォンハラスメントと名付けました。
(2)パスハラ:パスモができてから、定期券購入機や精算機で選択画面が増え、読んで判断するのに時間がかかってしまいます。後ろに人が並んだりすると本当にあせります。これをパスハラと名づけました。もっとも、若い人はすんなり使っているようなので、もしかすると”老ハラ”かもしれません。
(3)過ぎたるは:
昼間の失敗を、夜、寝しなに”何であんな失敗したかな?”って悔やみましたが。その時、諺の新しい解釈を思い付き、おかしくなって眠ってしまいました。それは、”もう終わった事は考えてもしようがない”という意味で”過ぎたるは及ばざるがごとし”を使うアイデアです。小学生などに言うと本当に間違えて覚えそうで怖いのですが。
(4)モーニング違い:
カンヌ国際映画祭で”もがりの森”がグランプリを受賞し、授賞式でモーニングフォレストと紹介されていました。morningじゃなくて、mourningだろうなと思って見ていましたが。この時、長い間気になっていたモーニングコートに関する疑問が目を覚ましました。モーニングコートの綴りはmourningだと思っていたので、何でお祝いの式典にも着ていくのかな?、と思っていました。そこで、辞書を引いてみると、発音は同じですが、モーニングコートの綴りはmorning coat(昼間用礼服)でした。
さらに、私はモーニングが燕尾服だと思っていましたが、evening coat(夜用礼服)が燕尾服でした(燕尾服は指揮者がよく着るもので体の後ろにだけ尻尾があり、ズボンも黒です)。
===
NEWS:今週の月曜早朝、出勤時に(2年ぶり位で)齊藤さんと駅ですれ違いましたが、今度は金曜の帰宅時8時半ごろ、また齊藤さんと駅ですれ違いました。齊藤さんで始まり齊藤さんで終わった不思議な一週間でした。
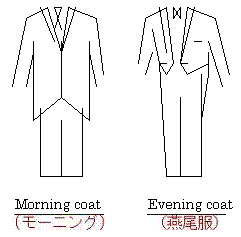
l23 ( 2007/06/10 05:27:19)
(1)麻疹抗体検査:
先月21日血液採取分の検査結果が返ってきました(23日に採血した人の分は判定キットが品切れで、結果がいつでるか分からないそうです)。検査はEIA価という数値で判定しています。これがどんな数値なのかよく分からないんですが、ネットで調べた感じでは0〜1000位の範囲で、大体は0〜130位で平坦に分布しているようです(ネット上のデータから推測したもので、科学的根拠はない)。4以上が免疫ありだそうです。
健康管理室に今回の測定結果(EIA価の分布)を教えてくれないか聞いてみましたが駄目でした。、
あまり情報が無いのも寂しいので周辺の3名にEIA価を聞いてみたところ、
50代で、子供の頃、実際に麻疹をやった人2名のEIAは50台でした(含む私)。
ワクチン接種で抗体を付けた人は、40代の人がEIA価8、30代の人は125でした。
(まあ、バラバラという位の情報しかありませんね)
(2)齊藤さん:
月曜早朝出勤したら、7時20分位に新鎌ケ谷という駅で卒業生の齊藤さんとすれ違いました。随分早い出勤で大変だなと思いましたが、
”朝の誰もいない時、じっくり仕事に取り組むのが至福の時間”みたいで(いかにも齊藤さんって感じですが)、とても元気そうでした。
千葉県を出る機会は少ないようですが、皆さんも見かけたら声をかけて下さい、とのことでした。
(3)コーラ:
コーラはカロリーが高そうなので敬遠していましたが、昨日”ZeroSugar”というのを見つけました。(コーラは私が高校の頃日本に上陸したので青春の味って感じで)何となく懐かしく、2日間で4本も飲んでしまいました。人工甘味料も、随分自然な味になりました。オススメです。
(4)スポンジケーキの耳:
2,3ヶ月前、大久保通りにケーキ屋さんができました。夕方になると店先に、ケーキを作る時にできる(残る)スポンジケーキの耳(端の茶色い部分)がビニール袋に入って150円で並べられます。おいしそうだし、安いし、一度買って食べてみたいな、と思っていました。火曜日、店も混んでなさそうだったので、1つ取って店内のレジに並びました。並んでしまってから、ケーキを買わないで老人がケーキくずを持って並んでいるのは美しくないな、と思いましたが急にやめるのも変だし、学生さんに見られないといいな、と思いながら買ってしまいました。味はまあまあですが、耳の部分が薄いのでポロポロで食べにくい感じです。もう買うまいと思っていましたが、昨日また、チョコレートケーキの残りみたいなのを並べていて、これがまたおいしそう。誘惑と戦う日が続きます。
(2007/6/7)
l22 ( 2007/06/10 05:26:09)
今更禁煙のすすめ
(1)60歳近くで初めて分かったこと:
近頃、前の職場や学生時代のメールグループから頻繁に訃報が届く(昨年の感じでは3,4ヶ月に1回位の感じであった)。60歳近くなると、急にリスクが高まることを実感する。喫煙の習慣は寿命を約5年縮めるそうだ。特に、(女性より平均寿命が短い)男性に気付いて欲しいことは、30歳でほとんど人生の半分に来てしまっているということである。60はズッと先だ、なんて考えないほうがよい。年を取るほど時間が経つのが速くなり、気が付けば60って感じである。
(2)国民に尊敬される国にして欲しい:
日本のがん医療はアメリカに比べ20年遅れていると言われ、先進国で最も苦痛を強いられる国だそうだ。この度やっと「がん対策推進基本計画」の素案が出た。ただ、この計画案では、委員会が強く主張した喫煙率半減目標を、厚労省が削除したそうである。たばこ業界や、たばこの税収に配慮したものらしい(これって、薬害エイズやアスベストと全く同じ構図じゃない!何の反省もしてないんだ!)。目先の利益を重視し、多くの国民に苦痛と、将来に大きなつけを残すものである。オーストラリアでは喫煙率を減らすため、たばこのパッケージに喫煙がもたらす恐ろしい結果の写真を印刷させている(これこそが国民の命を守る政治ではないのか)。日本は、消えた国民年金を短命策で逃れようとしているのではないかと疑ってしまう。
(3)お医者さんのチェック項目を参考にしよう:
私は以前、胃の具合が悪くてお医者さんに行ったことがある。その時、お医者さんに先ず聞かれたことは”たばこを吸いますか?”であった。たばこは胃にも悪いんだ、と思った。
先週、夜よく咳が出るので呼吸器科の先生に診てもらった所、問診の最初に、現在の喫煙習慣だけでなく過去の喫煙経験まで細かく聞かれた。
(4)JT(日本たばこ産業株式会社)への提案:
(現在、JTホームページで)”弊社は、「喫煙者率の引き下げの数値目標」を設定することに強く反対します”、と(ダーティーな)宣言をしている。
JTは、技術部門もあるようなので喫煙習慣をやめさせる薬や食べ物の製品開発をした方がよい(早く発想の転換をした方がよい)と思う。テレビ新聞等で大々的に”私達の夢は、弊社たばこ事業部がなくなることです”位のことを言って撃って出た方が社会のためにも、会社自身の健康のためにもよいと思う。
(2007/6/3)
l21 ( 2007/05/30 14:39:23)
Linux無線LAN覚え書き
(1)ヘルプ:昨年FedoraマシンにしたノートパソコンをWindowsマシンに戻そうとしてリカバリCDを購入し復元を試みましたがうまくいきません。ある人は、Windowsを完全に追い出した場合、リカバリCDでは戻らないのではないか、とのことでした。色々試したのですがダメだったので、やっぱりそうなのかな、と思っています。どなたか、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
(2)Linuxと無線LAN:Windowsに戻らなかったので、またFedoraに戻しました。無線LANカードを接続し、研究室のアクセスポイント(以下APと略)にアクセスしましたが最初アクセスできませんでした。
(この通信不能を解決するため、1週間随分回り道をしました)
Windowsで無線LANは簡単です。”スタート”から”接続”に行くと通信可能なAP(ネットワーク名)が表示され、希望のAPに”接続”すると、WEPキーを聞いてきて、キーを書き込めば通信可能になります。
LinuxではこのようなAP一覧表示がなく、”ネットワーク設定”時に必要な(後述のSSIDやWEP)設定を全て記入しておいて一気に起動します。そのため、うまくいかない時の問題点探しが容易ではありませんでした。
今回学んだこと:
(1)通信カードは11Mと54Mがほとんどで、11MはIEEE802.11b、54MはIEEE802.11gという通信規格で動作する(APはこの両方(11bと11g)を同時にサポートするよう設定できる)。
(2)Windowsで表示されるネットワーク名がAPのSSIDである。
(3)Windowsでネットアクセス時に要求されるWEPキーをLinuxでは設定時に書き込んでおく。今回、最初LinuxからAPにアクセスできなかったのは、WEPキーの初めに0x(即ち16進数)を指定していなかったためであった。WEPキーには色々なタイプがあるので注意が必要。
(4)Linuxがサポートしている無線LANカードは、(少し古い)11Mのものである。54Mカード用のドライバをインストールしようとしたが、色々問題が発生しうまくいかなかった。ネットに情報が載ってはいるが、Linuxの種類によって異なるのか、その通りいったものはなかった。
l20 ( 2007/05/26 16:03:25)
麻疹(はしか)
他大学で、麻疹が教職員から学生へ伝染したケースがあったということで、21、23日に教職員全員の抗体テスト採血がありました(結果が出るのは2、3週間先)。私より5、6歳若い先生(50歳前半)は子供の頃予防接種を受け本当の麻疹をやっていないそうです。ということは、団塊の世代が本物の麻疹で免疫を付けた最後の世代となります。たたき上げの抗体は予防注射の抗体より強いのではないかと思います。結果が出たらまた報告します。
予防注射の思い出
(1)回し射ち:私が子供の頃の予防注射は回し射ちです。10cm位注射液の入った注射器で一人1cm位づつ射っていきます。これを何年もやってきたので多分肝炎に感染しているだろうと思っていたのですが、数年前の身体検査で肝炎に感染していないことが分かりました。
(2)軍医:私が子供の頃は軍医上がりのお医者さんがいて、針の刺し方が乱暴で痛さが全然違います。子供もよく知っていて、痛くない先生の方に並ぶのですが、列の長さが違ってくると、先生に痛いお医者さんの方に移動させられます。その時は、不運!って感じでした。
(3)ツベルクリン反応:(これは今の子供たちもやっていると思いますが)赤い円が出来ないとBCGを打たれるので、検査の少し前になると物差しで円を叩いて大きくしました。全然赤くならない人は丸く引っ掻いて赤くしますが見破られ怒られた上にBCGに回される姿はあわれでした。
(4)日本脳炎:何と言っても痛いのは夏休み前の日本脳炎の注射でした。夏休みの楽しみが半減する思いでした。10年位前、昔の日本脳炎の予防注射は免疫が付かないことが分かった、という報道があった時は、情けなくなりました。
(5)海外:子供がアメリカの幼稚園と小学校に入る時、予防接種のやり直しを要請されました。特に幼稚園は厳しく、証明書を持っていかないと入れてくれませんでした。予期せぬ伏兵(英語、病名の英語、日米の接種の種類の違い、二重に接種を受けてよいのか、など何も分からず)に動揺しました。これから海外に行かれる方は日本の予防接種との違いなどを調べ、準備をして出かけた方がよいでしょう。
l19 ( 2007/05/23 15:12:37)
疲れた??
この日曜日、ゴルフプロツアーで高校1年生の石川君がプロを押さえ優勝した。彼は優勝インタビューで、プレー中注意したこととして、”疲れたという気持ちを起こさないようにした”と言った。
これは、示唆に富む言葉である。最近我々は、”疲れた!”というのが口癖になっていると思う。
”疲れた”という言葉には、”うまくいかなかった時の言い訳”と”ねぎらってもらいたい”という2つの甘えが隠れている。彼は、そんな甘えた気持ちを持っていては勝てない、ということを言っているのである。
この”疲れた”という表現は、昔からあったものではなく、30年位前から使われだしたものである。私が若い頃は星飛馬の時代であり、疲れていても”疲れた”なんて言う事はプライドが許さない時代であった。もし、”疲れた”なんて言う奴が居れば、言い訳がましい(いさぎよくない)情けない奴だと思われたし、指導者にでも聞かれようものなら”グランドをもう十周して来い”という時代だった。私の親の時代(戦時中)だったら半殺しにされたはずである。
30年くらい前、職場に、よく”疲れた”と言う人が現れ、”なんて人だ”と思ったものだが、数年の内に世の中に広く普及してしまった。
(自分達が甘えの構造を作ってしまっておいて言うのは申し訳けないが)若い人たちは、自分達が、えらく甘やかされている事を頭の隅に入れておき、自分を厳しく律して欲しい。グローバル化が進む現在、甘えが通用するほど世界は甘くない。弱冠15歳の少年が素晴らしいメッセージを発してくれたと思う。
l18 ( 2007/05/20 05:27:23)
秋葉系
連休のはざま、専門書(注1)とWiiを求めて秋葉原に行きました。秋葉は少し行かない間に、また変化しているようです。昔(注2)は秋葉系と言えば、パソコン少年というイメージでしたが、その後ゲーム系に変化し、さらにロリータ系に移ってきている感じがします。
”ゲーム機”と書いてあるお店も、入ろうとするとセクシー美少女画が壁一面に貼られていて、入るのを躊躇してしまいます。残念ながらWiiはどこにもありませんでした。
最近秋葉は修学旅行の見学コースに入っているのか、地方からの中学生や高校生と思えるグループが何組も歩いていました。その中の女子中学生達の話、
Aさん:ここでは人に会ったらモエ〜って言うんだよ。
Bさん:言わなくてもいいんだよ〜。
Cさん:言わなきゃダメなんだよ〜。
どっちなんだ!早く教えてくれ!!モ〜ェ!
突然、メイド姿の人に出会うこともあります。
おじさん、おばさん達は”お〜〜”て感じでニヤッとしますが、
女子高生達は、キャー!!って大喜び。
メイドさん達も意識しちゃって、少し誇らしげでした。
==
注1:秋葉専門書店案内(コンピュータ関係の専門書が結構そろっています)
(1)書泉ブックタワー(2)LAOXザ・コンピュータ館、
少しハード寄りなら(3)ラジオセンター(駅隣接)内、や(4)ラジオデパート(ラジオセンターを抜け中央通りを渡る)内に小さな書店があり、お勧めです。
名前が紛らわしいのですが駅前にあるのはラジオ会館で、ここでは今フィギャーが増殖中です。
==
注2:私にとって、秋葉には大昔(45年位前)という時代があり、私は元祖秋葉系を自負するものです。中学時代から無線器を作るために部品を買いに何度秋葉原に行ったことか。当時は家電量販店もありませんでした。今でもラジオセンターで部品の匂いがすると昔を思い出し元気が出ます。
次の秋葉通いは就職して間もない頃(30年位前)です。オーディオブームに乗せられ、アンプだスピーカだと新製品の視聴などに出かけました。重くて持てない様な低音スピーカを自作したこともあります(フィルターの設計を誤りメインのスピーカを壊し、あげくの果ては、邪魔だということで知らない間に捨てられてしまうという悲しい運命を辿りましたが)。
==
メイドさんの写真でも載せられればと思いましたが手に入らず、写真を撮りに行って警官に声をかけられてもまずいので諦めました。写真は、5/13日家の近くに出現した飛行船型UFOをベランダから撮ったものです(宙船かもしれません)。

l17 ( 2007/05/16 16:08:39)
音楽3度目の衝撃
過去に2度、”こんな音楽が、この世に存在するんだ!!”という衝撃を受けた経験があります。
(1)最初の衝撃は高校2年の時、学園祭か何かで(今は芸能人の)柴俊夫君達が演奏した”キャラバン”と”ワークソング”でした。民謡と歌謡曲で育った者には驚きでした。
http://www.youtube.com/watch?v=qeUan4As5wM
http://www.youtube.com/watch?v=-OphjWIqO0Y
(2)2番目の衝撃は20代後半だったと思いますが、銀パリ(5年位前に閉鎖されたシャンソンのライブハウス)で聞いた”コメディアン”です。それまで考えていたシャンソンと全く違う楽しさがありました。
http://www.youtube.com/watch?v=u-74Fw_ymig
(このシャルルアズナブールの歌は、くすんだ感じですが、ライブの歌は驚くほど明るく軽やかでした)
(3)もう2度と衝撃を受けることは無いだろうと思っていましたが、このGWに3度目の衝撃を受けました。
東京国際フォーラムで開かれていたクラシックの祭典「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」(熱狂の日)音楽祭(5/2〜5/6日)を覗いてきました。
私は5/5日午後、野外ホールでのルーマニアのジプシー楽団タラフ・ドゥ・ハイドゥークスの演奏会を観ました。
http://video.google.com/videoplay?docid=-3897380565800458303
(このビデオは前夜祭での同楽団の演奏です。情熱的な雰囲気はお分かりいただけると思います)ただこれだけでは私もビックリはしません。
私が衝撃を受けた演奏会(40分間)の模様を実況放送してみます。演奏の舞台は前夜祭のビデオと同じです。舞台の周りを1〜2m位(演奏者が舞台から降りてきて歌ったり演奏したりできる程度)ぐるっと空け、その後ろを観客がぎっしりと取り囲んでいます。
演奏者達の登場です。メンバーはジプシーのおじさん達そのものです。演奏は、調子も合わずいいかげんな感じでスタートしました。しかし、この時点で既に最前列にいた若い女性約2名が立ち上がり両手を上に挙げながら、音楽にあわせて体を動かし始めます。踊りと言うにはパターンが無いのですが、単にリズムを取っているというよりは激しい動きです(ビデオの始めの方の左端で踊っているような動き)。
最初はバラバラだった演奏と歌も、10分もすると段々調子が合ってきて多くの人が手拍子を始め、盛り上がってきました。20分もたつと、前の方で見ていた20〜25歳位の上品な美しい女性達(イメージ的には相本久美子、とか菊地凛子、とか平原綾香のような感じの人達)が10人位前のスペースへ出て行って最初の2人と同様激しくリズムを取って体を動かしだします。(この人達はなんなんだろう?着ているものは普段着っぽいので、さくらでもなさそうです。踊りは皆、勝手に体を動かしていて、決まりが有って踊っているのではない感じです。ある人はフラメンコ風に手を動かしていたり、ある人は沖縄の踊り風に手を動かしていたり、適当に回転したり飛び跳ねたり、激しく体をゆすったり、胸の動きを強調している人もいます。動作はみなバラバラですが、下手ではありません)
30分経過後からはさらにエスカレートし、踊っている女性は20人くらいに増えています。演奏も熱を帯び、音は大音量で耳の飽和点を超え完全に歪んでいます。女性達の動きも情熱的になり、陶酔状態に入っていく感じです。舞台上の笛吹きは彼女らを見ながら音楽をリードし、何か、彼女らを操っている感じです。コブラを笛で操る蛇使い、って感じがぴったりです。ハーメルンの笛吹き男もこんな感じだったのかなとさえ思います。終了近く、演奏と踊りは最高潮に達し、演奏はよりワイルドになり、踊を支配し、完全にシンクロしています。その様はセクシーでエロティックな感じさえします。音楽ってこんな側面があるんだ!!って驚きました。
l16 ( 2007/05/13 05:04:01)
母の日
お隣日大のキャンパスを通ったら紅白のサルビアが咲いていたので、(初めて見たので)写真を撮りにいきました。サルビアは道路に沿って並べられた花植えボックス(写真左)の一つに植えられています。
ちょうど掃除のおばさん(おかあさん)達が花に水をやっていたので、一寸立ち話をしたのですが、花植えボックスに植えられている草花は、おかあさん達が自腹で苗を買ってきて植えたものだそうです。これは大学も学生さん達も誰も知らない話だと思います。私達は自分の気付かない所で多くの善意に支えられているのかもしれないなと思いました。
感謝!!
お母さん達へ:いつも面倒を見てくれて有難う、花をいっぱい咲かせてくれて有難う(花々ほか、より)。
世界中のお母さんへ(そして、お母さんでない人達へも):いつも、見えない所で、みんなを支えていてくれて有難う。

l15 ( 2007/05/09 15:52:54)
下流志向
卒業生の三村君(広島からつくばに戻ったそうです)が”下流志向(講談社)”という本を推薦してくれたので、早速読んでみた。学習や労働を放棄する(下層社会へ向かっていく)若者の増加を、ユニークな視点で分析し解明を試みている。私が今まで考えもしなかった観点も色々示されていて(全てに賛同するわけではないが)、大変興味深かった。
感心した部分を私なりに整理してみると。
(1)不機嫌家族の誕生:お父さんは会社で働いていても今や給料袋を持ってくることもない。そのため、働いた証を、今日はこんなに働いて疲れたんだという不快感で示すことになる。お母さんも、家事だって大変なんだって不快感を示し、子供も塾で大変なんだって不快感を示す。こうして家の中は不機嫌大会になり、最も不機嫌な人が勝つ。ああ、不機嫌家族の誕生。
(2)学級崩壊(学生の反抗的態度:授業中話す、歩く、逆らう):最近の子供は、小さい時からお金を使っているので、消費者として自立している。そのため、子供達は授業を買っているという意識を持つ(先生は授業を売る人)。最もよい買い物をするには、不機嫌な態度で、その商品を蔑み、けちを付けることから始まる。そのため、一寸面白くなければ悪態をつく。テレビは、どうすれば最も売り主を困れせられるかを、反抗的態度の学生を英雄的に扱い応援する。かくして授業は崩壊していく。
(3)勉強は何の役に立つのか?:最近の学生は、何の役に立つか分からないと勉強しようとしないが、学問とは、そもそも勉強し理解し成長して初めてその価値や意義が分かるもので、学ぶ前の人には価値を説明し、理解してもらうことは難しい。
(4)最近の学生の知識は穴あきチーズみたいだ:最近の学生は知らない言葉や知識が出てくると、調べるのではなく、そんなものは存在しないものとして無視してしまう。そのため、学生の知識は穴あき状態で固定してしまう。(私の考え:これには賛同しない(したくないのかもしれない)が、最近の学生さんの理解しがたい行動が説明できる部分があるので怖い)
(5)格差の拡大:上層階級ほどセイフティーネットが張られていて、そこに属する人は、努力は報われると信じている。下層階級ほど(自立、自己責任の下)人々は孤立していて、努力は報われないと思っている。(多分、上層階級ほど努力が報われる仕組みになっているのだろうが)。そのため、上層の人々は努力をし、下層の人々はしないので格差は拡大する。下層の人々は、報われる確率が低くても、そこから這い上がるには努力しかないのに。
==
下の写真は、5/3日の牛島の藤です。樹齢1200年だそうで、平安時代からの藤色メッセージです。

l14 ( 2007/05/06 07:55:43)
1年生へ(2,3年生でも遅くない)
1ヶ月が過ぎましたが、大学生活はいかがですか?
私の大学1年の5月頃の経験を一つ紹介させていただきます。
私は大学で軟式庭球部に入りテニス三昧の生活をしていました。ちょうど今頃、
先輩が、”古谷、大学はどうだい?”と声をかけてくれました。
私は、”授業は毎日新しく難しいことの連続で、まいってます”と答えました。
すると先輩は”大学だもん毎日新しいこと出てくるの当たり前じゃないか”と言われました。
この答えでハッ!!と気付きました。
そうだ、毎日新しいことが出てくるのは当たり前で、それが知識や技術として身に付いてくるんだ。(難しいことを学ばなければ大学へ来た意味が無い)そのために大学へ来たんだった。
この時以来、授業に対する意識が180度変わりました。それまで、授業は与えられるものだったのですが、その時以来獲得するものに変わりました。新しく難しいことが出てくれば出てくるほど、これをマスターするとまた成長するんだという気になり難しい内容に積極的に取り組むようになりました。意識の変化で、勉強する楽しさが全然違ってきます。
皆さんの中に、まだ、授業がいやだな、と思っているいる人がいたら、新しく難しいことをマスターし、自分を成長させるために大学へ入ったことを思い出して下さい。
l13 ( 2007/05/02 13:59:08)
風薫る五月
40年以上前の読売新聞の”薫風のなかで”というコーナーで岸田衿子さんの”五月の絵本”という詩に出会いました。不思議な魅力があり、”風薫る五月”と聞くと、今でも必ず頭に浮かんできます。
「五月の絵本」
おととしの五月
奥さんとらいおんの歩いていた街道に
今年も土筆が萠えた
灰色の煙突が並んでも
くろい電柱がはえても
今日はだれもやってこない
あのたてがみも白髪まじりになったとか
薬屋の薬が品切れになったとかつたえきく
その昔 奥さんは十六歳
絵本と楽譜を駅にあずけて
らいおんと旅に出たのだった
白いほこりの道を 今日も風が吹く
オートバイが二台
トラックが一台
そのあとを
買い物籠をさげた奥さんが行く
となりには だれもいない

l12 ( 2007/04/30 05:56:41)
楽しくやってるかい?
昔の論文の間から、アメリカにいた時のメモが出てきたので紹介します。
==25年前のメモ==
アメリカ人からは、よく”楽しくやってるかい?”と声をかけられる。どうも、アメリカ人は楽しくやることが最高の人生と思っているらしい。大学の廊下に、ある先生が水の事故で亡くなられた、という紙が貼られていたので読んでみると、文末に日本だと”ご冥福をお祈りいたします”と書く所に、”ともかく彼は生前楽しくやっていた様に思う”と書いてあった。人生最後に振り返ってみて最も価値のあることは、”楽しくやった”ということかもしれない。
==メモ終わり==
楽しくやれれば苦労しないよ、なんて言わないで!!楽しくやることを忘れちゃってることもよくあるので。
l11 ( 2007/04/25 18:43:58)
駅の改装
(1)京成船橋駅
久しぶりで京成船橋駅を利用したら、駅がすごくきれいになり、ヨーロッパの駅みたいでした(写真)。でもホームが3階なので乗客は一苦労。JR船橋と乗り継いでいる人(でないと意味が分からないかもしれませんが):下りに乗る人は、踏み切りの警報がなくなったので、ひと電車乗り遅れちゃうことがありそうです。また上りの電車を降りた人は、遮断機が降り出した電車の前を走り抜けるスリルが味わえなくなりました。
改善点:ホームでカッコーと何か鳥の声を流していますが、鳴く間隔をもっと空けるか、流さない方がよいと思います。
(2)上野駅
久しぶりで地下鉄銀座線からJR上野駅に出た。構内は改装されていて、右も左も分からず、おのぼりさん状態になってしまった。
連れの者:高校時代毎日上野駅を使ってたっていうのに分からなくなっちゃったの?
私(半分冗談で):毎日、横を通ってた裸婦の銅像が見当たらないんで方向が分からなくなっちゃったんだ。
連れの者:やっぱりね。
やがて広場の隅の方に追いやられた1人の像を発見した。
心の中で:私は3人の像だと思っていたんだけどな。当時の学生には刺激的だった(水着写真が超過激ポルノの時代だった)ので3人に見えたのかな?近くに警官の詰め所が有り、未成年が視線を上げると注意されるので、よく見てなかったのかな?等々と考えてしまった。
自分の記憶機能が心配になり、ネットで調べてみたが、やはり1人の像(翼の像)しか出てこない。やっぱり私の記憶が混乱したんだと諦めかけたとき、あった!!”三相”という名の像らしく、広場からさらに奥のホームの人目に付かない所に移されたらしい。
http://www.dentan.jp/ueno/uenoeki/eki04.html
おみやげ販売スペースを増やすために、芸術作品を邪魔物扱いするとは。文化の森(上野の森)の誇りまで売ってしまう気か。そんなことだから、国立新美術館を六本木に持っていかれてしまうんだ!! 中、高校時代を過ごした上野には思い入れがあり、どうも力が入ってしまう。

l10 ( 2007/04/23 05:40:35)
オーラの見方
私はオーラの泉のファンであるが、土曜のゴールデンタイムへの移行には不安を感じる。(番組の最後に注意の喚起はあったが)小中学生は鵜呑みにするであろう、自殺など増えなければよいが。大人でも不幸な状況になると、見えないものに不安と怖れを感じる、そこにつけこむ宗教や霊感商法がでてくる可能性がある。
”有るか無いか分からないものを信じるのは、大変危険なことである”。
この世には、まだ科学的に証明されていないものがあるかもしれない。
霊能者は、何かを感じ取ることができ、それに”解釈”を付けて話しているはずである。
もし、科学的に証明されていないものが有ったとしても、非常に能力が限定されている人間の体(感覚と脳)と人間の知識で行うで解釈は誤っている可能性が非常に高い。この解釈は科学の発達で変わってくることはいくらでもある。ほんの数百年前まで、誤った解釈で人身御供や魔女狩りなどの悲劇が起きている。今後さらに科学が発達すれば、解釈が変わってくる可能性は非常に高い。
そもそも生物の中で人間は特別なものであるはずはない。解釈が人間にだけ成り立つようなのものであれば、誤りであると考えるべきである。
私がオーラの泉を見る楽しみの一つは、霊能者の話から、前世や霊界と異なる解釈ができないかを考えることである。今までに考えた仮説としては、
(1)物、人、場所などに、強い思念が(フィルムに写るように)写り込むという(科学的に証明されていない)現象があり、霊能者はそれを感じ取っている、とか
(2)宇宙を流れている何か分からないが風のようなものがあり、その風の速度が違うとその上の時間の流れが違う(相対性理論の時間の相対性)ので、霊能者はその風に写った過去や未来の情景を感じるのではないか。
等である。
彼らの脳に写る世界の話から、それらを含むもっと大きな科学的体系を考えるのはとても楽しいことである。一寸アインシュタインの気分になれる。
l9 ( 2007/04/18 14:19:49)
7775
575は俳句、57577は短歌、ですが7775ってのが有ることを知りました。先日、車でラジオを聴いていたら、都々逸(どどいつ)の投稿番組をやっていました。都々逸は昔の御座敷の唄と思っていたのですが、その番組ではメロディー無しの読み上げでした。その日の最優秀作品は、
・この世とあの世の違いは僅か めいど喫茶も娑婆にある
でした。番組の中で都々逸は、7775だという話があったので興味が湧き、ネットで調べたところ:
都々逸は7775の定型詩で、花柳界で唄われることが多かったせいか、恋心や心意気の句が多い、とのことでした。
誰でも良く知っている、
・親の意見とナスビの花は 千に一つの無駄もない
・ザンギリ頭をたたいてみれば 文明開化の音がする
なども都々逸だそうです。
ネットに落ちていた秀作を拾ってみました。
・遠くはなれて逢いたいときは 月が鏡になればよい
・顔見りゃ苦労を忘れるような 人がありゃこそ苦労する
・嫌なお方の 親切よりも 好いたお方の 無理が良い
・恋に焦がれて 鳴く蝉よりも 鳴かぬ蛍が 身を焦がす
・三千世界の 烏を殺し 主と朝寝が してみたい(高杉晋作)
大学の八重桜は今満開です。私も一つ挑戦してみました。
・朧月夜に 源氏の君か 九重匂う 八重桜
(野暮な注:源氏物語の朧月夜は色っぽい女性だったようで八重桜に例えられます。光源氏との関係を知りたい人は各自調べること(恐ろしいことを知ることになるでしょう))

l8 ( 2007/04/16 06:04:08)
メール応答分析
部下達を飲み会に連れていき席について、さて注文しようとしたら、みんな携帯の着信をチェックしていた、という話をテレビでやっていました。”ある、ある”と思い、携帯依存症だな、なんて笑って見ていましたが。
(1)よく考えてみると、私もこの特徴を利用させてもらっていることに気付きました。私は研究室の学生さんに連絡をする時は携帯にメールを送ります。理由は、確実で、すぐに見てもらえるからです(期待通り返事を返してくる人の割合、約90%)。
(2)適切に返事を返してこない(自分に都合のよい時しか返事を返さない、返事が来るまでに2,3日かかる、一切返事を返さない)約10%を人を分析すると、次の3つのタイプに分かれるような気がする(サンプル数は少ないので信頼性は高くありませんが)
タイプA:精神的バランスを崩していたり、崩しやすい人。
タイプB:他人の目を気にせず独自の価値観を持っている人。
タイプC:知り合い以外の着信を拒否している人。
タイプCは別として、タイプAとタイプBの比率は半々といった感じです。
(注:タイプAかBか、識別が難しい人がいる)
(3)傾向と対策
(1)携帯依存症の人達は、コミュニケーション能力を有する標準的な人で対策は不要です。
(2)上記タイプBの人達は、人と違う道を選ぶ貴重な人達ですがハイリスクですので自己責任ということで。対策は無効です。
(3)問題は、タイプAの方々への対応です。
(先生方へ:自戒も込め):メールに返事を返さない学生は、”返さない”のではなく”返せない”でいる可能性が高いようです。このような場合、”正論のきついメール”など送ってしまうと、ますます殻に閉じこもってしまいます。(傷が深くならない内に)冷静にコミニュケーションを取るよう努力しなくてはいけません(連絡が取りにくいので、これがなかなか難しいのですが)。
(学生さんへ):先生の要求(課題等)に応えられずメールに返事を出せないでいるのかもしれませんが、先生が欲しいのは課題等の結果ではなく、返事のメールなんです。とりあえず何でもよいから返事を返し、(これが出来れば苦労はないのかもしれませんが)できれば直接先生に会うようにしましょう。顔を見てしまえば、一般に先生は気が弱いですからきつい要求はしませんので。
l7 ( 2007/04/11 17:40:16)
くだらない出来事
(1)生協でホットコーヒーを買おうとした女子学生Aに、
B:”それ時代遅れだろ”
A:それを言うなら”時代遅れ”じゃなくて”季節外れ”だろ。
A,B:受ける!!(笑)
(2)新津田沼駅のジューサーバーで
私は、一寸勿体ないかな、と思いながら150円のミックスジュースを注文。
隣に来たテニスラケットを背負った小学5年生位の男の子が、慣れた感じで
”生絞りフレッシュジュース”とか、注文している。
そんなのあるのかなと、メニューを探していると、
お店の人がなるほどナマのオレンジを4つ位圧搾機で圧搾しジュースを作っている。
その内、メニューも目に入ってきて、値段を見たら280円。
自分で稼いでもいない小学生が、そんな高いの平気で飲んでいいの??
(3)カモちゃん
先日、隅田川で見かけたカモメが部屋へ飛んでくるようになりました。カモメのカモちゃんと名付けました。

l6 ( 2007/04/06 18:44:14)
マジあせる!!
(1)今朝、電車で私の前に乗り込んできた女子高生の会話。
女子高生:今朝昨日のお寿司の残り食べたら喉につっかえちゃって、牛乳で無理に飲み込んだら気持ち悪くなっちゃった。
マジ吐きそ〜、マジ吐きそ〜、と何度も繰り返す。
私の気持ち:マジかよ?マジにならないでくれ〜!マジやばい!!
恐怖に耐えきれず、次の駅で脱出した。女子高生がマジになると恐ろしいことを初めて知った。大体、昨日の寿司なんか食うな!!
(2)大学の裏の小学校の前にはハンプ(自動車が高速走行すると上下に激しく揺れる凹凸)がある。たまにハンプを高速走行する車もあるが、運転手がひどい目にあっている様子を、私は余裕で観察してきた。
船橋にはまだ下水道が完成していないのか時々”し尿回収車(昔バキュームカーと言った)”が走っている。先日、バキュームカーがハンプを高速走行してきた。吸引用ホースは飛び跳ね、はずれて歩道の方に飛んできそうだし、バケツもはげしく揺れ、中身が飛び跳ねている。これには私もマジあせった。ハンプ領域は、ゆっくり走れ!!
l5 ( 2007/04/05 11:19:49)
新学期
風邪で3日間寝込み、入学式も失礼してしまいました。今日は(明日からの授業の準備もあり)体調不十分ながら1週間ぶりに出てきました。これから、1年生のグループワークトレーニングや縦コン等があります(参加するかは体調次第です)。大学の桜はみんな散っちゃっただろうと思っていましたが、まだ咲いているものもありました。
授業が始まると、なかなか本サイトに書き込む余裕がなくなると思います。できれば週1位のペースでは書き込みたいと思います。暇な時には覗いてみて下さい。また、面白い体験や写真などありましたらお送り下さい。掲載させていただきます。

l4 ( 2007/04/03 09:23:22)
入学式
ご入学おめでとうございます。
東邦大学出身者で(多分)最も有名な人
(昨年お亡くなりになりましたが)
詩人:茨木 のり子 さん
の詩を紹介させていただきます。
=====
「自分の感受性くらい 」
ぱさぱさにかわいていく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
気難しくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか
苛立つのを
近親のせいにはするな
何もかもへたくそだったのはわたくし
初心消えかかるのを
暮らしのせいにはするな
そもそもが ひよわな志にすぎなかった
駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄
自分の感受性くらい
自分で守れ
ばかものよ
=====
「癖」
むかし女のいじめっ子がいた
意地悪したりからかったり
髪ひっぱるやらつねるやら
いいイッ!と白い歯を剥いた
その子の前では立往生
さすがの私も閉口頓首
やな子ねえと思っていたのだが
卒業のとき小さな紙片を渡された
ワタシハアナタガ好キダッタ
オ友達ニナリタカッタノ
たどたどしい字で書かれていて
そこで私は腰をぬかし
いえぬかさんばかりになって
好きなら好きとまっすぐに
ぶつけてくれればいいじゃない
遅かった菊ちゃん!もう手も足も出ない
小学校出てすぐあなたは置屋の下地っ子
以来いい気味 いたぶり いやがらせ
さまざまな目にあうたびに心せよ
このひとほんとは私のこと好きなんじゃないか
と思うようになったのだ
=====
l3 ( 2007/04/02 17:19:56)
歴史を考える時
先日、”教科書から、沖縄戦で日本軍による集団自決の強要があった、という記述が削除された”というニュースがあり、賛否の意見が報道されていた。
私の、60年の経験から、歴史を見るとき注意しなくてはいけないと思っている点を整理しておく。
(1)十把一からげ、にしてはいけない
私は中国での戦争に関して、2つの体験を基に、歴史を考える時、注意しなくていけないと思っている。
第1の体験は、アメリカのテレビで見た日本軍の蛮行の映像である(日本ではあまり放送されない)。第2の体験は、中国での戦争に参加した人の車内での会話である。その人の話によれば、”日本は中国で悪いことをして来たとよく言われるが、軍隊の規律は非常にしっかりしており、市民に危害を加えたりするようなことはなく、もしそのような事が起こると連帯責任で隊全体が厳しい制裁を受ける”という話であった。
以上のことから分かることは、戦争と言っても場所、時期、状況によって様々なケースがあり、全体で同じことが行われていたわけではない、ということである。
(2)文化の違いを考えなくてはいけない
時代劇で、落城の際に、城内の女子供までが自害するシーンを何度も見てきたし、歴史を扱うテレビ番組でも、そのような話はよくでてきた。武士の美学に”生きて辱めを受けるより、自害すべきだ”という考え方があったと思う。
そう考えると、沖縄戦で自害の強要(あるいは指示)があっても不思議はない。戦前の思想は、現代の思想より戦国時代の思想に近かったと思われる。現代の人権重視の文化で、戦時中の文化を評価するのは難しい。教科書でも、先ず、当時の人達の文化(考え方)を名記した上で、史実を隠さず提示すべきである。
(3)それでも歴史は繰り返す
私は親達から戦時中の話をよく聞かされて育った。そのため、戦時中のイメージは、かなり掴める気でいた。ところが、先日テレビで老人が”敗戦で軍旗を焼くのが非常につらかった”と涙しているのを見て驚いた。私の想像力は、とても戦時中をイメージできるようなものではないと気付かされた。そう言えば、想像力が十分働きそうな家庭内でさえ思い通りにはならないし、頭の良い人達がうまくいくと計算して始めた戦争でさえ泥沼に陥る。人間の想像力は自分の体験を通してしか働かない。しかも、想像力は失敗経験を通してしか育たないし、失敗経験も喉元過ぎれば忘れてしまう。歴史は繰り返すしかないのかもしれない。が、それでも、
(4)アインシュタインの言葉
第3次世界大戦では分らないが、第4次世界大戦では人間は石を持って投げ合い、棒で戦うだろう。
l2 ( 2007/04/01 06:37:33)
桜2(上野)
浅草からの帰り、上野公園にも寄ってきました。上野公園の桜は、染井吉野だと思いますが、色が白く、花の量が多く、雪が積もったような、綿帽子をかぶったような感じでした。桜の美しさは、美しさを超越した何かがあるような気がします。桜って不思議です。色々な場所(吉野、長谷寺、千鳥が淵、、)で桜を見てきましたが、どこも最高です。ただ、最高の場所が沢山あるんじゃなくて、ある場所を思い浮かべるとそこがダントツで最高なんです。別の場所を思い浮かべると、そこがまた最高になるんです。分からないでしょうね、私も分からないんだから。ついでに旧上野図書館(今は、子供図書館になっていますが、昔の内装を保存していて懐かしい)と昔懐かしい上野中学の方を回って帰ってきました。

l1 ( 2007/04/01 06:34:56)
桜1(隅田川)
日の出桟橋から浅草まで、隅田川の”お花見船”に乗ってきました。隅田川沿いの桜は、高速道から見るのもよいのですが、船からの眺めも結構でした。まさに、春のうららの隅田川...でした。川面を走る温み始めた風と、船を追ってくるカモメが印象的でした。

k25 ( 2007/03/31 06:22:50)
文化とは何か?
前書き:
日本で開かれた国際会議の歓迎パーティーで”日本文化の紹介”というコーナーがあり、太鼓の演奏が行われた。日本文化の代表が太鼓なのかな?という疑問が生まれた。また、よく、外国人に自国の文化を説明できるようでなくては国際人とは言えない、と言われる。文化ったって何を説明できりゃいいんだろう?というような疑問から、文化とは何だろうと考えるようになった。20年近く、本で調べたりせず、自分だけで、気になった時だけ、考えてきた。最近、やっと一つの結論に到達したのでここで紹介する。
文化とは:
ある地域又はあるグループの人たちが共有する、考え方、価値観、美意識、美学、勘違い、誤解、偏見。及び、それらをベースにした生活、芸術、芸能。
文化の特徴:
(1)文化の価値観や美意識は、合理性から乖離(かいり)しているもので、乖離が大きければ大きいほど、価値観を共有する人たちにとっては美しいと感じられる。(武士の文化(美学)が世界で通じなかった例:蒙古来襲の際の戦闘で、日本の武士は1人づつ前へ出て名を名乗り戦おうとするが、前へ出る度に、蒙古軍は皆で寄ってたかって1人を攻撃した)
(2)文化は基本的に合理的でないため、食うや食わずの所には生まれない。格差社会で、富に偏りがあり、豊かな所に生まれる。(王朝文化はあっても百姓文化はない)
(3)合理的でない所が弱点になり、そこを突かれて滅びることがよくある(風雅を重んじる平家の公達が、武力に屈する)。
(4)そもそも合理的でない勘違いだったりすると、グローバル化の中では消えていくものも多い(首長族の風習、纏(てん)足)
(5)裸の王様的美意識かもしれない(昔のゴミの山から拾ってきたような何千万円もするお茶の茶碗、春の草花が咲き乱れる民家の庭の方がずっと美しいかもしれない枯山水の名庭園)
(6)”ローカルな地域やグループ内”が”基本”なので、世界的(グローバル)になたら文化ではなくなる。
後書き(何で、こんなことをまとめているのか?):
グローバル化が進み、格差が進み固定化し、異常な犯罪が連日報道される。これらの問題を読み解き、将来を予測する手段の一つとして、上で示した”文化”の考え方が有効ではないかと思っている。例えば、マクロな視点で言えば、人間には合理的と見える世界的価値観が、地球の立場で見ると不合理で弱点となり、地球温暖化などの逆襲にあう、といったものである。ミクロなケースに関しては本サイトで折に触れ登場することになると思う。
k24 ( 2007/03/29 12:25:58)
美しい日本
外人が、写真を持ってきて”日本人はどうして、こんな醜いものを飾るんだ?”と聞いてきました。写真には、街路灯などに飾る(ビニール製)桜の造花が写っていました。突然の質問に、日本を代表して適切な返答ができず、しどろもどろになってしまいました。その時以来、街の景観が気になってしかたがありません。桜並木の下によくある提灯達も、ないほうが美しいでしょうね。
何と言っても最悪は電柱と電線です。家の中に蛸足配線の線が散らかっているような感じです。最近、電柱と電線の数が増えてきているように思います。
絶対なくして欲しいのは、のぼり旗です。特に車道近くに置いてあったりすると、視界が妨げられ、景観どころか大変危険です。

k23 ( 2007/03/28 21:17:16)
マニア
50才位の時、看護士さんと雑談をする機会があり、”最近、なんだかモーいやになっちゃうことがあるんですよね”という話をした。その看護士さんは(元精神科の看護士さんをしていたそうで)すぐに、それは男性の更年期障害で、初老性鬱(うつ)っていうんです、と教えてくれた。その時初めて(当時は、あまり知られていなかった)男性にも更年期障害があることを知った。もっとも、50才で初老と言われた事の方がショックだったが。男にも更年期があるという情報はその後大変役に立った。その後も、たまにやる気がなくなる時があり、その時は、今、更年期症状が入ってきてるな、と冷静に観察できたからである。
先日ニューズウイークで”鬱病大陸アメリカ”という記事を読んだ。その中で鬱病が”depression”というのだと知った。depressionは、”低下する”とか”不景気”という意味だったと思い、早速辞書を引いてみた。するとなるほど鬱病という意味もあった。驚いたのは、鬱病と対をなす躁(そう)病が”mania”と書いてあったことである。ひょっとして、鉄道マニア等のマニアの事かと思い”mania”を引いてみると、なるほどそのマニアだった。ということは、英語では鬱病は”落ち込み病”、躁病は”熱狂病”ということらしい。
記事によれば、アメリカでは男性の鬱病が増加しているそうだ。問題が深刻なのは、アメリカで”成功した男”の定義に、落ち込んだり、沈んだり、悲しんだりする人は含まれないことで、そのため鬱病と認めようとしない人が多く、事態を悪化させることが多いそうだ。
私は以前から、アメリカの”強くなくてはいけない”という信仰を心配している。そこでは、”coward”という単語が重要な働きをしているように思う。”coward”には”卑怯者”と”臆病者”という2つの意味がある。日本では、臆病者は卑怯者ではない。英語ではこれらが一つの単語になっているため、アメリカ(人)は臆病(=卑怯)であることを恐れ、強がって、必要以上に攻撃的になるのではないか、ということである。
k22 ( 2007/03/28 11:20:58)
謝恩会(遅くなりましたが)
以前、高いお金を出してホテルで謝恩会をするのは勿体ないので、PALでやったらと提案し、実施したことがありました。学生さんに高いお金を出してもらうのは申し訳ない、という気持からでした。PALでの謝恩会は、出席者も少なく盛り上がりませんでした。その時気付いたのは、謝恩会は、(先生への謝恩という形ではあるが)実は学生さん達の卒業パーティーだったんだ、ということです。それ以来、”学生さんに申し訳ない”という気持ちがふっ切れ、謝恩会を楽しませていただいています。
今年もプレゼントを戴いてしまいました(どうも有難うございました:申し訳なく思います)が、パーティーに呼んで頂くだけで十分ですので来年からはプレゼントのご配慮なきよう、お願いいたします。

k21 ( 2007/03/27 12:29:54)
駅の清掃ボランティア
私は、軽い鉄道マニアです。電車では、ついつい一番前で進行風景を見たり(未来を見る感じ)、一番後ろで後方を見たり(過去を見る感じ)してしまいます。明らかに後方より前方を見る機会が多いのですが、これは過去を振り返るのがいや、という訳ではありません。最後尾だと車掌さんと対面する形になり、視線を合わせない様にするのが大変だからです。前方を見ていて気になるのは駅の線路のゴミです。私は東武線、新京成、と乗り継いできます。私が通過する各駅で線路に落ちているゴミの数をおおまかに言うと、新京成2個位、東武線5個位という感じです。東武線でもゴミが1つも落ちていない駅もありますが、すごいのは新柏駅で2、300個は落ちています。鉄道を愛するものとしては許せないので、駅に電話しておきました。年を取ると、段々口うるさくなります。
k20 ( 2007/03/26 09:56:26)
挨拶と掃除
今年度の卒研で例年と違った点は、他研究室の学生さんが何人か私の研究室で卒研を行ったことです。普通、他研究室の学生さんが研究室を使っていると違和感があるのですが、今年度の人たちは違和感を感じさせませんでした。それは、何より挨拶が上手なことです。私が研究室に様子を見に行くと、部屋へ入るやいなや、研究室メンバーの誰よりも大きな声で気持ちよく”おはようございます”とか”こんにちわ”とか挨拶してきます。元気な挨拶に出会うと、何となく元気が伝わってくるようで気持ちがよくなりました。
もう一つは掃除です。関さんは、クイックルワーパーと掃除機を持ち込み、頻繁に床を清掃しゴミを捨ててくれました(どうも有難うございました)。今まできたなかった部屋は、段々きれいになりだしました。やがて、それまで、散らかし放題でいた研究室のメンバーも影響を受け、少しづつかたずけをするようになってきました。
”挨拶さえできればサラリーマン何とかなっちゃう”、と言うそうです。挨拶と掃除は人生の基本だと改めて認識させられました。(私も、デスクトップきれいにしなくちゃ!!)
k19 ( 2007/03/23 14:19:07)
人生訓にもなりそうな、素敵な詩を教えていただきました。
=====
” 祝
婚
歌 ”(吉野弘)
二人が睦まじくいるためには
愚かでいるほうがいい
立派すぎないほうがいい
立派すぎることは
長持ちしないことだと
気づいているほうがいい
完璧をめざさないほうがいい
完璧なんて不自然なことだと
うそぶいているほうがいい
二人のうち どちらかが
ふざけているほうがいい
ずっこけているほうがいい
互いに非難することがあっても
非難できる資格が自分にあったかどうか
あとで疑わしくなるほうがいい
正しいことを言うときは
少しひかえめにするほうがいい
正しいことを言うときは
相手を傷つけやすいものだと
気づいているほうがいい
立派でありたいとか
正しくありたいとかいう
無理な緊張には色目を使わず
ゆったりゆたかに
光を浴びているほうがいい
健康で風に吹かれながら
生きていることのなつかしさに
ふと胸が熱くなる
そんな日があってもいい
そしてなぜ 胸が熱くなるのか
黙っていてもふたりには
わかるのであってほしい
k18 ( 2007/03/22 11:41:29)
女性のキャラ
(1)柏の駅の改札を走って出てきた女性が、外で待っていた男性に抱きついて体をゆすりながら(甘えた声で)”ゴメン、ゴメン”と繰り返している。アッと言う間に男性の顔から険(けん)が取れ、デレッとなってしまった。(カゲの声:あ〜あ、まただまされちゃったよ)
(2)以前、看護学校で教えたことがある。授業終了後、ある女子学生Aさんと話していると、通りかかった別の(女子)学生さんが、Aさんに”なに営業笑いしてんのよ!!”と声をかけた。そう言われてみると確かに、遠くもなく、近くもなく、感じは悪くないが、特によくもない。(言葉ではどんなものか定義しにくい)営業笑いって技術が本当にあるんだ!!と感心した。
柳原可奈子に教えなくちゃ!!
テレビを点ければお笑い芸人ばかりで辟易し、ここ1年近く、お笑い番組を見ないようにしていた。先日偶然お笑い番組にチャンネルが当たってしまい、ムーディ勝山の歌に遭遇してしまった。どうしてあれが面白いと思い付いたのか、オリジナリティーの高さに感服した(何だか、やなメロディーが頭から離れない)。その時同時に、柳原可奈子を知った。(この人が有名なのかどうか知らないが)女性のキャラが乗り移ったとしか思えない芸は、絶品であった。”コギャルの物真似”を見ていると、演技と分かっていてもムカついてくるほどだった。お笑い芸は、まだ出てくるのか!!って感じである。
k17 ( 2007/03/22 11:06:34)
自分の頭で考えよう
(1)開花予想
先日、桜の開花予想がコンピュータの入力ミスで誤った、という話があった。半分理解でき(沢山のデータを出力するといちいちチェックすることはしないかも)、半分理解できない(結果を見て1人や2人おかしいと気付く人いなかったのかしら)話である。最近、一部の学生さんの行動で少し気になっていることがある。
(その1)プログラムを作ることが必要になると、先ず最初に、そのプログラムが落ちていないかインターネットへ探しにいくことである。研究で使うプログラムは、プログラミングの訓練も兼ねているのだから、自分で作るべきである。大体、人の作ったプログラムを使う場合、元々何の為に作ったものか分からないので、完全に理解し納得するまで使うべきではない。
(その2)拾ってきたプログラムの出力結果を何の疑いもなく提出することである。一寸考えれば間違ってることに気付くだろうに、ということがよくある。コンピュータの出力結果を見る時は、先ずは、自分で大体の予想を立てておき、コンピュータの結果は精度を上げるためのもと考えるのが普通だと思っていたのだが。
先日アメリカのニュースでも多くの学生がインターネット上の誤った資料を使ったリポートを提出した、という報道があった。コンピュータの出力結果やインターネットに載っている記事を何の疑いもなく受け入れる習慣が付いてしまっていないか心配になる。
”プログラムは自分で作ろう!!”、”結果はちゃんと自分の頭で考えよう!!”。
(2)タミフル
一昨日、厚生省がタミフルの10代の人への投与を控えるよう、お達しを出した。厚生省は、因果関係が確認できない、ということであったが、危険な可能性があるのなら、とりあえずストップをかければよいのに、と思っていた人は多いのではないか。お達しを出すのがどうして遅いのか、また、10代だけでよいのか、などまだ分からない点も多い。
(これと関係が有るのか無いのかは分からないが)物事の因果関係を算出する”検定”という学問分野がある。(私は少しかじった程度だが)その時の印象では、”検定結果”が私の直感と合っていないことが多かった。特に生命関係への適用では、人に冷たい結果になることが多かったように思う。人間は生命維持の本能から、検定の理論的結果より安全サイドで因果関係を判定するのかもしれない。因果関係の判定には、人間の直感も大切にする必要があるのではなかろうか。
大体、日本は薬の使い過ぎかもしれない。以前子供がアメリカで高熱を出しお医者さんにいった時、日本では抗生物質の薬が出るのが普通なのに、アスピリンしか処方されず、”こんなものでいいんだ”、と思った経験がある(これは20年位前の話で、今はどうなっているのかは知らない)。タミフルの使用量は日本が世界一だと聞く。タミフルは悪質インフルエンザに対する唯一の特効薬だとすると、やたらに使ってよいのか心配になる。タミフル耐性菌が出てくることはないのか?(以上の、薬に関する感想は全く素人としての意見です。本学には薬学部がありますが私は薬に対する知識はありませんので、誤解のなきよう)
k16 ( 2007/03/20 11:11:18)
ユートピア(桃源郷)?
梅、桃、桜、と言われる割りに。桜と梅の名所は沢山ありますが桃の花の名所はあまり聞きません。
昔から短歌や俳句に、梅と桜はよく詠まれますが、桃はあまり聞きません。
もう少し、注目されてもよい気がします。
先週、八潮(埼玉と東京の境)フラワーパークに、桃花園があると聞いて行って来ました。
桃は川岸に沿って150m位の場所に2列に並んで植えられていて満開でした。桃の色は比較的濃いピンクで、花の付き方も力強く、桜とはまた違った美しさがありました(桜に勝るとも劣りません)。
桃は、桃の節句の関係からか女性を連想させます。確かに、優しい感じだが力強い感じがあり、女性の美しさとタフさを象徴するものとしてピッタリだと思いました。
”桃だけが私の味方この恋を白き椿も梅も許さず”(与謝野晶子原作、俵万智訳)
の心が初めて分かりました(さすが、って思います)。
(八潮市は、桃源郷を目指しているようです)植樹面積が今の4倍位になると壮観だと思いますし、対岸の市にも働きかけ両岸で面積が今の20倍位になると河津桜級の観光スポットになると思います。
=桃源郷とは=
4世紀後半、武陵という所の漁師が小船で川を上っていくと、桃の花が咲き乱れている場所が現れ、桃林は川の水源まで続いていた。水源の山にはトンネルがあり、そこを抜けると戦乱を逃れて住み着いた人たちの平和な村があり大歓迎を受けた。漁師はやがて故郷へ 帰り役人に話すと、案内するよう言われたため先導したが二度と桃源郷に行くことはできなかった、そうな。『桃花源記』陶淵明著

k15 ( 2007/03/19 18:16:33)
美しい言葉
先週末、2つの美しい言葉に出会いました。
(1)オードリ・ヘップバーンが愛したSam Levinsonの詩
美しい唇のためには 親切な言葉を語りなさい
美しい瞳のためには 人々の良いところを見つけるようにしなさい
スリムな体のためには おなかの減った人に食べ物をあげなさい
美しい髪のためには 一日一回子供の手で髪をすいてもらいなさい
美しい振舞いのためには あなたはいつも一人ではないことを知りなさい
物と違って人は 絶え間なく心身の疲弊から、救い続けてあげなければなりません
誰も見捨ててはいけません
助けの手が必要となった時 あなたの手の先にその手があることを忘れないでください
歳をとると 自分に二本の手があることに気付くでしょう
一つは 自分自身を助けるために
もう一つは 他者を助けるために
(2)マザー・テレサの言葉
人は、不合理、利己的です。
気にすることなく、人を愛しなさい。
あなたが善を行うと、利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。
気にすることなく、善を行いなさい。
目的を達しようとする時、邪魔立てする人に出会うでしょう。
気にすることなく、やり遂げなさい。
善い行いをしても、おそらく次の日には忘れられるでしょう。
気にすることなく、し続けなさい。
あなたの正直さと誠実さが、あなたを傷つけるでしょう。
気にすることなく、正直で誠実であり続けなさい。
あなたのつくりあげたものが、壊されるでしょう。
気にすることなく、作り続けなさい。
助けた相手から、恩知らずな仕打ちを受けるでしょう。
気にすることなく、助け続けなさい。
あなたの中の最良のものを、この世に与えなさい。
蹴り返されるかもしれません。
でも気にすることなく、最良のものを与え続けなさい。
k14 ( 2007/03/19 18:13:55)
パンツ
ある学生さんに、”自分が興味を持っている事柄を例に、ゲーム理論を説明しなさい”、という課題を出した。1週間後学生さんは衣料品製造の戦略例を数ページにまとめてきて、説明してくれた。その中で、製品に”ジャケット”、”スカート”、”、”パンツ”、が出てくる。学生さんは、説明が”パンツ”のところへ来ると必ず、”これはズボンです”と注釈を加えてくれた。私だって、”パンツ”が”パンツ”じゃないことくらい、知ってるツーの!!
k13 ( 2007/03/15 14:12:50)
卒業式
ご卒業おめでとうございます!!。一時、卒業式を習志野文化会館で行っていましたが、文化会館が改修工事とかで使えず、また体育館に戻りました。(私は今、要職に就いていないので雛壇に登りませんが、以前雛壇に登っていた時)雛壇から卒業生達を見ていると、”これからどんな人生が待ってるのかな?”とか”しんどい事もあるだろうな”なんて思い、何か、いとおしさ(人生のせつなさ?)を感じ、”みんな良い人生が送れますように!!”って念を送ったものでした。今日も、低い所から”よい人生が待っていますように”、とお祈りしています”。

k12 ( 2007/03/13 15:52:58)
臍下丹田、心、健康法
”禅と弓”以来、少し禅づいて、”禅の名言”(高田著:双葉社)を読んだ。
色々な興味深い話が載っているが、その中で我々の役に立ちそうなものを並べてみる。
(1)”すべては良くなる”、”困ったことはおこらない”、”過去を思わず(過去の失敗を悔いるな、自分を責めるな、という意味)”を自分に言い聞かせるようにすると悪いことにはならない。言霊を大切に。
(2)我々の心は本来、神、仏の心と同じく清らかで美しいものなのだ。怒り、恨み、嫉妬などは煩悩によって起こる妄想の一種である。本来の心を輝かすように心がければ、心の闇(妄想)は消え去る。具体的には”闇は本来存在せず、心は本質的には清らかなものだ”という自覚を持つ。怒り、恨みなどが起こったら、これは妄想だと自覚する(苦悩の分離?)。
(3)内観の法(瀕死の白隠禅師に白幽仙人が授けた健康法):人間本来の清浄な心は臍下丹田(せいかたんでん:ヘソ下10cmm)にある。内観の法は、ゆったりと両手両足を開き横たわる。手足の力を抜く。ゆっくりとおなかに息を吸い込む。この息が静かに臍下丹田を満たすようにし、ゆっくり息をはき出す。息は鼻から出し、鼻から吸う。この時、”自分の臍下丹田には本当の心、清浄な心がある。自分の臍下丹田には輝く浄土がある。自分の臍下丹田には荘厳な仏が宿っている”と繰り返す。あるいは簡単に、腹部に手を当て、”ここをさすればすべての健康の泉が湧き出てくる”、と念じる。
k11 ( 2007/03/12 16:45:49)
名医(実名入り)
今までに2度、名医と思われる先生に出会いました。
(1)痔
30第後半、2年位、痔に悩まされました。近くの大きな病院などに行きましたが一向に良くなりません。当時有名だった漢方薬注入も試しましたがダメ、あげくの果ては超能力治療にまで行きましたがダメでした。いよいよ行き詰った時、東京の2本の指と言われる痔の名医の話を聞き、早速診てもらいに行きました。それは、青山にある平田医院といい、現在もあるようですが、私が診てもらったのは先代の先生です。日帰り手術と宣伝されていたのも、勇気付けてくれました。手術は一寸切って縫うだけで、ほんの数分で終わりました。術後1ヶ月位は週2回位通ったと思いますが、完治し、その後再発はしませんでした。名医にかかれば、数年の苦悩がほんの数分で解決します。なお、先生の書で”鬼手仏心(キシュブッシン)”という言葉を知りました。外科手術で、仏の心で大胆に(鬼の手のように)切る、という意味だそうです。
(2)歯周病
40歳位のころ、歯を磨くたびに出血するようになりました。たまたま近くの歯医者さん(つくばの松代歯科)に行くと、”このまま放って置くと50歳位には歯がなくなっちゃいますよ”と言われ、本格的歯石(歯垢?)除去をすることになりました。それは麻酔をかけて歯茎の奥の歯石を取っていくもので、全体の除去に5,6回かかりました。その後は出血もなくなり、昨年(柏に転居後)近くの歯医者さんへ歯石の除去に行った時、なかなか良い状態で50歳位の歯茎ですと褒められました。最初に偶然いった松代歯科は歯周病専門医という資格をもった人でした。そのため、柏でもネットで歯周病専門医(山口歯科)を選んで診てもらいました。山口先生と話していたら、山口先生と松代歯科の先生は大学時代の友達だと聞かされました(世間は狭い)。
k10 ( 2007/03/09 15:22:54)
Windows Vista
Vista対応と、プリンタ2台が故障したため、計算環境を更新した。
(1)計算機環境:
XPマシンDELL(2004年導入:側面を紅白に塗った、美しい!?)。
VistaマシンEPSON(今月5日納入:気が付けば研究室はDELLとHPばかり、今回は国産品をと)
モニタ3面(DELL、EIZO、WACOM):山内先生のHPを参考に3面を導入。マルチモニタは使い慣れるとやめられない。生産性が格段に向上するので最低2面は不可欠。EIZOのFlexScanS2000モニタはお値段が高かったが、それだけのことはある(美しいし、疲れないので、お薦め)。
プリンタOKIc3400(初めての沖):ここ10年近く頑張ってくれたのはキャノンレーザプリンタ、廃棄時に感謝の気持ちを禁じえなかった初めての機械。今回、キャノンと同時に具合が悪くなったのは2年目のリコーのジェルジェットプリンタ。私とジェルジェットとは余程相性が悪いのか、3年前買ったジェルジェットプリタが故障続きだったので、新品に交換してもらったものが今回故障した。
(2)Vista:
VistaはXPとは色々変った点があると聞いていたので、授業で使うソフトが問題なく使えるか、期待半分、不安半分で導入した。
期待していた点は、ユーザインタフェースである。エアロとかいう\"スケート犬\"のようなウインドウ表示は、前評判どおりで、その動きは快感であった。その他は、マルチデスクトップとか、もっと3次元的デスクトップを期待していたので\"期待が大きすぎたか\"という感じである。
Vistaの不安はXP用に開発されたソフトの互換性である。最初に困ったのは、周辺機器のドライバがVistaに対応していないことである。今回購入した沖のプリンタもドライバが対応していないため、ネットからダウンロードしてインストールする必要があった。ネットから落としたドライバは、CD版のように自動化されていない上に、説明が分かりにくい。私はネットワークプリンタ設定に失敗し、ネットワークアクセスが全くできない状態に陥った。これを回復しようとすると、Vistaの守りが堅いためなかなか詳細設定にたどりつけない。(ネット設定が分かっている私でも)これを解決するのに1時間以上要した。素人では回復不能ではないか思われた。また、XPマシンで使用したマルチモニタ用のデバイスのドライバもVistaに対応していないため、しばらくの間Vistaは1面モニタでいくしかない。
アプリでは、Javaは問題なく動き(今までに出なかった警告が1つ出たが)、Jcpadも問題なかった。MS-Agentを動かすVBscriptでは、動きは問題ないが、日本語の音声読み上げができなかった(一寸困る!!これから対策会議)。
その他基本的な所では、セキュリティーがきつくなり、やたら確認を取ってくるので、うっとおしいのと、自信がないと不安になってくる。また(私が使い方をマスターしていない精かもしれないが)コントロールパネルが表示されなくなり再起動を行わざるを得ないケースに遭遇した。
これらを総合すると、これからパソコンを買う方はVistaだが、今XPを使っている方は、急いでVistaに移行する必要はない、ということだろう。
(3)マルチモニタ奮戦記(約半年前):
DELLをマルチモニタにしようと、BuffaloのPCIカードを購入して2台めのモニタを接続したら元のメインモニタが映らない。色々試すうちに、カードに補助的に付いている出力を使えばよいことが分かる。それ用のコネクタを作るために金属加工が必要となった(指を怪我し大出血)。3台目用にはUSBでモニタを表示できるVIEWPORTという機器を山内先生からもらう(カードよりは応答が遅いかも)。これで3面モニタ完成。
マルチモニタ用カードはパソコンとの相性があるので、メーカに聞いてもわからず、試行錯誤が必要(2度とやりたくない)。国産のUSBモニタアダプタがあるようなのでVista対応か調べてみようと思っている。

k9 ( 2007/03/05 12:01:31)
弓と禅
(1)弓の構造
10年くらい前、筑波大公開講座”弓道”を3,4ヶ月位受講した。その後も弓を続ける機会はあったが、やめてしまった。理由は、弓の構造にある。矢が弓の竹の右側を通過するため、弦を離すと同時(ほんの少し遅れて)弓を持っている手首を返す必要がある。弓道とは、この放矢と左手首の返しのタイミングを学ぶものであるという結論に達した。矢が弓の中心を通る構造にすれば何の苦労もいらない。現にアーチェリーは、そのような構造になっているし、石弓も鉄砲のように撃つ。何でわざわざ難しくして、ひたすらタイミングを学ぶ必要があるのか?何で日本人は何百年もの間、弓に工夫を凝らさなかったのだろうか?ということになってしまった。
(2)弓と禅(日本の弓術:岩波文庫、ヘリゲル著)
最近”日本の弓術”を読んだ。短い本で(本論は50ページ程度)のなかで弓道と禅の本質を言い当てている。大正時代に、外国人のために書いたものなので、現代の日本人にも大変分かり易いので、お薦めである。要約するのは難しいので、ヘリゲルの師が述べた弓道の真髄を要約しておく。”仏陀の瞑想の絵の様に目をほとんど閉じると、的が自分の方に近づいてきて自分と一体になる。それは自分が仏陀と一体になったことを意味し、矢は有と非有の不動の中心にある。意識の世界では矢は中心から出て中心に入る。それゆえ、的を狙うのではなく自分自身を狙う。するとすると、自分自身と仏陀と的を同時に射中てることができる”
(3)降りてくる
上で書いた弓の真髄は、ありえないことの様に思える。しかし、野球の神様と言われた川上哲治は球を打つとき、飛んできているはずの球が静止するのを経験したというし、この種の神秘的体験は、よく耳にする。実はこの凡庸な私も(そんな高いレベルの話ではないが)研究で切羽詰まり、無心で考えている時、不意に答えのヒントが目の前に現れる現象を何度も経験している。私はこれを”降りてくる”と言っている。超科学的現象と思えないでもないが、研ぎ澄まされたアンテナに答えが引っかかってきた、ということかもしれない。この現象を導く秘訣は、この現象が起こることを疑わないことである。期せずして、ヘリゲルも”師の言う無の世界に入れるようになるには、入れることを疑わないことである”と言っている。
k81 ( 2007/03/03 12:37:27)
近況
今年度最後の論文が2月28日に仕上がりました。今日(3月3日)は、合格者のための研究室公開という行事で来ています。3月の公式行事は卒業式くらいで、その他、送別会等一寸したものはありますが、基本的にはリフレッシュ&充電期間で、ホッと一息つける時です。
早速、3月1日に河津桜を見に伊豆へいってきました。伊豆はもう春真っ只中であちこちの桜が満開でした。
(1)河津桜:
河津桜は、そめい吉野より濃いピンク色で、力強い感じの桜でした。花の額の精か、少しベージュが入っていて、でも品がよい感じで言うことなしでした。桜は川沿いに4km位にわたって咲いていてなかなかでした。
問題点は、露店が多すぎることです、桜並木に沿って隙間なく並んでいます。こちらも、ついつい花より団子に引きずられ、商魂が桜の風格をおとしめている感じです。また、当日は平日でしたが結構人が出ていて、休日はすごいことになるんだろうなと想像されます。
(2)大島:
一寸驚いたのは(地理の不勉強を露呈してしまいますが)、電車が伊東から河津に南下する途中、車窓に大島、新島等が大きく見えることです。特に大島は、その名の通り大きく、手漕ぎボートでもいけそうな感じでした。
(3)卒業旅行:
電車の中には、女性5、6人の卒業旅行グループがいました。彼女らは、車窓から見える桜に”きれーきれー”と歓声をあげていましたが、お嬢さん達の方がもっと華やいでる感じでした。
古風なら、
”その子二十歳(はたち)櫛に流るる黒髪のおごりの春の美しきかな”(与謝野晶子)
現代語訳の方が分かりやすければ、
”二十歳(はたち)とは ロングヘアーをなびかせて畏(おそれ)を知らぬ春のヴィーナス”(訳:俵万智)
ってとこかしら。

k82 ( 2007/03/03 12:36:35)
河津桜2

k83 ( 2007/03/03 12:35:22)
河津桜3

k7 ( 2007/03/03 06:09:12)
変身
今は昔(私が小学校高学年の頃)、霞ヶ浦から魚を売りに来るおじさんがいました。私の家ではよく雑魚(ザコ)というのを買って醤油で煮て食べました。雑魚とは魚を網で採ったとき網に残る1〜2cm位の小魚や海老などです。時々、雑魚より少し高級なワカサギを買いました(個人的にはワカサギより雑魚の方が好きでしたが)。私の家では、ワカサギに敬意を払い、そのおじさんをワカサギ屋さん、と呼んでいました。ある時、私は近くのお医者さんに行き、待合室で順番を待っていると、お医者さんの息子さんが”お母さん、ウナギ屋さん来たよ”と言うのが聞こえました。間もなく待合室に顔を出したのは”ワカサギ屋さん”でした。子供心に、”わずか数百mの移動でワカサギ屋さんからウナギ屋さんに変身するんだ”と感動しました。
雑魚
私より少し歳が上(戦前派)だと、家長制が生きていて、父親と長男だけ魚の切り身を食べ、後の女子供は雑魚を食べるというのがあったそうです。栄養学から見ると、切り身の一品より、小骨入りの雑魚の方が栄養があり、(そのためか分かりませんが)贅沢をしているはずの長男がひ弱だったりすることが多かったようです。最近スーパーで雑魚を見かけることはありません。雑魚はどこへ行った(佃煮?)?。私達も切り身の魚で贅沢をして、ひ弱になっちゃってるかもしれません?
k6 ( 2007/02/15 18:06:09)
ネックウオーマー
”風邪、のどから来る人”へ。私の風邪は必ず喉からきます。いつも予兆を感じると、(濡れ)マスクをしたりしていましたが効果はほとんどありませんでした。最近、一寸喉が怪しい時に、ネックウオーマをすると大変効果があることを発見しました。ネックウオーマとは、首に付ける円筒形の布で、スポーツ用具屋さんで1500円位で売っています。風邪、喉からくる人は是非お試し下さい
k5 ( 2007/02/13 16:15:02)
和田先生と情報処理
先日、(私の前の職場である)つくばの産総研から、”大先輩である和田弘さんが永眠された”というメールが届いた。和田先生はトランジスタ式コンピュータを開発された人で、”コンピュータの歴史”といった記事には、よく引用される。
http://www.technogallery.com/nec_c-and-c/1nen-no-ayumi/1985-1989/11.pdf
その後先生は大学へ移られ、そこで私は先生の研究室の大学院生になった。先生は趣味でみかん畑を作られていたため、卒業後も時々農作業のお手伝いに伺った。農作業の後、酒を飲みながら先生の珠玉の放談を聞くことは楽しみであった。ここでの先生のお話が、私の人生観や研究感に大きな影響を与えた。この雑記帳の ”E5:座右の銘 の恩師”とは先生のことである。ちなみに、我々が何の疑いもなく使っている”情報処理”という言葉は、先生がinformation processingという英語の和訳として造られた言葉である。先生のご冥福をお祈りいたします。
k4 ( 2007/02/02 18:35:07)
先輩との別れ
最近、卒業生のK子さんが寿退社されました。そして会社を去る日のエピソードを教えてくれました。K子さんには入社以来面倒を見てくれていた独身の(すごく優秀だけど、ちょっと愛の告白は苦手な)先輩がいました。先輩は、K子さん最後の日ということで、彼女にスケジュールを合わせ、彼女がグループの人達に送るお礼の手紙の作成と配布に、夜遅くまで付き合ってくれました。先輩と後輩の最後の作業が終わり、2人は会社を後にし、それぞれの家路につきます。分かれた後、彼女は先輩に携帯でお礼のメールを送ります。そのメールに先輩は次のメールを返してきます。
「駅のホームは寒いのに、なにやらほんわかとしました。あんがとな。」
==ここで十分感動した人は、以下のヤボなコメントを読まないように==
んー何だか、心のかなり奥の方の、それも、とてもデリケートな琴線に触れるのは私だけかしら。映画の1シーンを見ているみたい、寒いホームで携帯を見ている先輩、そしてバックグラウンドに小田和正の”さよなら”(さよなら さよなら さよなら もうすぐ外は白い冬 愛したのは 確かに 君だけ そのままの君だけ)が流れて。
k3 ( 2007/01/15 13:26:24)
癒し系美術館
昨年末、津田沼丸善でカレンダーを見ていたら、ミッシェル.ドラクロワの絵を使ったものがありました。
http://www.megapress.co.jp/art/delacroix/index.html
何だか懐かしい感じの絵です。そういえば、これに雰囲気の似た、子供達が(クリスマスだったか)雪遊びをしている、何となく心温まる感じの絵を見たことがあるな、って急に気になりネットで調べてみました。最初にひっかかったのは、グランマ.モーゼスの絵でした。
http://www.tv-tokyo.co.jp/kyojin/picture/031213.htm
でも、一寸違うな、って思っていたら柏高島屋でジェーン・ウースター・スコットの作品を売っていました。これ、かなり近いなと思ってネットで探したら、沢山の作品がありました。
http://www.megapress.co.jp/art/jane_wooster/index.html
同サイト、
http://www.megapress.co.jp/art/index.html
には、この他、癒し系の絵が沢山並んでいます。”欧米”じゃないんですが原田泰治の作品も共通するものがあるな、って思います。
http://www.tanukikoji.or.jp/matsuyama/harada/index01.html
以前、諏訪で彼の美術館を訪れた帰り、車内から見る風景が全て原田泰治風にデフォルメされて見えてくるのでビックリしたことがあります
k2 ( 2007/01/09 14:42:14)
心の形と構造
最近、健康ブームで、運動やダイエットへの感心は高い。楽だから、おいしいからといって横になってケーキばかり食べていては駄目で、”少しきつくても”運動をし、きらいでも野菜を採らなくてはいけない。一方、心も基本的には体と同じはずなので、我侭を通し、言いたい放題、やりたい放題やっているととんでもない状態になる恐れがある。体と同様に、周りと衝突したり傷つけあったりと、思い通りいかないことを経験し、自分を律していくことが重要なはずである。物が乏しい社会では寝転んでおいしいものばかり食べてはいられないので、自動的に運動不足や肥満の問題は解決された。物があふれ、災害や戦争がない平和な時代には、”怠けたい体”と”怠けたい心”の要求を自分で制御するよう心がけなければならない。特に心は、形が見えないので注意が必要である。私は、心にも(見えないだけで実は)骨格や筋肉、皮膚の他消化器や循環器、呼吸器のようなものがあるのではないかと思っている。異常な事件が続発する現代、心の形と構造を解明し可視化することは急務だと思う。今、もし我々の心を可視化してみると、多くの人は”超肥満で歩けなかったり”逆に”ガリガリにやせて、転んだらすぐ骨が折れる”ような状態になっているかもしれない。
k1 ( 2007/01/06 16:26:10)
去年今年(こぞことし)
年末年始、来年度の資料を書くか、テレビを見て過ごしました。印象に残った番組を3つほど。
(1)久しぶりにアニメ(NHK教育TV、”メジャー”)をたっぷり見ました。大人が見てもなかなか良い作品で、久しぶりでアニメで泣かされました。
(2)深夜見た”不思議の国のアリス(フジTV)”は秋葉系の女の子が半分幻想のようなトークを行っていて、あんな世界もありかな、って不思議な感覚を経験しました。
(3)NHK俳句で、なかなかよい作品を3つ知りましたので、並べてみます。
“去年今年貫く棒の如きもの”(虚子)
年が変わっても、変わらないものが一貫している、というものです。さすが、素人とはひと味違いますね。
“桃二つ並べてみれば瓜二つ”
これは川柳ですがよく出来てますね。
“大空のどこかが欠けし流れ星”
これも、何て美しい発想なんだ、って驚いちゃいます。
(
2007/01/03 13:42:34)
酒器
最近、めっきり酒が飲めなくなってしまいました。しかたがないので、わずかな量を最もおいしくいだだく研究を行うことにしました。以下に酒と酒器の相性の調査結果を報告させていただきます。写真は、現在のところベストマッチかな、と思われるものです。右端は、大きさの参考に900mlのジュースペットボトルを置いています。
(1)日本酒:基本的に冷酒しか飲みません。酒器には(左端)漆塗りの杯を推薦します。何となく時代劇の中に入った雰囲気を味わえます。
(2)ワイン:グラスとワインの味は無関係と思っていましたが、大違いでした。今まで、おまけに付いてきたグラスを使っていましたが、写真左から2つめのグラスは全く味というか香りというかが違います。オーソドックスでワイングラスとして売られているものがよいと思います。高価で奇抜なものを買ったこともありますが、全然だめでしたので。
(3)泡盛のお湯割り:焼酎系は泡盛しか飲みません。写真中央は卒業生からいただいた備前焼カップです(感謝)。分厚い壁をほんのり伝わってくる暖かさが何とも言えません。
(4)ビール:ギネスとか白ビールが好きです。右端の逆円錐型のカップは、愛知万博のドイツ館で購入しました。ビールの味が極端に良くなります。これが酒器と酒の関係を調べるきっかけになりました。

j2 ( 2006/12/28 18:00:28)
蓑虫
私の父(古谷をさむ)は、俳句三昧の余生を送っています。息子(私)に対して直接言えない不満や苦言を俳句にすることもよくあります。このほど、”一切を断ち蓑虫は蓑の中”(言いたいことはあるが、言うまい)という句が東京新聞の今年の年間大賞に選ばれたそうです。この他、”父と子と多くは言はず夜の秋”も、同新聞の入選句になったそうで、”孝行のことば死語なりクロッカス”なんてのまで作られちゃってます。私も随分発句に貢献した孝行息子だな、と感慨一入です。ちなみに、俳句で蓑虫は”鬼の子”(鬼が子に自分の衣をかけて、いまに迎えに来るからと言って捨てていき、子が親の来るのを待っている姿:枕草子)ということになっているようです。
j1 ( 2006/12/26 11:16:00)
サッカーと柔道
先日トヨタカップの準決勝と決勝をテレビで観戦したとき気付いたこと:私はサッカーはズブの素人だが柔道は少しかじったことがある。柔道は国際大会と国内大会で選手の組み手(組み方)が大きく異なる。国際大会では前かがみになり激しく襟を奪い合う。これに対し国内大会では両者が距離をとって比較的リラックスして襟を取る。後者(国内大会)の構えは、スキもできるが、技を出す空間ができ技を楽しめる。前者は、スキのない点取り合戦で、ハラハラはするが楽しめない。トヨタカップでの選手の位置取りはワールドカップに比べると、ガツガツ球に近づくのではなく、選手間の距離をとっているように見える。そのため、個人の技や戦法を楽しめる空間ができ技を楽しむことができたように思う。日本の柔道には勝敗と同時に技を楽しむ文化があるように、ヨーロッパや南米のサッカーにも勝負と同じくらいに技を楽しむ文化があるんだな、と思った。試合がグローバルになると勝敗でしか結果が語れないので、文化がないがしろにされる。経済活動も同様で、グローバル化と共に、お金での勝敗でしか評価されなくなり、スキ(遊び)のない社会になり、これが社会の閉塞感をもたらしているのではないか。
i3 ( 2006/10/16 10:33:33)
せつない
昨夜テレビで”10文字作文”ってのをやっていて、俳句より短い表現法があるのか興味が出て見てしまいました。昨夜の”お題”は、”せつない”でした。私の気に入った作品を3つ紹介します。
(1)徐々に沈む母の背泳ぎ
(2)じゃあ先生と組もうか
(確かに、こんな風に先生に言われるとせつないですね)
(3)おやじが寝言で平謝り
先日、電車内での女子高生の話。
”ゆうべ、親が夫婦喧嘩してて眠れなかったよ。夜中2時ごろガチャンって花瓶のようなものが割れる音がすると、お父さんの”ウー”って声がして、その後お父さんの声が聞こえなくなっちゃったんだ。お父さん死んじゃったんじゃないかって心配になっちゃって。”(ンー、お父さん、平謝りしかないかもね)
i2 ( 2006/10/16 10:30:40)
知らなかった!!
最近、ネックレスの”レス”はレース(紐)のカーテンのレース(レス)だって知りました。
音だけじゃ分かりにくい言葉ってありますよね。最近、あるおばさんから2つの質問を受けました。
(Q1)インターネットのグルグルって何?
(A1)あ、それは。インターネットをグルグル見て回るものですが、グルグルじゃなくてグーグルです。
(Q2)ゆびきたす、ってどうゆう漢字なの?
(A2)ああ、それは。湯引足じゃなくて、”どこにでもある”って意味の英語なんです。
どんどん新しい言葉が出てくるんで、ついていけませんよね。
i1 ( 2006/10/12 12:01:51)
最近知った3へ〜!!
(1)my茶碗:日本のように自分の食器(食事用茶碗)を持っている国は、あまりないそうです。言われてみれば、洋食や中華で自分の皿ってのも変な感じです。日本でも、my箸のない地方もあるようです(私の周辺では、千葉県でいうと君津以南に多いみたいです)。
(2)ぴょこぴょこ歩き:日本人の歩き方は、体が上下にぴょこぴょこ動く特殊な歩き方だそうです。これを象徴しているのが、行進です。行進の時日本人は膝を90度に上げます(高校野球の入場)が、ドイツや北朝鮮の軍隊の行進は足を前にまっすぐ伸ばして跳ね上げます。世界的には、膝を90度に曲げる方式は特殊な方式のようです。日本式は足を踏みおろす時ベクトルが上に向き、体は上に動きます。これでは前に進まないため、猫背にしたり頭を前に出して前方へのベクトルを作ります。そのため、歩行姿勢が悪くなるそうです。膝を曲げずに脚を出し、かかとから着地するのが美しい歩き方のコツとか。
(3)同日生まれ(直感では納得できない話):(数学的には)23人いると、その中で誕生日が同じ人がいる確率は50%を超えるそうです。サッカーの試合(選手+主審=23名)で、同日生まれの人がフィールドにいる試合は、半分以上です。そう言われてみると、結婚して親類の人数が増えた時、新親類の中に同日生まれの人がいるので運命を感じた人も少なくないのではないかと思います。私自身、実弟と義弟の誕生日が同じで驚いた経験があります、でもこれは運命じゃなくて数学的にはよくあることなのでした。
h6 ( 2006/09/21 17:39:17)
咲ん人(さきんど)
久しぶりで99年卒の郷智恵子さんと連絡が取れました。3年前に”咲ん人”(http://www.sakindo.co.jp)という会社を立ち上げ、順調に成長しているようです。最近池袋オフィスも開かれたそうで、以前は雷門でしたから少しづつ六本木に近づいてますね。陰ながら、期待し、応援しています。(学生さんへ:郷さんは在学中から、”会社を開くのが夢だ!”と言っていました。きちんと目標を持つこと。そして、望みは口に出して言うことが実現の秘訣です”)
h5 ( 2006/09/08 13:59:08)
ちょっといい話
大学まで来る間に大きな樹木があり、その木には”犬のフンは持ち帰ろう”という、ビニールでラミネートしたポスターが6本の大きな釘で打ちつけられていました。生木に大きな釘を打つのは感心しないので、船橋市に電話して、貼り主に取り去ってもらうようお願いしました。数ヶ月後、久しぶりでその木の横を通ったら、ポスターと釘は取り去られていました。ご協力有難うございました。
h4 ( 2006/09/08 13:49:56)
読書案内(200/9)
最近、”読んで良かった”と思う本に連続して出会いました。どれもお薦めなのです。(以下、私が読んだ順で、順番には何の意味もありません)
(1)逝きし世の面影(渡辺京二、平凡社ライブラリー)
自分の考え方のルーツが分かる気がします。人の考え方は普遍的なものと思っていますが、実は育つ過程で影響、教育されてきたもので、いつの時代でも正しいというようなものではないことが分かります。
(2)国家の品格(藤原正彦、新潮新書)
現在行き詰まっている社会の様々な問題を、”自由”という思想さえ疑って、考え直そうというもの。一気に武士道まで戻っちゃえ、って斬新な提案。昔、同氏の”若き数学者のアメリカ”って本読んだな!って思い出しました。
(3)病気にならない生き方(新谷弘実、サンマーク出版)
酸化食品を食うな、って提案。牛乳、ヨーグルト、マーガリンは最悪という、乳業にはショックな本。
(4)富の未来(アルビン.トフラー、講談社)
現在、世界(もちろん日本でも)で起こっている様々な問題の本質を、知識、時間、空間に求め読み解こうとするもの。大変優れた本です、絶対読まないとダメ。
(5)フェルマーの最終定理(シン、新潮文庫)
物理学者の物語は色々よく知られているが、数学者にも沢山の物語があったんだ、って感動する本。
h3 ( 2006/09/06 11:52:48)
2006/8/26に2004年卒同窓会(花火&ボーリング)が行われました。(2006/9)

h2 ( 2006/09/06 11:37:59)
旧聞ですが、昨年9月大畑君(H13卒)の結婚祝賀BBQ大会が行われました。その時の写真です。(2006/9)

h1 ( 2006/09/06 11:27:07)
2006年版HPへの移行に伴い、以前の”独談”コーナー(下記g以下)を、この”雑記帳”に引継ぎました。今後は、画像も使い、種々の出来事や感想を気軽の書き込んでいきます。(2006/9)
g ( 2006/09/06 11:12:15)
G1.ある卒業生の名言 2006/3
子供の結婚話で家庭内に波風が立つことはよくある。そのような状況で、ある卒業生の言葉:結婚は二人だけの問題じゃなくて、家族みんなのことなので、なかなかスムーズに進みませんね。もしかしたら、人生で一番慎重になるんじゃないかって思う今日この頃です。みんなが真剣に考えてるっていうのは、うれしいことですよ。きっと今は、意見を言う時期なんです。(若いのに、こんなことが言えるなんて、(><。))
G2.農家のおばさんの名言
近代的農作物工場(工場内は温度、湿度、光量はコンピュータ制御、水耕栽培で手は汚れず、腰を曲げることなく収穫可)で働く近所の農家のおばさん(60歳くらい)の言葉:テレビのインタビュアーが”ここはお宅の農業と比べてどうですか?”と聞いた。おばさんの答え”ここもいいけど、家で、とうちゃんと喧嘩しながらやる農業もいいもんだよ”。喧嘩はマイナスイメージでしか捉えていなかったが、コミュニケーションって捉え方もあるんだ、と驚く。(人生の理解の深さに頭がさがる)
G3.NHK俳壇ゲストの名言
夜桜は”ともし火”です、その後ろに暗い闇を背負っている。花も怪しい美しさで、これも一種の”ともし火”です、背景の混乱を隠してしまう(ゲストがここまで言ったかは定かでないが)。とすると、人も”ともし火”かも、誰でも”ともし火”かも、美しい”ともし火”だといいけど。
G4.故(落語)こさん師匠の名言
芸なんてものは若い時の芸が最高で、年寄りの芸は枯れてるなんて言うけれど、あれは本当に枯れちゃってるんだ。ただ、歳をとった人の芸には、その人の人格だけが残るんだ。せこいやつの芸はせこくなり、立派な人の芸は立派になる。何だか自分のことが心配になってきちゃいますね。
G5.誰が言ったか分からない名言
法律は現状(既得権)を守るためにある。法律は作った人が最高権力者である(自分に都合のよいように作るって意味)。社会が成熟すると、貧富の差が固定化するのはこのためである。新興勢力となるには、法律の抜け道を探す、か、まだ法律ができていない分野に進出するしかない。
G6.最近出会った短歌
いまどこに いるのだろうか あの時の 方程式が 解けていたなら(NHK短歌)
(感想)2年間大学受験で落ち続けたものにとって方程式がそのままで直接胸にささる。方程式を愛の方程式とか、人生の方程式って取っても感情移入の起こりやすい歌。
G7.最近出会った短歌
吹く風を 何いとひけむ梅の花 ちりくる時ぞ 香は勝りける(みつね、拾遺和歌集)
(解説)”梅は寒風なんか苦にせず、散る時にこそ強い香を放つ”って歌で、この歌を知る梶原源太景季は源平合戦の際、梅の枝を箙の背(矢ケース)に入れて戦った、と言われる。
G8.最近出会った短歌
姿見に 光あふるる 春の朝 卒業式へ 妻と見送る(NHK短歌)
(感想)卒業式のシーズンなので、心温まる一首を。
G9.現代用語辞典
電車の中で25歳くらいの女性が28歳くらいの女性の先輩と話している。25歳くらいの女性は、”マジスカ”を連発する。質問に来た学生が、”マジスカ”と相槌を打ってくることがある(タリメーヨ、テヤンデーベラボーメ!って感じ)。日本語乱れてる!!。耳慣れない言葉を聞いた場合は学生さんに聞くしかない。教わった言葉を並べてみると:
(1)萌:(秋葉系のものに対して)最高って感じ
(2)なにげに:意外と
(3)きょどる:挙動不審になる
(4)ヒッキー:引きこもり
(5)ウイース:おはようございます
(6)アザース:有難うございます
G10.決断
人生長いことやって来ると、色々な人生を見て来ることになる。その中でステップアップする人を何人か見てきた。彼らに共通する2つのパターンがある。第1のパターンは、決断が早く、決めたら迷わないことである。しかも、決断は、ハイリスクの方を選んでいる。一見泥舟に見えるものに潔く乗り込み必死に漕ぎ出している。岐路に立った時、時間をかけて様子を見、皆が安全と思える時に乗り込む人にはステップアップはなかった。
第2のパターンは、面白がってやる人である。くだらなく思えることを面白がってわき目もふらずやっている人に道が開けるのを何度かみた。くだらなさがよく見えてしまい、のめりこめない人は、いつも口ばかりで何もできなかった。
G11.何のために勉強するのか
1流の人は必要がなくても勉強し、2流の人は必要になった時勉強し、3流の人は必要になっても勉強しない、って話がある。最近アルバイトばかりやっている人が増えているような気がする。大学で勉強する理由は、(1)人生の選択肢が増える(2)チャンスを捕まえる能力を身に着ける(3)チャンスを感知する能力を身に着ける、ということだと思う。
(段々、説教がましくなってきたので、終わりにします)
f ( 2006/09/06 11:11:09)
F1.最近感動したこと 2005.9
a)常磐新線秋葉原駅をホームから上がってくるエレベータの壁には手すりと平行に線が走っている。そのため進行方向を見ていると真上(垂直上方)に昇っている錯覚に陥り、一寸怖くなる。エレベータが最後に水平に移る所ではよろけそうになる。降りる方は試してないが、もしかすると真逆様に落ちていく感じかも。実に奇妙な感覚なので、是非お試しあれ。
b)カンフー
NHK教育テレビ\"おしゃれ工房夏のボディを作るカンフーエクササイズ\"で見せた陳静先生の(横?後?)上方へのキック(正式名は不明)。バランスが全く崩れず、蹴りの方向が非常に高く、信じられない位美しい。インターネットにブルボンの宣伝があるが、ここでは少しぐらつく(http://www.bourbon.co.jp/cm/img/gidr3.mpg)。NHK/DVDカンフーフィットネスでは少しキックの位置が少し低い。番組内での大阪弁の語りも感動的だった。私もカンフーの秘密(?)練習を開始した。
c)超英文法
NHK教育テレビ\"ハートで感じる英文法\"(大西泰斗先生)は、英文法の教科書を書き換えなければいけないほど斬新で面白い。特に最近驚いたのは”英語に過去形は有っても未来形はない”という話。willは未来を表すのではなく、意思とか推測を表すのであって、それがたまたま未来と関連が深いので未来形のように思われているだけ。一寸伝わらないと思うので番組を見るのが一番。大西先生の本も購入したが、やはり生の番組の方が思いが伝わっくる。
d)いってらっしゃい
新京成新鎌ヶ谷駅ホーム売店のおばさんは、お客さんに、実に気持ちよく笑顔で”いってらっしゃい”と言う。言葉では説明できないのだが”こんな風に言ってもらえたら嬉しい”っていう感じの心のこもったトーンである。私は買うものがないので、誰かが買った時に言ってもらう”いってらっしゃい”に癒され励まされて一日が始まる。誰にも気づかれもせず、褒められもせず、路傍を静かに照らしている、灯(ともし)火って感じかな。(2006.3最近、このおばさん、いないみたい)
F2.落語型授業から漫才型授業へ
本HP”授業・ヒューマンインタフェース”のTVMLを見ると画面の2名が掛け合いで講義を進めている。これにより受講者の興味を引続けることに成功している。そういえば、テレビの講座ではしばしばこの形態がとれれている。一方学校の授業を思い起こすと、小学校から大学まで、1人の先生が黒板の前で話し続けている、いわゆる落語型である。今後2人の先生(一方は先生でなくてもよい)が教壇に立っている漫才型授業を積極的に導入する必要があるのではないか。
F3.相対的文化論(ってほどじゃないが)
a)声
以前、西洋人に”時代劇を観ると、侍が腹の底から出したような声で話すが、あれは何ですか?”と聞かれて答えに詰まった。確かに”昔の人はあんなしゃべり方してたのかな?”と思ったことはあるが、深く考えたことはなかった。相当奇妙に思えたらしい。それで言えば、オペラの発声法も奇妙な感じがする。素人考えでは、マイクが無い環境での美しい声の一つのピークなのかもしれないと思ってしまう。オペラを普通の声で歌うバージョンがあっても面白いなと思う。先の西洋人だが”日本の女性のしゃべり方は子供のようで、幼稚に見える”とも言っていた。TVでおなじみの田島先生は”日本の女性は男性に媚るため高い声を出す”と言われていたことがあり符合するかも。
b)不気味
日本人はカッコいいと思う歌舞伎の”見栄”も奇妙かもしれない。私は中国の京劇の”見栄”をみると、違和感があるので、外国人は歌舞伎の”見栄”も変なものに見えると推測される。最近のニューズウイークに”歌舞伎は儀式的なしぐさや物音が多いわりに内容は乏しい”というくだりがあった。チョンマゲも奇妙の代表であろう。私は中国の弁髪を見ると一寸不気味に見えるので、中国人はチョンマゲを見ると不気味に見えるに違いない。ついでに言えば、以前韓国の大統領が民族服で登場する場面を見たことがあり、何か不気味に思えたので、韓国人が小泉首相の羽織袴姿を見ると不気味に思えるに違いない。これが文化ってものかな?
e ( 2006/09/06 11:10:43)
E1.バレーにはワイン 2005/8
生まれて初めてバレー”白鳥の湖”を観た。会場に入った時から男性の少なさに悪い予感がした。予感はすぐ現実となった。男性のタイツ姿とジャンプした時の舞台の音が気になりどうしても物語に入り込めない。何で下半身裸のような格好で出て来なきゃならないんだろう?昔サロンのマダム方がバレーのパトロンだった時があり、受けをねらっているうちにあのようなコスチュームになったのかな、なんて邪推をしているうちに、なんだか男性バレリーナが可哀そうになってきて。一種のセクハラだな、なんて怒りがこみ上げてきた時休み時間に入った。もう飲まずにはいられない、と思いワインを注入して後半に入る。(後半)私の中に突然変化が起こった。舞台はバラ色になり、音楽は体を包み、踊りは自然で芸術的に物語と溶け合う、素晴らしい!!もう物語の中である。アルコールの精だろうか?一瞬にして私がバレーの楽しさを学習したのだろうか?女性は最初からバレーを楽しめるとすると、女性は普段私がアルコールを採ったような感じで世界を認識しているのかな?なんて考えてしまった。
E2.コンピュータ屋
私は電気工学科の出身で、学生時代よく先生が”俺たちは電気屋だ”と言った。学生たちも”電気屋”という言葉が好きで、よく使った。電気屋という言葉には、空論を吐く学者じゃない、電気の理論をマスターした職人だぞ、電気のことなら誰にも負けられないぞ、といった気持ちを喚起する感があり、プロ意識が芽生えるのを感じた。プロ意識がなかなか目覚めない学生さんは、”自分たちはコンピュータ屋なんだ”という自覚を1年生の内から持つようにするとよい。
E3.10倍100倍の法則
学生さんの中にプログラムが得意な人と苦手な人がいる。私はかつて、得意な人は苦手の人の2,3倍の時間をプログラムに費やしているだろうと考えていた。最近学生さんと話していて、得意な人は苦手の人の100倍以上の時間をプログラミングに費やしていることを知った(多分苦手でも得意でもない人は苦手な人の10倍くらい計算機を使っているのだろう)。こんなに差があるのか、とビックリした次第だが、実社会に目を向けると、スポーツ選手や芸能人の年収格差は100万円から億単位まで差がある。100万と1億の差はなんと100倍、丁度プログラムに裂いている時間の比と一致する。団塊の世代の常として貧富の差拡大には抵抗があるが、技術系の収入格差は無さ過ぎるのかもしれない。
E4.人相
長いこと人間をやっていると人相観(み)になるという。私は以前から歴史上の3人の肖像画に関して納得がいかなかった。第1は足利尊氏の馬上の絵である。いくら戦場の絵と言っても幕府を開いた人にしては風格が無さ過ぎる。2番目は源頼朝である。弟に非情な態度を取った人の顔とは思えない。第3は義経の絵である。一見泉谷xxx風で、京都で人気のあったイケメンには見えない。最近の研究で最初の2人(尊氏と頼朝)の絵は人違いだという結論になりつつあるらしい。義経像は疑問のままであるが、これも間違いであるということになるのではないかと、少し自信がでてきている。
E5.座右の銘
最近自分にも座右の銘があることを知った。あまりに身につきすぎていて気づかなかった。それは”考える人になるな”というもので、学生時代に恩師に言われた言葉である。”君らは○○だからいいアイデアなんて頭で考えたって出てきやしない。手足を動かして物を作っていく中で新しいアイデアは生まれるんだ”とのこと。○○を自覚する私は、肝に銘じて手足を動かして実際のものを作るようにしたきた。その精で、学生さんにも物づくりを強いていて、調査研究を卒研にしないようにしている。もちろん、何も考えないで進むのは無謀というものだが。
E6.
テレビ電波の自由化
”ニッポン放送”買収問題のころテレビで、電波(テレビ)は公共のもの、なんて議論があり、テレビ局の人が公器だ、なんて言っているのを聞くと、”マジカヨ!!”って、こちらの言葉までおかしくなってしまった。今日はマスメディアの改革案を挙げてみる。
<テレビ自由化の提案>
現在各テレビ局が行っている事業を以下のように独立させる。
(1)電波時間帯販売会社:番組を視聴者と広告会社の希望を調べて編成する会社
(2)番組制作会社:番組を作って売る会社
(3)取材会社:記事をとって来て売る会社
時間帯販売会社は番組を競争入札にし、誰でも番組の提案や製作を可能にする。取材会社は、取材記事を番組制作会社に売ることもできるし、直接電波時間帯販売会社に売り込むことができる。
(利点1)取材に競争原理が働き、現在の御用記者のような緊張感のなさが改善される。
(利点2)現在はテレビ局に入った一部の人しか番組制作ができないが、誰でもが製作し売り込む機会が与えられる
d ( 2006/09/06 11:10:17)
D1.電車内の高校生 2005/3/1
(1)2人の女子高生の会話
A:”私、国語の成績3なんだ。3って真ん中ってことだよね”
B:”違うよ、5段階評価だから、5を2で割ると2.5でしょ。
2.5が平均だから3は、真ん中より上ってことだよ”
A:”あ、そうか、そうだね”
私も危うく納得しそうになってしまいました。
(2)夜の電車内
座席に座っている男子高校生が、隣の人に覗かれないよう注意しながら、携帯で裸の写真を次々と画面に出して見ています。隣の人には見えないけれど、夜で外が暗いため窓に映り、立っている人達からは丸見えになっています。注意してあげたいけど、それも無理。
D2.プライバシー
プライバシーという言葉が広く使われるようになったのは30年位前からだったように思います。私達は子供の頃、隠し事があってはいけない。裏表があってはいけない、と教えられてきました。そのため、初めてプライバシーという言葉に出会った時、大変な違和感を持ちました。プライバシーって、隠し事じゃないかって。隠し事が公認され、”人に迷惑をかけなきゃ何やったっていいじゃないか”、さらに、”見つからなければ何をやったっていいじゃないか”、”見つかったって白を切ればいいじゃないか”、ってどんどんエスカレートしていってる気がします。
プライバシーも程々にしないと危険なんじゃないかって気がします。
D3.歳をとると、何故、月日の経つのが速いのか
これには色々な説がありますが、最近自らの経験から導き出した新理論を一つ紹介します。それは、”忘れてしまう(忘却)”からです。
歳を取ると忘れっぽくなって、朝起きて、一日を過ごし、夜になった時には、昼間のことを大方忘れてしまい、もー夜だ!となってしまいます。そんな事はない、と思う人は昼食に何を食べたか思い出してみるとよいでしょう。結構思い出せないものです。
食べたことも忘れてしまうようになると、もっと危険ですが。
D4.自分の精か?
最近、”現在の自分を決めているのは9割の努力と1割の運命だ”、と思っている人と、”現在の自分を決めているのは1割の努力と9割の運命だ”と思っている人がいることを知りました。マキュべりは”運命は我々の行為の半分を支配し、他の半分を我々自身にゆだねる”と言ったそうです。”9割の努力と1割の運命”と思っている人は、少し肩の力を抜いた方がよいかもしれません。うまくいかなくても半分は自分の精ではないし、うまくいっても、半分は自分の力ではありませんから驕らず、運命や環境に感謝すべきでしょう。”1割の努力と9割の運命”と思っている人は、もう少し自分の力を信じて努力すると、もっとよい状況が得られるかもしれません。
c ( 2006/09/06 11:09:36)
C1.
心配なマスコミ 2005.2.17
先日、サマーワの自衛隊基地にはマスコミの記者が誰も行っていないことを知りました。どうりでテレビで自衛隊の活動状況が報道さないわけです。アメリカ軍には従軍記者がいて報道を続けています。従軍記者というのも、軍の宣伝になり易く危険だと思っていましたが、誰も従軍しない、というのはもっと危険なことです。サマーワにマスコミが行かない理由は知りませんが、もし、危険だからという理由でマスコミ各社が記者を送っていないのでしたら、恐ろしいことです。良家の子女で高学歴の記者だけ集まっていると、危険を冒して真実を伝えようなんていう気概はなくなるんじゃないかと思います。もし、そんなマスコミだったら平時には立派なことを言いますが、いざとなると簡単に権力側に寝返ってしまいます。私の心配が真実でないことを願っています。
C2.忘れられた後段
最近、”井の中の蛙大海を知らず”に”されど深さを知る”という後段があることを知り一寸嬉しくなりました。あまり嬉しくはなりませんが、”桃栗3年柿8年、には柚子の大馬鹿18年”ってのがあるそうです。
”少年よ大志を抱け”にも次の様な長い後段があります(ネット上で見つけた上手な訳をお借りすると)。
”それは金銭に対してでも、自己の利益に対してでも無く、
また世の人間が名声と呼ぶあの空しいものに対してでもない、
人間が人間として備えていなければならぬあらゆることを
成し遂げるため。少年よ 大志を抱け”
C3.ITは社会を変える?
改革(一寸疲れた感じがある)の大きな要素に、閉鎖からの開放、があると思います。今、日本で最も改革が遅れているのは政治とマスコミという2大権力です。テレビなどは小さな閉鎖的業界が富と特権を独占して、自分たちの盛り上がりと刺激を垂れ流しているように思えます。政治も同様で、これが日本の閉塞感を作ってしまっています。
これを改革できるのはITしかないような気がします。良きにつけ悪きにつけ、ITは世の中の価値観を大きく変えつつあります。政治に関して言えば、数十年後には直接民主制あるいはそれに近いものになるでしょう。今、ホリエモンはマスコミの袋叩きに会っています。今回の騒動は、歴史学的には将来、”既得権益を守ろうとするマスコミと、情報を開放しようというITの最初の衝突”と位置づけられるでしょう。何か新しい社会が生まれる始まりの様な気がします。
b ( 2006/09/06 11:09:05)
B1.モー戦うのやめて!!(2004.9)
人間は犬や猿が予想もしえない思考や判断を行っている。人間の次に世界を支配する知的生物はどんなものか想像するのは面白い。次の生物と人間との違いは、人間と犬との違い位あるとすると、彼らの世界を予想するには荒唐無稽なアイデアでないと当たらない。様々な超能力を並べることはできるが、もしかすると”思い、夢、希望、愛”など、我々人間が考え出したと思っているものこそが真に存在し続けているもので、人間はその一表現形に過ぎない、ということになるかもしれない。そうなると、人間は物しか見えなかった生物として”人間”ではなく”物間”と呼ばれたり、”欲”によって栄え、”欲”によって滅びた、あさましい”欲物”などと呼ばれているかもしれない。
B2.国債を買わない(2004.9)
数年前、金融工学という分野が騒がれたことがある。工学と名がついたので、何となく親しみを感じ勉強したことがある。その時の印象を少々(1)経済成長中の時、株はみんなもうかり、経済下降中にはみんな損をする。(2)もうかると確信できた時に株を買うと必ず損をする。(3)国債を買ってはいけない。理由1:不健全な借金国家経済を助長しないため、理由2:必ず国債は紙くずになるため(多分インフレにより)。
a ( 2006/09/06 11:08:19)
A1.自由の履違え(2004.7)
少し前になるが、”自己責任論”が騒しかった時があった。あの時、国内の論調と、欧米メディアの人達の反応が大きく異なったのが印象的だった。(どうも原因が分かっていないようなので一言、言わせてもらうと)
この感覚の違いの原因は”自由”というものに対する認識の違いからくる。アメリカに行って日本との違いを最も強く感ずるのは”自由”のスケールの大きさである。イメージ的には日本の”自由”の大きさの10倍くらいあり、しかも輝いている。日本ではすぐ”自由には責任が伴う”とか言って、途端に自由が不自由なものになってしまう。日本人は自由な世界にいると思っているが、実は不自由な世界にいることに気づいていない。
早く、世界標準の”自由”が根付くとよいのだが。
A2.柔道の勝者はガッツポーズを取らないで欲しい(2004.7)
柔道で勝った選手が拳を突き上げガッツポーズをとっているのを見ると、悲しくなる、情けなくなる、恥ずかしくなる。元々、柔道では勝った時に相手を思いやりガッツポーズをとらないのが礼儀なのではないかと思う。これは単に思いやるだけでなく、相手に対する尊敬とか試合に対する敬意なんてものが入っているのではなかろうか。
武道の勝負には、単なる勝ち負けだけでなく深い精神性があって欲しい。勝って大喜びしている選手を見ると、何だかあさましい感じがする。特に金メダルを取るような選手は、ガッツポーズなどとらず、日本の深い精神文化を外国に紹介してやって欲しい。”柔闘”ではなく”柔道”なのだから。
A3.女子大生は卒業式に和服(袴)を着ないで欲しい(2004.7)
私は、女性が社会人になった時、男性と同等にやっていけるようにと思い教育をしている。それを知ってか知らずか女子学生はまじめに勉強する人が多い。ところが、卒業式になると、とたんに女性は和服に袴といった、カワイ娘ちゃん路線をとって参列する。隣で男性は現代の戦闘服であるスーツを着て並んでいる。これでは勝負は目に見えている。日本で女性の地位がいつまでたっても向上しないのは、女性自身の意識の低さにある。女性は、おかざりじゃないんだよ、スーツを着て参列しなさい。
A4.女子高生の世直し(2004.7)
数ヶ月前、京成舟橋駅で、ミニスカートの女子高生が27、8歳のサラリーマンのネクタイを馬の手綱のように引っぱって駅事務所につれていくのを目撃した。女子高生もやるもんだな!!
数週間前、東武線の混んだ車内で30歳くらいのバカップルがいちゃついていた。そこに乗り込んできた2人の女子校生は、バカップルを聞こえよがしに口撃しはじめた。”みっともない””いくつだと思ってんだ””女子高生に言われるようじゃ終わりだね”等々、2駅間速射砲のように続いた。さすがにおふたりも気づき、身を正した。すごい。
z ( 2006/09/06 11:04:05)
Z1.正義漢 (2000頃)
津田沼から大学を通るバスには(私的に)名物運転手がいる。空席がある時座らないと”危ないから座るように”としつこく注意する。それでも立ち続けていると急発進急停車を繰り返し倒そうとする。かつて言うことを聞かない女性が乗ってきたときがあり、急発進急停車の繰り返しとなった、女性は意地で平気な顔をしてバランスを取っている。乗客は車を降りると、皆もうむち打ち症状態だった。この運転手は車内での携帯電話にも厳しく、携帯電話を使っている人がいようものなら不要な車内放送を大音響で繰り返し、降車時には皆難聴状態に陥る。私はバスに乗るとき、この運転手と出会うのが楽しみなような怖いような複雑な感じで、いつも名札をチェックしてしまう。
Z2.願わなければ叶わない
スペインのテレビで闘牛士を目指している9歳の女の子がでた。現在女性の闘牛士は認められていない。この子に、インタビュアーが一寸意地悪な”将来闘牛士になれると思いますか?”という質問をした。これに対し女の子は”願わなければ叶いません”と言った。その通りである。ンー、子供に教えられた。