作曲
復習1:ピタゴラスが1オクターブの12キー決めました。
12キーの隣同士は半音(の距離)、2つ隣は全音(の距離)と言います。
復習2:12キーの内、半音の距離はしばしば不協和音となるので、曲を作る時はあまり使いません。過去には色々なキーを使う音階が使われましたが、現在では、曲を作る時は12音の中から7個のキーを使って作るようになってきました。
(理論的には、ドに対する不協和度を調べると、協和するのが{ミ♭、ミ、ファ、ソ、ラ}ということなので、この辺をベースにした7音が使われます。)
7音で最も一般的な音階が長調と短調と呼ばれるものです(半音の位置に注目)。
http://www.aki-f.com/kouza/riron/riron_2.htm
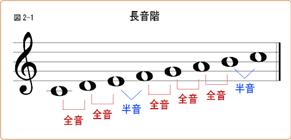
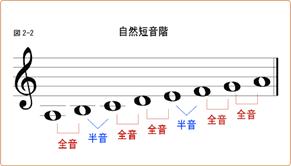
復習3:24の調
ハ長調、二長調、イ短調、等と24の調が、ありますが、これらは主音(一番下の音)の位置の違いです。調は、調号を見れば2つに絞れますが、同じ調号で長調と短調があるので、調号だけでは調は特定できません。例えば、調号のない長調はハ長調で、短調はイ短調です。
復習4:それでは、ハ長調とイ短調は区別が付かないかというとそうではありません。曲の始まりと終わりの小節の音が分かれば分かります。(和音参照)
(1)和音と和声:音階が決まると7つの和音(I〜VII)が決まります。
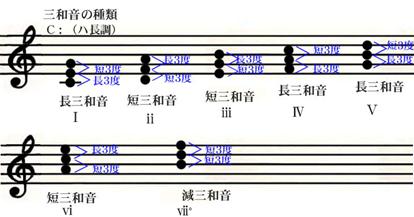
この内、I、IV、Vを主要3和音と言います。
(2)和音の3つの性格
トニック(主格):安定感があり、曲の始めと終わりに使われる。
Iの他III, VI
ドミナント(支配格):トニックに進みたがる。
Vの他III,VII,V7
サブドミナント:上記2つの中間。ドミナントの前に置かれ、終止を準備する。
IIとIV
(3)コード進行規則
Iの次は何でもよい。
IIの次はV。
IVの次にVIはこない。
Vの次はIまたはVI
VIの次にIはこない。
ハ長調では
IがC,
IIがDm
IIIがEm
IVがF
VがG
VIがAm
VIIがBdim
なので、アラビア数字をアルファベットで置き換えると、
Cの次は何でもよい。
Dmの次はG。
Fの次にAmはこない。
Gの次はCまたはAm
Amの次にCはこない。
となります。
(4)その他
リズムは曲全体で同じにする
4/4なら、強、弱、中強、弱と考える
(とりあえず)1小節1和音
各小節のメロディの1/2は、和音(コード)の音を使用
上記、強と中強には和音の音を使う方がよい
最後の小節の音は伸ばす
(課題)さて、ハ長調8小節の曲を作ってみましょう。
Sample4という簡易演奏ソフトを使います。
(付録)
ドレミファソラシド
C D E F G A B C
ハ二ホ ヘ トイロハ
ピアノの音が出せるサイト(1オクターブ):
http://www.ohfuji.ed.jp/e_information/piano.html#
ピアノの音が出せるダウンロードサイト:
http://www.ops.dti.ne.jp/~paopao/MySoft/Cmero/
作曲超入門(小中学生の作曲教室)1:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~p_giro/kids_hushi.htm
作曲超入門(小中学生の作曲教室)2:
http://www.scn1.edu.pref.ibaraki.jp/manande/h17/h17pdf/0504.pdf
コード進行を考えたくない人は、C->F->C->G->C->F->G->Cで作る。
この和音データは、
@CF @T4/4 L4 O3 'CEG'2 R2|'FAO4C'2 R2|O3 'CEG'2 R2|'GBO4D'2 R2|O3 'CEG'2 R2|'FAO4C'2 R2|O3'GBO4D'2 R2|O3 'CEG'2 R2|
(メロディー部を入れないとエラーになるかも)