��������P��@����������
�e�[�}�F�v�Z�@���K���ɂ��鑽����PC���g�����Q�[���܂��̓A�[�g�̐���
�ړI�FJava�ɂ�郁�f�B�A�����l�b�g���[�N�v���O�����̊�{���w�ԁB
�T�u�e�[�}�P�F�l�b�g���[�N�ڑ����ꂽPC�Ԃ̒ʐM���@�i�܂ރ}���`�L���X�g�j���w��
�T�u�e�[�}�Q�F�J�����摜�̏����@���w��
�T�u�e�[�}�R�F�i�K�R�I�ɁjJava�̃L�[�{�[�h���͂ƕ`�揈�����w����Ȃ�
�X�P�W���[���F
(��P��10/24)
�@�EPC�ԒʐM�v���O�������Љ�
�@�E�ȒP�ȃv���O�����̍쐬
�@�@�B����PC��������PC�Ƀf�[�^�𑗂�B��M����PC�̓f�[�^����ʂɕ\��
�@�@�B����PC���畡����PC�Ƀf�[�^�𑗂�B��M����PC�̓f�[�^����ʂɕ\��
�@�@�B��L�Q�����ŁA��M����PC�͎�M�f�[�^�ɉ����ĈقȂ�摜�i�Ԋۓ��j��\��
(��Q��10/31)
�@�E��̋Z�p���g���ă}���`PC�Q�[���A�܂��̓}���`PC�A�[�g�����B
�@�@�i�e���A��i�̒�Ă��A10/24���܂łɌ�����WiKi��Project�ɋL�����Ă������Ɓj
(��R��11/7)
�@�E�J�����摜�����@���Љ�
�@�E�ȒP�ȃv���O�����̍쐬
�@�@�B�J��������̉摜�����U�C�N�\������
�@�@�B�J��������̉摜����ԁA�A�A�炵���������o���A�ԁA�A�ɕς���B
(��S��11/14)
�@�E��R��̋Z�p�𗘗p�������������x�ȃv���O���������B
�@�@�i�Ⴆ�F���������̂��L�����������o����Ƃ��A�F���̐F�Ă�Ƃ��A����������Ƃ��j
�@�@�i�e���A��i�̒�Ă��A11/7���܂łɌ�����WiKi��Project�ɋL�����Ă������Ɓj
(��T��11/21�A�U��11/28)
�@�E��Ŋw�ʐM�ƃJ���������̋Z�p���g�����Q�[���܂��̓A�[�g�̐���
�@�@�i�}���`PC�ʐM�ƃJ�����摜������̂��x�X�g�����A�P�������x������̂ł��悢�B���ɃJ�����̏ꍇ�͕�����PC������މ��p�̕����ʔ����j
�@�@�i�e���A��i�̒�Ă��A11/21���܂łɌ�����WiKi��Project�ɋL�����Ă������Ɓj
�i���P�j ���̐l�̒�ĂɃR�����g�������悤�B��i��Ă̕ύX�͉\�B
�i���Q�j ���{�ꏊ��5�K���E���W�̗\��
�i�P�Q���ȍ~�̃X�P�W���[���͖���j
����Network Program�̂��߂̒m���m�F�@�@�@�@ �@2006/10/24�@furuya
���@�l�b�g�ʐM�ɂ͂o�b����肷��@�g�h�o�A�h���X�h�@�Ɓ@�g�|�[�g�ԍ��h���K�v
�i�{����IP�A�h���X��PC�̒ʐM�{�[�h�̃A�h���X�j
�@�@�@�@�@�@�@�@��w��IP�A�h���X�́A202.16.210.xxx �B
�@�@�@�@�@�@�@�@���������Ŏg�����[�J����IP�A�h���X�́A 192.168.0.xxx �B
�� �l�b�g���[�N�ʐM�`�ԂɁ@�s�b�o�@�Ɓ@�t�c�o�@������B
�s�b�o�F�@���M�Ǝ�M���m�F�����Ȃ���ʐM
�t�c�o�F�@���M����M�����ăf�[�^�𐂂ꗬ��
�� �s�b�o�̒ʐM�`�Ԃ́A�@�N���C�A���g-�T�[�o�����ŒʐM
�� �t�c�o�̒ʐM�`�Ԃɂ́A1�P�ʐM�̃��j�L���X�g�A��1�Α��̃}���`�L���X�g������B
�� �\�P�b�g�F�@Java�ł̒ʐM�v���O�����́APC���m���\�P�b�g�Ƃ����ʐM����ʂ��čs���B
�i���ӁFJava�̃\�P�b�g�̓o�C�i���f�[�^���o�C�g�z��ɓ������f�[�^�������Ƃ肷��ɂȂ��Ă���B���̂��߁A������String �^���𑗂�ɂ̓o�C�g��ւ̕ϊ��͕K�v�ɂȂ�j
�� ����̎����ł́ATCP�̃N���C�A���g-�T�[�o���f���AUDP�̃}���`�L���X�g���g���B
�N���C�A���g-�T�[�o���f���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���`�L���X�g
sender �����̎���
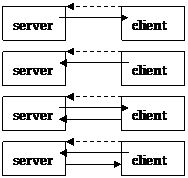
![]()
![]()
![]()
![]() �@�@
�@�@
![]()

�� �����̉ۑ�F�N���C�A���g-�T�[�o�̏�}�̉�3�����쐬�A�}���`�L���X�g�̊m�F
�� �ł����l�́A�f�[�^����M����PC�����j�^��ʏ�ɐԊۂ�`���B����ɂ͏�ō쐬�����v���O�������Ahttp://test1.fry.is.sci.toho-u.ac.jp/lecture/A4.html��F6.java�ɑg�ݍ��߂悢�B
�� ���N���C�A���g�\�T�[�o�v���O����
�i�P�j �T�[�o�v���O����
//NetServerimport java.net.*;import java.io.*;import java.util.Date; public class NetServer{ public static void main(String[] args){String msg; //���M�f�[�^�p�o�b�t�@
ServerSocket servsock;//servsock�I�u�W�F�N�g�̐錾
Socket sock; //sock�I�u�W�F�N�g�̐錾
OutputStream out; //out�I�u�W�F�N�g�̐錾
Date time; try{//�T�[�o�\�P�b�g�쐬
servsock = new ServerSocket(Integer.parseInt(args[0])); while(true){sock = servsock.accept(); //�N���C�A���g�̐ڑ��v���Ď�
out = sock.getOutputStream(); //�o�̓X�g���[���쐬
time = new Date();msg = time.toString() + "\n"; //yyyy-mm-dd �̓��t�ϊ�
for(int i=0;i<msg.length();i++){out.write(msg.charAt(i)); //���M�f�[�^��������
}sock.close(); //�ڑ��I��
}}catch(IOException e){ //�W���G���[�o�͏���
System.err.println("io trouble"); } }}
�i�Q�j�N���C�A���g�v���O����
//NetClientimport java.net.*;import java.io.*; public class NetClient{public static final int Len = 1024;//buf�T�C�Y
public static void main(String[] args){int k; //buf�ɓǂݍ��܂ꂽ�o�C�g�̍��v��
byte[] buf= new byte[Len]; //byte�z��̐錾,�̈�̊m��
//��M�f�[�^�pbuf
InputStream in = null; //input�I�u�W�F�N�g�̐錾,������
Socket socket; //socket�I�u�W�F�N�g�̐錾
try{//�\�P�b�g�쐬
socket = new Socket(args[0],Integer.parseInt(args[1]));//���̓X�g���[���쐬
in = socket.getInputStream();}catch(IOException e){ //�W���G���[�o�͏���
System.err.println("io �G���[");
} while(true){ try{k = in.read(buf); //�ǂݍ����byte�z��buf�Ɋi�[
if(k==-1){in.close(); //�ڑ��I��
break; }System.out.write(buf,0,k);//��M�f�[�^�f�B�X�v���C�o��
}catch(IOException e){ //�W���G���[�o�͏���
System.err.println("io �G���[");
System.exit(1); } } }}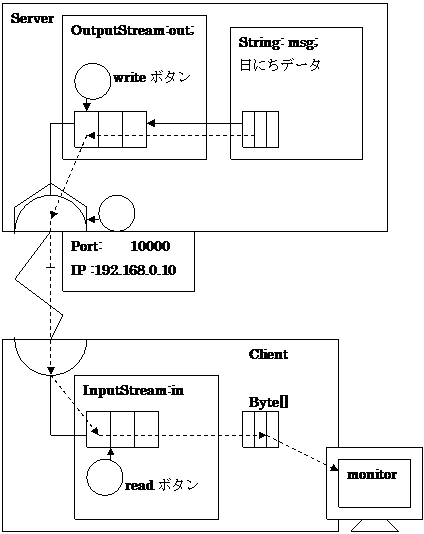
�o�b��IP�A�h���X�ׂ�ɂ́A�R�}���h�v�����v�g��ipconfig ���肪�l�b�g�ɂȂ����Ă��邩�ׂ�ɂ̓R�}���h�v�����v�g�ŁA ping <�����IP�A�h���X>
�����}���`�L���X�g�v���O������
�i�P�j�Z���_�[
/** multicast�Z���_�[
* multicastSender.java* �p�@��@ >java multicastSender 224.0.0.1
*/import java.net.*; class multicastSender{static final int MULTI_PORT = 10000;//�}���`�L���X�g�ڑ��p�|�[�g�ԍ�
static final int BUFSIZE = 1024; //�o�b�t�@�T�C�Y
static String message="Hello, I am a Sender."; public static void main(String[] args) {MulticastSocket sock = null; //�}���`�L���X�g�\�P�b�g
InetAddress ipadr = null; //IP�A�h���X
byte TTL = (byte)1; //TTLbyte[] buf = new byte[BUFSIZE];//���M�o�b�t�@
int len; //buf��
int k; //�o�C�g��
if(args.length != 1){ throw new IllegalArgumentException( "usage: >java multicastServer <IP_Address>"); } try {//IP�A�h���X�ݒ�
ipadr = InetAddress.getByName(args[0]); buf = message.getBytes(); len = buf.length;//�f�[�^�O�����p�P�b�g�ݒ�
DatagramPacket packet = new DatagramPacket( buf,len,ipadr,MULTI_PORT); sock = new MulticastSocket(); sock.setTimeToLive(TTL); sock.joinGroup(ipadr);sock.send(packet); //�f�[�^���M
sock.leaveGroup(ipadr); sock.close(); while(true){ } }catch(java.net.SocketException e){ System.err.println(e); }catch(java.io.IOException e){ System.err.println(e); } }}
�i�Q�j���V�[�o��
/** multicast���V�[�o�[
* multicastReceiver.java* �p�@��@>java multicastReceiver 224.0.0.1
*/import java.net.*; class multicastReceiver{static final int MULTI_PORT = 10000;//�}���`�L���X�g�ڑ��p�|�[�g�ԍ�
static final int BUFSIZE = 1024; //�o�b�t�@�T�C�Y
public static void main(String[] args) {int len; //�f�[�^��
int i; //�L�[�C���o�b�t�@�N���A�C���f�b�N�X
byte[] wbuf = new byte[BUFSIZE];//���[�N�o�b�t�@
MulticastSocket sock = null; //�}���`�L���X�g�\�P�b�g
InetAddress ipadr; //�}���`�L���X�gIP�A�h���X
if(args.length != 1){ throw new IllegalArgumentException( "usage: >java multicastReceiver <IP_Address>"); } try {//�}���`�L���X�g�\�P�b�g�ݒ�
sock = new MulticastSocket(MULTI_PORT);//IP�A�h���X�ݒ�
ipadr = InetAddress.getByName(args[0]); sock.joinGroup(ipadr);byte[] buf = new byte[BUFSIZE];//��M�o�b�t�@
//�f�[�^�O�����p�P�b�g
DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf,buf.length);sock.receive(packet); //�f�[�^��M
String recvdata = new String(packet.getData()); recvdata = recvdata.trim();System.out.println(recvdata);//��ʏo��
sock.leaveGroup(ipadr); sock.close(); while (true) {} }catch(java.io.IOException e){ System.err.println(e); } }}
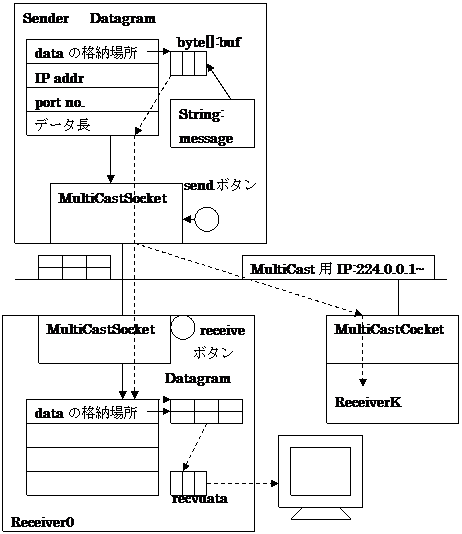
��������Q��������
���Ȋw����II�@ ��Q��@�l�b�g�ʐM����v���O�����̃q���g
�P��ł́A�Q�[������������͓̂�����Ȃ̂ŁA���l���Ă���Q�[���܂��̓A�[�g�̊�{����������Ă݂܂��傤�B
��Q��ڍ�i�̗p���́A(1)��ʂɊG��\���A(2)�l�b�g���[�N�ʐM�A(3)3,4���PC���g�p�B
���̎����Ă����i�C���[�W���`���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA�F����̒�Ă��q���g�ɁA����������l���Ă݂܂����B�Q�l�i���x�j�ɂ������������B
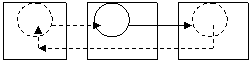 ��P�F�P�̊ۂ�3��̂o�b���
��P�F�P�̊ۂ�3��̂o�b���
���X�ɓ����B�����͂ǂꂩ��PC��
�O�ɂ��āA�ۂ������̏��ɗ�����
�{�^���������B���܂���������F���ς��B
��@�P�i�N���C�A���g�T�[�o�����j�F�o�b���m�ŃN���C�A���g�T�[�o���\�����āA�f�[�^�𑗂�A�ۂ�\������B
��@�Q�i�}���`�L���X�g�����j�F����1��o�b��p�ӂ��A��������}���`�L���X�g�ło�b�ԍ��𑗂�B3��̂o�b�́A�����̔ԍ��������Ă������A�ۂ�`���B
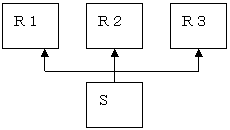 ��Q�F��T���B
��Q�F��T���B
�v���[���͂q�P�`�q�R�̃L�[�������B���
�ꏊ�Ȃ�ۂ��o���B
��@�F�r����P�`�R�̓��̂P�̐���
�q�P�`�q�R�Ƀ}���`�L���X�g����B�����̂o�b
�ԍ���������q����̏ꏊ�B
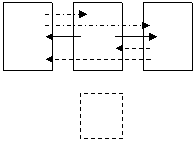 ��R�F�E�}�̎����̂o�b�̃L�[�������ƁA
��R�F�E�}�̎����̂o�b�̃L�[�������ƁA
�ׁi�E�⍶�j�̂o�b��ʂ̐F���ς��B
��@�F�E�̂悤�ɓ_���̂o�b��p�ӂ��A
�L�[�������ꂽ���Ƃ�_���o�b�ɑ���A
�F�ύX���_���o�b����w������ƊȒP�����B
�i���j��̗�ł́g�L�[�������Ɓh�Ƃ����b�ɂ��Ă��܂����A�e�U.java���g���ꍇ�A�}�E�X�Ń{�^�����N���b�N����悤�ɂ��������ȒP�����B
�����摜�\���v���O�����iF6.java�j�Ƃ̓����@
�i��{�I�ɂ͎��͂Œ��킷�邱�ƁB�ǂ����Ă�������Ȃ��ꍇ�ȉ����Q�Ɓj
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java .io.* ;
import java.net.* ;
public class F6 extends Frame implements ActionListener{
int pc= -1;
Point p;
//�又��
public static void main(String args[]){
ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g
Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g
OutputStream out ; // �o�̓X�g���[��
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
int n ;
Frame f=new F6();
f.setTitle("�{�^���N���b�N�����\��");
f.setSize(640,400);
f.setVisible(true);
try{
// �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬
servsock = new ServerSocket( 1001 ) ;
System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t
System.out.println( "�ڑ����t���܂���." ) ;
System.out.print ( "�L�[�{�[�h���當������͂����" ) ;
System.out.println( "�N���C�A���g�֑����܂��D" ) ;
System.out.println( "\"q\"���͂���ƃv���O�����͏I��" ) ;
out = sock.getOutputStream() ;
// ���[�v���ɌJ��Ԃ�
while( true ) {
n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ���
System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\��
out.write( buff, 0, n ) ;
if( buff[0] == (byte)'q' ) break ;
}
sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
//���i�Z�b�g
F6(){
setLayout(new FlowLayout());
Button b0=new Button("000");
Button b1=new Button("111");
Button b2=new Button("222");
b0.addActionListener(this);
b1.addActionListener(this);
b2.addActionListener(this);
add(b0);
add(b1);
add(b2);
p= new Point();
addWindowListener(new WinAdapter());
}
//����
class WinAdapter extends WindowAdapter{
public void windowClosing(WindowEvent we){System.exit(0);}
}
//�`��
public void paint(Graphics g){
String s="hello this is a string";
if(pc==0){
g.drawString(s,100,150);
}
if(pc==1){
g.drawRect(50,50,30,30);
}
if(pc==2){
g.drawOval(p.x,p.y,10,10);
p.move();
}
}
//�C�x���g
public void actionPerformed(ActionEvent ae){
if(ae.getActionCommand()=="000"){
pc=0;
repaint();
}
if(ae.getActionCommand()=="111"){
pc=1;
repaint();
}
if(ae.getActionCommand()=="222"){
pc=2;
repaint();
}
}
//repaint()�ʼn�ʃN�����[���Ȃ��悤�ɂ���ɂ͈ȉ���3�s����
// public void update(Graphics g){
// paint(g);
// }
}
class Point {
int x= 50;
int y= 50;
void move() {
x= x + (int)(Math.random()*10);
}
}
�� ���}���`�L���X�g�̃v���O������
// MSend.java
// �}���`�L���X�g�p�P�b�g���M�v���O�����ł��D
// �L�[�{�[�h���͂��C�}���`�L���X�g�p�P�b�g�֑��M���܂��D
// �g���� java MSend
//
import java.net.*;
public class MSend {
public static void main( String[] arg ) {
byte[] buffer = new byte[1024] ;
final byte TTL = 1 ;
final int PORT = 1002 ;
try{
InetAddress chatGrp =
InetAddress.getByName( "224.0.0.1" ) ;
MulticastSocket mSocket = new MulticastSocket( PORT ) ;
mSocket.joinGroup( chatGrp ) ;
while( true ) {
int n = System.in.read( buffer, 0, buffer.length ) ;
if( n > 0 ) {
DatagramPacket dp =
new DatagramPacket( buffer, n, chatGrp, PORT ) ;
mSocket.send( dp, TTL ) ;
} else break ;
}
} catch ( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
// MRecv.java
// �}���`�L���X�g�p�P�b�g�̎�M�v���O�����ł��D
// ��M�f�[�^����ʂɕ\�����܂��D
// �g���� java MRecv
import java.net.* ;
public class MRecv {
public static void main( String[] arg ) {
byte[] buffer = new byte[1024] ;
final int PORT = 1002 ;
try {
InetAddress chatGrp =
InetAddress.getByName( "224.0.0.1" ) ;
MulticastSocket mSocket = new MulticastSocket( PORT ) ;
mSocket.joinGroup( chatGrp ) ;
while( true ) {
DatagramPacket rPacket =
new DatagramPacket( buffer, buffer.length ) ;
mSocket.receive( rPacket ) ;
if( rPacket.getLength() > 0 ) {
System.out.write( buffer, 0, rPacket.getLength() ) ;
}
}
} catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
�� ���@�O��̉�
// Server1.java// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�ł��D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g�ɑ���D// �g���� java Server1
import java .io.* ;import java.net.* ; public class Server1 { public static void main( String args[] ) { ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g OutputStream out ; // �o�̓X�g���[�� byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�` try{ // �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬 servsock = new ServerSocket( 1001 ) ; System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t out = sock.getOutputStream() ; // ���[�v���ɌJ��Ԃ� while( true ) { int n = System.in.read( buff ) ; // �L�[�{�[�h�ǂݍ��� System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� out.write( buff, 0, n ) ; if( buff[0] == (byte)'q' ) break ; } sock.close() ; } catch( Exception e ) { System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Client1.java// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�f�[�^�����܂�.
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D�i�P��̂o�b�Ŏ��s���邱�Ɓj// �g�p�@ java Client1
import java.io.*;import java.net.* ; public class Client1 { public static void main( String[] args ) { byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�` Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g try{System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂� sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ; // ���͂̃X�g���[������� iStream = sock.getInputStream() ; } catch(Exception e){System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ; } try {System.err.println( "�T�[�o�[����̏���҂��܂�." ) ;
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂� while( true ) { int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ��� if( buff[0] == 'q' ) break ; System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� } sock.close() ; } catch( Exception e ) {System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Server2.java// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�D
// �N���C�A���g���瑗���Ă���f�[�^��\���D// �g���� java Server2
import java .io.* ;import java.net.* ; public class Server2 { public static void main( String args[] ) { ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�` InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g try{ // �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬 servsock = new ServerSocket( 1001 ) ; System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[������� // �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂� while( true ) { int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ��� if( buff[0] == 'q' ) break ; System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� } sock.close() ; } catch( Exception e ) { System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Client2.java// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�L�[�{�[�h���͂��T�[�o�ɑ���.
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D// �� java client2
import java.io.*;import java.net.* ; public class Client2 { public static void main( String[] args ) { byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�` Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[�� try{System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂� sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ; out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[������� } catch(Exception e){System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ; } try {System.err.println( "�T�[�o�[����̏���҂��܂�." ) ;
// ���[�v���ɌJ��Ԃ� while( true ) { int n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ��� System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� out.write( buff, 0, n ) ; //�T�[�o�ɑ��M if( buff[0] == (byte)'q' ) break ; } sock.close() ; } catch( Exception e ) {System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Server3.java// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�D
// �N���C�A���g���瑗���Ă���f�[�^��\�����A���̃f�[�^���T�[�o�ɑ���Ԃ��D// �g���� java Server3
import java .io.* ;import java.net.* ; public class Server3 { public static void main( String args[] ) { ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�` InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[�� try{ // �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬 servsock = new ServerSocket( 1001 ) ; System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[������� out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[������� // �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂� while( true ) { int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ��� out.write( buff, 0, n ) ; //�N���C�A���g�ɕԑ� if( buff[0] == 'q' ) break ; System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� } sock.close() ; } catch( Exception e ) { System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Client3.java// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�L�[�{�[�h���͂��T�[�o�ɑ���A�T�[�o// ���瑗��Ԃ���Ă���f�[�^����ʂɕ\������D (�P��̂o�b�Ŏ��s���邱��)
// ���s�@�@ java Client3
import java.io.*;import java.net.* ; public class Client3 { public static void main( String[] args ) { byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�` byte[] ibuff = new byte[4096] ; // �z��̒�` Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[�� try{System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂� sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ; iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[������� out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[������� } catch(Exception e){System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ; } try { // ���[�v���ɌJ��Ԃ� while( true ) { int n = System.in.read( buff ) ;// �L�[�{�[�h�ǂݍ��� System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� out.write( buff, 0, n ) ; //�T�[�o�ɑ��M int in = iStream.read( ibuff ) ; // �ǂݍ��� System.out.write( ibuff, 0, in ) ; // ��ʂ֕\�� if( buff[0] == (byte)'q' ) break ; } sock.close() ; } catch( Exception e ) {System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Server4.java// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g����D�N���C�A���g���瑗��Ԃ����f�[�^��\���D// �g���� java Server4
import java .io.* ;import java.net.* ; public class Server4 { public static void main( String args[] ) { ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�` byte[] ibuff = new byte[4096] ; // �z��̒�` InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[�� try{ // �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬 servsock = new ServerSocket( 1001 ) ; System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[������� out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[������� // �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂� while( true ) { int n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ��� System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� out.write( buff, 0, n ) ; int in = iStream.read( ibuff ) ; // �ǂݍ��� System.out.write( ibuff, 0, in ) ; // ��ʂ֕\�� if( buff[0] == 'q' ) break ; } sock.close() ; } catch( Exception e ) { System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }} // Client4.java// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�T�[�o���瑗���Ă���f�[�^��// �T�[�o�ɕԑ��D(�P��̂o�b�Ŏ��s���邱��)
// ���s�@�@ java Client4
import java.io.*;import java.net.* ; public class Client4 { public static void main( String[] args ) { byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�` Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[�� try{System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂� sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ; iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[������� int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ��� System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\�� out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[������� out.write( buff, 0, n ) ; } catch(Exception e){System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ; } try { // ���[�v���ɌJ��Ԃ� while( true ) { int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ��� out.write( buff, 0, n ) ; if( buff[0] == (byte)'q' ) break ; } sock.close() ; } catch( Exception e ) {System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ; e.printStackTrace() ; System.exit( 1 ) ; } }}
��������R���@�J�����摜�̏���������
�Q�ƁgJMF�v���O���~���O�K�C�h�hP.59��Fa.java
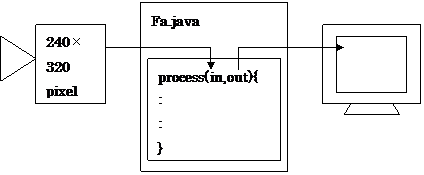 �������炵���v���O�����ł����A�J��������P�t���[���i�P��ʂ̂��ƂŁA�P�b�ԂɂR�O�t���[���ʃJ����������͂����j�����Ă��邲�ƂɁAP.62��process�Ƃ������\�b�h�����s�����B
�������炵���v���O�����ł����A�J��������P�t���[���i�P��ʂ̂��ƂŁA�P�b�ԂɂR�O�t���[���ʃJ����������͂����j�����Ă��邲�ƂɁAP.62��process�Ƃ������\�b�h�����s�����B
�摜�̓������Ɏ��̗l�Ɋi�[����Ă���i�摜�T�C�Y���Q�~�Rpixel�̏ꍇ�j�B
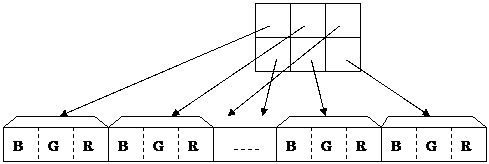 ��ʁi�E�}�̐����`�͂P�s�N�Z���j
��ʁi�E�}�̐����`�͂P�s�N�Z���j
������(inData��outData)
���̐}��R�i�ԁj,G�i�j,B�i�j�́A�W�r�b�g�̃o�C�g�F�̂ɁA��f���~�R�o�C�g�̃������̈悪�K�v�B�i����������ƁA�E�����z��̐擪�����H�j
RGB=0,0,0�����A255,255,255�����A255,0,0���ԁA�����B
�o�C�g�z��ւ̐��l�̑����a[i]=0xff;�Ƃ��Aa[j]=-1;�����255�̂��ƁAa[k]=(byte)5;�Ȃ�ĕ��@�����邩���B
process(in, out)������ƁA���}�̗l�ɓ��͉摜in���o�͉摜out��inData�Ƃ����z����o�R���đ����Ă��܂��B
�����Ă�A�ƌ����Ă����ӂ��K�v�ł��B����́A�z��̑���ł��BJava�ł͔z����I�u�W�F�N�g�Ƃ��Ĉ����܂��i���̂��ߔz��̐�������������������̂��v���o���ĉ������j�B
�I�u�W�F�N�g�̃R�s�[�́A�I�u�W�F�N�g���̂��R�s�[���ĐV�����I�u�W�F�N�g�����̂ł͂Ȃ��A���ʂ̃I�u�W�F�N�g��ʂ̖��ŌĂׂ�悤�ɂ��邾���ł��B�b����Ō����|�C���^�̃R�s�[�ɑ������܂��B
����Ńv���O����������ƁA�v���O�����̍\���͈ȉ��̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B
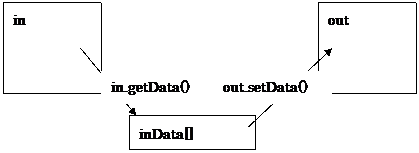
����inData[]�ɏ������摜�����j�^�ɕ\������܂��B
�ۑ�P�F�o�͉摜��Ԑ��������ŕ\�����悤�B
�ۑ�Q�F���E�܂��͏㉺�܂��͍��E�㉺���]�����摜��\�����悤�B
�ۑ�R�F�P�t���[���O�̉摜�Ɣ�r���A�ω��̗L�����Ƃ����Ԃ��h�낤�B
�ۑ�R�̃q���g�F�ߋ��̉摜�����܂��Ă����z���p�ӂ��A����ƌ��摜�̔�r���s���B
�i�z��̒��g��{���ɃR�s�[����ɂ́ASystem.arraycopy���g���ƕ֗��ł��B�Q�ƁF
http://www.javaroad.jp/java_array2.htm�Ȃ��j
System.arraycopy()��5�̈����������A���ꂼ��A���ԂɃ\�[�X�z��A�\�[�X�z��̗v�f�̍����̊J�n�ʒu�A�]����z��A�]����z����̊J�n�ʒu�A�R�s�[�����v�f�̌��ɂȂ�܂��B
�� �ߋ��̉摜�����܂��Ă����z��@�@byte [] oldData = new byte[240*320*3];
�́Aprocess�̊O�i�����゠����ł悢�j�ɒu�����ƁB
��������S���@�J�����f������������
No Idea�ȕ��ւ̍�i��
 �ĂP�F��ʂ��㉺�Q�ɕ������A�������͂P�t��
�ĂP�F��ʂ��㉺�Q�ɕ������A�������͂P�t��
�[���O�i�Â��j�摜��\���B
����ɁA��ʂ��S�ɕ������A���قnjÂ��摜��
�\������悤�ɂ���B
 �ĂQ�F��ʂ��R�ɕ����A�^���i�\�ߎB�e��
�ĂQ�F��ʂ��R�ɕ����A�^���i�\�ߎB�e��
�Ēu�����j�w�i�ɂ���B
����ɁA�����i�w�i�j���߂ɂ���B
 �ĂR�F�{�[�����ォ�������藎���Ă���悤��
�ĂR�F�{�[�����ォ�������藎���Ă���悤��
�`�悷��B
![]() ����ɁA����o���ƒ��˕Ԃ�Ƃ悢�B
����ɁA����o���ƒ��˕Ԃ�Ƃ悢�B
�i�{�[������Ȃ��ĐႪ�~���Ă���悤�ȕ`��ł������������j
�O��̉ۑ�̃q���g
�������������o������@�iprocess�t�߂̂݁j
�P�t���[���O�̃f�[�^��oldData�ɕۑ����A�V�����f�[�^�Ɣ�r�B�F�̕ω��ʂ�c�ɂR���F�̍��̐�Βl�Ƃ��Ď擾�B�ω��̑傫���s�N�Z����Ԃ����Ă���B
byte [] oldData = new byte[240*320*3];//�ߋ��ۑ��p
public int process(Buffer in, Buffer out) {
int i,j,k,l=0,m,a,b,c=0,d=0;
byte [] inData = (byte[]) in.getData();
byte [] outData = new byte[240*320*3];
for(i=0; i<240; i++){
for(j=0; j<320; j++){
c = 0;
for(k=0; k<3; k++){
d = ( i * 320 * 3 ) + ( j * 3 );
a = inData[ d + k ];
b = oldData[ d + k ];
c += Math.abs( a - b );
}
if( c > 400 ){ //�F�ω����傫���s�N�Z����Ԃ�
outData[ d + 0 ] = 0x00;
outData[ d + 1 ] = 0x00;
outData[ d + 2 ] = -1;
}
else{
outData[ d + 0 ] = inData[ d + 0 ] ;
outData[ d + 1 ] = inData[ d + 1 ] ;
outData[ d + 2 ] = inData[ d + 2 ] ;
}
}
}
// �f���ɍ��т�����
// for(int i=8000; i<14000; i++) inData[i]= 0x00;
/* �d�ˏ���---�@
byte[] outData= (byte[]) out.getData();
for(int i=30000; i<40000; i++) outData[i]= 0x00; */
out.setData(outData);
out.setFormat(in.getFormat());
out.setLength(in.getLength());
out.setOffset(in.getOffset());
System.arraycopy(inData,0,oldData,0,320*240*3);
return BUFFER_PROCESSED_OK;
}
��������T���@���܂łɏo��������_������
�P�D�J��������̐F�F���������ς��������
���̃v���O������Fa.java��process()���ł��B�Ԑ������傫��������A�^�Ԃɂ��悤�Ƃ����v���O�����ł����A�ǂ������܂������ĂȂ��悤�ł��B�ǂ�����悢�̂ł��傤���H
byte [] oldData=new byte[240*320*3];
public int process(Buffer in, Buffer out) {
int i,j,k,l;
byte [] inData = (byte[]) in.getData();
byte [] outData=new byte[240*320*3];
i=0;
while(i<230400){
if(inData[i+2]>200)
outData[i+2]=255;
i+=3;
}
out.setData(outData);
System.arraycopy(outData,0,oldData,0,240*320*3);
out.setFormat(in.getFormat());
out.setLength(in.getLength());
out.setOffset(in.getOffset());
return BUFFER_PROCESSED_OK;
}
�Q�D�T�[�o�ɑ����̃N���C�A���g���H�����ꍇ
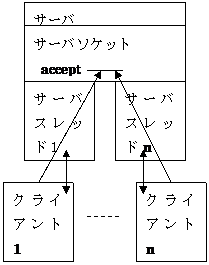 ���̏ꍇ�A�T�[�o�X���b�h��accept��
���̏ꍇ�A�T�[�o�X���b�h��accept��
(1)�N���C�A���g����̐ڑ��v������t���A
(2)�N���C�A���g�̃\�P�b�g���擾���A
(3)�T�[�o�X���b�h�����
(4)�N���C�A���g�ƃT�[�o�ԂŌ�M
�Ƃ����������s���B
���T�[�o��
// McServer.java
// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�N���C�A���g����̃f�[�^��\��
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D
// �� java McServer
import java.net.*;
import java.io.*;
class McServerThread extends Thread {
protected Socket sock;
public McServerThread(Socket s) {
sock = s;
}
public void run() {
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
try {
System.out.println("Connected");
InputStream iStream = sock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[�������
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂�
while( true ) {
int n = iStream.read( buff ) ; // �ǂݍ���
if( buff[0] == 'q' ) break ;
System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\��
}
sock.close();
System.out.println("Connection Closed");
} catch (IOException e) {
System.err.println(e);
}
}
}
public class McServer {
static int port = 10007;
public static void main(String[] args) {
try {
ServerSocket server = new ServerSocket(port);
Socket clientsock = null;
System.out.println("Server Ready");
while(true) {
clientsock = server.accept();
McServerThread t = new McServerThread(clientsock);
t.start();
}
} catch (IOException e) {
System.err.println(e);
}
}
}
���N���C�A���g��
// McClient.java
// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�L�[�{�[�h���͂��T�[�o�ɑ���.
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D
// �� java McClient
import java.io.*;
import java.net.* ;
public class McClient {
public static void main( String[] args ) {
byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�`
Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g
OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[��
try{
System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂�
sock= new Socket( "127.0.0.1", 10007 ) ;
out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[�������
System.err.println( "�T�[�o�֑���f�[�^����͂���" ) ;
// ���[�v���ɌJ��Ԃ�
while( true ) {
int n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ���
System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\��
out.write( buff, 0, n ) ; //�T�[�o�ɑ��M
if( buff[0] == (byte)'q' ) break ;
}
sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
�N���C�A���g���}���`�X���b�h�ɂ��邱�Ƃ��l������B
���̏ꍇ��IP��PORT�̓����N���C�A���g�T�[�o�\�P�b�g���e�X���b�h���ō���Ă����������ȁi������Ă����j
�Q�D�P�̃v���O�����ɃN���C�A���g�ƃT�[�o�̃\�P�b�g��t���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��P�[�X������B�����ł́A�P�̃v���O�������T�[�o�X���b�h�ƃN���C�A���g�X���b�h�������̂������B
�e�v���O�����̓L�[�{�[�h���͂�ɑ���\������B�P�Ȃ鑗��M�Ȃ�P�̃\�P�b�g�ł��ł��邪�A��������K�v������P�[�X������B
���N���C�A���g�T�[�o�P��
// ServerC1Th.java
// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g����D�N���C�A���g���瑗��Ԃ����f�[�^��\���D
// �g���� java ServerC1Th (�ŏ��ɂ�����C1�����s)
import java .io.* ;
import java.net.* ;
public class ServerC1Th {
public static void main( String args[] ) {
ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g
Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[��
try{
// �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬
servsock = new ServerSocket( 1001 ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t
System.out.println( "�N���C�A���g����ڑ�����܂���!" ) ;
out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[�������
ThreadC1 tc1= new ThreadC1();
tc1.start();
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂�
while( true ) {
int n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ���
System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\��
out.write( buff, 0, n ) ;
if( buff[0] == 'q' ) break ;
}
sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
class ThreadC1 extends Thread {
byte[] ibuff = new byte[4096] ; // �z��̒�`
InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g
Socket csock;
public void run(){ //����o�͂��Ȃ�
try{
System.out.println( "�X���b�h�J�n" ) ;
csock= new Socket( "127.0.0.1", 1002 ) ;
iStream = csock.getInputStream() ;// ���̓X�g���[�����
int in = iStream.read( ibuff ) ; // �ǂݍ���
System.out.write( ibuff, 0, in ) ; // ��ʂ֕\��
}
catch( Exception e ){}
}
}
���N���C�A���g�T�[�o�Q��
// ServerC2Th.java
// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1002�Ԃœ��삷��T�[�o�D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g����D�N���C�A���g���瑗��Ԃ����f�[�^��\���D
// �g���� java ServerC2Th�@�i�ŏ���C1�����s�j
import java .io.* ;
import java.net.* ;
public class ServerC2Th {
public static void main( String args[] ) {
ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g
Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
OutputStream out = null ; // �o�̓X�g���[��
try{
ThreadC2 tc2= new ThreadC2();
tc2.start();
// �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬
servsock = new ServerSocket( 1002 ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t
System.out.println( "�N���C�A���g����ڑ�����܂���!" ) ;
out = sock.getOutputStream() ; //�o�̓X�g���[�������
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂�
while( true ) {
int n = System.in.read( buff ) ; // kb�ǂݍ���
System.out.write( buff, 0, n ) ; // ��ʂ֕\��
out.write( buff, 0, n ) ;
if( buff[0] == 'q' ) break ;
}
sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
class ThreadC2 extends Thread {
byte[] ibuff = new byte[4096] ; // �z��̒�`
InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g
Socket csock;
public void run(){ //����o�͂��Ȃ�
try{
System.out.println( "�X���b�h�J�n" ) ;
csock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ;
iStream = csock.getInputStream() ; // ���͂̃X�g���[�������
int in = iStream.read( ibuff ) ; // �ǂݍ���
System.out.write( ibuff, 0, in ) ; // ��ʂ֕\��
}
catch( Exception e ){ System.out.println( "�X���b�h�G���[" ) ;}
}
}
����
�S�D�\�P�b�g�ԒʐM�Ɂi�o�C�g�łȂ��jObjact���g��
�f�[�^���o�C�g�ő���ƁA���l�╶����𑗂�̂Ƀo�C�g�ւ̕ϊ����K�v�Ȃ̂Ŗʓ|�B�����ŁAJava��Object�N���X�𑗂�悤�ɂ�����@���Љ�܂��B�C���[�W�I�ɂ́A����������������ʂ�Object�Ƃ������ɓ���đ��銴���B
/**�i�\���m���FJava��Object�N���X�j
Java�ł̓I�u�W�F�N�g�̒��_��Object�N���X���Ă̂������āA�S�ẴI�u�W�F�N�g�͂��̉��Ɉʒu���Ă��܂��B�ł�����A����int�╶����String��Object�Ƃ��Ĉ������Ƃ��ł��܂�(Object�N���X�ŗp�ӂ���Ă��郁�\�b�h�����p�\�Ƃ����Ӗ�)�B�����ł͐���int�ƕ�����String��Object�ɕϐg��������@�ƁAObject���猳�̐����ƕ�����ɖ߂����@�������܂��B�i�����ƕ�����́A�����������Ⴄ�̂Œ��ӁI���̈Ⴄ���͎��K�j
(i) ����int��Object�ɕϐg��������@�F����int��Object�ł�Integer�ł��B
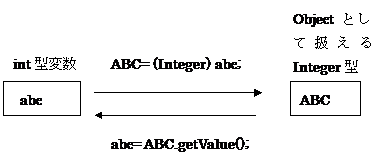
(ii) �@������String��Object�Ƃ��Ďg�����@�F
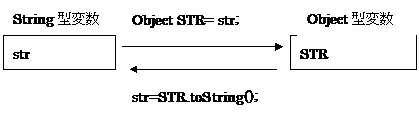
�i��̂Q��ł͂��܂��ܕϐ����ɁAabc,�@ABC�Ƒ啶���A���������g���Ă��܂����Aabc,xyz�Ƃ��S�R�ʂ̕ϐ����ł��܂��܂���j
**/
���āA�\�P�b�g�̓o�C�g�f�[�^�𑗂���̂Ȃ̂ŁAObject�𑗂�ꍇ�ɂ͎�ύX���K�v�ł��B
�o�C�g�ő��鎞�͏o�̓X�g���[�������̂�sock.getOutputStream()�Ƃ��Ă��܂������A
Object�𑗂�ɂ�
ObjectOutputStream os= new ObjectOutputStream(sock.getOutputStream());�Ƃ��܂��B���̓X�g���[���̏ꍇ�����l�ŁAsock.getInputStream()�Ƃ��Ă������̂��A
ObjectInputStream is= new ObjectInputStream( sock.getInputStream()) ;�Ƃ��܂��B
����ł́A�����ƕ������Object�ɂ��đ���N���C�A���g�T�[�o�v���O�����������܂��B
�iA�j ����int��Integer�ɂ��đ���ꍇ
���T�[�o��
// Serveros1.java
// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�ł��D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g�ɑ���D
// �g���� java Serveros1
import java .io.* ;
import java.net.* ;
public class Serveros1 {
public static void main( String args[] ) {
ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g
Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g
OutputStream out ; // �o�̓X�g���[��
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
try{
// �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬
servsock = new ServerSocket( 1001 ) ;
System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t
// out = sock.getOutputStream() ;
ObjectOutputStream os= new ObjectOutputStream(sock.getOutputStream());
// ���[�v���ɌJ��Ԃ�
int n=0;
while( n<2 ) {
Object on= "Hello";
System.out.println( on ) ; // ��ʂ֕\��
os.writeObject( on );
n++;
}
// sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
���N���C�A���g��
// Clientos1.java
// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�f�[�^�����܂�.
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D�i�P��̂o�b�Ŏ��s���邱�Ɓj
// �g�p�@ java Cliento1
import java.io.*;
import java.net.* ;
public class Clientos1 {
public static void main( String[] args ) {
byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�`
Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g
InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g
try{
System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂�
sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ;
}
catch(Exception e){
System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ;
}
try {
System.err.println( "�T�[�o�[����̏���҂��܂�." ) ;
// ���͂̃X�g���[�������
ObjectInputStream is= new ObjectInputStream( sock.getInputStream()) ;
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂�
while( true ) {
Object on= null; // �ǂݍ��݃f�[�^
on= is.readObject();
String n= on.toString();
System.out.println( n ) ; // ��ʂ֕\��
}
// sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
����
�i�a�j������𑗂�v���O����
���T�[�o��
// Serveros1.java
// ���̃v���O�����̓|�[�g�ԍ�1001�Ԃœ��삷��T�[�o�ł��D
// �L�[�{�[�h���͂��N���C�A���g�ɑ���D
// �g���� java Serveros1
import java .io.* ;
import java.net.* ;
public class Serveros1 {
public static void main( String args[] ) {
ServerSocket servsock = null ; // �T�[�o�p�\�P�b�g
Socket sock ; // �\�P�b�g�̓ǂݏ����p�I�u�W�F�N�g
OutputStream out ; // �o�̓X�g���[��
byte[] buff = new byte[1024] ; // �z��̒�`
try{
// �T�[�o�\�P�b�g�̍쐬
servsock = new ServerSocket( 1001 ) ;
System.out.println( "�N���C�A���g����̐ڑ���҂��܂�!" ) ;
sock = servsock.accept() ; //�ڑ���t
// out = sock.getOutputStream() ;
ObjectOutputStream os= new ObjectOutputStream(sock.getOutputStream());
// ���[�v���ɌJ��Ԃ�
int n=0;
while( n<2 ) {
Object on= "Hello";
System.out.println( on ) ; // ��ʂ֕\��
os.writeObject( on );
n++;
}
// sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
���N���C�A���g��
// Clientos1.java
// �l�b�g���[�N��̃T�[�o�ɐڑ����C�f�[�^�����܂�.
// ���̃f�[�^����ʂɕ\�����܂��D�i�P��̂o�b�Ŏ��s���邱�Ɓj
// �g�p�@ java Cliento1
import java.io.*;
import java.net.* ;
public class Clientos1 {
public static void main( String[] args ) {
byte[] buff = new byte[4096] ; // �z��̒�`
Socket sock = null ; // �T�[�o�ڑ��p�\�P�b�g
InputStream iStream = null; // �f�[�^�ǂݎ��p�I�u�W�F�N�g
try{
System.out.println( "�T�[�o�ڑ����܂�!" ) ;
// �\�P�b�g���쐬���܂�
sock= new Socket( "127.0.0.1", 1001 ) ;
catch(Exception e){
System.err.println( "�l�b�g���[�N�G���[!" ) ;
System.exit( 1 ) ;
}
try {
System.err.println( "�T�[�o�[����̏���҂��܂�." ) ;
// ���͂̃X�g���[�������
ObjectInputStream is= new ObjectInputStream( sock.getInputStream()) ;
// �f�[�^�̏I���܂ŁC�ȉ��̃��[�v���J��Ԃ��܂�
while( true ) {
Object on= null; // �ǂݍ��݃f�[�^
on= is.readObject();
String n= on.toString();
System.out.println( n ) ; // ��ʂ֕\��
}
// sock.close() ;
}
catch( Exception e ) {
System.err.println( "�l�b�g���[�N�̃G���[!" ) ;
System.err.print( e ) ;
e.printStackTrace() ;
System.exit( 1 ) ;
}
}
}
����
��������U���@�w�l�k�i��P��ڂɎ������\���ύX�j������
�z�z�����FC Magazine 2001 2�A�hXML�����h
�\���m���FXML��HTML�̐i���`���邢�͔��W�`�ƍl���Ȃ��悤�ɁB
���ȁ[�AXML���Ă��ꂾ�����I��
XML���̂́A����������ł����ł��Ȃ��A�P�Ȃ�g�^�O�h��p�����f�[�^�\���@�ƍl���邱�ƁB
�z�z����Fig.3��XML�����̗�i�A���AFig.3�̐錾���́g���܂��Ȃ��h�ADTD�͕��ʎg��Ȃ��̂Ŗ����j�ŁA�{�̂�Fig.3�́g�����h�Ə����ꂽ�����BFig.3�́g�����h������Ε�����ʂ�A���Ɓ��ŋ��܂ꂽ�i�e��������Ɍ��߂�j�^�O�ƁA�����Ɓ�/���ň͂܂ꂽ�f�[�^�����Ȃ�B����Ε�����Ƃ���A���ꂪXML�����̑S�āB
��XML�̂������Ƃ��끄
�݂�Ȃ�XML��Web�W�������ƔF�߂āA������g���g�d�|���h������Ă��܂����Ƃ���B
��\�I�ȂQ�̎d�|��
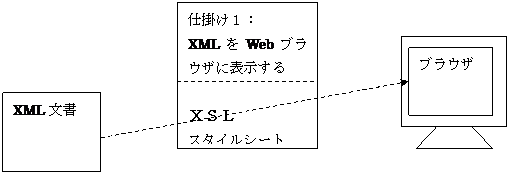 �i1�j�d�|���P�FXML�������u���E�U�ɕ\��������@������XSL�Ƃ����X�^�C���V�[�g�𗘗p�ł���悤�ɂ����B
�i1�j�d�|���P�FXML�������u���E�U�ɕ\��������@������XSL�Ƃ����X�^�C���V�[�g�𗘗p�ł���悤�ɂ����B
������List.4��List.3��XML�������AFig.7�̂悤�ɕ\������X�^�C���V�[�g�ł��B���̂悢�l�Ȃ炱�̂R������ǂ��Ȃ��Ă���̂�������i�����j�B
(2)�d�|���Q�FXML�������i�f�[�^�x�[�X�Ȃǂ́j�f�[�^�Ƃ��āA�v���O�����ŏ�������i��ʂɂ͏������ʂ��u���E�U�ŕ\�����邱�Ƃ������j���߂̊��W�iAPI���ƌĂ��j��p�ӂ����J�����B
�v����Ɋ����g����XML�����̈ꕔ���ȒP�Ɏ��o�����菈�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
���̐}�́A���̗l�q�������Ă���B��̗�Ƃ��ẮA������P.25~26�ł��B�����List7��XML�f�[�^����������Fig.9�̂悤�ɕ\��������̂ŁA�u���E�U�ɕ\������HTML�����iList8�j�̂S�s�ڂ�17�s�ڂ���AJavaScript�v���O����(List9)���Ă�ł���B����List9�̒��ő�R��XML��������g���Ă���B
�i���P�j �v���O���������XML��DOM�Ƃ����I�u�W�F�N�g�Ɓi�ɁH�j���ď������Ă���B
�i���Q�j Java�X�N���v�g�ȊOJava�Ƃ�C++�ł�DOM��������B
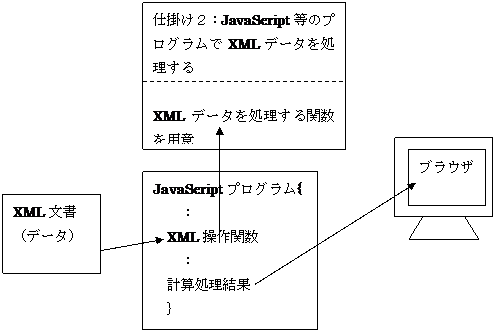
1)List8��17��List9���Ă� 2)List9��19��List7��List8�̃A�C�����h�ɓǂݍ��� 3)List9��36��List8��24(=List7)������
�i��jList7,List8,Fig.9,List9�̊W
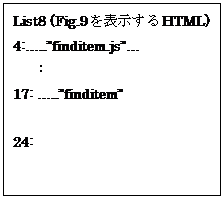
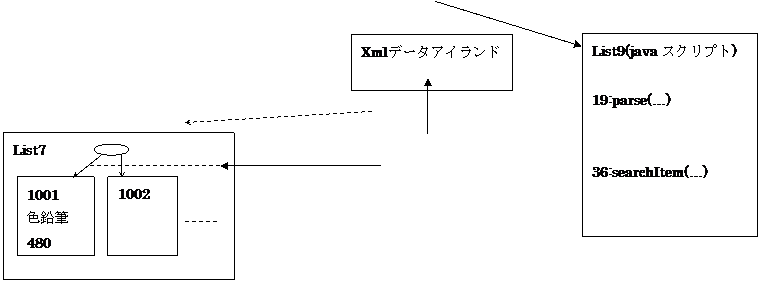
��U��̉ۑ�F�摜���Q�w�肳��Ă���XML�t�@�C��������B�e�摜�͎��̂悤�ɋL�q����Ă���B
<img>
�@<src>test.jpg</src>
�@<alt>�e�X�g</alt>
�@<width>100</width>
�@<height>100</height>
</img>
(1) ���̂Q�̉摜����ׂĕ\������xsl�t�@�C�����쐬���悤�B
(2) �t�@�C��������͂���Ɖ摜���o�͂���javascript���쐬���悤�B
Java�X�N���v�g�̊�{�\���́A�z�z����List9�𗝉����x�[�X�ɂ��邱�ƁB
����V���@Ajax�iAsynchronous JavaScript+HTML�j����@Web2.0�̃C���t���j��
����̘b�́AWeb�T�[�o��ɂ���g���X�ύX�����f�[�^�i�x�[�X�j�h���l�b�g�̃��[�U�ɁA�g�ǂ�����Ē��邩�h���Ęb�B�iHTML�͕\�������Ńf�[�^��~�����Ȃ��̂ŁA�f�[�^��Web�T�[�o��Ƀt�@�C���Ƃ��Ēu���Ă���j�����ŁA����Web�T�[�o��̃t�@�C���𑀍삷��d�g�݂��K�v�ƂȂ�B
�i�d�g�݂P�jCGI—�t�^�`
�i�d�g�݂Q�jPHP—�t�^�`
�i�d�g�݂R�j�`jax—���̉�
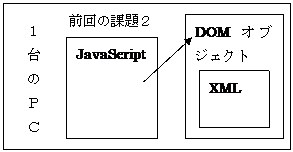 JavaScript��XML�𑀍삷����@��
JavaScript��XML�𑀍삷����@��
�O��w�i���ȁH �ۑ�2�ł��j�B
�v����ɉE�}�̂悤�ɁAXML�f�[�^��
DOM�I�u�W�F�N�g�ɂ��Ă��܂��A
�����JavaScript���瑀�삷��B
���삷��ɂ́AP.28��Table2���g�p�B
���āA�{��Web2.0�쐬�c�[���@Ajax�@�iAjax= JavaScript + XML �j
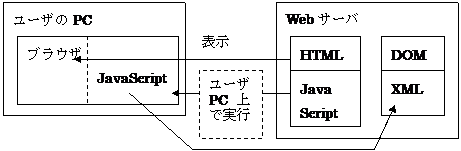
�O��̉ۑ�Q��Ajax�Ƃ̈Ⴂ�́AXML�t�@�C����Web�T�[�o��ɂ�����Ă��ƁB
JavaScript�̓��[�U�u���E�U��Ŏ��s����邽�߃T�[�o�̕��S�����Ȃ��B
�T�[�o�ƃ��[�UPC����������i����Asynchronous�j�ɓ����B
�`��������JavaScript����XML�𑀍삷�������Ă���B
���́A����Ȍ`�ԁiJavaScript�{XML�j�ɂ�����邩�iWeb2.0�̃c�[���ƌĂ�邩�j�B
(1) GoogleMap���n�}�f�[�^��XML�Œ�Ajax�ő���iHP�ɒn�}�荞�߂�j
�i���̏ꍇWeb�T�[�o��Google�̃T�[�o�Ƃ������ƂɂȂ�B�j
(2) Yahoo���l�b�g�����f�[�^�x�[�X��XML�Œ��Ă���̂ŁAHP���璼�ڌ�����
(3) Yahoo��Ajax�p�̐F�X��HP�쐬�c�[������Ă���B
(4) RSS,moo���C�u����,Rico,Scriptaculous(�e��G�t�F�N�g�i�t�F�[�h�Ƃ��j)���g����
�O��̉ۑ�Q�i�Ƃ悭�����ۑ�j�̃T�[�o�g�p�o�[�W����
����figs.html����
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
<title>Sample</title>
<script src="prototype.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
function tryAjax(uri){
target = "disp";
new Ajax.Updater(target, uri, {method: "get"});
}
</script>
<style type="text/css">
#disp{
border: 1px solid #aaa;
width: 250px;
height: 250px;
padding: 5px;
}
</style>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" id="button01" name="button01"
value="No.1" onClick="tryAjax('fig1.xml')">
<input type="button" id="button02" name="button02"
value="No.2" onClick="tryAjax('fig2.xml')">
</form>
<div id="disp"></div>
</body>
</html>
����������������
����fig1.xml����
<div>
<p>figure 1</p>
<img src="fig1.jpg" alt="��">
</div>
����������������
����fig2.xml����
<div>
<p> figure2 </p>
<img src="fig2.jpg" alt="�e���g�E��">
</div>
����������������
��̑��Afig1.jpg��fig2.jpg��p�ӁiANHTTP���f�X�N�g�b�v�Ɋg�����炱���S�ăf�X�N�g�b�v�ɒu���j
����Ƀ��C�u����prototype.js��p�Ӂihttp://prototype.conio.net/��Just the .js, please����_�E�����[�h���Aprototype.js�Ɩ��Â����j
��́Ahttp://localhost/higs.html�Ƃ���悢�B
Ajax�̓T�|�[�g�\�t�g���c��Ȃ̂ŁA�g���l�������ŕ����܂��傤�B�i�c�[����C�u��������R�����ċ��͂����A�܂��݂�ȃo���o���ɊJ������Ă��銴���B���������Ɛ��������͂��j
***�O��̉ۑ�̓���***
�i�ۑ�P�j�n糂���̍�
--XML�t�@�C��--
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="1.xsl" ?>
<image>
<img>
<src>deai.gif</src>
<alt>DEAI</alt>
<width>39</width>
<height>25</height>
</img>
<img>
<src>ringo.gif</src>
<alt>DEAI</alt>
<width>22</width>
<height>24</height>
</img>
</image>
--XSL�t�@�C��—
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl" xml:lang="ja">
<xsl:template match="/">
<HTML lang="ja">
<HEAD>
<title>image</title>
</HEAD>
<body>
<xsl:apply-templates select="//*" />
</body>
</HTML>
</xsl:template>
<xsl:template match="src">
<img>
<xsl:attribute name="src">
<xsl:value-of />
</xsl:attribute>
</img>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
----------------------------------------------------------
�i�ۑ�Q�j
����items.html����
<HTML>�@<HEAD>
<SCRIPT
LANGUAGE="JavaScript" SRC="finditem.js"></SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
Gazo Kensaku
<FORM ID="controls">
number:<INPUT TYPE="TEXT"
NAME="itemId" VALUE="1" SIZE="4">
<INPUT TYPE="BUTTON"
VALUE="push" ONCLICK="finditem(controls,xml)">
</FORM>
<img src="fig0.jpg"
name="ans">
<xml
id="xml"></xml>
</BODY>
</HTML>
����finditem.js����
function
finditem(form, xmldocument){
var fname= "items.xml",
output=
form.output,
itemId=
form.itemId.value;
var document= parse(fname,
xmldocument),
topLevel=
document.documentElement;
searchItem(topLevel, itemId);
}
function
parse(docname, xmldocument){
xmldocument.async= false;
xmldocument.load(docname);
return xmldocument;
}
function
searchItem(node, itemId){
var child, i, text="";
for(i=0; i<2; i++) {
child=
node.childNodes(i);
if(child.childNodes.item(0).text == itemId) {
document.ans.src= child.childNodes.item(1).text;
break;
}
}
}
����items.xml����
<?xml
version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<?xml-stylesheet
type="text/xsl" href="item02.xsl" ?>
<image>
<img>
<num>1</num>
<src>fig1.jpg</src>
</img>
<img>
<num>2</num>
<src>fig2.jpg</src>
</img>
</image>
������������
�t�^�`
![]()
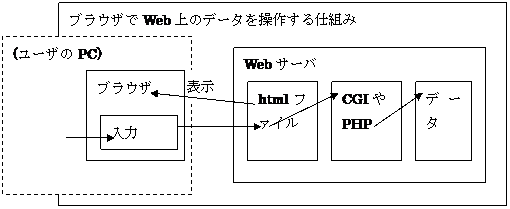
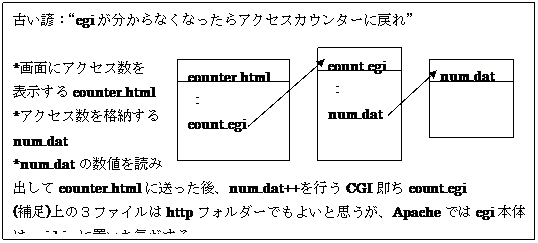
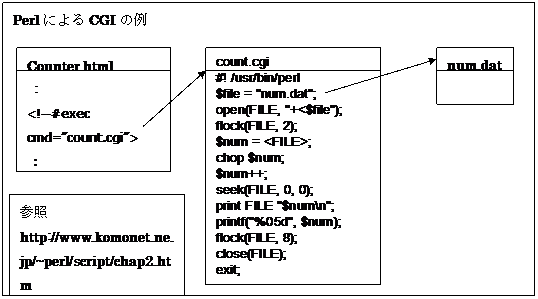
*count.cgi�̂P�s�ڂ�perl�̂��肩
*CGI��perl�łȂ��Ă��悢
�o�g�o�ł́A���̂悤�ɂȂ�i�Q�ƁFhttp://php.s3.to/counter/�j
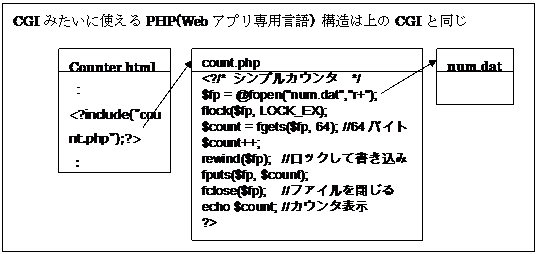
�t�^�a�@�@Web�T�[�o�̏���
�i��P��̎��A�T�[�o�𗧂��グ�܂������A�����͂���Ɠ����ł��BPC��IP�͑�P��Ɠ��������A�|�[�g��80�Ԃ��Ă����j
ANHTTP����Windows�p�ȒPWeb�T�[�o������̂ł�����g�����B
http://www.st.rim.or.jp/~nakata/
�iWeb�T�[�o�Ƃ��Ă͂��̊O�A�ł��m���x�̍���Web�T�[�o��Apache�ABlack Jumbo Dog���Ă̂��L��܂��B�j
�iANTHHP�̎��ȉ𓀌`�����_�E�����[�h���A�f�X�N�g�b�v��Unzip����ƃf�X�N�g�b�v�ɓW�J�����̂ŁA5����3�K�̎����ł́A���̕����悢�����j
��́A�f�X�N�g�b�v��html�t�@�C�������h�d��
http://localhost/�`.html
�Ƃ���Ƃg�o��������B
Perl�̏���
�_�E�����[�h���ăC���X�g�[���APerl\bin�̏ꏊ��CGI�̂P�s�ڂɏ����B
PHP���g�������l
PHP���_�E�����[�h���ăC���X�g�[��
��
ANHTTP��CGI�g����悤�ɂȂ��Ă��邩�m�F
��
ANHTTP��SSI�i�J�E���^�̂悤�Ƀy�[�W�A�N�Z�X���ɓ���j�g�p���m�F�B�܂��Ahtml�t�@�C����shtml�Ƃ��������悢�����B