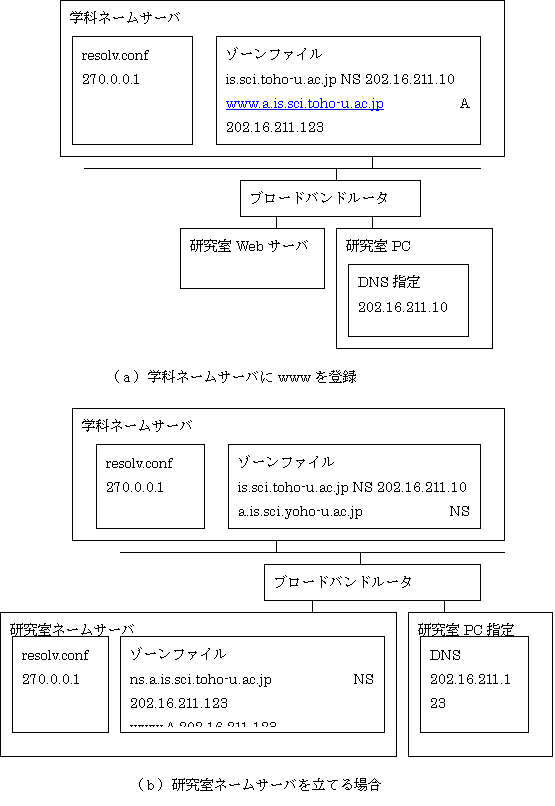���Ȋw����II �@Local Area Network (LAN) �\�z�����}�j���A��
�����ڎ�
Goal �F�N�ł��������̃l�b�g���[�N���\�z�E�Ǘ��ł���悤�ɂ���
�P�� �FLinux�ɂ��Web�T�[�o�̍\�z
Sub-goal �P�D�P �FLinux �T�[�o�̃C���X�g�[���Ƒ���
Sub-goal �P�D�Q �FLinux�@ �̑���Ɋ����
Sub-goal �P�D�R�F�z�[���y�[�W�����
Sub-goal �P�D�S�FWeb�T�[�o�̗����グ�Ɠ���m�F
�Q�� �FIP�A�h���X�ƃl�b�g���[�N�ʐM
Sub-goal �Q�D�P �FIP�A�h���X�̎d�g��m��
Sub-goal �Q�D�Q �FWindows�}�V����Linux�}�V���̃l�b�g���[�N�ʐM�ݒ�@��m��
�Q�D�Q�D�P -- Windows2000�̃l�b�g���[�N�ݒ�A�y�ѐݒ�m�F
�Q�D�Q�D�Q -- Linux�̃l�b�g���[�N�ݒ�A�y�ѐݒ�m�F
Sub-goal�Q�D�R�Fping�ŒʐM������
�R�́@�F�͋[�������l�b�g�̍\�z
Sub-goal �R�D�P �F�u���[�h�o���h���[�^���g���Ė͋[�������l�b�g���[�N���\�z����
�R�D�P�D�P – �u���[�h�o���h���[�^��DHCP�@�\�𗝉����ݒ肷��
�R�D�P�D�Q -- �͋[�w��Home Page��IP�A�h���X���g���Ė͋[������PC����{������
Sub-goal �R�D�Q �F���z�T�[�o�̐ݒ�Ɗm�F
�S�́@�F�l�[���T�[�o�̐ݒ�
Sub-goal �S�D�P �FDomain Name System (DNS)�ƃl�[���T�[�o�̎d�g��m��
Sub-goal �S�D�Q �F�w�Ȃ�HP�ɖ��O�Łihttp://www.is.sci.toho-u.ac.jp/index.html�j�A�N�Z�X���Ă݂�B�m�F�FDNS��202.16.211.10�Ɍ����Ă��ˁA���ꂪvenus�Ȃi�{���̊w�Ȃ�venus��202.16.210.28�����ǁj�j�B
Sub-boal �S�D�R �F�w�Ȃ̃]�[���t�@�C�������������āA�O�����猤������www�ɃA�N�Z�X�ł���悤�ɂ��悤�B
Sub-goal �S�D�S �F�����̌������h���C���Ƀl�[���T�[�o�𗧂ĂĂ݂�
�inslookup���߂ŁADNS�����܂������Ă��邩�m�F���悤�j
�ȏ�A�ȒP�ł��傤����ŁA�݂�Ȃ���l�O�ł��B
�P�́@Linux�ɂ��Web�T�[�o�̍\�z
�P�D�P�@Linux�T�[�o�̃C���X�g�[��
LinuxOS���C���X�g�[������ہA�C���X�g�[����̎g�����ɑ������C���X�g�[�����\�ł���i�f�X�N�g�b�v�p�\�R���b���[�N�X�e�[�V�����b�T�[�o�j�B�ǂ̕����ŃC���X�g�[�����Ă��A��ő��̌`�Ԃɍč\���\�ł��邪�A�T�[�o�ɂ���ƌ��܂��Ă���T�[�o�Ŏn�߂悤�B
�i�P�j Linux�̓�����CD��CD�h���C�u�ɓ���ēd��������
�i�Q�j RedHat�C���X�g�[����ʂŁgENTER�h�L�[������
�i�R�j Welcome To Red Hat��ʂŁA�hNEXT�h�L�[������
�i�S�j ����Japanese�A�L�[�{�[�hJapanese�A�}�E�X�i�{�^����/PS2�j�A�Ɛi��
�i�T�j ���V�KRedHat Linux �C���X�g�[����I��
�i�U�j �C���X�g�[���^�C�v�Ł��T�[�o��I��
�i�V�j �����p�[�e�B�V�����A�S�Ẵp�[�e�B�V�����폜�A���̌�A�\���̂܂܂Ői��
�i�W�j �l�b�g���[�N�����̂܂�DHCP
�i�X�j �t�@�C�A�E�H�[���ݒ��DHCP��WWW�͒ʉ߂���悤�Ƀ`�F�b�N������
�i�P�O�j�ǂ�ǂ�i��
�i�P�P�jroot�̃p�X���[�h�ݒ�ijikken2�j
�i�P�Q�j�p�b�P�[�W�I��
X Window�AGNOME�A�G�f�B�^�A�O���t�B�J���C���^�[�l�b�g�A�e�L�X�g�x�[�X�̃C���^�[�l�b�g�A�T�[�o�ݒ�c�[���AWeb�Z�[�o�AWindows�t�@�C���T�[�o�i������ʂ�����Mozilla���C���X�g�[������Ȃ������C������j�ADNS�T�[�o�A��I���B
�i�P�R�jCD�������A�w���ʂ�ǂ�ǂ�i�ށi�b�c�Q�C�b�c�R���w���ʂ�}���j
�i�P�S�j�u�[�g�f�B�X�N�́g���Ȃ��h
�i�P�T�j���X�i��
����ŏI���
�i�����I�Ɂj�ċN��
�i�P�j ���[�U�o�^
�i�Q�j �V�X�e���o�^�͂��Ȃ�
�i�R�j�����A�����i�ނƁA�Z�b�g�A�b�v�I��
�P�D�Q�@Linux����}�j���A���iWindows�Ƃ̈Ⴂ�j
Linux�̃��[�U�C���^�t�F�[�X��GNOME�i�O�m�����̓m�[���j�ƌĂ�AWindows�Ǝ��Ă���B
Windows�Ƃ̑Ή��ƍ���
�i�P�j Web�u���E�U��Mozilla�ƌ����A�n���}�[�N�����P��N���b�N����ƊJ���i��W�N���b�N�j�B
�i�Q�j Windows�̃R�}���h�v�����v�g�iDOS���j�ɑ�������̂́A�g�V�X�e���c�[�����^�[�~�i���h�ł���B
�i�T�[�o�̗����グ�Ȃǂł́AOS�̐ݒ�t�@�C����������ꍇ�������̂ŁAroot�ɓ����čs���̂��\�ł����A���S�̂��߁A�ł��邾���A���ʂ̃��[�U�Ń��O�C�����A%su -�@�Ń��[�g�Ɉړ����č�Ƃ����悤�j
�i�R�j �e�c�A�b�c�́A�}�E���g�Ƃ���������s��Ȃ��Ǝg���Ȃ��B�}�E���g������s���ƁA�e�c�Ƃb�c�}�[�N����ʍ���Ɍ���A�h���b�O���h���b�v���\�ɂȂ�B
�i�t���b�s�[���}�E���g����ɂ́A�g�V�X�e���c�[�����f�B�X�N�Ǘ��h�Ń}�E���g�A�A���}�E���g����B�I���ӁI�A���}�E���g���Ă���e�c�����o���Ȃ��ƃV�X�e�����ςɂȂ�j
�i�S�j �t�@�C���̃O���t�B�b�N����iWindows�̃t�H���_�j�́A��ʍ���̃z�[���i�Ɓj�}�[�N���v�N���b�N����ƃE�C���h�E������A�g�ړ��h���Ƀf�B���N�g�����������ƃt�@�C���ނ��\�������B�\�������t�@�C���A�C�R�����h���b�O���h���b�v�ł���B
�i�T�j Windows�̃R���g���[���p�l���ɑ���������͖̂����A�ݒ�̓��C�����j���[����s���B
�i�U�j �e�L�X�g�G�f�B�^�́i�C���X�g�[�����ɃG�f�B�^�w�肵���jgedit���g�����B���{��ϊ���Windows�ƈꐡ�������̂́A�p��Ɠ��{�ꃂ�[�h�ؑւ́g���p/�S�p�L�[�h�ł͂Ȃ��A�g�V�t�g���X�y�[�X�A�L�[�h�ł��B
�P�D�R�@ �z�[���y�[�W�̍쐬
�z�[���y�[�W��/var/www/http/�̉��Ɂ@index.html�Ƃ����t�@�C��������邱�ƂɂȂ��Ă���B
�i���i�z�[���y�[�W������Ƃ��@http://yahoo.co.jp/�@�ȂǂƂ�邪�A���͍Ō�́@/�@�̌��index.html�@���ȗ�����Ă���j
��
su –
��root�ɓ���A�ȒP�Ȃg�o������Ă݂悤�B�ł��ȒP�Ȃ��̂́A
<HTML>
<BODY>
This is my Home Page.
</BODY>
</HTML>
�ł��B
�^�[�~�i���E�C���h�E�ŁA�쐬����index.html�̃t�@�C������������i# ls -al�@�R�}���h�j�ƁA
index.html�͓ǂݏo���֎~�ɂȂ��Ă���̂�chmod�œǂݏo���\�ɂ���B
# ls –al�@�ƑłƁA
-rw --- --- 1 root index.html
�Ƃ����s���\�������B�Ō��---�͈�ʃ��[�U���Aindex.html�������݂��A�Ǐo�����A���s���A�ł��Ȃ����Ƃ������Ă���B�z�[���y�[�W�����Ă��炤�ɂ͓ǂݏo���\ r-- �ɕύX����K�v������B�t�@�C���̑����ύX�R�}���h��chmod�Ȃ̂ŁA
# chmod 604 index.html �Ƒł�
�m�F�����F�E�G�u�T�[�o��HTTP���t�����˂Ȃ�Ȃ��B���j���[�̃Z�L�����e�B�[��HTTP���t���\���m�F���Ă������B
�P�D�S Web�T�[�o�̗����グ
�����\���m���F�h�T�[�o�𗧂��グ��h�@�Ƃ́���
�悻�̂g�o�����Ă��鎞�́A�悻�̃R���s���[�^��ł̓E�G�u�T�[�o�������Ă���B�T�[�o�𗧂Ă�ɂ͇@�ݒ�t�@�C����p�ӂ��A�A�f�[�����ƌĂ��T�[�o�v���O�����𑖂点�Ă��K�v������B�ݒ�t�@�C���̓T�[�o���ƂɈقȂ邽�߁A�ʑΉ��ƂȂ邪�A�f�[�����̑��点���͋��ʓ_�������B�T�[�o�v���O�����̃v���O�������͍Ō��d�i�f�[�����Ɉ���Łj���t���Ă���B�Ⴆ�A�E�G�u�T�[�o�̃v���O��������httpd�ł���A�l�[���T�[�o�iDNS�j�̃v���O��������named�ł���B
�v���O�����̑��点���ɂ͎��̂Q������
�i�P�jGNOME�̏ꍇ�F�h�V�X�e���ݒ聄�T�[�o���T�[�r�X�h�Ƃ��ǂ��āA�T�[�o�ꗗ�\���o���A�������T�[�o�����n�C���C�g����ƁA���̎��s���\�������B�������N���b�N����ƋN���A���~�I���ł���B
�i�Q�j�^�[�~�i������̃e�L�X�g���͂̏ꍇ�F���ʃT�[�o�v���O������/var/rc.d/init.d�@�̉��ɂ���A�N������ꍇ�� #
httpd start �Ƃ��A#
named start�@�ƂȂ�B
�T�[�o�v���O�������Q�Ƃ���g�ݒ�t�@�C���h�̐ݒ�@���Q����B
�i�P�jGNOME��ʂ���ݒ�c�[���̏�������čs���F�ȒP�ł��邪�A����ȃP�[�X�ɑΉ��ł��Ȃ��B
�i�Q�j�e�L�X�g�G�f�B�^�Őݒ�t�@�C�����쐬����F������A����ȃP�[�X�ɑΉ��ł���B
�`�D�E�G�u�T�[�o�iapache�j�F�ݒ���͏��Ȃ����A�ݒ�c�[�����g���̂��]�܂����B
�a�D�l�[���T�[�o�ibind�j�F���Ȋw����II�ł́A�u���[�h�o���h���[�^�̉��Ƀl�[���T�[�o��u���̂ŁA��������ł���A�ݒ�c�[�����g���Ȃ��B�����ŁA�G�f�B�^�ō쐬����B
�����\���m���I��聁��
�E�G�u�T�[�o�̐ݒ�F
�h�V�X�e���ݒ聄�T�[�o��HTTP�h�@�Őݒ���J�n�B�ݒ�̍ہA�Ӑ}�I�ɏ������ނ̂͂P��T�[�o�������A��͂��̂܂܂ł悢�B
�T�[�o���F�@�Ⴆ�Aa�������Ȃ�@www.a.is.sci.toho-u.ac.jp �Ƃ���B
�E�G�u�T�[�o�̓���m�F�F
�E�G�u�u���E�U�𗧂��グ�Ahttp://127.0.0.1/ ���{�����悤�Bindex.html ������A���ꂪ�A
�Ȃ���� Test Page ���\�������B
�T�[�o�������Ă��邩�̊m�F�́A�^�[�~�i������A
���@ps aux | grep httpd �@�@�ƑłB
�����̂��߂ɁF�@���������̂g�o�����ɂ́H
Linux�Ƀ��[�U�o�^����ƁA/home�̉��Ƀ��[�U���̃f�B���N�g���i�t�H���_�[�j���ł���i/home/���[�U���j�B���̒���public_html�Ƃ����f�B���N�g�������A���̒���index.html�Ƃ����z�[���y�[�W�t�@�C��������ĊO������ϑ��ihttp:/�T�[�o�[��/~���[�U��/�j�B
�Q�D�l�b�g���[�N�ʐM
�Q�D�P �h�o�A�h���X
�v�Z�@���ʐM����(�Ⴆ��HP������)�ꍇ�́A����̌v�Z�@��IP�A�h���X�Ƃ������E�Ɉ�����Ȃ��ԍ��i�d�b�ԍ��ɑΉ�����j�Ŏ��ʂ���BIP�A�h���X�͂R�Q�r�b�g�ŁA���̔ԍ��͐��E�I�ɊǗ�����Ă���B�R�Q�r�b�g�ł͐��\���̐��܂ł���킹��A���Ȃ킿���E���ɐ��\���ȉ��̌v�Z�@�����Ȃ���A���ׂĂ̌v�Z�@��IP�A�h���X��U�邱�Ƃ��ł���B�e���ɂ͘A������IP�A�h���X�����蓖�Ă��A���̒��ł́A���̈ꕔ���w���ЂȂǂ̑g�D�Ɋ��蓖�Ă�B����ɁA��w�ł͊e�������ɂ��̈ꕔ���^����A�Ⴆ�A���Ȃ̂e��������������Ă���IP�A�h���X��202.16.211.112-137�i�P�U�j�ł���B
�h���C���F
��X�̏Z���́A���{�A��t���A�D���s�A�Ƃ������h���C���̊K�w�\���ŕ\�����BIP�A�h���X���A����Ɏ����h���C���\���ɂȂ��Ă��܂��B�Ⴆ�A�{�wF��������www�v�Z�@�́Awww.fry.is.sci.toho-u.ac.jp�ŁA���{jp�A��wac�A���M��wtoho-u�A���w��sci�A����is�A�ÒJ��fry�Ƃ������h���C���\���ɂȂ��Ă��܂��B
���M��w���������IP�S�͓̂��M��w�̃h���C���A�e����������������P�U�͂e�������̃h���C���ƌĂ�A���ꂼ��P�O���[�v���`�����Ă���B�e�������̃h���C���̃l�b�g���[�N��}�ŕ`���ƈ�{�̒ʐM���ɃR���s���[�^���R�l�N�^�łȂ������`�����Ă���B
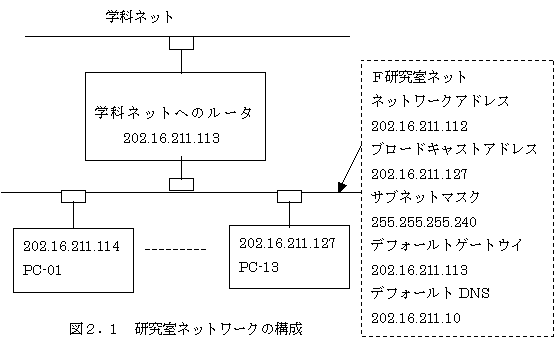
�e�������ł́AIP���P�U������Ă���ƌ����ƁA�e�������̐��ɂP�U���PC��ڑ��ł���悤�Ɏv�����A���͂P�R�䂵���Ȃ��Ȃ��B�P�U��IP�̂����ŏ��̔ԍ��i��̗�ł�112�j�̓l�b�g���[�N�A�h���X�ƌĂ�A�g���Ă͂����Ȃ��B�܂��A�Ō�̔ԍ��i��̗�ł�127�j�̓u���[�h�L���X�g�A�h���X�ƌĂ�Ďg���Ȃ��B�����P�f�t�H�[���g�Q�[�g�E�G�C�ƌ����Ďg���Ȃ����̂�����B
���������̌v�Z�@�͒��ڐ��łȂ����Ă���g���ԁi����h���C���j�h�Ȃ̂ŁA���ڌ�M���ł���B����ɑ��A�����������w�O�̌v�Z�@�ƌ�M���悤�Ƃ���ƁA���[�^��ʂ��ăp�P�b�g���O���֑���o���˂Ȃ�Ȃ��B��M�悪�����������O���ʂ���̂ɃT�u�l�b�g�}�X�N���g���A�O���Ƃ̌�M�̏ꍇ�̃f�[�^�i�p�P�b�g�j���t�悪 �f�t�H�[���g�Q�[�g�E�G�C�ł���B
�T�u�l�b�g�}�X�N�F
�ePC�͑��̌v�Z�@�ƌ�M���悤�Ƃ��鎞�A�悸�A��M�悪�����������ۂ��̔��f���s���A���肪�������������Ȃ璼�ڌ�M���͂��߁A�������O���Ƃ̌�M�̏ꍇ�f�t�H�[���g�Q�[�g�E�G�C�Ƀp�P�b�g�𑗏o���B���̓������O�����̔��f�ɃT�u�l�b�g�}�X�N���g����B�ePC�͎�����IP��m���Ă���̂ŁA������IP �ƁA�T�u�l�b�g�}�X�N��AND���Ƃ������̂��A��M��IP �ƃT�u�l�b�g�}�X�N��AND����������̂������ꍇ�����������Ɣ��f����B
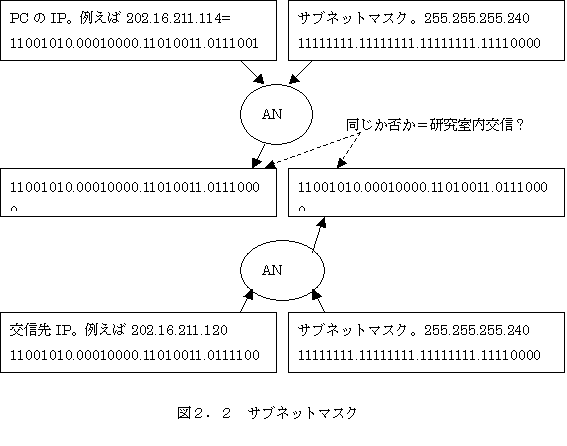
�T�u�l�b�g�}�X�N�͂P�{�̐��ɂȂ��钇�ԁi�h���C���j��PC�𑼂̃h���C����PC�Ƌ�ʂ��邽�߂̂��̂ł���B�T�u�l�b�g�}�X�N�Ƃ����Ɠ�������邪�A�ʂ̌�����������A�g�A������IP�Q�w��h�A�Ƃ��g����IP���ʕ��h�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�e�������ł����ƃT�u�l�b�g�}�X�N��
255.255.255.240�@=�@11111111.111111111.11111111.11110000
�ł���B������IP �̓��A�T�u�l�b�g�}�X�N�̏�ʂ́g�P�h�ɑΉ����镔���͑�w���番���^����ꂽ���̂ŁA���ʂ��h�O�h�̕����ɑΉ����镔�����A�������Ŏ��R�Ɏg���镔���ł��邱�Ƃ������Ă���B�����ƕ�����₷�����t�ł����ƁA���������g����P�U��IP�̓l�b�g���[�N�A�h���X����n�܂�P�U�A�����A
202.16.211.112����202.16.211.137�ł��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�Q�D�Q �FWindows�}�V����Linux�}�V���̃l�b�g���[�N�ʐM�ݒ�@
�e�o�b�̃l�b�g���[�N�ݒ�͎��̂S���ڂł���
�i�P�jIP�A�h���X
�i�Q�j�T�u�l�b�g�}�X�N
�i�R�j�f�t�H�[���g�Q�[�g�E�G�C
�i�S�j�f�t�H�[���gDNS�i�ڂ����͂S�͎Q�Ɓj
(1)IP�A�h���X�FIP�A�h���X�̌��ߕ��͂Q����B���́A�ݒ莞�_�Ɍ��߂Ă��܂��h�A�h���X�Œ�h�ł���A������͏�ʃu���[�h�o���h���[�^�Ɍ��߂Ă��炤�h�����ݒ�iDHCP�j�h�����ł���B����̎����ł͂܂��A�A�h���X�Œ�𗘗p���A���Ɏ����ݒ�����݂�B
(2)�T�u�l�b�g�}�X�N�FIP�A�h���X����������������Ŏ����I�Ɍ��܂�B
(3)�f�t�H�[���g�Q�[�g�E�G�C�FIP�A�h���X�����炤���A�w�肳���B
(4)�f�t�H�[���gDNS�FIP�@�A�h���X�ł͂Ȃ��A�v�Z�@���Ō�M���鎞�̓d�b�ԍ��ē��}�V��
�Q�D�Q�D�P�@ Windows2000�̏ꍇ
�}�C�l�b�g���[�N��
�Q�D�Q�D�Q�@ Linux�X�̏ꍇ
�Q�D�R�@ ping �ŒʐM
�����̃l�b�g���[�N�͎��̐}�̗l�ɂȂ��Ă���B�W���́i�X�C�b�`���O�j�n�u���Q�J�X�P�[�h�ڑ�����Ă���i�P�S���X�C�b�`���O�n�u�Ɠ������Ɓj�B�n�u�͒P�ɒʐM���ƍl����悢�B�����Ɋw�ȃT�[�ovenus������A����ɂ�202.16.211.10�Ƃ���IP �A�h���X���U���Ă���B�͋[��������IP�A�h���X�͐}�Q�D�S�̂悤�Ɋ��蓖�Ă�B
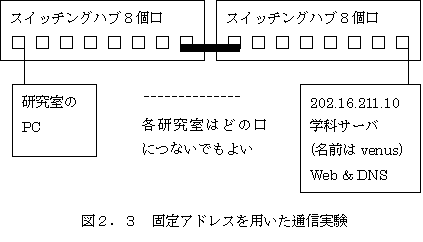
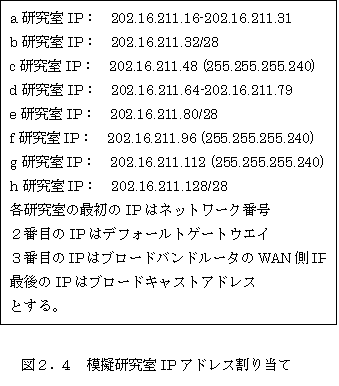
�e�������̂Q��̃}�V���ɁA�Q�D�Q�߂Ɏ������Œ�A�h���X�w���p���ăl�b�g���[�N�ʐM�ݒ���s���A�X�C�b�`���O�n�u�ɂȂ���Venus�ƒʐM�ł��邩�m�F���悤�B
IP�A�h���X�������Ă�����̓��m���ʐM�ł��邩�ǂ����̊m�F�ɂ́Aping�R�}���h���g����B(Windows�̏ꍇ)�R�}���h�v�����v�g�A(Linux�̏ꍇ)�^�[�~�i������Aping �R�}���h��ł��Ă݂�B
���@ping 202.16.211.10
����ŁA�Ԏ�������ΒʐM�ł��Ă��邱�ƂɂȂ�B
�i���F�u���[�h�o���h���[�^�̓f�t�H�[���g�ŕԎ���Ԃ��Ȃ��̂Œ��Ӂj
�R�D�u���[�h�o���h���[�^���g�����͋[�������l�b�g���[�N�̍\�z
�R�D�P �������l�b�g���[�N�Ɩ͋[�������l�b�g���[�N
�}�R�D�P�͌��݂̏��Ȃ̃l�b�g���[�N�\���ł��B�w�Ȃ�L3�X�C�b�`����ʐM�����������̕ǃR�l�N�^�ɐL�тĂ���i�}�R�D�P�Q�Ɓj�B�������ł͕ǃR�l�N�^�ɉ��������Ȃ��A�����Ƀu���[�h�o���h���[�^��PC��ڑ��ł���B�������̐��i�}�R�D�P�̑����j�ɂ͂P�U��IP�A�h���X���^�����Ă���B�S�͂Ŏ������ʂ�A�P�U�̂h�o�̓��A�l�b�g�A�h���X�A�u���[�h�L���X�g�A�h���X�A�����ă��[�^�Ɍv�R��IP���g����̂ŁA�������Ő^�Ɏg����IP�͂P�R�ł��B�������̐���L3�X�C�b�`���Ń��[�^�ɐڑ�����Ă��āA���̌������Ɗu������Ă���B
�����ō\�z����͋[�l�b�g���[�N�͐}�R�D�Q�̂悤�ɁAL3�X�C�b�`�̑���Ɂi�X�C�b�`���O�j�n�u��p���Ă���B�n�u�͒P�Ȃ�ʐM�d���ƍl����悢�B���̂��߁A�������P�U��IP�Ƃ���������V�~�����[�g�ł��Ȃ����A�قƂ�ǂ͎��l�b�g���[�N�ƈ�v���Ă���B
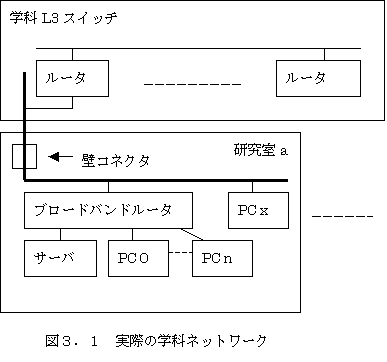
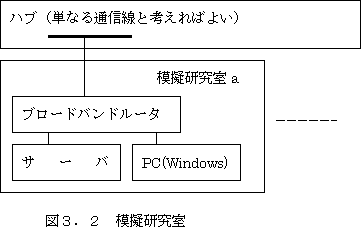
�\���m���F�u���[�h�o���h���[�^
�ŋ߁A�ƒ�łk�`�m��g�ސl�������u���[�h�o���h���[�^�����y���Ă����B�g�����́A�}�̂悤�ɁA�v���o�C�_����̒ʐM���Ƀu���[�h�o���h���[�^���Ȃ��A���̉��ɕ����̂o�b���Ȃ��B�v���o�C�_������炤�����̃O���[�o��IP�̓u���[�h�o���h���[�^������ɐU��APC�ɂ͉ƒ���i�u���[�h�o���h���[�^�̉��j�����Œʗp���郍�[�J���h�o��U��B����ƁA�ƒ���̂o�b���m�͒��ڌ�M�ł��鑼�A�o�b�̓C���^�[�l�b�g�ɂȂ������v�Z�@�ɃA�N�Z�X�ł���悤�ɂȂ�B�A���A�C���^�[�l�b�g���̌v�Z�@����ƒ���̂o�b�͌����Ȃ��i�O���[�o���h�o�������Ă��Ȃ����߁j���߁A�����I�ɂ̓C���^�[�l�b�g������u���[�h�o���h���[�^�̉��̂o�b�ɃA�N�Z�X�ł��Ȃ��B�������A�ŋ߂͌l�p�̃E�G�u�T�[�o��u���ăz�[���y�[�W�����J�������l�����������߁A�E�G�u�T�[�o�Ȃǂ̓���ȃT�[�o�@�\�����[�J��IP��U�����o�b�ɍ\�z���A������O���Ɍ��J����@�\���p�ӂ����悤�ɂȂ��Ă����B���̋@�\�͉��z�T�[�o�A���邢�̓|�[�g�t�H���[�h�ƌĂ��B
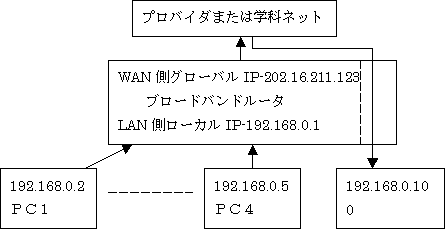
�u���[�h�o���h���[�^�̋@�\�F
�u���[�h�o���h���[�^�̋@�\������Ǝ��̂Q�ɂȂ�B
�i�P�j�h�o�}�X�J���[�h�F�u���[�h�o���h���[�^�̂k�`�m���ɐڑ����ꂽ�o�b�Ƀ��[�J���h�o��U��iDHCP�@�\�j�Ƌ��ɁA�����̂o�b���C���^�[�l�b�g��̌v�Z�@�ɃA�N�Z�X�ł���悤�ɂ���iNAT��NAPT�@�\�j�BDHCP�ło�b�ɂh�o��U��ꍇ�A�o�b���̃l�b�g���[�N�ݒ�ł́h�h�o�͎����擾�h�ɂ���B�܂��A�����擾��IP�����炤�ꍇ�A�h�o�͓d������ꂽ���ɐU���Ă����̂ŁA�o�b�̂h�o�͏�ɌŒ�ł͂Ȃ��Ȃ�B
�i�Q�j���z�T�[�o�i�ÓI�}�X�J���[�h�Ƃ��|�[�g�t�H���[�h�Ƃ��Ă��j�F���[�J���h�o��U����PC�ɃT�[�o�𗧂āA���̃T�[�o�@�\�Ɍ����āA�C���^�[�l�b�g�����痘�p�ł���悤�ɂ���B��̓I�ɂ̓C���^�[�l�b�g��̌v�Z�@�̓u���[�h�o���h���[�^���T�[�o�Ǝv���āi�u���[�h�o���h���[�^�̃O���[�o��IP�ɃT�[�r�X�v���������j�A�N�Z�X���A�u���[�h�o���h���[�^�����̗v�����T�[�o�Ɏn���B�i���̎��A�T�[�o�ɂ͌Œ�̃��[�J���h�o��U���Ă����j
�u���[�h�o���h���[�^�̐ݒ�@
step1:�u���[�h�o���h���[�^��LAN���ɂ����o�b���gIP �����ݒ�iDHCP�̂��Ɓj�h�ɂ��A
step2:Web�u���E�U�ŁgHTTP://192.168.0.1�h�Ɠ��͂���B
����ɂ��ݒ��ʂ������̂ŁAWAN���ALAN���̐ݒ蓙���s���B
3.1.1 – �u���[�h�o���h���[�^��DHCP�@�\�𗝉����ݒ肷��
��̎����ł́A�o�b�ɒ��ځA�Œ�̃O���[�o��IP��U���ĒʐM�������s�����B�����ł́A�u���[�h�o���h���[�^��WAN���ɂ͌Œ�O���[�o��IP��U��ALAN����PC��Ip �A�h���X�̓u���[�h�o���h���[�^��DHCP�@�\�Ŏ����I�ɐU��B
�e�������ɂ͂P�U�̃O���[�o��IP�����蓖�Ă�A�}�ɂ͊e��������IP�͈́i�h���C���j��F�X�ȕ\�L�@�Ŏ����Ă���B
�e�������́A�}�𗝉����A�u���[�h�o���h���[�^�Ƃo�b�̐ݒ���s���Aipcongig,/sbin/ifconfig�Őݒ���m�F���Avenus�ɑ���ping���o���ĒʐM�����܂������Ă��邩�����m���߂悤�B
DHCP�̐ݒ�ł́A�����PC�ɂǂ�Ȑ�����U�邩���߂�B
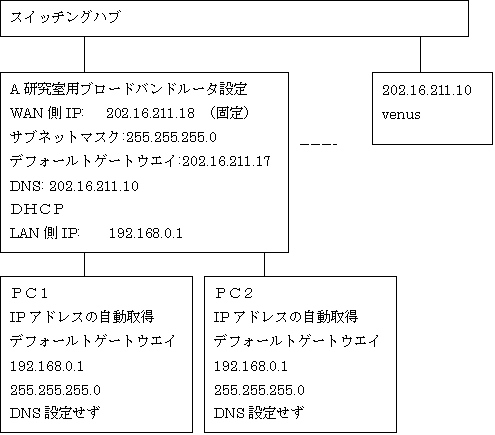
3.1.2 �@PC����venus�̃z�[���y�[�W�ɃA�N�Z�X���Ă݂悤
�E�G�u�u���E�U��http://202.16.211.10�Ɠ��͂��A�z�[���y�[�W�������邩�m�F
/*** tric ***/
�`���b�g�g���b�N
�{���̊w�ȃl�b�g�Ɩ͋[�w�ȃl�b�g�̓`���b�g�Ⴂ�܂��B�ǂ̐��͏�̕����痈�Ă���̂ʼn��ƂȂ��}�̂悤�Ɍv�Z�@�̌��̂悤�Ɋ����邪�A���ۂ͉����P�[�u���̌��ƍl����Ƃ悢�B�����A���̉��̕��ɂ͂P�䃋�[�^���Ȃ����Ă���B
�}�ŕ`���ƁA�A�̂悤�ɂȂ�B��̓I�ɂ͕ǂ̃R�l�N�^�Ƀn�u��ڑ����A�P�R��̂o�b�C���邢�͂a�a�q�������ɂȂ��Ƃ��ł���B�����Ȃ�ƁA�n�u�ɂȂ���o�b�܂��͂a�a�q�̃T�u�l�b�g�}�X�N��255.255.255.240�ł��邱�Ƃ͂���������B�������̂܂܂̌`��͋[�����Ŏ������悤�Ƃ���ƁA�������a�a�q�̏�ɁE�����P�i���[�^��u���K�v������B����̎����́A�������ȗ������A�}�̂悤�Ɍ������̂a�a�q���w�ȃn�u�ɂȂ��ł���B��������ƁA�e���������قȂ�h���C���Ƃ��Ĉ����Ȃ��Ȃ�A�w�Ȃ̑S�h�o�������h���C���ɂȂ�B
���̂��߁A�a�a�q�̃T�u�l�b�g�A�h���X��255.255.255.0�ƂȂ�B�ݒ�ł͈ꉞ�A���ۂ̊w�Ȑݒ�ɍ��킹�A�f�t�H�[���ƃQ�[�g�E�G�C��p�ӂ��Ă��邪�A���ۂɂ͎g���Ă��Ȃ��B
�i���̘b��������A�����Z�~�v���j
�܂Ƃ߂�ƁA�{���̌������ł��́A�a�a�q�̃T�u�l�b�g�}�X�N��255.255.255.240�ɂ��Ă��������A�Ƃ������ƁB
/*** trick end ***/
3.2 ���z�T�[�o
���z�T�[�o�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g���̌v�Z�@�Ƀu���[�h�o���h���[�^���T�[�o�ł��邩�̂悤�Ɍ���������@�\�ł���B��̓I�ɂ̓u���[�h�o���h���[�^��LAN��PC�i�Œ�̃��[�J��IP���U���Ă���j�ɁA�T�[�o�𗧂ĂĂ����āA�O������u���[�h�o���h���[�^�ɗ����A�N�Z�X�v�����T�[�o�ɗ����Ă��@�\�ł���B
���̐ݒ�́g���x�Ȑݒ�h�����z�T�[�o�@�Őݒ��ʂɐi�ށB
�E�G�u�T�[�o�����J���������́AHTTP��I��ʼn��z�T�[�o�ɒlj�����B
���z�T�[�o�̊m�F�́A���������܂��́A�w�ȃT�[�o����z�[���y�[�W�����Ă��炤�A�����Ȃ��B
�S�D�c�m�r�ƃl�[���T�[�o
�����\���m���F�ǂ�����Ėڎw���v�Z�@��T���̂�����
�C���^�[�l�b�g�ɂ̓h���C�����ƂɃl�[���T�[�o�����݂��A���E���̃l�[���T�[�o���A�g���ăh���C������IP�A�h���X��Ή�������DNS(Domain
Name System)���\������i�l�[���T�[�o��DNS�T�[�o�Ƃ��Ă��j�B�ŏ�ʂ̃l�[���T�[�o�́u���[�g�T�[�o�v�ƌĂ�A�S���E��13��z�u����Ă���B�e�l�[���T�[�o�͎������Ǘ�����l�b�g���[�N�ɐڑ����ꂽ�R���s���[�^�̃h���C������IP�A�h���X�̑Ή��\�������Ă���A�h���C�����A�O����̖₢���킹�ɓ�����Bwww.is.sci.toho-u.ac.jp�Ƃ����h���C�������������R���s���[�^��IP�A�h���X��T���ꍇ�A�܂������̃h���C���̃l�[���T�[�o�ɖ₢���킹�A�����ɂȂ�����[�g�T�[�o�ɖ₢���킹��B���[�g�T�[�o�� jp�h���C���S�̂��Ǘ�����l�[���T�[�o�̃A�h���X����̂ŁA���� jp �h���C���̃l�[���T�[�o�ɖ₢���킹�𑗂�Bjp �h���C�����Ǘ�����l�[���T�[�o�́A����� ac �h���C���̃l�[���T�[�o�̃A�h���X���A ac �h���C���̃l�[���T�[�o��
toho-u �h���C���̃l�[���T�[�o���A toho-u �h���C���l�[���T�[�o�� www �Ƃ����R���s���[�^��IP�A�h���X������B
����
�S�D�P�@DNS�ƃl�[���T�[�o�̎d�g��
���܂ŁAping��z�[���y�[�W������Ƃ��A�h�o�A�h���X���g���Ă��܂������A����Ȑ����o�����܂���B�����ŁA�d�b�ԍ��ē��i�l�[���T�[�o�j�̓o��ł��B�ǂ����Ƀl�[���T�[�o�𗧂āA�o�b�ݒ莞�ɂc�m�r�̂��肩���h�o�ŋ�������ł����A�v�Z�@���𖼑O�Ŏw�肵�Ă��A�n�r�����O����h�o�ׁA�A�N�Z�X���Ă����B
����
ping�@venus.is.sci.toho-u.ac.jp�@�Ƒł��Ă݂悤�B�a�a�q�̂c�m�r��202.16.211.10�ɂȂ��Ă���A�Ԏ����Ԃ��Ă���ł��傤�B
4.2 �F�w�Ȃ̃]�[���t�@�C�������������āA�O�����猤������www�ɃA�N�Z�X�ł���悤�ɂ��悤�B
�l�[���T�[�o�𗧂Ă�ɂ́A�i�Œ�j���̂R�̐ݒ�t�@�C�����K�v�ł��i�}�S�D�P�Q�Ɓj�B
�@/etc/named.conf
�A/var/�]�[���t�@�C��
�B/etc/resolv.conf
�l�[���T�[�o�ɂ͂Q�̎d��������܂��B���̎d���͌v�Z�@������h�o�����Ƃł���i�@�A���g�p�j�A��Q�̎d���́A���O�ϊ��Ɏ��ǂ̌v�Z�@�ׂɂ䂭���ł��i�B���g�p�j�B
(i)���O����h�o�����߂�F���̎d���ɂ�named.config�ƁA�ϊ��e�[�u���ł��鐳���������i�]�[���t�@�C���j���g����Bnamed.conf�͐������t�@�C���̂��肩�ƁA�t�@�C�����������܂��B�����̓]�[���t�@�C���ƌĂ�܂��B
�C���X�g�[���̍�DNS���w�肵�Ă����ƁA�A�A�A���p�ӂ����̂ŁA�A�A�A����������������悢�B
�����A�A�A�A��
www.a.is.sci.toho-u.ac
202.16.211....�Ə����Ă����ƃz�[���y�[�W���݂�̂ɁA
http://www.a.sci.toho-u.ac.jp�@�Ƃ����L�����g����B
�i���F�c�m�r�̐ݒ�́A��x�c�m�r���~�߂čĎ��s���Ȃ��ƗF�D�ɂȂ�Ȃ��B�j
(ii)�l�[���T�[�o�̂��肩��T��
resolv.conf�͂ǂ�Linux�}�V���ɂ�����A�g�p����i�ԍ��ē��j�l�[���T�[�o���w�肵�܂��B�l�[���T�[�o�̏ꍇ�A��{�͎������g�Ȃ̂ŁA�A�A�A�Ƃ���B
����
�w�Ȃ̃l�[���T�[�o�ɁA�������̃E�G�u�T�[�o��o�^���悤�i�}�S�D�Q(a)�Q�Ɓj�B
�O������E�G�u�T�[�o�����w�肵�ăz�[���y�[�W������ɂ̓]�[���t�@�C���Ɍ������E�G�u�T�[�o����IP�̑Ή����������߂悢�B�]�[���t�@�C���Ɍ������E�G�u�T�[�o��o�^���āA�O������Q�Ƃ��Ă݂悤�B
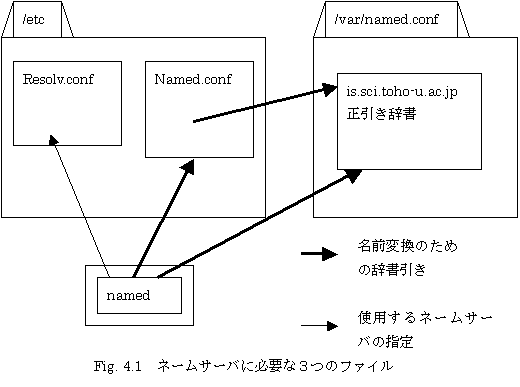
�S�D�R�@�������̃l�[���T�[�o�����
�O�߂ł͈ꉞ�A�T�[�o�𖼑O�ŃA�N�Z�X�ł���悤�ɂȂ�܂������A�����̃T�[�o�����J���悤�Ƃ���ƁA�S�Ċw�Ȃ̃l�[���T�[�o�ɓo�^����K�v������A�w�Ȃ̃l�[���T�[�o���Ǘ�����l�͑�ςł��B�����ŁA���ʂ͌������Ƀl�[���T�[�o�����āA�w�ȃT�[�o�ɂ͌������l�[���T�[�o�݂̂�o�^���܂��B���������̌v�Z�@�̖��O�͌������T�[�o�ɔC������B
�}�S�D�Q�@�l�[���T�[�o�̐ݒ�