ネット市の電気紙芝居
この市では図書館(ウエブサーバー)の本を家から見ることができます。図書閲覧者はPCに(窓口番号/図書館名/書名)を入力すると、本の目次ページが画面に表示されます。図書館には色々なサービスがあるため、サービス窓口番号を指定するする必要があります。ホームページを見るサービス窓口はhttp(80)です。PCに映し出されるページは一見、図書館から本のページがそのまま送られてきていると思いがちだが、実は図書館の読書係りが本を読み上げ、その声がPCのブラウザ君が大急ぎで画面に絵を描いて、本のページが送られてきたように見せかけています(図1)。
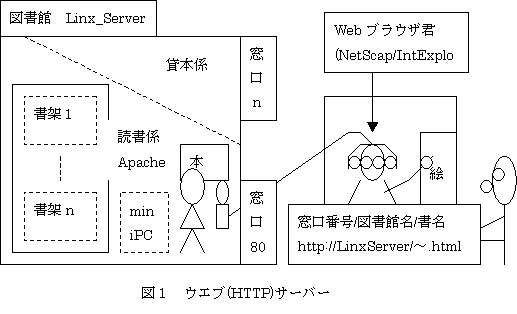
ホームページ閲覧サービスを行うソフトウエアとしてはLINUXにAPATCHというものが付いてきますが、自分の好みに合わせてホームページ閲覧サービスをデザインできます。これがウエブサーバの設定と言われるものです。
主な設計ポイントは以下の通りです。
(1) 基本的には書架は1つとなっているが、複数の書架を用意するか否かの選択。研究室で各学生がHPを作る時に必要になります。
(2) 本の中には難しい英語の単語(プログラム実行要求:CGI)を使う人もます。この行が出てくると読み上げ係りはminiPCを走らせて翻訳し分かり易い言葉に換えてから閲覧者に伝えます。このminiPCを装備するか否かの選択。
(注)アパッチには1台の計算機中に複数の仮想的サーバを用意することができ、これを仮想サーバと呼ぶ。ブロードバンドルーターの仮想サーバと別物なので注意。
設定レベル1:何も設定しない場合。
/var/www/html に、index.htmlというホームページファイルを作って、外部から観測。
設定レベル2:Linuxにユーザ登録すると、/homeの下にユーザ名のディレクトリ(フォルダー)ができる(/home/ユーザ名)。その中にpublic_htmlというディレクトリを作り、その中にindex.htmlというホームページファイルを作って外部から観測(http:/サーバー名/~ユーザ名)。
(自分で観測)外からHPを見なくても、サーバー上で観測できます。
http://127.0.0.1 と入力してみましょう。
設定レベル3:興味のある人はCGIを使えるようにしてみよう。
サーバの立上げ
Step1: PCにLinuxのCDをセットし再起動
赤帽男のセットアップ開始画面になるàNext
Step2:言語選択画面でJapanese選択à次へ
Step3:キーボード選択でJapaneese選択à次へ
Step4:マウス選択では自動検出マウスがハイライトされるので、確認しà次へ
Step5:インストールの種類(パーソナルデスクトップ、ワークステーション、など)選択
どれを選んでもよい(参考書でもバラバラ)が“サーバ”でいこうà次へ
Step6-1:ディスクパーティションでは“自動”に、おまかせà次へ
もし警告が出たら “はい”をクリック
Step6-2:既存パーティションの削除を聞いてくるので、
(新規インストールの場合)“削除” à次へ
削除の再確認がくるので、“はい” à次へ、…パーティション結果が表示される
Step7:ブートローダー設定はデフォールト(GRUB)のまま。パスワードも設定せずà次へ
Step8-1:ネットワーク設定:サーバなのでIPアドレスを固定(DHCPを使わない)にし、
“起動時にアクティブ”にする。
IPアドレスは、192.168.1.1 にしましょう。(たいした根拠はありません。202系のグローバルIPを割り当てることもできますが、ここではローカルIPとポートフォワードの組み合わせでいくことにします。また、192.168.1.xにしたのは、192.168.0.xをPCに割り当てたので、セキュリティ上別の方がよいかな、という程度のものです)
サブネットアドレスは、255.255.255.0にします(254台のサーバが使えるかも)。
Step8-2:ゲートウエイは学科ネットへの出口ですので、ブロードバンドルーターの裏口番地となります。
Step8-3:DNSのIPアドレスは、情報科DNSのアドレスに合わせ、 202.16.210.18とします。à次へ
Step9:ファイアウオールは、ブロードバンドルータで作るので、設定しなくてよい
Srep10:追加言語、“なし” à次へ
Step11:タイムゾーンに“東京”選択à次へ
Step12:rootパスワードを適当にきめるà次へ
Step13:パッケージグループ選択
<デスクトップ>では、Window System, GNOME
<アプリケーション>では、エディタ、グラフィカルインターネット、テキストベースのインターネット、Office/生産性、グラフィックス、
<サーバ>では、サーバ設定ツール、Webサーバ
を選びます。à次へ
以上で、インストールの準備完了
これよりインストールà次へ
Step14: à次へà次へà…ディスクの交換…次へà次へ
Step15:ブートディスク作成“せず”。à次へ
おめでとう、インストール完了!!!!!!
Step1:再起動すると、GRUBが動き出しRedHatを選択(これしかない)するとRedHatLinux
が動き出し、
Step2: login画面になる
Linuxの真のディレクトリ構造(apacheを中心に見ると)
/
/bin
/boot
/etc/rc.d/initd/httpd:apacheスクリプト
/etc/httpd/conf/httpd.conf:メイン設定ファイル
/etc/usr/sbin/httpd:httpd本体
/etc/hosts:サーバ名
/home/irhan
/var/www/html/index.html:HP用
/var/cgi-bin
ウエブサーバを通して見た仮想的ディレクトリ
/index.html
/cgi-bin
便利機能
(1)松225:httpdが動いているかの確認
ps aux|grep httpd
(2)松212: /etc/hostsに自サーバー名記述
(3)