第2章 模擬情報科ネットワーク
A. 模擬情報科ネットワーク
図1は実験で構築する模擬情報科ネットワークで、情報科のLANに似せたものです。研究室 LAN は何台かのPCと1台のWebServerで構成されます。PCは他研究室のホ−ムページにアクセスできます(模擬学科ネットをWANにつなげば学外ホームページにもアクセス可)が、他研究室(WAN側から)からはアクセスできません。WebServerは研究室LANから外部に情報を発信する唯一のサーバです。ここにホームページを用意すれば、それを外部から見ることができます。研究室LAN内にDNSは置きません(DNSは情報科ネットのDNSを利用します)。研究室DNSが無いということは、研究室LAN内のPC同士はPC名を使って交信できないことを意味します(PC番号を使えば交信できます)。研究室のPC同士の情報交換はLAN内FTPやWindowsのファイル共有を使いましょう。
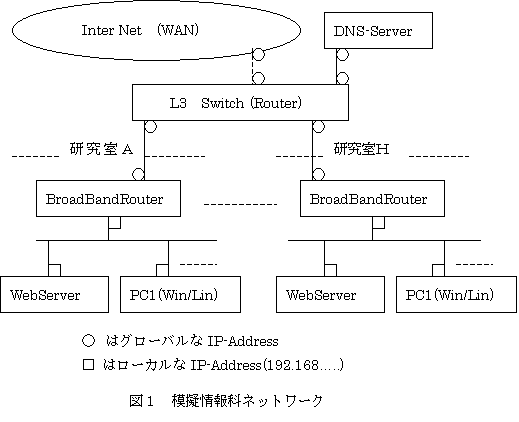
B.情報科ネットとネット市の対応
理学部4号館4階のネットワーク室にはL3スイッチという装置があります。この装置は理学部ネットという公道と情報科ネットという公道をつなぐ郵便局(ゲートウエイ)です。L3スイッチは初登場ですので、道路地図示すと次のようになります。
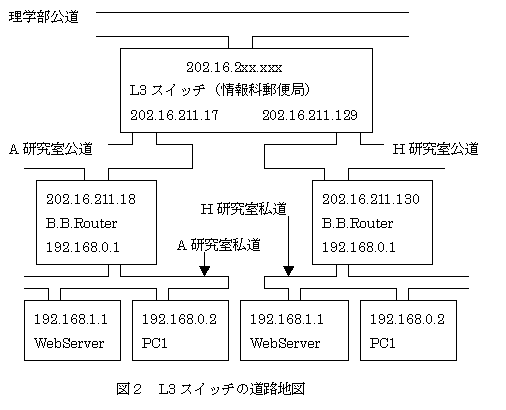
L3スイッチから各研究室までネットワークの通信線が引かれています。各研究室には16個のグローバルIPアドレスが与えられています。16個のうち1つはL3スイッチと研究室の接続部に使われます。すなわち、このIPアドレスが公道上の研究室ネットの番地ということになります。L3スイッチから研究室の入り口近くの壁に伸びている線に、ハブをつなぎ、そこに研究室の
PCを並べることもできますが、外部から侵入される恐れがあります。そこで、研究室ではL3スイッチからの線にブロードバンドルータを接続し、その下に研究室PCをつなげて研究室ネットを構成します。研究室PCから見るとブロードバンドルーターが研究室公道と研究室私道をつなぐゲートウエイ(郵便局)になります。
不思議の国との対応を整理すると、ブロードバンドルーターは郵便局BLに対応し、研究室のPCは郵便局の個人家に対応します。
ネットワークとコンピュータの観点から研究室ネットの動作を記すと、次のようになります。ブロードバンドルーターに接続したPCに電源を入れると、DHCPが作動しPCに、現在使われていないローカルIPアドレス(郵便局固有番地)を振ってくれます。この時PCのデフォールとゲートウエイはブロードバンドルーターの私道側のアドレスとなります(研究室外へのパケットはブロードバンドルーターに送られます)。
研究室ネットには何台かのPCと研究室ホームページを公開するためのウエブサーバを用意することにします。上の説明でPCに対してはDHCPでIPアドレスを振ることにしましたが、ウエブサーバはブロードバンドルーターの仮想サーバ(一般にはポートフォワードと呼ばれる)という機能で外部に公開します。仮想サーバとは、ブロードバンドルーターの特定のポート(棚段)に届くパケットを決められたPCに送る機能です。不思議の国では郵便局の1段貸棚がこれです。具体的にはブロードバンドルーターの80番ポート(http)にきたパケットをウエブサーバに転送します。
C.予備知識
コンピュータをインターネットに接続するには、IP管理組織からIPアドレスを取得する必要があります(電話番号のようなものです)。このIPアドレスはグローバルIPアドレスと言われ、世界に1つしかない番号です。ネットワーク上のコンピュータ同士は、このIPアドレスで相手を特定するので、IPアドレスを持っていないコンピュータは交信不能ということになります。
会社や大学が普通IPアドレスをもらう時は1つのアドレスをもらうのではなく”ある範囲(続き番号)”のIPアドレスをもらいます。”ある範囲”をドメインと言います。IPアドレスの範囲の表記法は、色々あります(予備知識1参照)ので、どれで表記されていても理解できるようにしておきましょう。
予備知識1 実験で使うグローバルIPアドレス範囲の色々な表記法 IPアドレス範囲:202.16.211.0-202.16.211.254 プレフィックス表記:202.16.211.0/24(上位24ビット固定) サブネットマスク表記:202.16.211.0/255.255.255.0 2進数:1100 1010 .0001 0000 .1101 0011 .0000 0000
この世界に1つのグローバルIPアドレスに対し、ローカルIPアドレスというものもあります。これは、世界からは見えなくても、会社内だけで交信すればよい場合にはグローバルIPアドレスを取得せず、会社内LANにだけ見えるIPアドレスを付けます(電話の内線みたいなものです)。ローカルIPアドレスには普通192.168.x.xが使われます。
D.模擬情報科ネットのIPアドレス割り当て
模擬情報科ドメインのグローバルIPアドレスは202.16.211.0/24とします。ということは情報科ドメインには256個のIPアドレスがあることになります。但し、ドメインには次の2つの特殊なアドレスがあり、これらは使うことができません。
ネットワークアドレスは 202.16.211.0 で、
ブロードキャストアドレスは 202.16.211.255 です。
ブロードキャストアドレスとは、ドメイン内の全PCにデータを同時に送る時に使うアドレスです。
図3はIPアドレスの詳細です。各研究室にはIPアドレスを16個ずつ割り当てることにします。A研究室: 202.16.211.16/28、 B研究室: 202.16.211.32/28、 、 、 、
H研究室: 202.16.211.128/28
図3 模擬学科ネットのIPアドレス構造
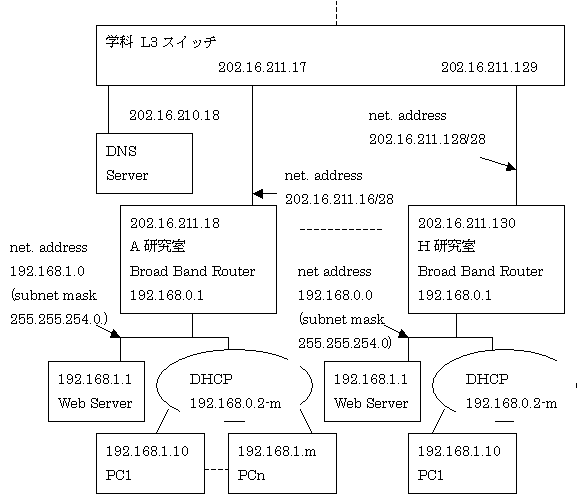
D.ネットワーク設定
このネットワークを動作させるには色々な準備が必要です、
(1)ブロードバンドルーター(郵便局)の設定
設定に入る前に少し準備
L3スイッチにつながった研究室のネットの道路地図は今までのものと少し違います。図2のように引き込み道路の形をしています。引き込み道路の入り口の番地が研究室IPのうちL3の口に与えられたIPアドレスです。ブロードバンドルータのWAN側出口には研究室に与えられたIPを振る必要があります。これがブロードバンドルーターの公道番地です。私道側はDHCPが勝手に番地を振ります。
・WAN(公道)側の(グローバルIPアドレス)番地設定
・LAN(私道)側の番地設定(出荷時初期設定してある)
・DNSの設定
・デフォールトゲートウエイ(L3スイッチの研究室IPアドレス)の設定
・バーチャルホストの設定(静的マスカレードとかポートフォワードとも呼ばれる)
(2)PCの設定(不可欠なのは次の3情報)
ネットワークに接続するPCには次の情報が不可欠です。
(1)自分のIPアドレス(自分の番地を壁に貼っておくことに相当)
(Windowsの場合)マイネットワーク->プロパティ―->TCP/IP...で
・ブロードバンドルーターからDHCPで割り当ててもらう場合は”IPアドレスを自動的に取得”とする。
・(グローバルIPなどを)自分で書きこむ
(2)DNS設定(IPを名前で呼びたいとき番号案内会社の電話番号を壁に貼っておくことに相当)
DNSのアドレスを設定することは不可欠だが、ブロードバンドルーターとOSの組み合わせによっては自動設定
されるので、ブロードバンドルーターのマニュアルを参照。ちなみに、IOデータのブロードバンドルーターとWindows98の組み合わせでは、”DNSを使わない”と設定する。
(3)(デフォールト)ゲートウエイの設定(私有地外へアクセスする時のパケットの送り先)
ブロードバンドルーターに接続されたPCはブルードバンドルーターに送らないことには外部に遅れないので、ゲートウエイとしてはブルードバンドルーターの私有地側の番地を書きこむ。ブロードバンドルーターの私有地側の番地はブロードバンドルーター出荷時に決まっている。IOデータ―社の場合192.168.0.1です。
以上
E.実験
目的: 研究室のPCから他研究室のHPを参照できるようにする。
前提:PCにはWindows又はLinuxがインストールされていて、ウェブブラウザが使用可(B.B.Routerが設定可)。
実験1:B.B.Routerの設定
実験2:WebServerの立ち上げ
実験3:DNSサーバはこちらで用意し、データの設定のみを行う