A.“ネット市”を空から見ると
図1はネット市の1部を上空から見た地図です。大きな公道が2本(A,B)見え、そこに会社や郵便局が並んで建っています。郵便局は2つあり(AB,BL)、郵便局ABは道路Aと道路Bをつなぐ働きをしています。これに対し郵便局BLは私有地をもち、この中に小さな家が並んでいます。会社や郵便局には国から番地が与えられていますが、郵便局私有地の家には国の番地はなく、局が独自に番地付けをしています。番地は道路ごとに付けられているため、2つの道路に面した郵便局は道路ごとに2つの番地を持ちます。郵便局私有地の家には公の番地がないため会社から直接家の番地を指定してアクセスできません。各道路には郵便配達が1人づついて、自分の受け持ちの道路の郵便配達をしますが、受持ち以外の道路には出ていきません。
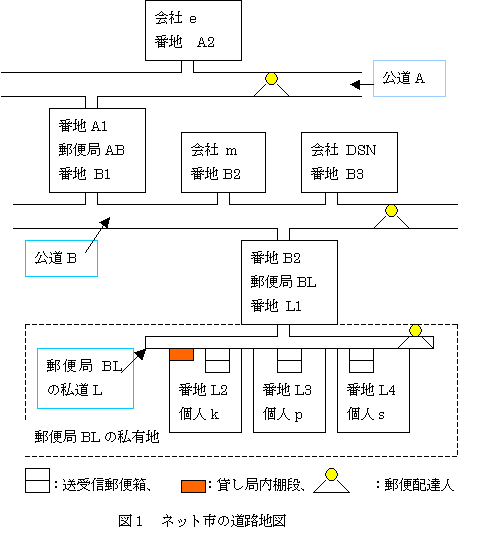
B. 実際(情報科)のネットとの対応
* 図の会社や家はコンピュータに相当し、番地はIPアドレスに相当します。
* 郵便局ABは普通の郵便局のイメージです(公道同士を結ぶ働きがあり、ゲートウエイとも呼れる。学科のL3スイッチは、これに相当し学部のネットAと学科のネットBをつないでいる)。
* 郵便局BLは私道L沿いの住民が作った私設郵便局と考えてもよい(研究室のブロードバンドルータがこれに相当)。
* 郵便局の私有地の家から公道に面する会社にアクセスできますが、公道の会社からはアクセスできません。普通の家はこれで満足していますが、中には図の個人kさんのように、“外からのアクセスを認めて欲しい”、と言い出す家があります。その時は、特例として“郵便局BL内の貸し棚”を借りて、公道側からアクセスできるようにします(後述:静的IPマスカレード)。普通この個人kは個人開設のウエブサーバです。
C.ネット市の郵便システム
ネット市の郵便システムは往復小包便サービスしかありません。往復小包便とは、小包を送ると、着信先で中身を入れ替えて、送信元に小包が戻ってくる郵便方式です。往復小包便を利用できるのは、個人と会社の2者です。会社は国に申請して公道に面した土地をもらい会社を建てます。これにより会社の番地が決まります。郵便局(BL)私有地内の個人が小包便を利用する場合は、私道Lに面した“送受信郵便箱”を使って小包を送ります。会社は往復小包を受けて中身を変えて返送することが出来ますが、個人の家の場合基本的には往復小包便を発送し返答を受け取るだけです。
往復小包の発送や受取りは、会社、郵便局、個人用家にある”送受信郵便箱”という特殊な箱を通して行います。送受信郵便箱は、郵便配達人が小包を配達してくれる時の郵便受け機能の他、送りたい小包を入れておくと配達人が小包を取り出して送り出してくれます。
また、送受信郵便箱は形も変わっていて中に棚段が沢山あります(図2)。個人は小包を送り出す時、どこかの棚段に小包を入れます。すると、往復便で返ってくる小包は送り出した棚段に戻されます。(強調:返送小包は、送出した棚段に戻ってきます)
小包を受け取り、送り返す会社の送受信郵便箱も棚になっています(営業課の棚段、広報課の棚段、、、って感じです)。
* *専門用語** 小包をパケット、棚段のことをポートと呼ぶ変わり者もいます。
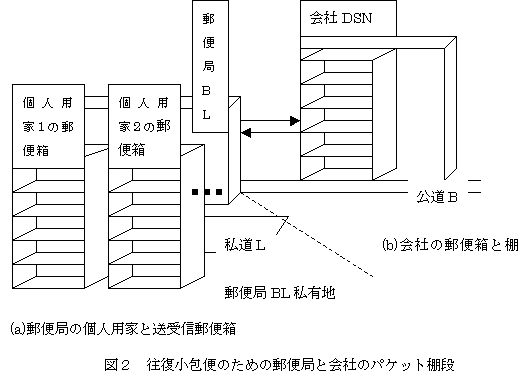
各道路にいる配達人は道路沿いの送受信郵便箱を常に見まわり、発送小包があるとそれを取り出して配送します。送受信郵便受けを正面から見ると図3のように、送受信棚の上に大きな看板が3つ付いています。
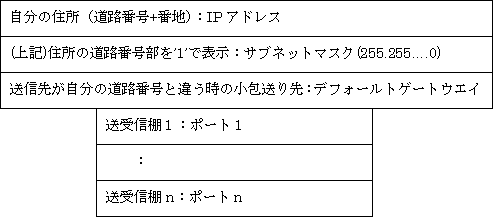
図3 家、郵便局、会社の各道路に面した送受信棚
配達人は受け持ちの道路を出ることはできません。配送先は小包に付いている荷札(図4)の”あて先(着信先)”を見て決めます。あて先が、自分の道路に面していれば(看板の上2つで判断可)直接配達することができますが、別の道路にある会社(看板の上2つで判断可)への小包も少なくありません。他の道路に面する会社への小包は、3つめの看板”他道路用(送り先が自分の道路と違う時)小包配送先番地”という看板に書いてある番地に配達します(この“他道路用転送先”はデフォールトゲートウエイと呼ばれるIPアドレスです)。普通、この他道路用配送先は他道路につながる郵便局の自分側の番地(IPアドレス)です。
小包には行き先や戻り先を示す荷札をつけます。図4は荷札の構造です。送り先と(着信先)戻り先(発信元)の情報が必要なのは当然ですが、発信元と着信先には棚段があるので、発信元と着信先の棚段番号も記入する必要があります。
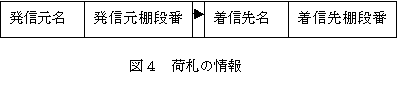
小包に付ける荷札の管理は厳重で、図4に示す4つの情報以外書く事を禁じられています。そのため、小包が郵便局を経由して目的地に届く場合、郵便局で荷札書き換えが行われます。
ここで、郵便局BLの個人用小屋1を借りている人がDNS社に往復小包を送る場合の例を紹介します。
郵便局BLの番地L2の小屋を借りている個人kがDNS社に往復小包を送る場合、荷札には“発信元:L2->着信先:DNSの番地”と書いてあるはずです。配達人はDNS社の番地が私道L上ではないので、個人用小屋1の送受信箱の上の看板 “他道路用配送先(この場合郵便局の番地L1)”をみて郵便局裏口(道路Lに面した入り口の集配箱)に届けます。
郵便局で、もしこの荷札のまま表門(公道Bに面した門)の集配箱に入れてしまうと、配達人がDNS社に運びます。ところが往復便なのでDNS社が小包を送り返そうとすると、発送元がL2になっています。番地L2は郵便局BLが勝手に付けた私有地内の番地なので、DNS社にしてみると、どこから来たのか分かりません。これを解決するには、郵便局BLで荷札を書きかえる必要があります。どう書き換えるかというと、荷札の発送元を郵便局の表門の番地B2にします。そして書き換えたことを記録簿に記録しておきます。こうすると、DNS社では返送先を郵便局BLにして送出すことができ、郵便局では記録簿を元にL2に送り返すことができます。
上の例は、郵便局での荷札の書き換えと記録簿への記載を少し、はしょって説明ました。実際は郵便局内にも6万段以上の棚段があり、それらをうまく使って小包の往復を実現しています。次にその様子を示します。
図5は郵便局の1部です。n番の家の人がr1の棚段を使って、会社dの棚段r10に往復小包便を送った時の、小包の荷札の変遷を示しています。
(1)個人が小屋の郵便箱に置く発送小包の荷札には、
[ 発送元私書箱番号n, 発送元棚段番号r1, > 送り先会社番号 d, 送り先会社棚段番号 r10 ]
を書きこんであります。例えば、ホームページを見るときr10は80番ですし、普通r1は1024以上の大きな番号です。
(2)郵便局では、荷札の発送元の項目を次のように変更し、
[ 郵便局番号s, 郵便局内棚段番号r2, > 送り先会社番号 d, 送り先会社棚段番号 r10 ]
のようにします。
ここで注意していただきたいことは、郵便局sでは小包を郵便局の棚段r2に移している点です。そして、この棚段間の移動は移動記録簿に記載しておきます。
荷札の発送元情報は往復便の帰りに必要になります。会社dが個人nに小包を返送しようとすると、個人nの番地と、経由郵便局番号sを荷札の発送元に書き込めればよいのですが、荷札の制約(4項目しか書き込めない、という)から2つの発送元を書いておくことはできません。
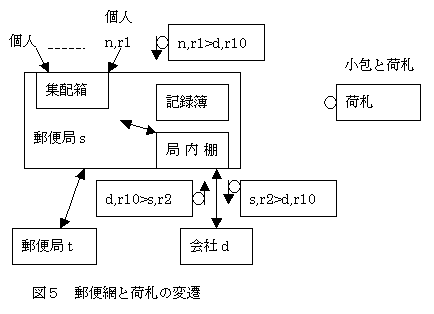
そこで、送り出した棚段に返送便を正しく返送するために郵便局内の棚段を使います。郵便局が、個人の発送した棚段番号のままで小包送ってしまうと、複数の個人が同じ棚段番号で送出した場合、会社からの返送便が郵便局の同じ棚段に戻ってきてしまい、どの個人に返せばよいのか分からなくなります。そこで送信小包を、番号が重ならないように決めた局内棚段に置き、その発送元(個人小屋番地)を記録簿に記録しておけば、返送小包が局内棚段に戻ってきた時、記録簿から発送個人を特定し配送することが出来ます。
(3)一方、往復小包便が送られてきた会社では小包に商品を詰め、送り元情報を元にパケットを送り返します。 図5の場合、到着小包から送り元郵便局と局内棚段番号を取りだし、返送用荷札の着信先情報部に書き込みます。発送元は会社dになります。
[ 会社番号d, 会社棚段番号r10,
> 郵便局番号
s,局内棚段番号
r2 ]
(4)会社dから郵便局の局内棚段r2に小包がもどってくると、r2にはどの個人から来たものか記録簿に書いてあるので、最初に往復便を送出した最初の棚段に配達することができます。
D. 郵便局の構成と往復小包便の仕組
郵便局内で働いているのは次の3人です。
1、発送元変更係:配達人が郵便局に運び込んだ小包について、先ず、小包荷札の発送元情報を自分の郵便局番号に書き換える共に、書き換えした旨(発送元情報)を記録簿に記録します。その後、発送のため発送先に近い入り口の集配箱に入れる。(彼の名はNAT君:Network Address Translation)
2、局内仕分け係:配達人が運んできた小包を、局内棚段に移します。この時、“どの個人から来たものを、どの局内棚段に移した”か記録しておき、小包が局内棚段に戻ってきた時、元の発送元宛てに送り出します。この時、局内仕分け係りは、荷札の発送元部の棚段番号を個人郵便箱の棚段番号から局内棚段番号に変更します。局内仕分け作業は発送元変更係と密接に連携を取りながら行います。(彼女の名はNAPTちゃん:Network Address Port Translation。あだ名はIPマスカレードちゃん:マスカレードとは仮想舞踏会:厳密に言うと1つの家の管理をするのがNAPTで複数の家の処理をするのがIPマスカレード)。NATとNAPTにより、荷札の発信元情報(局番と棚段番)は共に変更される。
3、家の住所自動割当て係:個人の家に住所を割当てる(彼の名はDHCPおじさん:Dynamic Host Configuration Protocol)。
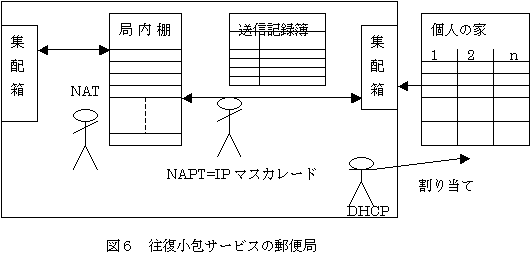
(注):私有地を持つ郵便局の労働者はNATとかNAPTとか可愛い名前で呼ばれるが、公道間をつなぐ郵便局ABの様な場合、NAPT,NAT機能はゲートウエイとかルータとか紛らわしく、かつ味気ない名前で呼ばれる。
E. サービス(ウエブサーバ等)提供もしたい個人のための送受信棚の貸出し
上で述べた個人の家は、往復小包便を送り出すだけのユーザでしたが、中には会社を開くほどではないが、往復小包便を受けて中身を変えて送出すことができれば嬉しい、と思っている個人もいる。その人のために、郵便局は棚段の貸出しというサービスを用意しています。
これは、局内棚段の1段を個人に貸し出すものです。図7が、その様子です。
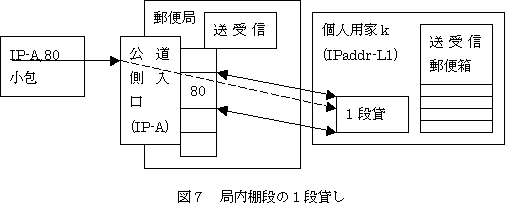
個人の家k(IPアドレスL1)は郵便局の公道側の80番の棚(ポート)を借りたとします。すると、郵便局の公道側(IPアドレスA)の棚80番に送られた小包を強制的に個人(IPアドレスL1)のポート80に送り込んでくれます。
個人用の家では送られてきた小包を加工して送り返せます(注、1段貸しは小包の中身を加工して送り返すのに使い、往復便の発送には使いません)。1段貸しは個人用ウエブサーバなどに使われます。これは郵便局内でNAPTちゃんの手をわずらわせない(80から80へ)ので静的マスカレードとか、ポートフォワードとか、仮想サーバ、呼ばれます。
<さらに凝りたい個人に:DMZ(非武装地帯)>
さらに凝りたい個人は、DMZという機能を用いることにより、郵便局に、会社を開いたり、買い上げ専用小屋を持つこともできます。DMZはブロードバンドルータによりサポートされている機能が異なるので、マニュアル参照して下さい。
F.ネット市の住人は数字が苦手
市民は小包を送る会社の名前は分かりますが、会社の番号を数字で覚えることができません。でも、小包の荷札には会社番号を数字で記入する必要があります。この国には電話番号案内のように、会社名から会社番号を教えてくれる会社があります(DNS:Domain Name System)。この、名前から数字に変換する処理は郵便局が、DNS社に聞いてやってくれます。ということは、郵便局内の壁または、にはDNS社の会社番号が貼ってあるはずです。DNS社のアドレスは個人の家に書いておく場合もあり、この区別がよく分かりません(OSによる気もします)